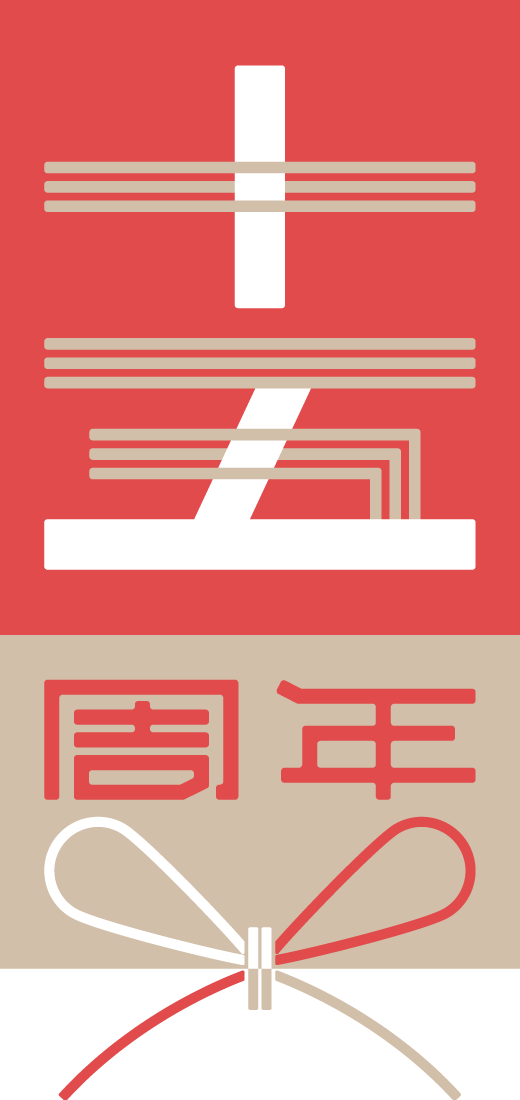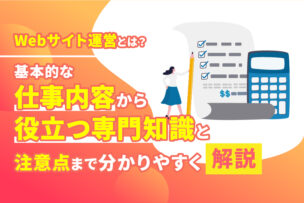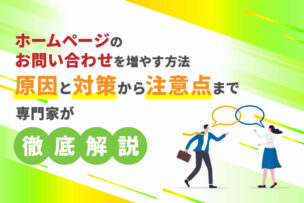記事の監修

Web集客・マーケティングの専門家として、15年間にわたり厳格な基準と緻密な戦略をもって中小企業の成功を導く。
一時的な集客の手法に頼ることなく、中長期的な効果を持続させる本質的なWeb集客の構築に注力。
『恵ある集客を。』をスローガンに掲げてクライアント様のサービスや商品の核心的な魅力を、的確にターゲットに伝えることを重視したWebサイト運用をサポート。
SEO対策に意味がないと言われる理由は「進化」しているからです。効果のあるSEO対策を実行するためには、時代と共に進化してきた検索エンジンとAI技術の進化をしっかりと理解することから始めましょう。効果のない従来のSEO対策を見直し、最新の効果的なSEO対策を講じることで、必ず効果は表れてきます。
STEP 1|検索エンジンとAI技術の進化を理解する
STEP 2|効果のないSEO対策は辞めて改善を
STEP 3|現代に通用する効果的なSEO対策の実行
目次
「SEO対策に意味はない」は誤解?現在のSEOを取り巻く状況
近年はSEO対策を行っても、新規顧客の獲得や集客に繋がりにくいため、意味がないという声も聞かれます。では、本当にSEO対策は意味がないのでしょうか?
ここでは「SEO対策に意味はない」と言われる現代の実情をお伝えします。
SEO対策はオワコン?効果がないと言われる現状
一部で「SEO対策はオワコン」と言われるのは、従来のSEO対策が通用しなくなったことや、AI検索が背景にあります。
現在は、ChatGPTのような生成AIが検索結果に直接回答を出すため、ユーザーがサイトを訪問しないケースも増えました。しかし、これはSEO対策が不要になったわけではありません。むしろ、AIに「信頼できる有益な情報」として選ばれるために、新たなSEO対策を実行する必要があるのです。
つまり、表面的なテクニックではなく、検索ユーザーとAIの両方にとって価値のある「高品質で信頼性の高いコンテンツ」を提供することが、現代のSEO対策において必要不可欠なのです。
従来のSEO対策が通用しない?
かつては効果があったものの、現在では通用しない、あるいはGoogleからのペナルティ対象となるようなSEO対策が存在します。これらの手法は、検索エンジンのアルゴリズムが進化し、ユーザー体験を重視する方向にシフトしたことで、逆効果となっていることが理由として挙げられます。
代表的な例が、キーワードの詰め込みです。これは、記事内に不自然なほど大量なキーワードを含める手法で、かつては上位表示に繋がることもありました。しかし現在は、読みにくくユーザーにとって価値がないと判断され、評価を下げる原因となります。
また、低品質な被リンクの購入も同様です。検索エンジンは被リンクのサイトを信頼性の指標としますが、人為的につくられたり、関連性の低いサイトからのリンクを大量に購入したりする行為は、不正な操作と見なされペナルティの対象となるのです。
現代のSEO対策は、これらの技術ではなく「ユーザーファースト」の原則に基づいて、高品質で信頼性の高いコンテンツを提供し、自然な形で評価を得ることが求められています。
あわせて読みたい
SEO対策に意味がないと言われる理由とは?
一部では「SEO対策は意味がない」という意見も聞かれますが、実際には表示順位を高めるためにSEO対策は非常に重要です。
先ほども少しお伝えしましたが、現在では検索エンジンのみならず、「検索AI」からの評価も検索順位に大きな影響を与えているからです。従来はGoogleアルゴリズムに基づいた評価が検索順位に直結していましたが、今では生成AIが検索ワードを理解し、信頼性のあるWebページから回答を導き出して表示するシステムが普及しています。
このように、SEO対策は時代とともに変化しています。もはや検索エンジン向けの対策だけでなく、生成AIや検索AIに対する対策も実施することが重要となっているのです。
ここでは、SEO対策に意味がないと言われる背景を、時代とともにご紹介します。
生成AI・検索AI技術(GoogleのAIO、ChatGPT、Perplexity AI)の普及
SEO対策に「意味がない」と言われる原因の一つに、生成AIや検索AI技術の急速な普及が挙げられます。
GoogleのSGE (Search Generative Experience) やChatGPT、Perplexity AIといったツールは、ユーザーの検索意図をしっかりと理解し、複数のWebサイトから最適な情報を探し出して、直接回答を生成します。これによって、ユーザーは検索結果ページに表示されたAIの回答だけを確認し、求めている情報を得るケースが増えてきました。
この変化は、従来のSEO対策による「検索結果での上位表示」の価値を一部低下させたように感じるでしょう。なぜなら、ユーザーが生成AIの回答だけで満足すれば、その回答の参照元であるWebサイトまで訪問しない可能性も大いに考えられるからです。
しかし、これは「SEO対策の意味がなくなった」わけではなく、「AIに選ばれるSEO対策」へと進化していることを意味します。AIが信頼できる情報源として自社のWebサイトを選択するようなコンテンツ、つまりE-E-A-Tを満たし、有益かつ高品質なコンテンツこそが、新たな時代のSEO対策となるのです。
アクセスが伸びても売上や利益が上がらない
SEO対策が実を結び、アクセスが伸びたとしても売上や利益など、収益が増えないというケースもあります。コンテンツの書き方や訴求が適切でなければ、求める成果を得ることが難しいのです。
検索ユーザーは、記事内に求める情報がなかったり、内容が分かりにくければ、コンテンツから離脱してしまいます。ユーザーの検索意図とコンテンツの内容が一致しない場合や、そもそもコンテンツが読まれていない場合には、アクセス数が増えたとしても、成果に繋がりにくいのです。
コンテンツごとに訴求方法を工夫しなければ、求める成果を得ることは難しくなるでしょう。
アルゴリズムアップデートで順位が安定しない
Googleのアルゴリズムアップデートで順位が安定しない場合も、SEO対策の効果を感じにくくなるでしょう。
Googleは、ユーザーの役に立つ情報を上位表示させるため、常にアルゴリズムのアップデートを実施しています。中でも、検索順位に大きな影響を与えるコアアルゴリズムがアップデートされれば、上位表示されていたページの順位が大きく変動することもあります。
しかし、Googleは「検索ユーザーの利便性を高めること」を目的としたアップデートを行うため、ユーザーファーストのコンテンツを制作していれば、上位に表示させることも可能でしょう。
アルゴリズムのアップデートに合わせて対策方法を変えることも大切ですが、常にユーザーのためになるコンテンツ制作を心がけることも大切です。
あわせて読みたい
SEO対策の成果が現れない?考えられる理由とは
SEO対策において意識すべきポイントを抑えても、成果を実感できない場合は、どのような原因が考えられるのでしょうか。ここでは、SEO対策の成果が現れない際に考えられる理由を、Web集客コンサルタントの専門的な目線からご紹介します。
サイトを立ち上げて間もない
サイト立ち上げからの期間も、検索の表示順位に影響します。サイトを立ち上げてからあまり時間が経過していない場合、上位表示されにくいことも考えられます。理由としては、サイトの専門性や権威性、信頼性が足りないことと、外部サイトからの被リンクがないことが挙げられます。
実は、サイト内の情報が網羅されておらず、専門性や信頼性が検索エンジンに伝わらなければ、ユーザーに有益ではないと判断されることがあるため、上位表示が難しくなってしまうのです。
サイトの信頼性や専門性は、他サイトからの被リンクによって判断されます。そのため、サイトを立ち上げて間もなく、被リンク数が少なければ、上位表示が困難なのです。
上位表示を目指す場合は、継続してユーザーの役に立つような質の高いコンテンツを届け続ける必要があるということです。
競合サイトに比べて情報が乏しい
競合サイトに比べ、情報が乏しい場合も、SEO対策の成果を実感しにくいでしょう。求める情報が満載の競合サイトと、情報不足な自社サイトならば、前者の方がユーザーに寄り添ったコンテンツであることは言うまでもありません。
質の良い情報が充実したサイトは、検索エンジンからも評価を得られます。しかし、競合サイトと同じ情報を掲載しているだけでは、上位表示を目指すことは困難です。コンテンツを作成する際は、情報を網羅的に紹介しながら、競合他社サイトとの違いとして、自社だけのオリジナルな情報を記載することが重要です。
十分な情報を用意しながら、独自性のある情報を加えることを意識しましょう。
サイト構造や内部リンクが整っていない
サイト構造や内部リンクが整っていなければ、上位表示を目指すことは難しくなります。
ユーザーファーストの質が高いコンテンツを用意していても、サイト構造や内部リンクなどが適切な形になっていなければ、検索エンジンは正しい情報を得られないため、適切な評価をしてもらえません。
検索エンジンは自社サイト内や外部サイト内のリンクを頼りに、コンテンツを巡回し、タイトルや見出しを伝えるHTMLタグから記事内の情報を収集しています。ユーザーだけでなく、検索エンジンにとっても、情報を収集しやすいサイトにすることが大切です。
検索順位が芳しくない場合には、サイト構造や内部リンクが最適化されているかを意識してみてください。
あわせて読みたい
効果のないSEO対策の事例
意味のないSEO対策とはズバリ、ユーザーファーストでない施策のことです。例えば、ユーザーが求めている情報を提供していないコンテンツや、ユーザビリティを無視したコンテンツの制作などは、意味のないSEO対策の代表と言えるでしょう。
ユーザーファーストでないコンテンツが「SEO対策の意味がない」と言われる理由としては、主要な検索エンジンであるGoogleが「世界中の情報を整理し、世界中の人がアクセスできて使えるようにすること」を使命としているからです。その結果、ユーザーの役に立たないコンテンツは検索の妨げになると判断され、アクセスを阻害されます。
検索エンジンに評価されない施策を行うWebサイトは、アルゴリズムの変動やアップデートに弱く、高順位が保てません。よって、SEO対策を行っていても「効果がない」と感じるのです。
2025年最新の効果のないSEO対策
2025年になって効果が期待できないSEO対策は、具体的にどのような対策になるのでしょうか?ここでは、効果のないSEO対策を詳しくご紹介します。
意味のない長文コンテンツ
意味のないSEO対策として考えられるのは、やたらと文字数を増やした長文コンテンツです。単純に長文を目指しているため、内容が薄く、検索意図を満たすコンテンツと言えません。読者にとっては、途中で挫折してしまうほどの文字量のため、離脱率を高める要因となってしまうでしょう。
●ページコンテンツを深掘りした文字数
長文コンテンツを作る際は、しっかりした構成のもとに作成してこそ読み手の理解を得られます。構成のもと、ページコンテンツを深掘りした結果の文字数であることが必要です。長文コンテンツによる深掘りは、読み手に対して次の訴求を可能とします。
- コンテンツの専門性
- コンテンツの網羅性
- コンテンツの信憑性
これらの要素をもとに深掘りしている内容であればユーザーに役立つコンテンツになるでしょう。
●長文より品質重視、結果長文はあり
長文コンテンツは、品質重視で考えるべきです。ページコンテンツを深掘りすることは、コンテンツの品質を高める効果があります。専門性や網羅性などを追求した結果、長文になるのであれば必要量として品質の向上になるでしょう。
意味のない本文内のキーワード出現率
ひと昔前のSEO対策でひんぱんに行われていたキーワードの詰め込みは、もはや時代の産物です。単純にキーワードを羅列した文章は、逆にしつこく感じたり、機械的に感じたりします。
本文内にキーワードを詰め込んで出現率を上げる方法は、いまだに活用しているWebサイトもあります。しかし、キーワードの詰め込みは上位表示どころかペナルティになることも考えられるため、注意しましょう。ひとつのコンテンツに対して、ユーザーの検索意図にマッチングしたひとつのキーワードで深掘りした本文を作成する必要があります。
●キーワードに執着し過ぎて文章をくずさない
また、キーワードの出現率を意識しすぎると文章が崩れてしまう可能性があります。コンテンツに必要なのは、読み手となるユーザーの読みやすさです。キーワードに執着し過ぎて文章をくずしてしまわないように注意しましょう。あくまでも、読み手主体で考えることが大切です。
意味のない本文中の挿入画像
意味のないSEO対策として考えられるのは、本文中で使われる挿入画像です。本文中で使われる挿入画像が本文のコンテンツと関係している画像であれば違和感がないでしょう。ところが、本文のコンテンツとかけ離れた画像を使うことで読者のコンテンツに対しての感情移入を妨げます。例えば、確定申告の用語解説コンテンツの画像に海の風景を使用した場合、本文と画像のギャップで読者は困惑してしまいます。
●本文内容や見出しとかけ離れた画像はNG
本文に挿入する画像は、本文の内容や見出しと合った画像を使いましょう。例えば、先ほどの確定申告の用語解説コンテンツであれば「相談しているイメージ画像」や「申告書の画像」などです。くれぐれも本文や見出しとかけ離れた画像は使わないようにしましょう。
意味のないジャンル違いの外部リンク
意味のないSEO対策として、外部からの被リンクなどが考えられます。現在では、意味のないジャンル違いの外部リンクは、ペナルティの対象となる恐れがあります。
●同じジャンルのリンクを多く受けていることが重要
外部からのリンクを受ける場合は、自社Webサイトと同じジャンルのリンクを受けることが重要です。同じジャンルの外部リンクであれば、多く受けることで評価向上を期待できます。
AI生成コンテンツのコピペ公開
AIで生成した文章やコンテンツをそのまま公開しているようなコピペコンテンツも、SEO対策の妨げとなります。冒頭でもAI技術の発展について触れましたが、現代では特に、AI技術を活用したツールが誕生し、誰でも簡単に綺麗で整った文章を作成できるようになりました。しかし、AIが生成したコンテンツを見破ることが可能なのも、現代の検索エンジンの進化した技術です。
綺麗で整った文章は一見、検索順位に良い影響を与えると誤解する方もいるかもしれません。しかし、すべてのコンテンツがAIで生成されるようになったらどうでしょう。どの記事を読んでも同じような内容しか書かれておらず、本当に知りたい情報が見つからないケースが考えられます。また、どのWebサイトも類似した内容になることで、独自性がなくなってしまうのです。
AIで生成することはダメとは言いませんが、あくまでも参考にする程度にとどめ、自社の強みや特徴を消さないように注意する必要があります。
ユーザーニーズを無視した機械的なコンテンツ更新
検索するユーザーの明確な目的や、ユーザーの検索意図の変化を考慮せず、機械的なコンテンツ更新は意味がありません。例えば、更新の事実を記録するためだけに過去の記事の日付のみを更新したり、微修正に留めたりする行為は、SEO対策とは言えないのです。
なぜなら、情報が古いまま間違った情報提供をしている可能性があるからです。ユーザーにとっての最新情報や「価値」を提供できていないため、検索順位の向上に繋がらないのです。
モバイルフレンドリーを軽視したWebサイト設計
モバイルフレンドリーを軽視したWebサイト設計も、もはや効果的なSEO対策とは言えません。スマートフォンの普及により、多くのユーザーがモバイル端末からウェブサイトにアクセスしています。そのため、表示速度が遅い、タップしにくい要素がある、レスポンシブデザインに対応していないなど、スマートフォンユーザーの利便性を損なう設計は、ユーザー体験を著しく低下させます。
構成化データの「形式的」な利用
構造化データは、Googleの検索結果で商品の価格や評価を際立たせます。WebサイトのHTML内に特定の情報を記述することで、検索結果上でユーザーの目を引く表示が可能となります。
しかし、この構造化データを「形だけ」利用することには意味がありません。例えば、Webサイト上に存在しない商品のレビューの星の数を偽ったり、実際よりも高い評価を付けたり、または全く関係のない内容の情報を記述したりすると、Googleはその嘘を見抜きます。
たとえ一時的にリッチリザルトとして表示されたとしても、最終的にはペナルティを受けたり、全く表示されなくなったりするリスクがあるのです。
あわせて読みたい
2025年最新の効果的なSEO対策

それではここからは、2025年最新の効果的なSEO対策についてお話しします。重要なことは、Webサイトやコンテンツは一度作ったら終わりではなく、日々変化するユーザーニーズ対応していかなければならないことです。そのため、Webサイトのパフォーマンス解析を継続して行い、改善していくことは、これからのWebサイト運営にとって不可欠となっています。
Googleが評価する「質の高いコンテンツ」
2025年現在、Googleが最も評価するのは「質の高いコンテンツ」です。質の高いコンテンツは、ただ単に情報量が多いコンテンツというわけではありません。ユーザーの検索意図を的確に理解し、悩みや課題を完全に解決できる情報を提供しているかどうかが重要です。
例えば、おすすめの商品をランキング形式で紹介するだけのコンテンツは、ユーザーの検索意図を満たしているとは言えません。ユーザーはどんな商品がおすすめで、なぜおすすめなのか、その商品はどんな悩みを解決できるのか、という情報を求めています。
ユーザーが何のためにそのワードで検索しているのかをしっかりと理解する必要があるのです。

めぐみやのWebコンテンツ制作代行
見込み客に響くWebコンテンツ作りにお悩みではありませんか?
ターゲットを確実に捉えるコンテンツ制作で見込み客の獲得をサポート致します。
ユーザーの使い勝手の良さ(Core Web Vitals)
効果のあるSEO対策としてGoogleのガイドラインに適したサイト設計を目指すには、ユーザーの使い勝手を優先することが必要です。Googleでは、ユーザーの使い勝手の向上を測定するためにCore Web Vitalsを指標に判断しています。
Web Vitalsは、Webコンテンツを利用するユーザーの使い勝手の良さを測定する品質の指標です。ユーザーエクスペリエンス向上に向けた指標として、Web担当者向けの改善に役立つ指標を提供しています。
Googleでは、Web Vitalsによる指標をあらゆる観点から測定しています。その中でも重点的に評価に影響する中心的な要素がCore Web Vitalsです。Core Web Vitalsは、以下の3つの要素を重点に置いています。
- サイトの読み込み速度(LCP)
- サイト操作の反応速度(FID)
- ページコンテンツの視認性(CLS)
データ参照元:Google Developers 「Web Vitals の概要: サイトの健全性を示す重要指標」
サイトの読み込み速度(LCP)
Core Web Vitalsでは、サイトの読み込み速度を重要視しています。サイトの読み込み速度の指標は、LCP(Largest Contentful Paint)として測定されます。速度の指標となるため、Webページなどの表示速度数値が小さければ小さいほどGoogleに評価されるでしょう。理想の数値は、Webページが表示されるまでの時間が2.5秒とされています。
たとえば、無駄に設置されたコンテンツと関係のない画像や読み込みに時間の掛かる動画コンテンツ、広告などで構成されたWebページがあるとします。意味のない画像コンテンツや動画コンテンツにより、Webページの読み込みが遅くなれば、コンテンツ到達前にユーザーが離脱してしまいます。
ページ読み込み速度の改善は、ユーザーの離脱をなくすSEO評価につながるでしょう。
サイト操作の反応速度(FID)
Core Web Vitalsでは、ページの表示速度と同じく、ページ内で実行するアクションに対しても反応速度が短かればユーザーの使い勝手を評価されます。
Webページには、あらゆる移動ボタン(リンク)やアクション実行ボタンが設置されます。設置してあるボタンを押したのに、反応が遅いと評価が下がり、反応が早いと評価が高くなる仕組みです。この指標をFID(First Input Delay)と言います。
ページコンテンツの視認性(CLS)
Googleの評価指標として重視しているのは、CLS(Cumulative Layout Shift)です。CLSは、Web上に公開されたページのレイアウト崩れや表示崩れなどを評価します。考えられるレイアウト崩れは、PCでは表示されているボタンがスマホ表示で確認すると、テキストと重なり押しづらくなっているなどです。
CLSの評価も、レイアウト崩れと判断される数値が低いことが理想となるでしょう。Core Web Vitalsで重点に置く指標は、Webサイトの技術的な修正で解決できます。Web担当者に知識や経験がなければ、専門家の意見を参考に進めてみることも必要です。
専門性と権威性、信頼性の担保(EAT)
Googleでは、先ほど解説した技術面における評価指標「Core Web Vitals」以外にも、ページコンテンツの内容を判断するEATを重視しています。EATは、以下の3つの要素を略した呼び名です。
- Expertise(専門性):サイトに関連する特定の分野にくわしい専門家による見解
- Authoritativeness(権威性):サイトに関連する特定の分野で公認されている存在
- Trustworthiness(信頼性):サイト運営者およびサイトコンテンツの信頼性
EATは、Googleによるサイトコンテンツの品質を評価する際の指標です。小手先のSEO対策ではなく、EATの要素を含めたコンテンツをつくることで品質の高いコンテンツとして評価されます。品質の良いコンテンツは、検索順位を上げるために大きな影響を与えるでしょう。

めぐみやのWebサイト制作
効果的なWebサイトを作りたいけれどどうすれば良いかお悩みではありませんか?
集客と運用の実績を活かし御社ビジネスの成果に直結するWebサイトを構築致します。
信頼と実績の「E-E-A-T」を確立する
Googleでは、先ほど解説した技術面における評価指標「Core Web Vitals」以外にも、コンテンツの内容を判断する「E-E-A-T」を重視しています。「E-E-A-T」は、以下の4つの要素のことを指します。
- Experience(経験):実際にサイトの内容を経験して個人的な視点や独自の見解に基づいた情報を提供しているか
- Expertise(専門性):サイトに関連する特定の分野に詳しい専門家による見解が示されているか
- Authoritativeness(権威性):サイトが特定の分野で公認されているか、影響力がある存在と認められているか
- Trustworthiness(信頼性):サイト運営者やコンテンツの情報が正確で、公正であり、ユーザーが安心して利用できるか
「E-E-A-T」は、Googleによるコンテンツの品質を評価する際の指標です。小手先のSEO対策ではなく、「E-E-A-T」の要素を含めたコンテンツを制作することで、品質の高いコンテンツとして評価されます。品質の良いコンテンツは、検索順位を上げるために大きな影響を与えるでしょう。
ユーザー体験
Core Web VitalsやEATの評価を上げる取り組みは、ユーザー体験の品質を高める効果につながります。効果のあるSEOは、ユーザーファーストを基準として考えることが大切です。SEOには、近道や抜け道はないのでコンテンツに不足しているEATの要素をいかに補うかが求められるでしょう。
検索エンジンとユーザーにとって「満足」を提供する
Google検索で上位表示を目指すには、検索エンジンとユーザー双方に「満足」を提供することが大切です。
これまでで解説したとおり、検索エンジンはE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)に基づいて、ユーザーの検索意図を解決できる質の高い情報を求めています。AI検索の進化に伴い、Webサイトの信頼性が非常に重要です。
そして同時に、ユーザー体験も不可欠です。コンテンツの価値はもちろん、ページが見やすいか、サイトが快適に使用できるかなど、ユーザーの利便性が重視されます。
ユーザーが満足すれば、滞在時間が延びるため、結果として検索エンジンからの評価も高まるでしょう。
あわせて読みたい
自分でできる効果的なSEO対策のコツ
これまでの機械的な施策が多かったSEO対策から、これからはより、お客様の立場に立った企画や対策が、今後のWeb集客として貢献していく事になります。下記の関係が今後のSEO対策における一つの考え方です。
SEO対策 = 検索エンジン対策 < SEO対策 = お客様目線の企画・対策
また、これからはSEO業者だけに頼らないサイト運営体制の整備が不可欠となります。そして、人口の減少でマーケットが縮小傾向の中、今後より一層、Web集客の難易度は高くなると予測します。
集客する見込み客を明確にする
具体的にはどのような事を行えばよいのでしょうか?まずは、見込み客の目的を明確にする事から始まります。相手の顔が見えないWebだからこそ、この作業は非常に大事になります。自社の視点、第三者の客観的視点などを織り交ぜて、御社の見込み客像を考察しましょう。
自社の視点
集客する見込み客を自社の視点で明確にする場合は、自社ビジネスにより与えられる価値を具体化します。例えば、自社ビジネスで扱う商材が学習教材の場合、見込み客は小学生や中学生、高校生などの子どものいる保護者となるでしょう。自社の視点を含めて判断すると、対象となる見込み客に継続した利用を求めたいところです。
継続した利用を求める場合は、学習教材を継続して使うことで得られる効果や実績などをしっかりと伝えることで、見込み客にとっての価値を生み出す必要があります。
第三者の視点
第三者の視点で考えると、集客する見込み客に対して費用対効果などを明確にします。その際に、比較対象となる他社類似商品などと比べて、「自社商品は他社にない強みがある」という特徴のアピールが必要です。
見込み客のニーズを満たすWebコンテンツを提供する
見込み客を集客する事は、意外にもシンプルです。それは、見込み客のニーズを満たす(集客出来る)コンテンツを提供する事です。そして、それを継続することが大切です。
SNSを活用した多様な集客経路
見込み客のニーズとマッチングさせる場所は、Webページのおもな流入先である検索エンジンばかりではありません。現代では、TwitterやInstagram、Facebook、LINEなどのSNSやコミュニケーションアプリからの流入も大きな集客力を持っています。
SNSは、それぞれのチャネルごとに特徴があり、その特徴を生かしてコミュニケーションをはかれれば、多様な集客経路の構築が可能です。とくにSNSユーザーは、特定のテーマに対して共感してつながっています。そのため、検索エンジンで流入してくるユーザー以上に、強いニーズを持った見込み度を期待できます。
画像や動画などからの流入も考慮すべき
見込み客のニーズを満たしたWebコンテンツでは、画像や動画の設置も欠かせません。検索ユーザーは、画像や動画で検索してくる可能性があるからです。たとえば、画像の場合はGoogleが提供する検索連動型スマホアプリ「Googleレンズ」からの流入を期待できます。
Googleレンズは、検索の要素をキーワードではなく、スマホで撮影した画像をもとにWebで公開されている画像から一致する画像を選んで紹介します。そのため、自社商品に関する画像は多ければ多いほど有利になるでしょう。
また、動画の場合は動画投稿サイト「YouTube」に投稿した動画と連携することで、相互流入を期待できます。YouTubeを利用するユーザーが動画視聴を機会にWebサイトへ訪問してくることも考えられるでしょう。
あわせて読みたい
最終的にたどり着く場所を自社サイトにする
意味のないSEOから脱却して有用なWebサイトを運営するには、自社Webサイトが最終的にたどり着く場所であるべきです。自社Webサイトが最終的にたどり着く場所となるための要素は、Webサイト内で疑問を残さないで解決させることではないでしょうか。
スマホの普及から現代のインターネット検索は、身近な生活インフラ化してきました。ひと昔前であれば、インターネット検索がパソコンユーザーの特権でもありました。現在では、パソコン操作の苦手な人でもスマホで手軽にインターネット検索を利用できます。それだけに、満足のいく回答がなかったWebサイトは、すぐに見切りを付けられます。
見切りをつけても、ユーザーは検索エンジンが表示している他のWebサイトへ移動することが簡単です。そのような理由からも、自社Webサイトを最終的にたどり着く場所というイメージでつくり込む必要があります。
検索エンジンからの流入とSNSからの流入どちらも満足のいく回答が必要
Webサイト内で疑問を残さないで解説させるコンテンツは、検索エンジンからの流入とSNS流入のどちらも満足いく回答を用意しなければなりません。「検索エンジン向け」とか「SNS向け」とか分けるのではなく、どちらのユーザーが訪れても納得のいくコンテンツを作成する必要があります。
ユーザーに役立つコンテンツを追求する姿勢が必要
検索エンジンからのユーザーやSNSユーザーのどちらも満足させる回答に共通するポイントは、ユーザーに役立つコンテンツを追求する姿勢です。コンテンツの画像ひとつにしても、「この画像があればユーザーの理解が高まる」という状況が考えられます。
また、コンテンツの本文でも、「この部分を読んでいる人は、この疑問を持つだろう」と判断できた場合は、その疑問に対しての回答を自社Webサイト内で返す姿勢が大切です。
専門家の見解は不可欠
運営するWebサイトを最終的にたどり着く場所にする考え方を実現することは、簡単ではありません。Googleが評価するCore Web VitalsやEATの要素を入れることが必須です。そのうえでWebサイトのコンテンツを充実させる必要があります。
Web担当者にとっては、負担のかかる面が多くなるため、専門家の活用をおすすめします。知識や経験を備えた専門家の見解により、時間と労力を最短にできる取り組みが期待できるでしょう。
E-E-A-Tを高める
先ほども触れましたが、E-E-A-Tは、Googleがコンテンツを評価する上で、重要視している項目です。E-E-A-Tを分かりやすく言うと、権威のある専門家が執筆した記事や、実際に商品を使用したことがある人のレビュー記事を、より評価し信頼するというものです。
代表的なE-E-A-T対策としては、専門家や権威のある人物が執筆または監修されていることをコンテンツ内に掲載したり、掲載情報の信頼性を担保するため、信憑性の高いデータや調査結果を掲載する方法があります。
クオリティの高いサイトを目指す際は、E-E-A-Tを意識することが大切です。
あわせて読みたい
SEO対策に効果がないのではなく「進化」している
変化の激しいWeb業界でも、商売の鉄則は常にお客様目線。Googleも「ユーザーファースト」を徹底しています。小手先のSEO対策ではなく、ユーザーとAI双方に価値のある「高品質なコンテンツ」を提供することが、2025年のSEO対策を成功させるカギとなるでしょう。お客様目線でのWebサイト運営を心がけましょう!
- ユーザーファーストのSEO対策が重要
- Googleは専門性、権威性、信頼性を基準としたコンテンツを高く評価している
- 見込み客のニーズを満たすコンテンツの提供を継続することが重要
SEO対策やその効果に関するよくあるご質問
最後によくあるご質問をいくつかご紹介致します。
みなさまのWeb集客にお役に立てば幸いです。
その他、ご不明な点がございましたら以下のリンクよりお気軽にご相談下さいませ。
無料オンライン相談はこちらからどうぞ。
Q
SEO対策が意味ないと言われる理由は何ですか?
A
一部の方は、検索エンジンのアルゴリズムが常に変わるため、特定のSEO対策がすぐに古くなる可能性があると考えています。
Q
SEO対策をしない場合、どのようなデメリットが考えられますか?
A
SEO対策をしないと、サイトの検索エンジンのランキングが低下し、潜在的な顧客のトラフィックが減少する可能性があります。
Q
すべての企業がSEO対策を必要とするわけではないのでしょうか?
A
事業の種類や目標によっては、他のマーケティング戦略がより効果的である場合もあります。
Q
「SEO対策は意味ない」という説に対する専門家の意見は?
A
弊社も含め多くの専門家は、適切に行われたSEO対策は効果的であると考えていますが、一時的なトリックやブラックハットSEOは避けるべきだとも言っています。
Q
SEO対策の中で特に意味がないとされる施策はありますか?
A
キーワードの過度な詰め込みや不自然なバックリンク作成など、過去のブラックハットSEOの方法は現在では効果的でないと考えられています。
Q
SEO対策を適切に行うためのポイントは?
A
コンテンツの質を重視し、ユーザーのニーズを満たす情報を提供すること。さらに、技術的な最適化や適切なキーワードリサーチも重要です。
Q
SEO対策とPPC広告の違いは?
A
SEO対策はオーガニックな検索結果のランキングを向上させるためのもので、PPC広告は広告をクリックするたびに支払う形式のWeb広告です。
Q
「SEO対策は意味ない」という意見に共感する人たちはどのような業界に多いのでしょうか?
A
インフルエンサーマーケティングやSNS広告に重点を置いている業界など、検索エンジンのトラフィックに依存していない業界でこの意見に共感する人が多いかもしれません。
Q
SEO対策に対する誤解や間違った情報は一般的にどのようなものがある?
A
すぐに結果が出る、一度行えば永続的に効果がある、全てのサイトが同じ対策で効果を得られる、などの誤解があります。
Q
SEO対策が「意味ない」とされる場面の一例を教えてください。
A
ニッチな市場や特定の業界で、検索ボリュームが非常に少ないキーワードに対するSEO対策は、労力に見合った成果が得られない場合があります。