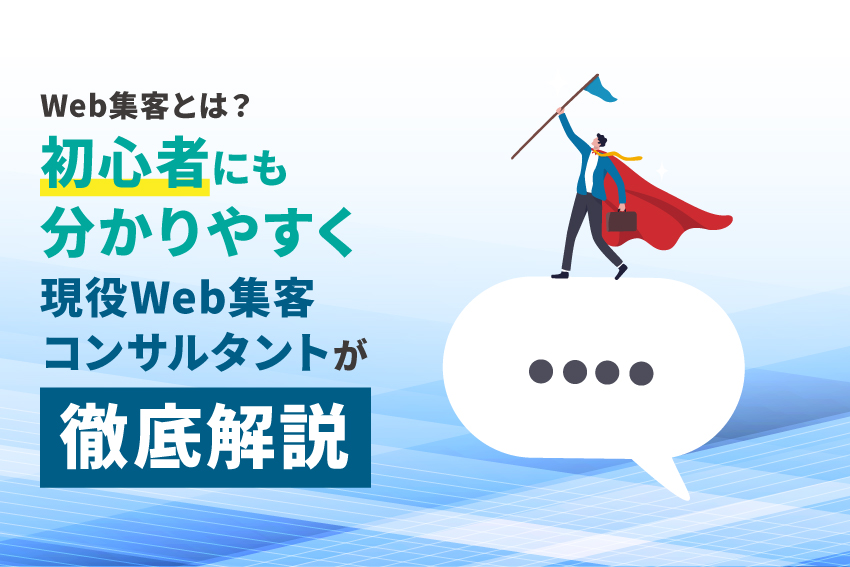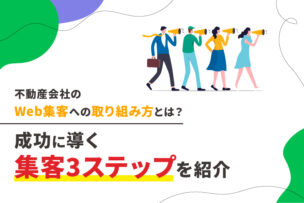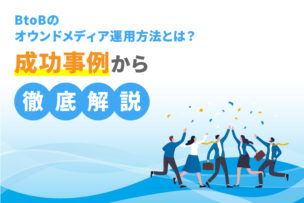記事の監修

Web集客・マーケティングの専門家として、13年間にわたり厳格な基準と緻密な戦略をもって中小企業の成功を導く。
一時的な集客の手法に頼ることなく、中長期的な効果を持続させる本質的なWeb集客の構築に注力。
『恵ある集客を。』をスローガンに掲げてクライアント様のサービスや商品の核心的な魅力を、的確にターゲットに伝えることを重視したWebサイト運用をサポート。
「Web集客こそ、これからのビジネスに残された大きな可能性」という期待感から、この記事にたどり着いたかもしれません。今回は、Web集客について徹底的に解説していきます。
「Web集客とは何か?」にはじまり、具体的な手法の紹介とそれぞれのメリット・デメリットについて紹介していきましょう。さらに、web集客に取り組むためには、どのような考え方が必要なのか?これまでのWeb集客とこれからのWeb集客の動向について、取り上げていきます。
「もっとWeb集客について知りたい」や「営業をWeb集客で展開したい」など、検討中の企業の営業担当にとって、この記事がWeb集客をはじめるターニングポイントとなることでしょう。
- Web集客について詳しく知りたい方
- Web集客の手法について知りたい方
- Web集客の取り組み方と成功事例を知りたい方
目次
Web集客とは?
それでは、今回の記事のテーマ、Web集客について解説していきます。Web集客とは、どのように定義されるでしょうか?それは、インターネットを活用した集客方法すべてを“Web集客”と定義されるのです。
具体的には、検索エンジンやソーシャルネットワークサービス(SNS)、動画投稿サイト、広告掲載などオンライン上でユーザーが接するあらゆる媒体に手掛けることができる集客手段になります。インターネットユーザーが、日常生活の中で利用しているサービスの中で、当然のようにオンライン決済が行われる活動のことです。
たとえば、日常生活の中で友人とチャットツール「LINE」を使って連絡を取る人は多いことでしょう。友人とのチャット会話で使う「スタンプ」を有料で手に入れた人も少なくありません。この有料スタンプを手に入れるためにオンライン決済する行動1つにしても、Web集客の原理がはたらきかけています。
LINEのスタンプを販売する先に何が見えてくるのでしょうか?今回は、Web集客の種類や基本的な知識について解説します。ぜひ、Web集客の目的やWeb集客と相性の良い業種、費用対効果などを参考にしてみてください。
Web集客の目的
Web集客を活用するほとんどの企業がインターネットによる獲得顧客の増加を目的としています。それは、スマートフォンの普及が拡大した現在のインターネット環境において、ますます優先される集客活動となるのです。
具体的には、インターネットを利用するユーザーに向けて次のようなユーザーの行動を目的とします。
- 自社の認知拡大
- 宣伝活動
- 資料請求の申し込み増加
- 会員登録の増加
- サービス利用の増加
- 顧客とのコミュニケーション
上記にあげたWeb集客の目的を事業活動として行う企業が増えているのです。
Web集客と相性の良い業種
Web集客の目的に向けた企業の事業活動に、インターネットの仕組みが後押しするようになります。中には、Web集客と相性の良い業種もあるでしょう。Web集客と相性の良い業種の特徴は、「個人的な調べものや悩み」を解決するキーワードと関連していることです。
特に、周囲の人におおやけに相談できないような個人的な内容の場合、インターネットでの需要が高くなります。具体的には、次のような業種です。
- 金融
- 美容関連
- 健康・医療関連
- 法律関連
- 旅行・観光関連
- 結婚・異性の相談
日常生活の中で、身近なお店に行って解決できること(スーパーやコンビニなど)はWeb集客との相性が良くありません。身近では解決できなくて、特殊であり、専門的な知識や技術をもっていることがWeb集客と相性の良い業種となります。
Web集客のメリット
Web集客は、リアルビジネス以上に費用対効果を高められるでしょう。その理由は、リアルビジネスの実店舗営業の場合は、顧客へのサービス提供に「人」、「時間」、「場所」に限りがあるからです。
たとえば、国内観光の旅行代理店に窓口の営業スタッフが5名在籍していて接客する場合、1度に5組以上のお客さんと商談はできません。しかし、Web集客の場合は、オンライン上に1人もスタッフを常駐させる必要もなく、集まってくるお客さんを接客していくのです。その費用対効果と言えば、接客人数に限度がないことがあげられます。
あわせて読みたい
Web集客の歴史
Web集客の歴史は、インターネットの普及とともに始まりました。1990年代より、ウェブサイトの制作や検索エンジンの最適化を中心として普及し始めました。2000年代に入ると、検索連動型広告が登場し、広告主はコンバージョンを目的にした集客が可能になりました。その後、SNSの登場やスマートフォンの普及により、ソーシャルメディア広告やモバイル広告へと流れが変わっています。
現在では、AI技術を活用した広告が注目されています。また、属性を絞った訴求となるコンテンツマーケティングやインフルエンサーマーケティングなど、多様な集客チャネルが登場してきました。このような動きから、Web集客はインターネットの進化とともに変わり続ける仕組みといえるでしょう。
Web集客の手法(種類)
Web集客に向いている業種が費用対効果の向上を目指して、オンライン上に施策を施すには、具体的に何に取り組めばよいのでしょうか?これより、Web集客の手法の種類を具体的に紹介していきます。
オーガニック検索からの集客(SEO対策)
Web集客の堅実な方法として、オーガニック検索による集客があげられるでしょう。オーガニック検索とは、ユーザーがインターネットで調べものをするときに、検索エンジン(Googleなど)の検索窓に「調べたい文言(キーワード)」を入力する行動のことです。
検索行動により、検索結果ページの上位に掲載されたWebサイトが「調べもの」の回答を満たせるクオリティを備えていることが必要になります。このオーガニック検索による検索結果ページの上位に表示されるための取り組み(施策)が、検索エンジン最適化(SEO対策)です。
SEO対策としては、外部施策となる良質な被リンクを受けることや検索ユーザーに役立つコンテンツを提供する施策があげられます。その取り組みの結果、オーガニック検索より流入してきたユーザーにとって、質が高く価値あるWebサイトとなるのです。
企業サイト
オーガニック検索からの流入先としては、具体的に企業サイトがあげられます。従来の企業サイト(コーポレートサイト)の場合、単なる「会社紹介」や「サービスの宣伝」が掲載された企業目線の内容でした。ところが、昨今の企業サイトはユーザーに役立つことを前提としたサイトデザインやコンテンツを提供するようになっています。
ブログ
また、企業サイトとは別にWebサイトのテーマを基準にしたブログの運営もオーガニック検索からの流入によるものです。ブログの場合は、記事コンテンツの追加更新により検索エンジンの評価を向上させていきます。
メリット
オーガニック検索からの流入を目的としたSEO対策のメリットは、次の通りです。
- 広告運用と比べると費用をかけないで低料金で施策ができる
- SEO対策により上位表示できた場合は中長期的に安定した集客ができる
- 検索キーワードからの流入のため成約率の高いユーザーが集まる
- 検索上位表示による自社の認知活動につながる
SEO対策のメリットをまとめると、「低予算で中長期的に安定した集客」となります。
デメリット
SEO対策には、デメリットもあります。企業の取り組みとしてSEO対策には、どのような問題点があるのでしょうか?
- 施策を施してから効果が出るまで時間も手間もかかる
- 検索キーワードの競合を上回るコンテンツの制作が必要
- 需要の高い検索キーワードには競合も多く施策の難易度も上がる
- 定期的に実施される検索エンジンの仕様の変更による順位変動
SEO対策のデメリットは、常に検索順位の変動を把握しながら、施策に手間と時間をかけていく地道な取り組みが必要な点です。
検索連動型広告による集客
次に検索連動型広告による集客について紹介しましょう。検索連動型広告とは、先ほどのオーガニック検索の検索結果ページにおいて、検索キーワードの検索結果にふさわしい内容のテキスト広告を広告枠に掲載する取り組みです。検索連動型広告のことをリスティング広告ともいいます。
メリット
検索連動型広告のメリットは次の通りです。
- 検索キーワードに需要のある成約されやすいユーザーに訴求できる
- 広告を即出稿、すぐに反応を確認できる
- SEO対策より即効性がある
検索連動型広告のメリットは、自社提供のサービスに高い価値を持つユーザーの検索結果ページに即日、広告を出稿でき、すぐに反応を確認できる即効性があげられます。
デメリット
検索連動型広告のデメリットは、出稿したい広告枠をオークション形式の入札制で金額が決まる点です。そのため、資金力のある大手企業との入札競争になると、予算オーバーのため、出稿を断念することもあります。
ディスプレイ広告等による集客
ディスプレイ広告をはじめとするリターゲティング広告などは、外部のWebサイトやWebアプリの広告枠に掲載される広告です。主に、画像広告や動画広告、テキスト広告などで掲載されます。ディスプレイ広告などは、広告枠にバナー表示されることが多いため、バナー広告とも呼ばれるのです。
メリット
ディスプレイ広告のメリットとして、自社の商品やサービスの認知拡大の効果が見込めることがあげられます。また、ディスプレイ広告などは検索行動を起こさない「何となくインターネットを閲覧しているユーザー」に向けた潜在的な訴求が可能です。
デメリット
ディスプレイ広告などのデメリットは、検索連動型広告と比べたら、成約率が高くない点になります。潜在顧客への認知活動にはなっても、購買行動をとる段階ではないユーザー層のためです。
記事広告・純広告による集客
続いて、記事広告や純広告の集客を見ていきましょう。記事広告とは、ポータルサイトなどで、いかにも広告と思われるようなバナー広告とちがって記事の1つとして認識される記事自体が広告となっている広告手法です。また、記事広告はタイアップ広告ともいわれます。
もう1つの純広告とは、ポータルサイトなどWebメディアの広告枠を購入して掲載する広告手法のことです。
メリット
記事広告や純広告のメリットは、掲載するポータルサイトなどメディア媒体のブランド効果を利用することができます。大手ポータルサイトに掲載されることにより、メディアの持つ既存の訪問者に向けた露出度の高さから、自社の信頼性向上や認知拡大につながることでしょう。
また、記事広告や純広告はターゲット属性を絞って掲載することが可能です。そのため、第3者の立場になった広告コンテンツの作成が必要になります。その理由は、ターゲットとなる属性に共感される広告コンテンツにより、潜在顧客への訴求効果が高まるからです。
デメリット
記事広告や純広告は、出稿費用が高めな点がデメリットとしてあげられます。どちらの広告も1つの広告枠で30万円~200万円ほどの費用が想定されるでしょう。
SNS経由の集客
次にSNS経由の集客について紹介しましょう。SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)は、インターネット上による人と人とがつながり、コミュニケーションをはかるツールとなります。
主なSNS
主なSNSは、FacebookやTwitter、Instagram、LINEなどです。取り上げた4つのSNSには、スマートフォンなどを購入した際に標準アプリとして使える点が利用者の多さを表しています。
メリット
SNSの集客によるメリットは、既存のファンの共感を高めることができる点です。また、SNSでつながっているファン(見込み客)に対して、信頼性が高まる投稿を続けることにより、強固な購入先としての関係を築くことができます。このように、SNSによる共感と信頼は、他の集客方法以上に高めることができるのです。
デメリット
SNS集客のデメリットは、SNSのシステム上、アカウントの凍結や停止などを受ける場合もあることでしょう。新規アカウントを作成して露出度を高めるために、何人ものユーザーにフォローをしたり、何人ものユーザーに友達申請を送ったりすることがスパム行為とみなされる場合もあるからです。
動画サイト経由の集客
続きまして、動画サイト経由の集客について案内しましょう。動作サイトとは、YouTubeのような動画投稿サイトのことです。動画投稿サイトは、Web集客の中でも閲覧ユーザーの意識を引き寄せる効果があります。
その理由は、動画という特性が、視覚だけではなく、聴覚や次に展開される動きなどに意識を誘導できるからです。特に、YouTube動画はWebサイトとの相性もよく、YouTube動画チャンネル内で、興味を持った見込み客を自社のWebサイトに誘導するパターンも多くなります。
メリット
動画サイト経由での集客のメリットは、Webサイトやテキスト広告のような文字で伝える訴求よりも短時間で濃く伝えることができる点です。また、投稿された動画に興味を持ったユーザーは、自分のアカウントのSNS上で拡散していくこともあります。つまり、動画サイトによる集客は広告以上の認知拡大効果を期待できるのです。
デメリット
動画投稿サイトの集客のデメリットは、動画コンテンツの制作に時間や手間がかかる点になります。自社に動画制作に長けているスタッフがいなければ、動画制作会社に撮影や編集を依頼することもあるでしょう。しかし、動画制作にかかるコストは1つの動画を制作するだけで100,000円以上かかることが考えられます。動画のクォリティを求めたらなおさらのことです。
外部メディア経由の集客
次に、外部メディア経由での集客を案内します。外部メディアとは、自社のWebサイト以外の関連サービスの外部企業のWebサイトや、個人ブログ、企業ブログなど他のメディア経由からの集客のことです。純広告と仕組みが似ている点がありますが、広告の掲載ではなく、外部メディアに関連リンクとしてリンクを貼ってもらう方法になります。
メリット
外部メディアによる集客のメリットは、広告運用とちがい、高い費用が発生しない点です。BtoBでの取引のある企業同士ならば、無償で関連リンクの設置を受けてくれる場合もあります。
デメリット
外部メディアによる集客のデメリットは、広告の出稿のような仕組みがないことです。そのため、相手先のメディアの運営状況次第でリンクを外されたり、リンクアドレスを間違えたりされても修正依頼を頼みづらくなります。
メルマガ紹介による集客
続いて、メルマガ(メールマガジン)紹介による集客について、案内しましょう。メルマガ紹介は、無料と有料の2通りがあります。読者数を保持するメルマガ媒体に無料で掲載してもらう場合、コストがかからない集客になるでしょう。
有料の場合は、メルマガ広告としてメルマガの広告枠料金を支払うことにより掲載されます。後者の有料の場合は、自社のビジネスに関連した内容のメルマガに掲載されることが必要です。
メリット
メルマガ紹介によるメリットは、検索エンジンのルールに沿う必要がない点です。検索エンジン上で評価されるWebサイトは、検索エンジンの評価基準をクリアしています。一方、メルマガの場合、配信者の売り込みなどプッシュ型の訴求ができるのです。
したがって、メルマガ配信者と読者の信頼関係ができあがっている媒体の場合、関連情報として紹介されるだけでも成約につながる訴求効果が高くなるでしょう。
デメリット
メルマガによる紹介は、場合によってメールが開かれないことも想定されます。そのため、有料のメルマガ広告だとしても、開封率が低ければ読んでもらえないことになるのです。特に、モバイル端末で設定する迷惑メールフィルタによりスパムメールと判断されたら、ユーザーに届くことがなくなります。
アフィリエイト広告からの集客
次は、アフィリエイト広告を活用した集客を紹介しましょう。アフィリエイト広告とは、成果報酬型の外部媒体を活用した広告の運用です。
アフィリエイト広告の仕組みは、広告の掲載を依頼する広告主と広告を掲載するアフィリエイター(メディア運営者)を仲介するASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)が管理運営していきます。
アフィリエイトは、広告を掲載したメディア経由により成果発生が発生した場合、アフィリエイターに報酬(紹介料)を支払う仕組みです。
メリット
アフィリエイト広告のメリットは、アフィリエイターが成果を出さなければ報酬を支払う必要がありません。クリック課金型の広告とちがって成果発生なので、無駄な費用がかからないのです。
デメリット
アフィリエイト広告のデメリットは、メディア運営者が成果獲得のために、過剰な訴求をすることも考えられます。特に、アフィリエイターの紹介は、誇大広告になりがちなので広告掲載において、ルールを決める必要があるでしょう。
直接訪問集客
直接訪問客とは、テレビやスマホのQRコードからのアクセスやブックマーク登録からアクセスしてくるユーザーです。または、名刺やチラシ、新聞などオフラインにおいて、URLを知りアクセスしてくる場合もふくみます。
メリット
直接訪問してくるユーザーの中でも、ブックマーク登録されたユーザーの場合は、安定した定着顧客になる可能性が高いです。継続的な関係を保てる点がメリットとなります。
デメリット
面識のない他人のWebサイトをブックマーク登録したり、QRコードを読み取ってWebサイトに訪問したりするようなコンテンツを用意することは簡単ではありません。したがって、直接訪問されるようなWebサイトに成長させるまでに時間と労力が必要になります。
業種別Web集客のコツ

Web集客は、業種によって集客方法が異なるのでしょうか。ここでは、業種別Web集客のコツを解説します。
飲食店の場合
飲食店のWeb集客は、実際に店舗へと足を運んでもらう必要があるため、見込み客に対して来店する理由を高める必要があります。たとえば、大手グルメサイトなどの露出度を活用する方法もあるでしょう。飲食店の場合は、「地域名+ジャンル」キーワードで検索されることも多く、とくにランチタイムなどは限られた時間の中でニーズのある顧客とお店をマッチングさせなければなりません。よほどの希少性のある人気店ではない限り、そのときの需要を取りこぼさない具体的な特徴が求められます。
また、飲食店の場合は顧客が自らSNSで投稿し、話題になることも考えられます。その動きを活用した「SNS投稿につきクーポンを贈呈」など、顧客行動に便乗した施策も有効です。
美容室の場合
美容室のWeb集客は、ビジュアル重視の特徴からもWebサイトのデザイン性などが求められます。美容室は、美容師の技術などが特徴になります。他には、具体的な髪の毛の悩みなどに特化したサービスは、パーソナライズ性の高いWeb集客向けと考えられるでしょう。
整体・マッサージなどの場合
整体院やマッサージなどは、カラダの痛みに対しての情報入手と相性の良さがあります。たとえば、腰の痛みや膝の痛みなどです。部分的な痛みに関しても、どのように痛むのか症状を具体化することで、より緊急性の高いユーザーとつながる可能性があるでしょう。
宿泊施設の場合
宿泊施設の場合は、大手宿泊ポータルサイトへの参画も方法のひとつです。ただし、宿泊予約したユーザーは宿泊施設の公式ページでサービス詳細を確認することも考えられます。その際、公式ホームページのコンテンツが充実していないと、顧客のリピーター化を見込めないかもしれません。コンテンツの充実では、口コミや画像を多く使うことが重要です。
リフォーム業者の場合
新築ではなく、いまある物件をリフォームして使う人も少なくありません。リフォーム業者の場合は、単に「家を改築できる」だけではなく、「築何年経過した浴室をこのようにリフォームした」というビフォーアフター画像や動画コンテンツが効果的です。新築の場合の費用とリフォームの場合の費用とで比較できるコンテンツもあれば、検討中の見込み客の判断材料にもなるでしょう。
塾・習い事の場合
塾や習い事の場合、学習塾のWeb集客では過去の具体的な進学実績などを掲示することで検討中のユーザーが目安として判断できます。それは、ピアノやプログラミング教室なども同じことで、受講生が「どのような未来を実現できたか」という訴求ポイントではないでしょうか。習うことによるベネフィットが明確であれば、同じような未来を描いている見込み客を集めやすくなります。
あわせて読みたい
Web集客方法を3つに分類できる
いままで紹介してきたWeb集客の手法に共通することは、すべて媒体(メディア)を経由している点です。そして、Web集客におけるメディアは、3つに分類することができます。
オウンドメディア
オウンドメディアとは、企業が自社で運営するメディアのことです。具体的には、次のような媒体があげられます。
- Webサイト
- ブログなど
効果
オウンドメディアには、次の効果を期待できます。
- ブランディング
- 情報発信の自由度
- ユーザーからの共感
- 検索エンジンの評価
- 集客コストの削減
●ブランディング
オウンドメディアは、企業の情報発信で、ビジネスの存在や製品・サービスの魅力をより多くの人々に知ってもらえるようになります。ブランディングは、競合他社との差別化要因を明確にできます。その差別化される要因は、自社の強みでもあり他社にない特徴です。早い段階で自社の強みを明確にすることでブランディングの構築にもなるでしょう。ブランディングは、認知拡大のために欠かせない施策と考えられます。
●情報発信の自由度
オウンドメディアは、コンテンツの自由度が高いメディアです。自分で作成したコンテンツを自由に発信できるため、情報発信の自由度が高さが特徴となります。自社に関する情報や、業界のトピックなどを自由に発信できるでしょう。
●ユーザーからの共感
オウンドメディアは、ユーザーとのコミュニケーションが取りやすく共感を生み出せるメディアです。企業がSNSアカウントと連携することで、コメントやDMなどを通じて、ユーザーからの質問や意見を直接受け取ることができます。
●検索エンジンの評価
オウンドメディアは、検索エンジンから評価を受ければ上位表示が可能です。企業にとっては、メディアの運営がSEO対策にもつながります。その要因は、検索エンジン大手Googleの評価は、コンテンツの品質にあることと関係しています。ユーザーにとって役立つコンテンツであることは、検索エンジンの評価にもつながると考えられるでしょう。
●集客コストの削減
オウンドメディアの運用は、集客コストの削減にもなります。PRや広告などの集客は、その都度コストの掛かる施策です。企業はメディアを使って情報発信することで、ユーザーとの直接的な接触が増えます。その結果、信頼度も高まりコストを抑えながら集客効果を上げることが期待できます。
注意点
オウンドメディアは、自由度が高いメディアでもあります。そのため、メディア構築のルールを決めておかないと低品質なコンテンツを発信するかもしれません。常にユーザー目線であることを意識して、信頼性の高い情報発信を心がけることが重要です。
また、オウンドメディアの運用では著作権に配慮する必要があります。他人の著作物を無断で使用したり、盗用したりすることは避けましょう。いわゆるオリジナルコンテンツを作ることが求められます。さらに、オウンドメディアを運用する場合は、定期的な更新が必要です。更新頻度が低いと、訪問者数が減少することも考えられます。定期的な更新を心がけ、訪問者にとって価値のある情報を提供することが大切です。
アーンドメディア
アーンドメディアとは、基本的に無料で活用するSNSや無料ブログサービスなどの拡散されるメディアです。具体的には、次のような媒体になります。
- YouTube
- Amebaブログをはじめとする無料ブログサービスなど
効果
アーンドメディアの効果は、消費者自身が商品やサービスについて投稿する点にあります。消費者自らが発信する情報となるため、リアルな声や意見が共有されるでしょう。消費者からの情報は、商品やサービスに興味を持つユーザーにとって有益な情報となります。
また、アーンドメディアによる情報発信は、広告に比べてコストを抑えられます。口コミや評判は、信頼性が高く、消費者の興味を引きやすいため、認知度の向上も期待できるでしょう。
アーンドメディアは、SNS上で拡散される可能性も秘めています。SNSで拡散できれば、多くのユーザーにリーチすることも可能です。拡散効果により、認知度の向上や購買意欲の喚起など、あらゆる効果を期待できます。
注意点
アーンドメディアは、消費者自身が投稿するため、企業側が情報発信をコントロールできません。そのため、ネガティブな情報を発信された場合はその情報を制御できなくなる可能性があります。そのため、企業側は、消費者からの意見を真摯に受け止め、迅速かつ適切な対応で取り組む必要があります。
ペイドメディア
ペイドメディアとは、費用をかけて認知拡大を目指す広告などの掲載をするメディアのことです。具体的には、次のような媒体になるでしょう。
- 純広告
- メルマガ広告
- リスティング広告
- ディスプレイ広告など
効果
ペイドメディアは、広告主がターゲットとする層に対してメディア広告を掲載する手法です。ターゲット層への興味関心の高いアプローチが容易になります。企業は、広告掲載媒体を選択することで、自社商品やサービスに興味を持ちそうなユーザーにアプローチできる点が集客効果として考えられます。
注意点
ペイドメディアの注意点は、適切な広告掲載媒体の選定が効果を左右する点です。そのため、ターゲット層に合った媒体を選ぶ必要があります。また、広告クリエイティブの設計にも注意が必要です。適切なコピーと画像を使用することが、広告のクリック率やコンバージョン率を向上に影響します。
「広告のデザインや文章が媒体の雰囲気に合っているか」や「消費者が興味を持ちそうな情報が含まれているか」などを出稿前にチェックしなければなりません。
重要な部分としては、ペイドメディアが広告料金を支払うことで成立する施策であることです。そのため、適切な広告予算を設定しなければなりません。適切な予算設定により、目的に応じた効果的な広告出稿を運用できます。
Web集客の課題
それでは、今後のWeb集客における課題について見ていきましょう。オンライン需要が高まる時代背景から、Web集客に参入する企業も増加している傾向です。そのような状況から、次のようなWeb集客の課題が取り上げられます。
目的が明確でないと継続が難しい
Web集客は、1度行えば持続できるほど簡単な施策ではありません。ただし、Web集客による効果を引き出せるようになれば費用対効果は高くなります。自社のWeb上の施策をそのような位置まで到達させるまでの時間や労力が必要なのです。
つまり、Web集客に取り組むうえでの目的を明確にしておかないと、途中で挫折してしまうことも考えられます。Web集客で一番大事なことは継続だからです。
有料広告の費用高騰
従来ならば、時間をかけられない企業などがWeb集客をする際に、有料広告を活用してきました。しかし、有料広告の「時短効果」に価値を見出した大手企業などが資金力を投入するようになったのです。
したがって、有料広告は即効で結果を得られるけれど、入札制の広告や広告需要の増加などにより、費用が高騰している現状になります。
競合と差別化するコンテンツ作成
このように、Web媒体自体が乱立している現状は否定できません。そのため、企業は同じようなサービスを同じような切り口で訴求しても顧客に伝わらないのです。Web集客は、乱立する競合と差別化をはかることが最も重要な取り組みとなります。
そのために必要なことが、競合と差別化できるコンテンツの作成なのです。
あわせて読みたい
Web集客に取り組むための思考
Web集客における課題をふまえて、今後はどのように考えて取り組むべきなのでしょうか?ここでは、いままでのWeb集客の思考とこれから必要になる思考を取り上げてみます。
いままでの考え方
従来までのWeb集客は、長期目線でじっくり取り組むSEO対策による検索上位表示と短期目線ですぐに効果を得る広告によるものに分類されていました。
広告によるWeb集客(短期戦略)
広告によるWeb集客の中でもリスティング広告は、SEO対策と対照的な活用となります。リスティング広告を活用する企業の場合、「すぐに反応を知りたい」「この検索ワードで売れるか知りたい」という即効性を求めた短期戦略として活用されてきたのです。
SEO対策によるWeb集客(長期戦略)
逆に、SEO対策を施す企業の場合は、効果の表れを半年後から1年後に想定して、コツコツと検索結果ページの上位表示を目標に取り組みを継続していきます。長期戦略のため、目的や計画があいまいだと途中で挫折してしまうこともあったのです。
これからのWeb集客に必要な思考
このように、いままでのWeb集客の考え方は“長期目線”か“短期目線”のどちらかで取り組むか?選んでいました。しかし、インターネット需要の高まる環境とWeb集客に参入する企業の増加から、長期や短期と戦略を分けて取り組むだけでは生き残れなくなってきたのです。
短期戦略と長期戦略を織り交ぜて実行する
そこで、重要になるWeb集客の考え方は「短期戦略も長期戦略も両方を織り交ぜて実行するのが大切」となります。Web集客は、短期戦略の現状分析の即効性と長期戦略の安定した持続性を両方兼ね備えた考え方により、強固な集客のための媒体を作り上げていくのです。
差別化戦略による競合対策と強みの訴求
さらに、Web集客における短期と長期の戦略を織り交ぜながら、増加する競合と差別化を図れる戦略のために、自社の強みを訴求していくことに注力することが必要になります。そのためには、次のような点を重視することが必要です。
●ターゲティングによる施策
これからのWeb集客は、具体的なターゲットを明確にして、ターゲットに向けたコンテンツの制作や情報の発信方法で取り組むことがあげられます。
●自社の強みの訴求
ターゲットを設定する際は、自社の強みになる部分に強い価値観を持つ特定の個人にまで絞り込む必要があるでしょう。ターゲットと自社の強み部分がかみ合うことにより、有効な訴求が展開できます。さらに、自社の強み部分こそが競合との差別化につながるのです。
●施策にかかるリソース事前確認
さらに、競合と差別化を図るためにリソース状態を確認しましょう。人的リソースや時間的コストなどを総合した予算を組んで、どの程度のコストを施策にかけられるのか?事前に確認するのです。
●顧客の行動と効果測定による精度向上
競合と差別化を図るための施策を実行していくうえで、日々の分析が必要になります。それは、自社が施すWeb集客に対して、「顧客がどのように行動を起こしているのか?」など解析ツールや効果測定などで分析をしながら精度を高めていくのです。
Web集客の取り組み方

それでは、Web集客の取り組み方について解説します。手順としては、以下のように進めていきます。
目標を決める
Web集客は、目標を決めることが大事です。目標を決めずに進めてしまうと異なる方向へ進んでしまう可能性もあります。小さな目標の積み重ねで進めていくことを念頭におきましょう。Web集客の目標を設定する際は、小さな目標をKPIとして段階ごとに設定します。最初の目標をクリアしたら次の目標をクリアするイメージで進めます。
たとえば、個人や企業がWebサイトを持たなくても無料で自分のブログを持ち運営できるサービス「note」があります。Noteでは、初心者のブロガーが継続しやすい機能を満載しています。それは、何らかの小さな達成ごとに付与されるバッジです。
初めての投稿が完了するとバッジが付与されたり、何日か連続で投稿するとバッジが付与されたりします。このような小さな目標達成の積み重ねが初心者の継続を促すモチベーションへとなっていきます。
例にあげたnoteのような小さな目標を積み重ねて大きな目標へと近づいていく設定が実現性を向上するでしょう。
ペルソナを設定する
目標を設定したら、具体的なターゲットを明確にします。そのターゲットは、ペルソナ設定により、架空の個人を想定します。ターゲットを個人レベルまで絞り込むことで、具体的な訴求を実現できます。ペルソナの設定は、単なる属性の設定ではありません。
自社ビジネスに対して高い価値を持つターゲット層を個人レベルまで設定します。それは、年齢や性別だけではなく、居住地から社会的な身分、趣味趣向まで多岐にわたります。詳細に設定することで、ペルソナを対象にした訴求も具体的になるでしょう。
態度変容段階ごとにターゲット層を設定する
Web集客では、設定したペルソナの購買心理状態を意識した施策を施します。その施策では、態度変容を段階ごとに設定することが重要です。態度変容の段階ごとにターゲット層の確度が異なるため、その段階に適したコンテンツを用意しましょう。
カスタマージャーニーマップで視覚化する
態度変容の段階ごとの設定は、カスタマージャーニーマップで視覚化します。カスタマージャーニーとは、顧客体験を視覚化したものです。その視覚化した顧客心理をマップ上にあらわし施策を施します。
カスタマージャーニーマップは、非認知状態の潜在顧客が興味関心を抱き、見込み度を高めていくにつれ購買層へと変容していく状況を見える化できます。企業のWeb担当者だけではなく、組織で顧客の態度変容を理解するうえで重要な指標となるでしょう。
施策をPDCAで回す
Web集客では、ここまで設定した施策を実際に実行してみることが重要です。実行した結果、どこかの段階で想定外の結果となることも考えられます。その部分をそのままにしておかないで、修正し新たな仮説のもとで再度実行することが重要です。このように、施策をPDCAで回すことがWeb集客の精度を向上させます。
あわせて読みたい
Web集客の成功パターンとは
先ほどの競合と差別化を図る強みの訴求を実行するWeb集客とは、コンテンツマーケティングやオウンドメディアを活用する手法になります。どのように取り組みことが成功パターンとなるのでしょうか?
短期戦略で顕在顧客を獲得
オウンドメディアは、長期戦略のWeb集客です。通常は、メディアにアクセスが集まりだすまでに時間がかかります。しかし、Web集客での成功パターンでは、オウンドメディアとなる媒体の需要を短期戦略で反応を見ていくのです。
その方法として、検索連動型広告を活用していきます。オウンドメディアが検索エンジンから評価を受ける前に顕在顧客を集めることにもなるでしょう。
SEO対策で潜在層へ訴求
さらに、短期戦略と同時進行でSEO対策も進めていきます。広告経由での流入については、ユーザーの行動パターンを分析して、さらに流入が想定されるキーワードを展開していくのです。その分析結果により、需要のある検索キーワードにより、SEO対策を施していきます。この噛み合わせにより、未知なる潜在層への訴求となるでしょう。
SNS利用で流入経路拡大
また、広告戦略とSEO対策に取り掛かりながら、SNSを利用した流入経路の拡大も同時進行していきます。検索エンジンだけではなく、Web上で分散されるユーザーが集まる場所に流入経路を広げていくイメージです。
このように、これからのWeb集客は短期や長期の施策を同時に展開していくことが成功パターンとなります。
Web集客に成功した事例
それでは、実際にWeb集客に成功した企業の事例を3つ紹介していきましょう。
ライオン
ライオン株式会社(LION)は、自社Webサイト「LIONウェルネスダイレクト」により、Webサイトを通じた顧客とのコミュニケーションをはかることに成功しました。ライオンの成果は、従来のWebサイトを改善して10年で売上が1700倍まで増加したことです。
カゴメ
カゴメでは、「みんなとカゴメで作るコミュニティ」というユーザーとつながるコミュニティサイトを運営しています。カゴメの成功パターンは、敷居の高かった顧客とのコミュニケーションをコミュニティメディアにより実現しました。
その結果、顧客参加型のオムライス検定やファン株主、ユーザーに選ばれたサウンドロゴなど、顧客とつながりを持った事業展開のヒントを得られるようになったのです。カゴメは、Webメディアを企画する前と比べて、売上も3.8倍に向上しています。
ニシカワ
布団・寝具のニシカワは、Webサイトを戦略的に展開したことにより、離脱率を抑えることができました。特に購入顧客の行動分析に取り組み、コンバージョンにつながる顧客の特性を明確にできたことが成功の要因です。
結果的にWebサイトからのコンバージョンが1.8倍に増加しています。この事例では、Web集客の顧客行動の分析によるデータを活用して施策したことが成功につながったのです。
あわせて読みたい
Web集客を外注した場合
先ほど紹介した3つの企業の成功パターンから、コンテンツマーケティングやオウンドメディアの有効性を理解されたでしょうか?Web集客は、広告運用とSEO対策を同じように重視しながら、活用していくことが大切です。ただし、これからのWeb集客を自社で内製していくことは容易ではありません。
そのため、Web集客は専門家に外注することも本業に取り組み時間を確保した手段となるでしょう。
専門業者の知識と経験を反映できる
Web集客を外注に依頼した場合のメリットについて、案内します。それは、Web集客の専門業者の知識と経験が自社のWeb集客に反映されることです。
専門業者がプロの目線から、「どのように改善したほうがいいのか」を実際の経験をふまえた判断で知ることができます。Web集客は、自社のリソースを整える前に、専門業者への相談から始めてみたらいかがでしょうか。最終的には、専門家への依頼が回り道のない効率的な道でビジネスを進める方法と考えられます。
まとめ
今回は、Web集客の定義からはじまり、それぞれの集客方法について解説してきました。さらに、これからのWeb集客に必要な考え方は、それぞれの集客方法の特徴を生かした同時に行うことが大切です。ここで紹介したWeb集客の種類は、時代の変化とともに形を変えていくことでしょう。しかし、集客の本質部分は、変わりません。それは、常に相手を意識した施策であることです。
商品やサービスを提供する相手を理解しないで満足させられません。Web集客では、その商品やサービスを利用して満足してもらえることを成果に実施します。そのため、事前準備に手間や時間が掛かることもあるでしょう。しかし、その準備を乗り越えれば、費用対効果の高い運用を実現できると考えられます。そこでポイントとなるのが、自社の強みを見つけることです。自社の強みを明確にできれば、競合他社との差別化をはかれます。
今後も加速していくことが予想されるWeb需要の高さから、参入する競合との差別化こそがWeb集客で生き残れる取り組みとなるでしょう。ぜひ、役立ててみてください。
- Web集客の手法は検索エンジン、SNS、動画投稿サイト、広告掲載など多岐にわたる
- Web集客の目的は自社の認知拡大、資料請求の申し込み・会員登録・サービス利用の増加、顧客とのコミュニケーション
- Web集客はリアルビジネスよりも高い費用対効果を実現できる
あわせて読みたい
Web集客に関するよくあるご質問
最後によくあるご質問をいくつかご紹介致します。
みなさまのWeb集客にお役に立てば幸いです。
その他、ご不明な点がございましたら以下のリンクよりお気軽にご相談下さいませ。
無料オンライン相談はこちらからどうぞ。
Q
Web集客とは何ですか?Web
A
Web集客とは、インターネットを使用して顧客やリードを獲得する手法や戦略を指します。Webサイト、ソーシャルメディア、メールマーケティングなどのオンラインツールを活用して行われます。
Q
Web集客の主な方法は何ですか?
A
SEO(検索エンジン最適化)、PPC広告(ペイ・パー・クリック)、コンテンツマーケティング、SNSマーケティング、メールマーケティングなどが主な方法です。
Q
SEOとは何ですか?
A
SEOは、Webサイトが検索エンジンの結果ページで上位に表示されるように最適化する技術や戦略のことを指します。
Q
PPC広告のメリットは何ですか?
A
PPC広告は、広告をクリックする度に広告料を支払う形式で、即時のトラフィックを獲得できる、ターゲット層を細かく設定できる、予算を設定しやすいなどのメリットがあります。
Q
SNSマーケティングの重要性は?
A
SNSは多くのユーザーが利用しているため、ブランドの認知度向上やコミュニケーションの場として非常に有効です。
Q
Web集客におけるコンテンツの役割は?
A
コンテンツは、ユーザーの関心を引き付け、信頼を築き、コンバージョンに繋げるための重要な要素です。
Q
メールマーケティングの効果的な使用方法は?
A
ターゲットとなるユーザーに合わせたカスタマイズされた内容の提供や、適切なタイミングでの送信、リストのセグメント化などが効果的です。
Q
Web集客のためのランディングページのポイントは?
A
明確なコールトゥアクション、ユーザーの関心を引くデザイン、信頼性を高める要素(例: 口コミやレビュー)の導入などがポイントです。
Q
Web集客のROIを測定する方法は?
A
Web解析ツールを使用して、コンバージョン率、クリック数、訪問者数などのKPIを定期的に測定・分析します。
Q
Web集客戦略を成功させるためのコツは?
A
ターゲットとなる顧客のニーズを正確に理解し、それに合わせたコンテンツやキャンペーンを実施すること、また、データを基にした継続的な最適化が鍵です。