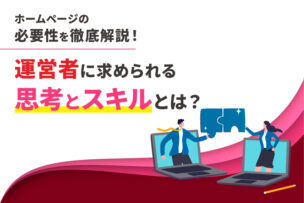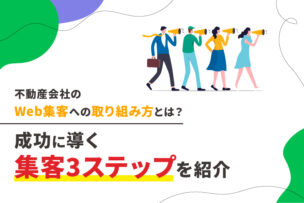記事の監修

Web集客・マーケティングの専門家として、13年間にわたり厳格な基準と緻密な戦略をもって中小企業の成功を導く。
一時的な集客の手法に頼ることなく、中長期的な効果を持続させる本質的なWeb集客の構築に注力。
『恵ある集客を。』をスローガンに掲げてクライアント様のサービスや商品の核心的な魅力を、的確にターゲットに伝えることを重視したWebサイト運用をサポート。
作って公開したままで放置状態のホームページを「そろそろリニューアルしないと」などと、何となく考えていませんか?
おそらく、ホームページをリニューアルすることが、「だいぶ前に作ったから見飽きてきた」「ホームページ経由での問い合わせがない」「競合のホームページがスタイリッシュで魅力的になっている」というような理由になっていることでしょう。
ホームページをとりまく環境はめまぐるしく変化しています。それは、消費者心理の多様化や、スマホ保有率の増加による情報入手の手軽さが影響しています。ホームページは、より具体的な伝え方をしなければ埋もれてしまうかもしれません。そのため、時代の変化とともに「伝えるため」のリニューアルが必要になってくるのです。
この記事では、ホームページのリニューアルを考えているWeb担当者が「失敗しない為にどうすべきか?」という点に着目します。ホームページのリニューアルに目的と目標をしっかりと定めておくことが大切です。
さらに、ホームページのリニューアルで必要なステップと運用面の再検討まで紹介していきましょう。Web担当でホームページのリニューアルが課題の方は、ぜひ、取り組みの参考にしてみてください。
はじめにホームページのリニューアルの概要から進め方までを簡単に説明致します。
- ホームページのリニューアルについて知りたい方
- ホームページのリニューアルの効果とメリットについて知りたい方
- ホームページのリニューアルの具体的な進め方を知りたい方
目次
ホームページのリニューアルとは?
ホームページのリニューアルとは、既存のウェブサイトを技術的、視覚的、または機能的な側面で一新するプロセスを指します。リニューアルは企業や組織が市場競争力を維持し、ユーザーエクスペリエンスを向上させるために不可欠な要素です。目的は多岐にわたり、デザインの近代化、UX(ユーザーエクスペリエンス)の向上、またはSEO(検索エンジン最適化)対策などがあります。
リニューアルの前に考慮すべきポイント
リニューアルに取り掛かる前に、いくつかの重要な点を検討する必要があります。まずは、現状分析をしっかりと行いましょう。アクセス数やコンバージョン率をはじめとしたKPI(重要業績評価指標)を理解することが重要です。次に、リニューアルの目的を明確に設定します。集客の向上を目指すのか、ブランドイメージの強化が目的なのか。そして、予算と期間もきちんと設定しておく必要があります。
リニューアルのプロセスとステップ
ホームページリニューアルは、計画的に行う必要があります。プランニングフェーズで全体の方向性を設定し、デザインとコンテンツの制作に進むのが一般的です。テストとフィードバックを経て、最終的に新しいホームページをローンチします。この過程では、プロジェクトの目的やタイムライン、予算に照らし合わせて各ステップを慎重に進める必要があります。
リニューアル後のフォローアップ
リニューアル後は、パフォーマンスの測定と改善が継続的に必要です。Google Analyticsなどのツールを用いて、新しいホームページがどれだけの成果を上げているのかを評価します。また、ユーザーフィードバックを積極的に収集し、必要な修正を行っていくことが重要です。
リニューアルの成功事例と失敗事例
成功したホームページリニューアルの事例は多く、その成功の要因は上記で説明したような明確な目的設定と徹底した計画にあります。一方で、失敗するリニューアルも少なくありません。成功するためには、目的に応じた戦略と、その実行、そして継続的な改善が必要です。
いかがでしょうか。おおよそホームページのリニューアルについてはご理解頂けかと思いますので、
次は各項目の詳細を説明します。
ホームページのリニューアルにおける大事な考え方
冒頭で取り上げたホームページのリニューアルを「何となく周りがそのような雰囲気だから」というぼやけた理由だけで考えるのではなくて、明確な考え方を持つ必要があります。明確な考え方とは、次の2点を明らかにすることです。
- 目的は何か
- 目標はどこにあるか
ホームページのリニューアルは、具体的な目的を持って、どんな目標を設定するかが大切です。
ホームページをリニューアルする目的は何か?
ホームページをリニューアルするにあたって、「リニューアル後に求める状態」を明確にしておきましょう。
目的は明確にする必要がある
目的を明確にしておかなければ、ホームページのリニューアルを進めていく段階で、本来の目的とはずれた方向に進んでしまうことが考えられるからです。
たとえば、「問い合わせを増やしたい」ことが目的なのに、ホームページのヘッダーに使うロゴマーク作成に時間ばかりをとられてしまっていれば、一向に「問い合わせ」を増やすことができません。このような目的と違うことに時間をとられないためにも、目的は明確にしなければならないのです。
ホームページにより何がしたいのか?
また、目的を明確にするためには「ホームページにより何がしたいのか?」を運営者自身が再確認する必要があります。「売上を伸ばしたいのか」、「訪問者を増やしたいのか」、「リピーターになってもらいたいのか」など方向性を明確にすることです。
誰に向けた情報発信なのか?
さらに、ホームページのリニューアルにあたって、「誰に向けた情報発信となるのか?」という点を再認識しておきましょう。具体的には、「このような属性の人に伝えたい情報発信」となることを目的の方向性に定めていくのです。
ホームページのリニューアルに向けた目標は?
次にホームページのリニューアルに向けた目標について見ていきます。目的が明確になれば、より具体的な目標を立てることができるのです。
リニューアルの目標を具体的に設定する
ホームページをリニューアルする目的が「売上を伸ばす」ことであれば、現状の売上からどの程度の伸び率を求めていくのか?を具体的に設定することになります。
目標が具体的でないと、目標達成までのプロセス段階で断念してしまうことが考えられるでしょう。そのため、リニューアルの目標はできる限り具体性を持たせることが望まれます。
あわせて読みたい
よくあるリニューアルのタイミング
それでは、ホームページをリニューアルするタイミングでよくある状況を紹介しましょう。
デザイン面に古さを感じたとき
最もよくあるタイミングは、ホームページのデザインに古さを感じたときです。店舗と同じでホームページもデザインを変えないままだと、他のサイトと比べて古く感じることも考えられます。
機能面の改善が必要なとき
ホームページ制作ソフトやテンプレートなどの機能が、現状のWeb表示に対応できなくなっていたり、エラーを出したりするようになった時も挙げられるでしょう。さらに、ホームページ内のジャンル分類が複雑になることで、リニューアルが必要になる場合もあります。
老朽化したシステム構成による作業過多
また、古くなったホームページ作成のシステム構成では、作業が増え続けていることに限界を感じることもあるでしょう。たとえば、手打ちのコーディングが必要なシステムでは、ページを増やすための手作業も増えてくるからです。
このような老朽化したシステム構成は、レガシーシステムと呼ばれ将来的にOSの終了などで使えなくなることも考えられます。デジタル化が騒がれている昨今では、古いシステムの活用がリスクを大きくすることも考えられるため、作業過多以上に再考が必要です。
ホームページの構造自体が複雑化しているとき
リニューアルが必要なときは、ホームページの複雑な構造も要因として考えられます。よくある複雑な構造は、最初に構成を階層構造で作成していないため、後から追加した要素と従来の要素との関係性がおかしくなってしまうパターンです。
当初からあるホームページでは、すでにあるカテゴリ傘下に複数の記事を投入していることも考えられます。そこに新しく記事を追加していくうえで階層構造がおかしくなる可能性もあるでしょう。たとえば、ホームページのメインテーマが「大阪のプログラミングスクール」の場合、すでにあるカテゴリの中に、「全国のプログラミングスクール」を追加したとします。
従来のホームページ上で大阪にあるプログラミングスクールを紹介しているのに、加えて全国のプログラミングスクールを紹介することで構造上、全国の方が広くなるため複雑な構造になることが考えられるからです。サイトの構造は階層をロジカルに整理することから見直しましょう。
お問い合わせ・購入数が減少しているとき
ホームページをリニューアルする目的は、お問い合わせや購入が減少している状況で判断することが多いことでしょう。ビジネス目的で公開しているサイトが本来の目的を果たしていなければ改善が必要です。販売が目的となるECサイトであればなおさらのことでしょう。
ホームページは、自社の営業ツールとして24時間365日無人で対応する集客を実行します。そのような役割を持っているホームページがサイトに訪問してきた見込み客の行動心理を変容できなければリニューアルが優先課題となります。
外部要因による不具合が生じているとき
外部要因となるブラウザのバージョンアップに対応できなくなって不具合を起こした場合もリニューアル時期の判断となります。不具合は、ブラウザだけではなくホームページのデータを格納しておくサーバ環境も関係します。適切なサーバ環境の見直しなどは、専門家の見解が必要です。
スマホに最適化されていない
ホームページをリニューアルするタイミングとして、最も重要に受け止められるのがスマートフォン表示に対応していないことです。スマートフォンからホームページを見たときに見にくければ検索エンジンの評価も下げてしまうでしょう。たとえば、文字が小さくて見にくいことや「問い合わせボタン」や「リンク」などが他のテキストに近すぎてクリックできないなどスマホユーザーを考慮したレイアウトでないと検索エンジンの評価にも影響します。
●デザイン
リニューアルのよくあるタイミングとして、競合他社のホームページのデザインが良くなっているときに、緊急性を感じることもあります。デザインが古いうえに情報を見つけにくい状態では、競合が選ばれてしまうことも考えられるからです。
ただし、ホームページのデザインは日々進化しているため、「これで大丈夫」という状態はありません。競合の多いジャンルでビジネスを展開している場合は、競合分析をはじめとする環境分析が必要です。
●表示速度
ホームページでは、トップページに動画コンテンツを挿入したり、動的なバナーや画像など装飾を施し過ぎて、表示速度に影響が出始めてくることも考えられます。ホームページは、URLをクリックしてからデバイスに表示されるまでのスピードが評価に影響します。
表示速度の遅いホームページでは、それだけで評価を落としてしまうかもしれません。そのため、ホームページのリニューアルを考えることもあります。
あわせて読みたい
ホームページのリニューアルによるメリットと効果
以上のように、ホームページをリニューアルするタイミングは、時代の流れによりテクノロジーも進化してくることにより訪れるのです。そのため、リニューアルは必要不可欠にもなります。では、ホームページをリニューアルした場合のメリットと効果を見ていきましょう。
リニューアルによるメリット
ホームページのリニューアルによるメリットは、次の3つがあげられます。
- ブランドイメージの向上
- ユーザービリティ向上
- コンテンツサービス品質向上
ブランドイメージの向上
ホームページのリニューアルにより、デザインが新しくなることによって閲覧者の好感度も上がることでしょう。そのため、企業のブランドイメージの向上にもつながります。
ユーザービリティ向上(機能面)
ホームページをリニューアルすることにより、最新の機能を導入することも可能です。特に、スマートフォン表示の最適化を実現することでユーザービリティの向上になります。そのため、ホームページのリニューアルは検索エンジンの評価を上げることになるのです。
コンテンツ構成の見直しによるサービス品質向上
ホームページの構成を重視しないで継続してきた場合、アクセスしてきた訪問者にとって、読みづらいコンテンツになっていたことでしょう。リニューアルによって、ホームページのコンテンツ構成を見直すことができます。
コンテンツ構成を一度、整理して新しく組み立てることで、ホームページを通したサービス品質の向上となるでしょう。
リニューアルによる集客効果
それでは、ホームページをリニューアルした場合の集客効果はどのように表れるのでしょうか?
検索エンジンに評価されて上位表示が期待できる
リニューアルしたホームページは、見た目的なデザインや表示速度、スマホ表示などユーザービリティも向上します。コンテンツの構成もわかりやすく知りされていれば検索エンジンに評価されるのです。
そのため、検索エンジンに評価されたホームページは上位表示されやすくなるでしょう。
スマホユーザーのアクセスが増える
さらに、スマートフォン表示に対応していれば、スマホユーザーのアクセスも増えてきます。昨今のWeb集客はモバイル端末からのアクセスが多いことから、見込み客の獲得に大きな期待が持てるのです。
あわせて読みたい
ホームページのリニューアルにかかる費用
では、ホームページのリニューアルにかかる費用について、見ていきましょう。ホームページのリニューアルにかかる費用は、既存のホームページの状態にも左右されます。そのため、Web制作業者によってもばらつきもあり、リニューアルする規模にもよるので一概には表せません。
費用相場を知る
ただし、目安としてホームページのリニューアルにかかる費用の相場を考えたら、制作費より安くなることは考えづらいことが言えます。つまり、ホームページの制作に30万円かかった場合、リニューアルするときにも同額の30万円が必要になるケースが多いのです。
場合によっては、ホームページを制作した費用よりも高くなることも考えられます。あくまでも、参考程度ですが、リニューアルの費用も安ければ1万円台から受ける業者もいるでしょう。たとえば、ホームページの背景だけを変更してもリニューアルになります。
つまり、リニューアルする内容によって、1万円~30万円、場合によっては100万円以上かかることもあるのです。
専門業者に相談してみる
ホームページのリニューアルは、依頼するホームページの規模にもよります。そのため、まずは専門業者に相談してから判断することがおすすめです。
ホームページのリニューアル進め方7ステップ

さて、ここからはホームページのリニューアルの進め方について解説していきます。全部で7段階で進めていくので参考にしてください。
ヒアリングから始める
ホームページのリニューアルは、ヒアリングが欠かせません。リニューアルを依頼する場合は、制作会社からのヒアリングで自社の目的を明確に伝える必要があります。いくら専門知識と経験を兼ねそなえた専門家でも、顧客の依頼する真の目的が見えてこないと誤解を招くことが考えられるでしょう。
これはホームページのリニューアルに限ったことではありません。ビジネス全般において、受発注の事前確認は徹底して行わなければ完成後の見当違いでトラブルや時間ロスを招くでしょう。そのため。ヒアリングの段階で明確な目標を提示することは必須です。
現状の残すべき点と改善点を客観的に抽出
まず、現状のホームページの残しておくべき点と改善すべき点を明確にします。その際、主観的な意見で「この部分は気に入っているから残しておいて欲しい」と判断しないことです。ホームページは、あくまでも訪問者目線を重視します。そのため、客観的に取捨選択をしていくのです。
ホームページが達成する目的を数値で設定
客観的な判断では、数値が有効です。ホームページに求めている達成目的に対して、「訪問者をたくさん増やしてほしい」とか、「問い合わせが殺到するようにしてほしい」、「SNSで話題になるようにしてほしい」などと、イメージだけで具体的な目標がないとお互いの主観が食いちがう可能性もあります。
- 「訪問者をたくさん増やしてほしい」→現状が1日10アクセスの場合は10倍の100アクセスなど
- 「問い合わせが殺到するようにしてほしい」→現状が月間10クリックであれば5倍の50クリックなど
- 「SNSで話題になるようにしてほしい」→Instagramで1,000人のフォロワーを獲得したいなど
これら要望は、依頼先の制作会社にもよりますが、明確な数値目標があれば、打ち合わせ時点で「可能」か「不可能」か、を明確に判断できます。たとえば、「アクセス数と問い合わせのクリック数については施策を施せるがInstagramの1,000人フォロワー増加は難しい」など、依頼先制作会社から明確な回答を得られるでしょう。
目的を明確な数値であらわすことで、事前のすり合わせもスムーズになります。また、具体的であるため、達成しやすくなるメリットにもなるでしょう。
ホームページの課題を分析
ホームページをリニューアルするには、現在のホームページを取りまく課題を抽出する必要があります。訪問者が増えないホームページの問題点を客観的に抽出して、その改善をリニューアル目標に設定します。
たとえば、「問い合わせバナーがサイト背景に埋もれて見つけにくい」や「ぱっと見、何のサイトなのかイメージできない」など、現状の問題点を忖度(そんたく)なく抽出しましょう。そのうえで、リニューアルでやるべき課題をリストにあげていきます。
- 問い合わせバナーがひと目でわかるようにリメイク
- トップページのヘッダーでサイト内容を伝えるキャッチを挿入
- 文章を次が読みたくなる構成にリライト
- サイト内に疑問を残さないユーザービリティへの配慮
- 敵宣画像を挿入して読者の理解度を高める
これらは、あくまで例になりますが、できる限り問題点を明確にできれば、それに対しての課題を明確化できます。
競合となるホームページを分析
ホームページのリニューアルで課題部分を明確にする場合は、競合となる(比較対象となる)ホームページの存在が必要です。競合のホームページの現状や優れている部分、惜しい部分などを抽出して自社のホームページと比較します。その際、自社の強みとなる部分は残して競合の優れている部分を自社でどのように補填するかを検討するイメージです。分析の段階では、立場の異なる意見を客観的に集めることも必要ではないでしょうか。
構成を設定
ホームページのリニューアルする課題が明確になれば、その後のコンテンツ企画やワイヤーフレーム制作の土台となる構成を考えます。構成を設定する際は、マクロの視点とミクロの視点が必要です。別な言い方をすると、鳥の目と虫の目のどちらも意識した客観的な視点で構成を設定します。
コンテンツ企画
次に、リニューアル後のコンテンツを企画します。現状で残しておく部分に肉付けしたり、新しく必要な部分を追加したり、全体像を明確に設計していくのです。この時点で実行すべき改善策は明確になっています。
ワイヤーフレーム制作
全体像は、ワイヤーフレームに反映させて視覚化していきます。ワイヤーフレームはホームページの設計図のようなものです。設計図がなければ家が建たないことと同じで、ホームページもワイヤーフレームがなければ始まりません。依頼主と製作者双方が理解できる客観的な設計図であることが大切です。
デザイン制作
リニューアルと言っても、見た目がまったく変更されることも少なくありません。ワイヤーフレームができたら、今後も通用するレイアウトであることを加味したデザインの土台を作っていきます。それは、ホームページ全体のイメージとなるからです。
ここで古い感覚のままで客観的な判断ができないと、そもそものホームページの役割を誤解している可能性が高くなります。ホームページは、所有する会社の忘備録的な記録ではありません。あくまでも第三者に見せて行動を起こしてもらう媒体のひとつです。そこをはき違えてしまうと、リニューアルの効果を引きだせないでしょう。
システム構築
デザインの設定が決まれば、続いてホームページに導入するシステムの構築をします。システムの構築は、業種によって違ってきます。販売サイトであれば、ショッピングカート機能も必要になるでしょう。会員制ビジネスの場合は、顧客管理システムも必要になります。
それぞれの業種に合わせたシステムの構築を導入し、企画によるサイトコンテンツの設置を勧められるでしょう。また、システムの構築は必要最低限から始めましょう。流行だからとか、競合で使っているからだとか感覚的な理由で導入することはお勧めしません。
すべては、訪問者目線を基準にした判断です。「ここまで読み進めた訪問者に対して、ここでショッピングカートを設置しておくと便利ではないか」など、訪問者目線で必要であれば、システムの導入は付加価値となるでしょう。
運用開始
さて、いよいよリニューアルされたホームページの運用開始となります。ホームページは、リニューアルした時点から、新しい運用が始まるのです。新しくスタートしたホームページの運用では、日々の解析調査により過去のデータと比較することができます。そのため、運用開始とともにホームページの改善で得られた成果を日々の解析から判断しましょう。
あわせて読みたい
リニューアル後の運用における検討課題
ホームページのリニューアルを6ステップで紹介してきました。では、リニューアル後の運用で、検討が必要な課題について見ていきましょう。言いかえると、リニューアル後の運用は、「何をすればいいのか」についてです。
コンテンツ更新
リニューアルされたホームページを公開したまま放置をしないようにしましょう。ホームページの更新は検索エンジンの評価にもつながるからです。常にコンテンツを更新していく意識を持って定期的に追加していきましょう。
効果測定
ホームページをリニューアルしたら、効果測定をしなければ改善効果を把握できません。リニューアル前に行った目的の数値化は、ここで活かされます。数値分析を対象データと比較検証してどの程度、リニューアルによって改善できているか、足りていないかを判断します。
数値分析を対象データと比較検証
数値結果を対象データと比較する際は、「なぜそのような結果となったのか」と考える仮説検証が必要です。仮説を立てることは、次の施策で活かされます。それが成功であっても失敗であっても有効です。そのため、改善結果の検証については積極的な取り組みで進めましょう。
専門家の見解が必要
ホームページのリニューアルでは、改善結果を検討することや仮説検証について、経験がないと主観的な方向へ向いてしまう可能性もあります。自社内製で進めていると、客観的な意見が見えにくくなり、最終的に自社都合で判断してしまうかもしれません。そのような体制では、ホームページをリニューアルしても本末転倒な結果を引き起こすかもしれません。そのため、客観的な視点による判断は欠かせないでしょう。客観的な判断は、その道の知識や経験を備えている専門家の見解が必要です。
社内の認識確認
新しくなったホームページの存在を知っているのがWeb担当者だけにならないように、社内でホームページがリニューアルされたことを共通認識することは重要です。新しいホームページの効果で、自社にどこから問い合わせが来るかわかりません。そのため、社内で共通認識をしておく必要があるのです。
効果測定で得た結果から具体的な課題を明確化する
ホームページのリニューアルは、効果測定で得た結果を社内共通認識の課題にします。もし、Web担当の部署だけで周知しているままだと、リニューアルが進むにつれて他部署から進捗を止めるような横やりを入れられるかもしれません。そのため、社内での共通認識と同時に具体的な課題も明確化する必要があります。
課題を明確にする際は、全社共通の課題として把握できる具体性も担保できるようにしましょう。
訪問ユーザーを増やすための施策
また、新しくなったホームページは新装開店のリアル店舗のように大きな可能性をもっています。新しい可能性を確かめるためにも、ホームページに訪問してくれるユーザーを増やすための施策も打っていきましょう。具体的には、広告運用やSNSの連動などがあげられます。
訪問ユーザーの課題解決を優先したホームページ
訪問ユーザーの課題解決を優先したホームページには、広告運用やSNSの連動などが効果的です。広告の運用は、直接収益を求めるものではなく、検索キーワードとのマッチングを調査するための運用が求められます。そのため、「このキーワードに対してこれだけの反応があった」というデータ取りを目的に展開しましょう。
また、SNSとの連動においては自社ビジネスの競合にない特徴を訴求した投稿などで共感を集めます。地道な戦略でも積み重ねることで将来的な成果へと近づくことが考えられるでしょう。
システム管理
ホームページの運用では、システム管理も重要な部分となるでしょう。日々の業務との連携の中で、予期せぬエラーを起こしたり、社内システムとの連携ができなかったりすることもあります。日々の業務と同じく重要な取り組みになるのです。
予算
このように、ホームページの運用にもコストはかかります。リニューアルにかかる費用だけではなく、新しくなったホームページの運用にも人的コストや時間的コストがかかるのです。そのため、ホームページの運用にかかる費用も予算に組み込む必要があります。
内製か外注か
ホームページの運用は、内製でやるべきか外注に依頼すべきか判断が求められます。自社に専門知識がない場合は、専門家への依頼が近道となるでしょう。たとえ、内製化したとしてもその担当者が本業も兼ねていた場合、ホームページの運用で考えられる緊急時のトラブルへの対応が間に合わないケースも考えられます。その点も含めて内製か外注か判断することが必要です。
外注する場合の注意点
ホームページの運用を外注することも選択肢の1つです。外注により、自社の人的リソースの負担を軽くすることができます。ただし、外注に依頼する前の相談段階で、次のことを確認することが必要です。
- 運用部分のどこまでを依頼できるのか
- 自社のコンテンツ・管理体制・集客を理解してくれるか
- 運用における重要な改善点を積極的に提案してくれるか
- それらを含めた費用が妥当な金額か
以上の点を相談の段階から具体的に答えてもらうために、専門業者に対して明確な目的や目標を開示していくことが大事です。
依頼するタイミングを考慮する
専門家への依頼は、タイミングを考慮しましょう。それは、依頼先の専門家の都合というわけではなく、自社で目的や課題を具体的に判断できる状態ということです。よくあるタイミングの悪さは、専門家への依頼が遅くなりすぎて、手遅れになることも考えられます。自社内製で取り組み、何が問題なのかもわからなくなるほど複雑化しないうちのタイミングをはかりましょう。
何を得意とする制作会社なのか事前に調査する
依頼先の専門業者は、何を得意とする制作会社なのか事前に調査することが重要です。ホームページ制作会社は複数存在しますが、どこの業者に依頼すればよいかはその業者の強み次第ではないでしょうか。
その業者が「BtoB集客を得意とする」や「BtoC向けのショッピングサイトを得意とする」など、何か強みを打ち出していることが見つける際のポイントです。何でもできる業者は、逆に言えば全部が中途半端かもしれません。そのため、事前に業者の強みを調査してみましょう。
過去の実績と自社ビジネスとのマッチングを重視する
依頼する制作会社は、過去の実績を公開していることを優先しましょう。その理由は、過去の実績と自社ビジネスとのマッチングを判断できるからです。自社のビジネスが「ものづくりの製造業」である場合は、製造業のホームページ制作の経験がある業者を見つけましょう。業種によっては、応用を効かせることも可能ですが、その業種の制作経験があるかないかは、成果にも大きく影響します。そのあたりも重視して調査しましょう。
まとめ
いかがでしたか?今回はホームページのリニューアルについて取り上げてきました。ホームページのリニューアルは、企業のリアル店舗を新装開店するほどの大きなイベントとなります。それだけに、リニューアル後の展開にも期待がかかることでしょう。
まずは、明確な目的を持ってホームページを運用していくために、専門業者に相談をしてアドバイスを受けることからはじめてみましょう。
- ホームページのリニューアルは技術的、視覚的、機能的な面で既存のWebサイトを一新するプロセス
- 着手前に現状分析が必要でアクセス数やコンバージョン率などを理解しリニューアルの目的を明確にする必要がある
- ホームページリニューアルは計画的に行う必要がある
あわせて読みたい
ホームページのリニューアルに関するよくあるご質問
最後によくあるご質問をいくつかご紹介致します。
みなさまのWeb集客にお役に立てば幸いです。
その他、ご不明な点がございましたら以下のリンクよりお気軽にご相談下さいませ。
無料オンライン相談はこちらからどうぞ。
Q
ホームページリニューアルの主な目的は何ですか?
A
ホームページのデザインや機能を最新のトレンドや技術に合わせて更新し、ユーザーエクスペリエンスを向上させることが主な目的です。
Q
リニューアルのタイミングはどのように決めるべきですか?
A
サイトの訪問者数やコンバージョン率が低下してきたとき、またはデザインや機能が古くなったと感じたときが適切なタイミングです。
Q
リニューアル時に注意すべきポイントは?
A
既存のSEO対策を損なわないようにすること、モバイルフレンドリーなデザインを取り入れること、ユーザーの行動を分析して最適なUI/UXを提供することです。
Q
リニューアル費用はどれくらいかかるのですか?
A
リニューアルの規模や要望によって変わりますが、事前に明確な予算を設定し、必要な機能やデザインをリストアップするとスムーズに進行します。
Q
リニューアル後の効果測定はどう行うべきですか?
A
アクセス解析ツールを利用して、訪問者数、滞在時間、コンバージョン率などの指標を比較・分析します。
Q
リニューアルする際、デザインのトレンドはどう確認すれば良いですか?
A
Webデザインの賞を受賞したサイトや、業界の専門誌、ブログをチェックすると最新のトレンドを把握することができます。
Q
既存のコンテンツはそのまま使えますか?
A
既存のコンテンツはSEOやユーザーのニーズに合わせて一部改修や更新が必要な場合があります。
Q
リニューアルする際の最も一般的なミスは何ですか?
A
訪問者のニーズを考慮せずにデザイン中心で進めることや、SEOの対策を十分に取らないことが挙げられます。
Q
リニューアルプロジェクトの進め方のヒントはありますか?
A
明確な目標設定、ステークホルダーとのコミュニケーションの確保、プロジェクトの進行状況の定期的な確認が重要です。
Q
リニューアル時に外部の専門家やエージェンシーの協力は必要ですか?
A
リソースや知識に応じて、外部の専門家やエージェンシーの協力を得ることで、より専門的で効果的なリニューアルが可能となります。