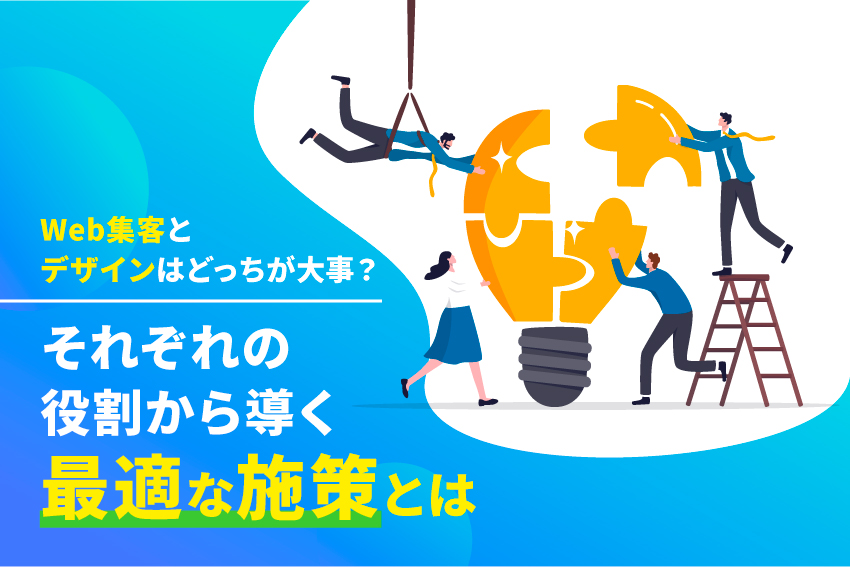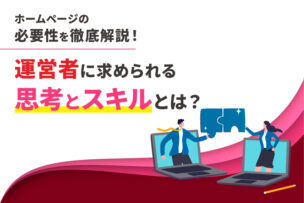記事の監修

Web集客・マーケティングの専門家として、13年間にわたり厳格な基準と緻密な戦略をもって中小企業の成功を導く。
一時的な集客の手法に頼ることなく、中長期的な効果を持続させる本質的なWeb集客の構築に注力。
『恵ある集客を。』をスローガンに掲げてクライアント様のサービスや商品の核心的な魅力を、的確にターゲットに伝えることを重視したWebサイト運用をサポート。
Webサイト制作において、よく聞く「Webサイトを作るなら、デザインを重視しないといけない」と「Webサイトは集客してこそ意味があるデザインは二の次だ」という2つの考え方があります。どちらかというと、Webデザイナーの場合はデザインよりだったり、Webマーケティング担当の場合は、集客よりだったりもするでしょう。
今回の記事では、Webサイトで大事なことが“集客”と“デザイン”に分かれている状況から、それぞれの関係性と役割を紹介していきます。さらに、デザインと集客の関係性から、Webサイトを運営していくために本当に重要なことは、自社のサービスの特性を考慮したバランスの良い施策です。このバランスを重視した集客とデザインについて解説していきます。
今後の自社Webサイトの方向性で悩んでいる担当者にとって、判断のヒントに役立てれば幸いです。
Web集客とデザインの関係性
Web集客とデザインは、どんな関係性を持っているのでしょうか?Web集客とデザインは、どちらもWeb施策の中で重要な役割を果たします。言いかえると、デザインは、「見た目」でWeb集客が「中身」のようなものでしょうか。
とても本質的なテーマとなるので、Web集客とデザインの関係性について、詳細に解説していきます。
良いデザインと悪いデザイン
Webサイトのデザインにおいて、良いデザインと悪いデザインをどのように見分ければいいのでしょうか?実際に良いデザインと悪いデザインはどのような点が違うのでしょうか?取り上げてみました。
良いデザイン
まず、良いデザインの例をあげてみました。
- 訪問者にとって居心地の良い全体イメージ
- 配色やレイアウトに一貫性のあるデザイン
- 3秒でどんなサイトか判断できる
- 見やすい大きさのフォントを使っている
- レスポンシブを意識している
- サイト構造がわかりやすい
- サイト内を移動するのに使い勝手がいい
- 画像や背景が適切なサイズになっている
良いデザインとは、全体的なイメージと配色やレイアウトに統一感があり、安心してWebサイト内に滞在していられるデザインです。新規訪問ユーザーが、Webサイトに訪問して3秒以内に、「何のためのサイトか」判断することができるデザインが求められます。
常に、訪問者にとって「見やすいこと」が優先されていて、画像やフォント、サイト構造、移動リンクなどストレスを感じないで閲覧できるデザインが推奨されるのです。
悪いデザイン
続いて、Webサイトの悪いデザインの例をあげてみましょう。
- 意味もなくキレイでクールなデザイン
- 配色やレイアウトにメリハリのないデザイン
- デザインに凝り過ぎて欲しい情報にたどりつかない
- 見づらい小さなフォントを使っている
- レスポンシブを意識していない
- サイト構造が全くわからない
- 他のページに行くリンクが見当たらない
- 使用する画像やイラストが適切なサイズになっていない
Webサイトの悪いデザインとは、サイト運営者が満足する主観的なデザインになっていることがあげられます。「この配色にこだわりがある」と主観的にデザインを設定してしまうと、自己満足だけのWebサイトとなるのです。
ビジネス目的ではなく、趣味の領域であれば問題ありませんが、アクセスを集めてビジネス展開をしていく目的であれば、主観的なこだわりは不要になります。常に、訪問者にとって、居心地と使い勝手の良いデザインであることが大事です。
あわせて読みたい
良い集客と悪い集客
次に、良いWeb集客と悪いWeb集客について、取り上げていきましょう。
良い集客
では、良い集客から見てみましょう。
Webサイトの良い集客とは、「相手に伝わること」です。できる限りシンプルな内容をターゲットユーザーの役に立つように伝えていきます。この姿勢を維持していくだけでも、訪問者の共感を得ることができるのです。
また、集客したいターゲット属性に役立つ新しい情報を更新していくことで、ユーザーに共感を与えられます。良い集客とは、Webサイトの取り組みに共感を持ってくれるユーザーを集めることなのです。
悪い集客
それでは、Webサイトの悪い集客の例を見ていきましょう。
- 目的が不明なWebサイト
- どのように読み進めていいのかわからない
- 誰に向けた内容なのかわからない
- Webサイトに一貫性がない
- 時代にそぐわない内容
悪い集客は、Webサイトにより訪問者の不安を大きくしていくことになります。「このWebサイト大丈夫かな」「このサイトで販売している商品を買っていいのだろうか」など、Webサイト全体から出てくる疑問点が訪問者の不満を高めることになるでしょう。
また、時代にそぐわない内容のまま、更新を怠っているWebサイトも訪問者の満足度を下げることになります。
あわせて読みたい
良いデザインとコンテンツ量の関係
続いて、良いデザインとコンテンツ量の関係について解説しましょう。先ほど、良いデザインについて紹介してきました。良いデザインは、訪問者に好印象を与えてWebサイトのコンテンツを「読んでみようかな」という気持ちにさせます。
そこで、コンテンツ量が充実している“情報密度”の高いWebサイトになっていれば、ユーザーの理解度を向上させることができるのです。ただし、情報密度はWebサイトのユーザビリティの高さや共感性があることが前提になります。
コンテンツとデザインは共存関係
上記のように、コンテンツとデザインは共存しているのです。良いデザインは、訪問ユーザーに“居心地”と“安心感”を与えて、豊富なコンテンツ量により集客が実現していく流れになります。つまり、Web集客とデザインは、共存していく関係にあるのです。
あわせて読みたい
Web集客の役割
それでは、Web集客とデザイン、それぞれの役割について見ていきましょう。まず、Web集客の役割から案内します。
認知の拡大
Web集客における役割の1つ、認知の拡大とはブランディング効果のことです。自社のビジネスに対して、WebサイトなどWeb媒体を活用し、「世界観」を築いていくことになります。あくまでも、ユーザーが抱く自社のイメージです。自社のイメージは、競合他社から差別化されていることが重要になります。
見込み客を集める
Web集客の役割として、見込み客を集めることがあげられるでしょう。自社のブランドイメージが差別化されたものならば、自社が提供するサービスに価値を持つユーザーが集まるのです。
たとえば、文房具の「シャープペンシル」だけでは、どこにでもある商品ですが、「芯が折れない最後まで尖っているシャープペンシル」だった場合、芯が折れることにストレスを感じていた見込み客が「この芯が折れないシャープペンシルを探していた」と集まってくるようになります。
潜在層へのアプローチ
Web集客は、リアル店舗とちがって見込み客になる可能性を秘めた潜在層に向けたアプローチが可能です。
先ほどの例から、リアルな文房具店で「芯が折れないで最後まで尖っているシャープペンシル」を取り扱っていても、店舗に訪れなければ見つけることができません。また、店舗内でも、一般的なシャープペンシルに紛れて並べられているだけでは存在をアプローチしていないことになるのです。
ところが、Web集客では潜在層へのアプローチとなるターゲットを絞った具体的な提案が可能になります。Web集客は、「芯が折れなくて最後まで尖っているシャープペンシルがあるならば使いたい」と思っている潜在ユーザーに存在を伝えることが、リアル店舗以上に可能なのです。
あわせて読みたい
売上と利益の向上
先ほどの例のように、Web集客はリアル店舗のアプローチとは比較にならない規模で顧客に訴求することができます。しかも、国内すべての範囲に向けたターゲットにアプローチをすることが可能です。
Web集客は、地域エリア限定的ではない分、売上の増加も期待できます。さらに、Web集客は売上に対してのコストが紙媒体や訪問営業ほどかからないため、利益率も伸びてくるのです。したがって、Web集客は売上と利益の両方を向上させることができる施策となります。
あわせて読みたい
Webデザインの役割

それでは、Webデザインの役割についても見ていきましょう。
ヴィジュアル要素が与えるブランディング効果
Webデザインは、Web集客におけるコンテンツマーケティングの要素となるブランディング効果を共通して高められます。Webデザインは、Web集客の軸となるコンテンツを演出する役割を持っているのです。
コンテンツとデザインが共存関係にあるのは、ヴィジュアル要素を高めたブランディング効果をお互いに高めていることによります。そのため、コンテンツとデザインが上手くかみ合えば、Web集客の可能性も高まってくるのです。
共感・信頼・安心
さらに、Webデザインはイメージにより訪問者に「共感」や「信頼」、「安心」を与えます。具体的には、Webサイトの「配色」であったり、「人物画像」であったり、「表示パフォーマンス」であったりするのです。
もし、訪問者を度外視した主観的なWebデザインであれば、Webサイトに安心して滞在することもできません。Webサイトのイメージが悪ければ信頼も薄れてきて、挙句の果ては共感できないことから離脱していくことになります。
そのため、Webデザインの役割として、訪問者に「共感」と「信頼」、「安心」を伝えることがあげられるのです。
ユーザビリティ
先ほどのWebデザインの役割になる「共感」と「信頼」、「安心」を伝えることは、ユーザビリティの向上になります。さらに、Webデザインによるユーザビリティは、Webサイトの表示速度やスマートフォンに最適化された表示にも影響していくのです。
まさに、Webデザインがなければ、「ユーザビリティを向上させることができない」と言っても過言ではないでしょう。
あわせて読みたい
Web集客とデザインのバランス
いかがですか?Web集客の役割とWebデザインの役割をそれぞれ見てきました。結論として、どちらか片方が大事ではなく、Web集客もWebデザインの両方に重要なポイントがあります。
そのため、Web集客とWebデザインは、自社サービスの特性を考慮した上でバランス良く施策していくのが大切になるのです。
自社サービスの特徴により違う
Web集客とWebデザインのバランスは、業種やビジネスモデルによって違ってきます。たとえば、自社のサービスが若年層をターゲットとしたフォーマルファッションの販売の場合、重視すべきはデザインではないでしょうか。
もちろん、コンテンツによる集客も大事ですが、訪問したWebサイトのデザインが時代遅れだったり、サイトカラーの配色が汚かったりすれば、展示しているファッションのイメージも下がるのです。そのため、重視するのはデザインになるでしょう。
このように、自社のサービスの特徴に合わせてバランスをとっていくことが必要です。
キレイだけど集客できないこともある
逆に、デザインばかりを重視して、モード色を強調したWebサイトでは集客できないことも考えられます。確かに、クールでキレイなWebサイトはイメージ的に悪い影響を与えません。
しかし、ユーザーにとっては、クールでキレイなWebサイトに対して親近感を感じなくなる可能性もあるのです。具体的には、完璧に着飾ったWebサイトは、生活感がない非日常的なため、「自分には敷居が高い」と判断してしまうことが考えられます。
そのような理由からも、デザインが良いだけでは集客ができないのです。
あわせて読みたい
集客しても売上につながらないこともある
また、デザインが良いWebサイトのアクセスが増えてきたとしても、売上につながらないこともあります。それは、集客まではできていても「他のサイトへの期待感」や「他のサービスと比較」など検討の余地を残しているからです。
Web集客の役割として、最も重要な部分がブランディング効果になります。ブランディング効果を駆使できれば、「他を検討してみたい」と思わせることがないのです。その理由は、ブランディングによる競合との差別化ができていれば、集客から売上につながる導線もできています。つまり、「集客=売上」となるのです。
あわせて読みたい
Web集客とデザインはバランスよく施策
以上のことをふまえて考えてみると、Web集客とデザインは切り離さないことが大切になってきます。さらに、自社のビジネスの特徴と照らし合わせたバランスよい施策が必要になってくるでしょう。
まとめ
今回は、WebデザインとWeb集客の関係性について、解説してきました。この記事を読むまでは、「デザインに力を入れるべきか、集客に力を入れるべきか」迷っていたことでしょう。ですが、WebデザインとWeb集客のそれぞれの役割からも、どちらもお互いを支えあって共存しているのです。
そして、自社のビジネスの特徴に合わせてバランスよく施策することで、Webによる「集客=売上」の実現が期待できます。
- Webサイトで重要なのは「集客」と「デザイン」の両方
- 良いデザインは居心地の良い全体イメージで3秒でサイトの目的が理解できる構造になっている
- 効果的な集客は理解しやすく役立つコンテンツの更新と効果測定に基づく改善が必要
Web集客とデザインに関するよくあるご質問
最後によくあるご質問をいくつかご紹介致します。
みなさまのWeb集客にお役に立てば幸いです。
その他、ご不明な点がございましたら以下のリンクよりお気軽にご相談下さいませ。
無料オンライン相談はこちらからどうぞ。
Q
Web集客におけるデザインの重要性は?
A
Web集客におけるデザインは非常に重要です。良いデザインはユーザーの信頼を勝ち取り、サイトの滞在時間を延ばし、コンバージョン率を向上させる要因となります。
Q
デザインのトレンドはどのように変わってきているのか?
A
デザインのトレンドは常に変わっていますが、最近ではフラットデザイン、レスポンシブデザイン、ダークモード対応などが注目されています。
Q
レスポンシブデザインのメリットは?
A
レスポンシブデザインの最大のメリットは、様々なデバイスサイズに適応できるため、ユーザーエクスペリエンスが向上し、SEO評価も高まる点です。
Q
ユーザーエクスペリエンス(UX)とデザインの関連性は?
A
デザインはUXの一部です。良いデザインはユーザーの行動を導き、見込み客のニーズや期待に応えることができるものであるべきとめぐみやでは考えています。
Q
Web集客を目的としたランディングページのデザインのポイントは?
A
明確なCTA、直感的なナビゲーション、信頼性を高める要素(例: お客様の声)、高品質のビジュアルコンテンツなどがポイントです。
Q
Webデザインにおけるカラー選択の重要性は?
A
カラーはユーザーの感情や行動に影響を与えます。適切なカラー選択はブランドの印象を強化し、目的に合わせた行動を促すことができます。
Q
Webサイトのデザインをリニューアルする際の注意点は?
A
既存のユーザーの混乱を避けるため、変更箇所を明確にし、必要であれば変更の理由や利点をユーザーに伝えることが重要です。
Q
効果的なWeb集客デザインのための最初のステップは?
A
ターゲットオーディエンスのニーズや行動を理解すること。この情報をもとにユーザージャーニーを考慮したデザインを構築することが効果的です。
Q
モバイルファーストのデザインの重要性は?
A
モバイル利用者が増加している現代において、モバイルファーストのデザインは必須です。モバイルでの閲覧が快適であることは、Web集客の効果を大きく向上させる要因となります。
Q
ユーザビリティとデザインのバランスを取るための方法は?
A
ユーザーテストやフィードバックを活用して、デザインの美しさと機能性を絶えず評価し、調整することが重要です。
Q
アニメーションや動的要素をWebデザインに取り入れる際の注意点は?
A
過度なアニメーションはユーザーを混乱させる可能性があります。目的に合ったアニメーションを選択し、サイトの読み込み速度やユーザビリティに影響を及ぼさないように注意する必要があります。