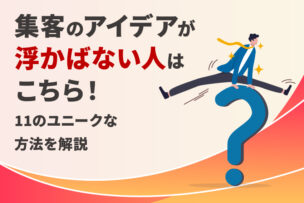記事の監修

Web集客・マーケティングの専門家として、13年間にわたり厳格な基準と緻密な戦略をもって中小企業の成功を導く。
一時的な集客の手法に頼ることなく、中長期的な効果を持続させる本質的なWeb集客の構築に注力。
『恵ある集客を。』をスローガンに掲げてクライアント様のサービスや商品の核心的な魅力を、的確にターゲットに伝えることを重視したWebサイト運用をサポート。
「実店舗の集客に限界を感じてWeb集客を検討している」
「Web集客は、どの方法を選べばいいの?」
最近では、インターネット環境の整備やスマホユーザーの増加、さらにリモートワークの需要拡大でWeb集客がますます注目されている状況です。Web集客の必要性を感じている店舗経営者やこれからECサイトを立ち上げようとしている参入予定者も少なくないことでしょう。
Web集客は、検索エンジンを活用したWebサイトやSNS、広告など様々です。では、一体どの方法を選べば良いのでしょうか?
今回の記事では、Web集客方法について解説します。Web集客6つの種類と選ぶポイントについても説明しましょう。コロナ時代で変わりゆく消費者行動への対処として、Web集客を検討中の企業ご担当者様はヒントにお役立てください。
- Web集客について詳しく知りたい方
- Web集客の種類について知りたい方
- 成功するWeb集客戦略の作り方について知りたい方
目次
Web集客とは?
Web集客とは、インターネットを使用して顧客を獲得またはリテンションする一連の戦略と手法のことを指します。このアプローチは、ビジネスがオンラインプレゼンスを高め、製品やサービスに対する需要を創出するために不可欠です。Web集客は、検索エンジン、ソーシャルメディア、電子メール、その他のオンラインプラットフォームを介して行われます。
Web集客のメカニズムは、ターゲットとなる顧客層に合わせて最適化されたコンテンツと広告の展開から成り立っています。これにより、企業は特定の目標層に対して最適化されたメッセージを送り、顧客エンゲージメントを高めます。Web集客の目的は通常、売上の増加、ブランド認知度の向上、または特定の行動(例:登録、ダウンロードなど)の促進などがあります。
Web集客の主な手法
Web集客はいくつかの主要な手法で行われます。以下でも詳細を説明しますが、最も一般的なのは、SEO(検索エンジン最適化)です。これは、特定のキーワードで高いランキングを得るための戦略と実装手法です。 SEO以外にも、SNSマーケティングがあり、FacebookやInstagramなどのソーシャルメディアプラットフォームでブランドを訴求します。コンテンツマーケティングでは、有益な情報を提供することで顧客の信頼を勝ち取ります。ペイドアド(広告)は、ターゲットとするオーディエンスに直接的な広告を表示させる方法です。最後に、メールマーケティングは、電子メールを用いて顧客と直接コミュニケーションを取る手法です。
Web集客の効果的な実施方法
効果的なWeb集客のためには、いくつかの重要なステップがあります。こちらも以下で具体案を説明しますが、最初に、ターゲットオーディエンスを特定する必要があります。これにより、メッセージとコンテンツがそのターゲット層に最適化され、高いエンゲージメントが期待できます。次に、データ解析を行い、どの手法が最も効果的であるかを判断します。データに基づいて戦略を調整することで、ROI(投資対効果)を最大化します。
多チャンネル戦略も重要で、顧客が使用するさまざまなプラットフォームに適応します。最後に、予算とROIを常に監視し、戦略を最適化することが重要です。効果的なWeb集客は、これらの要素がしっかりと整って初めて実現します。
あわせて読みたい
Web集客が中心となる時代到来へ
コロナウイルスの影響を受けて2020年から現在に至るまで、あらゆる生活様式が変わりました。人と人との接触に対して密を避けることが感染症対策として浸透する中、飲食店やカラオケボックス、遊技場などあらゆるサービス利用が見直されてきました。
変化は、個人生活だけではなく、企業のビジネスにおいてもDXの波とともにオンライン需要が増してきました。出社しないでリモート対応による働き方は、インサイドセールスのオンライン商談やオンライン打ち合わせなどを一般化してきたのです。オンライン需要の拡大の先に見えるのは、Web集客になります。
オンライン上の接触が増えれば、そのタイミングからスムーズにWeb集客へと連携していくことが当然の流れのようになります。まさに、Web集客が中心となる時代の到来です。
テレワークの定着
Web集客が中心となる要因では、Webを介したコミュニケーションツールの台頭が考えられます。Webを介したコミュニケーションツールは、テレワークを支えてきました。具体的には、以下のツールがあげられます。
- ZoomやGoogle meetなど:Webビデオ会議システム
- Chat WorkやSlackなど:タスク管理やグループワークが可能なWebチャットツール
- Googleワークスペース:ドキュメント・スプレッドシート・スライドなど共有ビジネスツール
上記にあげたコミュニケーションツールは、テレワークの促進を支えてきました。リモート環境で情報の共有が可能になる点を非ITの経営層や取引先に証明した形になりました。その流れに乗り、オンライン環境のやり取りから自然にWeb集客へつながるため、Web集客は欠かせない状況になってきました。
Webなくして語れない実社会
リモート対応におけるWeb集客だけではなく、実社会においてもWebなくしては語れない状況です。教育現場やスキルアップのための学習など、試験会場まで移動する際の交通費や会場を借りるコストなどが抑えられるオンライン学習システムの導入。さらに、企業の人事採用におけるマッチングアプリの活用などもあげられます。
実社会においても、直接訪問を最低限に抑えた非対面取引が活用されて、非対面対応の問題点を解決するサービスやツールの導入が活性化してきました。まさしく、実社会もWebなくしては、語れない状況です。このように、Web集客はこれからの時代、集客の中心的な存在となります。
あわせて読みたい
Web集客方法の選び方
本記事では、Web集客方法を大きく7つに分けてご紹介します。その前に、適切なWeb集客方法の選び方を解説いたします。以下の3点を参考に、Web集客方法を選択してみてはいかがでしょうか。
自社サービスとの相性
自社サービスとの相性が良い方法を選びましょう。自社の取り扱う商品やサービスによって、集客効果が変わります。
例えば、若年層をターゲットとしている商品・サービスであれば、TwitterやInstagramなどのSNSプラットフォームを利用すると良いでしょう。しかし、BtoB製品を取り扱っている場合は、SNS利用者のニーズには合いません。オウンドメディアでのコンテンツ制作や、メールマーケティング、ニーズの高いユーザーにアプローチできるリスティング広告が効果的です。
自社の商品・サービスと相性が良い方法を実施することで、予想以上の集客効果が見込める可能性があります。ただし、サービスの特徴や商品の特色によって一概には言えないため、実施してみて効果を感じられない場合は、速やかに別の集客方法に切り替える心構えも大切です。
ターゲットに合わせた戦略
ターゲットに合わせた戦略を立てましょう。どんな世代のユーザーにホームページを見てほしいか、顕在層と潜在層どちらへアプローチするのかによっても方法は異なります。
例えば、ラーメン店を営んでいるケースをご紹介します。中年男性をターゲットとした場合は、豪快にラーメンを頬張る動画投稿をしたり、黒を貴重とした広告を出すと効果的でしょう。反対に、成人女性をターゲットとした場合は、お洒落な背景や装飾をした写真をSNSに投稿したり、女性インフルエンサーにPRしてもらうことで集客に繋がります。
検索エンジンでも、男性が検索するワードは「ラーメン こってり」「ラーメン 二郎系」などが人気です。しかし、女性が検索するワードは「ラーメン 女性 入りやすい」「ラーメン 女性 一人」などが多いのです。
このようにWeb集客方法を考える上で、ターゲットの存在は無視できません。SEO対策を行う上でも、ターゲットに合わせた最適なキーワード選定をする必要があります。
予算を確認
Web集客に使用できる予算を確認しましょう。無料で実施できる方法もあれば、有料で実施する方法もあります。
例えば、無料で実施できるSEOを活用した方法は、効果が出るまで時間がかかります。反対に、有料で実施できる広告を利用した場合は、即効性が期待できるでしょう。
有料広告が出ている期間は高い集客が見込めます。しかし、無理のある費用をかけて広告を出せば、掲載期間が終了した途端に集客できなくなり、いっときの散財となってしまうでしょう。
Web集客にかける予算によって、すぐに効果を発揮させられるケースもあれば、中長期的な集客が見込めるケースもあるのです。
あわせて読みたい
Web集客方法1「検索エンジン」活用
Web集客方法のひとつとして、検索エンジンの活用があげられます。検索エンジンの活用は、検索エンジンサービスのGoogleやYahoo!による検索結果の上位表示を獲得するための施策です。施策として考えられるのは、以下5つの方法になります。
自然検索
自然検索とは、検索ユーザーが検索エンジンの検索窓に入力したキーワードに対して、検索意図をもとに最適な検索結果として上位に掲載するWebサイトを使った集客方法です。
自然検索は、Webサイトの品質から評価を獲得する金銭コストよりも、時間や労力の掛かる施策となります。自然検索により上位表示されることでアクセスユーザーを集める目的を持ったWebサイトの種類を紹介しましょう。
ポータルサイト
ポータルサイトは、あるテーマに関して、関連する外部Webサイトへのリンクを設置している入り口的(ポータル)な役割のあるWebサイトです。
例にあげると、Yahoo!Japanの公式サイトのトップページにさまざまなリンクが設置されている総合サイトのようなイメージになります。
企業サイト
企業サイトは、会社紹介のWebサイトです。従来の企業サイトは、会社の名刺的な役割を持っていました。そのため、どの企業においても、会社概要や代表あいさつ、経営理念などを掲載したビジネスメッセージだけの硬い印象でした。
現在の企業サイトは、斬新なデザインや自由な発想で独自性を打ち出している企業も少なくありません。
ECサイト
ECサイトは、インターネット完結で商品やサービスを購入決済できるネットショッピング向けのWebサイトです。ECサイトには、ポータル要素のある大手ECサイトから個人のECサイトまでさまざまあります。Webサイトの秘匿性やセキュリティの強化と、個人のスマホアプリから簡単に決済できる仕組みが追い風となっています。
企業ブログ
企業ブログは、ブログ機能のある企業が運営するWebサイトです。企業における日々の出来事や取り組んでいる活動などをブログ形式で発信します。企業サイトにブログを備えている場合もあり、一体化していることも考えられるでしょう。
オウンドメディア
オウンドメディアは、企業がオーナーとして運営するメディアのことです。企業ブログと同じように捉えられることも考えられますが、ターゲット読者層やメディアの在り方などに違いがあります。企業ブログは、会社の主観的な情報を発信する媒体です。
一方のオウンドメディアは、読者となるユーザー属性を明確にして、そのユーザーに役立つコンテンツで構成されている客観的な情報発信媒体となります。
マップ検索
自然検索として、テキスト検索ではなくマップ検索からコンテンツに誘導する施策を紹介します。
MEO
MEOは、マップエンジンの最適化施策(Map Engine Optimizationの略称)です。Googleマップと連動した地図エンジンの表示結果に、上位表示されるための施策となります。おもに実店舗や地域活動などにおいて、地図検索結果と連動した訴求が可能です。
MEOは、地域検索を活用していることからローカルSEOともいわれます。
画像検索
GoogleやYahoo!の検索方法のひとつに画像検索があります。画像検索は、キーワード検索では探せない対象の名前が不明のときに効果を発揮する検索方法です。画像イメージから商品名や人物などを特定できる特徴があります。
Google lens
画像検索を採用したGoogleが提供するサービスとして、Google Lensがあります。Google Lensは、Android端末限定のアプリです。Googleアプリの音声入力の横に設置されています。Google Lensを使うと、撮影した画像をもとに最も近い答えをWebページや広告などで返します。商品名が不明なときに、撮影した画像から商品を特定する際に便利な機能です。
Web集客においては、画像の回答になるWebコンテンツから商品購入へ誘導する仕組みを活用できます。
有料検索
有料検索は、その名のとおり金銭コストをかけて出稿する検索結果ページの有料枠を活用したWeb集客です。検索結果ページでは、有料検索による表示枠が自然検索表示より優先されます。検索結果ページ上部や下部などに掲載されている有料で出稿できる広告です。
リスティング広告
リスティング広告は、有料検索の代表的な広告媒体です。検索連動型広告とも呼ばれ、検索ユーザーが入力した検索キーワードに対して、検索結果ページの広告枠に掲載されるテキスト広告。掲載料は、検索ユーザーによるクリックごとの単価制となります。
出稿にあたっては、掲載先キーワードのクリック単価入札が必要です。キーワードにより、クリック単価が高騰する場合が考えられるため、需要の高いキーワードに対して自社ビジネスとの費用対効果を考えなければなりません。
Googleショッピング広告
Googleショッピング広告は、リスティング広告と同じ検索結果ページに表示される広告です。検索キーワードが商品やサービス名に関連しているまたは、該当する場合に「画像・販売価格・在庫状況」などとあわせて表示されます。リスティング広告枠の上部に画像付きで表示される広告です。
出稿には、Google広告のショッピングキャンペーンを活用する必要があります。
メディア広告
メディア広告は、企業が商品・サービスの宣伝、企業ビジネスの認知拡大を目的として利用するWeb集客方法です。メディア広告は、インターネットだけに限らずテレビやラジオ、新聞雑誌なども含めた掲載媒体を総称します。インターネット上では、Webコンテンツ媒体すべてをメディアとして捉えられるでしょう。
この記事では、WebサイトとSNSを切り分けて紹介しているため、Webサイト関連のメディア広告を紹介します。
ディスプレイ広告
ディスプレイ広告は、Webサイト上の広告枠に掲載するバナー通して配信される広告です。広告の形式は、画像や動画、テキスト、音声などで構成されます。インプレッション(広告表示)数やクリック数による料金と、定額料金による掲載方法が主になるでしょう。
Yahoo!広告(YDN)
Yahoo!広告は、先述した検索連動型の「検索広告」と「ディスプレイ広告(YDN)」の2種類で構成されています。YDNは、Yahoo!Japan公式サイトの広告枠に掲載されるディスプレイ広告のひとつです。
YDNは、大手ポータルサイトの集客力を活用できるため、広告枠によってはクリック単価が高騰する可能性があります。Yahoo!広告の検索広告は、Yahoo!Japanの検索結果ページ以外にもexciteや朝日新聞DIGITALなど提携先サイトにも掲載される点が特徴です。
記事広告
記事広告は、タイアップ広告ともいわれニュースサイトやポータルサイトなどに掲載された記事自体が広告となる集客方法。一般的な広告ではなく、記事コンテンツとして認識される可能性もあります。記事自体が広告となるため、想定する読者に向けて興味関心をひくコンテンツの提供が可能です。
メルマガ広告
メルマガ広告は、Webサイトへの誘導手段として活用されるメルマガ媒体を使った広告出稿方法となります。
読者数の多いメルマガや関連性の高い読者層に支持されているメルマガなどを掲載媒体として、メルマガ本文中の広告枠に掲載する仕組みです。メルマガ配信者がメール本文中で紹介する形式やメール本文の末尾に広告として追記される形式などがあります。
あわせて読みたい
Web集客方法2「SNS」活用
Web集客方法では、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)を活用した方法が需要を拡大しています。
個人のスマホ普及が進む中、電話利用と同じかそれ以上の習慣的な活用が定着しているSNS。スマホを利用開始したユーザーが当然のように、LINEやInstagramのアカウント登録をして日常生活のコミュニケーションに活用します。
SNS自然検索
SNS自然検索は、SNS上で自然に拡散されて認知拡大する状態です。とくに匿名性の高いTwitterなどで話題となり「バズる」という拡散状態が該当します。SNSのトレンドとなり、自然検索で拡散できれば広告出稿コストを抑えることが可能です。
Twitterは、匿名により短文投稿(140文字以内)が特徴的なSNS。気軽に短文投稿ができるため、利用者層も幅広く活用しています。投稿したツイートは、アカウントをフォローするフォロワーのホーム上に表示される仕組みです。
また、ハッシュタグやキーワード検索でツイートがフォローされたり、リツイートされる可能性もあります。先ほど触れたバズる要素を持ったSNSとなるため、ツイート拡散によりアクセス流入を増やすことも期待できるでしょう。
Facebookは、Twitterとは異なり特定の個人として身分を明かして活用するSNSです。個人のスマートフォンとの連動により、Web上でリアルなコミュニケーションをはかれるサービスになります。
アカウント設定の段階で、自分の身分(出身地・出身校・勤務先など)を登録することにより、システムが友達候補として属性の近いユーザーを検出する点が特徴です。リアルなコミュニケーションツールになります。
Instagramは、Facebookを提供する米国の企業Metaが運営する写真投稿を主体とするSNSです。個人が自分のスマホから簡単な編集加工をして写真や動画を投稿できる点が特徴となります。
投稿した写真には、ハッシュタグやアカウントタグの埋め込みができるため、興味をひく写真投稿からフォロワー数の獲得につなげることも可能です。
LinkedInは、ビジネスに特化した個人名や身分を公開したうえでコミュニケーションをはかるSNSです。
Facebookユーザー以上に、ビジネス目的で登録しているユーザー同士のつながりを期待できます。仕事の発注や契約、人材募集などでも活用されているため、個人属性を経歴やスキルなど、詳細に設定する必要があるSNSです。人材募集やBtoB取引に向いています。
LINE
LINEは、個人のスマホアプリとして電話感覚で活用されるコミュニケーションチャットツールです。接点を持った見込み客に対して、関係性を深めるためにLINE上でつなぐ手法が活用されます。
SNS広告
SNSでは、広告枠が用意されています。それぞれのSNSが持つ特徴を活かした広告出稿により、共感度の高いユーザーを獲得できるでしょう。
- Twitter広告
- Facebook広告
- Instagram広告
- LinkedIn広告
- LINE広告
Twitter広告
Twitter上のタイムラインやキーワード検索結果に表示される広告がTwitter広告です。Twitter広告は、ユーザーごとに表示内容を最適化して掲載できます。
Facebook広告
Facebookのフィード上には、一般投稿と一緒に広告も掲載されています。Facebook広告は、フィード上やストーリーズに掲載される広告です。
Instagram広告
Instagram広告は、Instagramのコンテンツにある写真や動画にあわせて表示される広告。Facebook広告との連動が可能なため、同時出稿により流入数の拡大が期待できます。
LinkedIn広告
LinkedIn広告は、実在する企業名や企業人などが登録してリアルビジネスについてコミュニケーションをとる特徴から、個人のビジネス経歴をターゲティングできます。
また、登録情報が具体的なため、広告自体が企業からのオファーとなっていたり、違和感を感じさせない点が特徴です。
LINE広告
運用型の配信となるLINE広告は、日常のコミュニケーションツール上で表示される広告です。「TwitterやFacebookは使わないけれどLINEは、毎日使っている」という層に向けたLINE上で訴求する広告となります。
SNSでのコンテンツマーケティング
ソーシャルメディアを使用してコンテンツマーケティングを行うことは、ビジネスの集客効果を高める有効な手段です。FacebookやInstagram、TwitterなどのSNSは、情報の拡散力が高く、さまざまなユーザーと直接コミュニケーションをとることが可能です。これらのプラットフォームで魅力的なコンテンツを共有することで、ブランドへの関心を高め、新たな顧客を獲得することができます。また、フォロワーとのインタラクションを通じて、ブランドの人間性を表現し、顧客ロイヤルティを向上させることもできます。
あわせて読みたい
Web集客方法3「動画投稿」活用
Web集客には、動画投稿を活用した施策もあります。
YouTube動画
動画投稿サイトのYouTubeでは、Webサイトへの誘導手段として動画を活用できます。とくに動画編集技術がなくても簡単に作成した動画投稿が可能です。動画投稿からのアクセス流入には、再生回数やチャンネル登録者数を増やす必要があります。
YouTube広告
YouTube広告は、動画投稿サイトYouTubeの動画内のバナーや動画コンテンツ再生前に流れる動画広告などのことです。YouTube利用者の行動履歴を参考に適切な広告が配信されます。インプレッション課金やクリック課金による仕組みです。
動画を用いたストーリーテリング
動画は視覚的な情報を伝える強力なツールであり、ビジネスのストーリーテリングにおいてもその効果を発揮します。商品やサービスの特徴を詳しく説明したり、企業のビジョンやミッションを伝えたりすることで、視聴者の感情を揺さぶり、ブランドへの関心と信頼を深めることができます。さらに、動画はSNSやウェブサイト上で簡単に共有でき、広範な視聴者にメッセージを伝えることが可能です。よりエンゲージメントの高いコンテンツを提供することで、効果的なWeb集客を実現します。
Web集客方法4「コンテンツマーケティング」活用

コンテンツマーケティングは、高品質なコンテンツを作成・配信し、ターゲットとなる顧客の関心を引きつけ、ブランドへの信頼とリレーションシップを構築する手法です。具体的には、ブログ記事、ホワイトペーパー、ビデオ、インフォグラフィック、Eメールニュースレターなど、様々な形式のコンテンツを作成します。
これらのコンテンツは、顧客の問題を解決する有益な情報を提供することで、自社の専門知識や経験を共有し、読者の問題解決を支援することでブランドの信頼性を高める効果があります。また、定期的に新しいコンテンツを公開することで、ウェブサイトへの再訪問を促し、ユーザーとの関係を深めることができます。さらに、SEOにも有効であり、適切なキーワードを用いることで検索エンジンのランキングを向上させることが可能です。
ブログや記事の作成
ブログや記事は、コンテンツマーケティング戦略の中心的な要素であり、企業やブランドが自身の知識、専門性、価値を顧客に伝えるための重要な手段です。これらのコンテンツは、WebサイトのSEO(検索エンジン最適化)効果を高め、より多くの訪問者を引き付けるための手段としても機能します。
記事やブログの作成は、目的に合わせて適切なトピックを選び、読み手が関心を持つような内容を提供することが重要です。例えば、業界のトレンドについての記事や、商品の使用方法、専門的な知識を分かりやすく伝えるハウツー記事などが考えられます。
また、ブログや記事の作成においては、読み手に対する洞察が非常に重要です。顧客が何に関心があるのか、どのような情報を求めているのかを理解し、それに基づいた内容を提供することで、ブランドと顧客との強固な関係を築くことができます。
さらに、コンテンツは定期的に更新することが求められます。新鮮な情報を提供することで、訪問者が再度サイトを訪れる理由を提供し、ブランドへの信頼と関心を維持することができます。
ブログや記事の作成は時間とリソースを必要としますが、これらのコンテンツはWeb集客における重要な要素であり、効果的な戦略を通じて企業の知名度を高め、顧客との強固な関係を築くことができます。
SEOの活用方法
SEO(検索エンジン最適化)は、ウェブサイトの検索エンジンランキングを向上させ、より多くのトラフィックを獲得するための手法です。これには、キーワードの選定、メタデータの最適化、内部リンクの強化、ユーザーエクスペリエンスの改善などが含まれます。また、定期的に新しいコンテンツを公開し、そのコンテンツが読者に価値を提供することが、SEO効果を最大化するための重要な要素です。
ゲストポスティング
ゲストポスティングは、他のウェブサイトやブログで記事を公開し、その記事を通じて自身のウェブサイトへのリンクを得る手法です。ゲストポスティングは、より広範なオーディエンスにリーチし、自社の専門知識を示すことが可能となります。また、ゲストポスティングはSEOにも有効であり、質の高いバックリンクを得ることで、ウェブサイトの検索エンジンランキングを向上させることができます。
Eメールマーケティング
Eメールマーケティングは、メールを通じて直接顧客とコミュニケーションをとる効果的な手法です。ニュースレターやプロモーション、情報提供などを行うことで、顧客との関係を深め、再訪問や購入を促すことができます。
また、パーソナライゼーションを活用して個々の顧客に合わせたメッセージを送ることが可能です。更なるエンゲージメントの向上を図るためには、まずターゲットとなる顧客の理解が必要です。これには、顧客のニーズや行動パターン、購入の決定要因などを把握することが含まれます。
次に、明確な目標とKPI(Key Performance Indicator)を設定します。これにより、戦略の進行状況を具体的に測定し、必要に応じて調整することが可能となります。
最後に、Web解析ツールを活用し、集客活動の結果を分析・改善します。これにより、戦略の有効性を確認し、最大のROI(Return on Investment)を得ることができます。
あわせて読みたい
Web集客方法5「アフィリエイト」活用
Web集客では、アフィリエイトを活用した方法があります。アフィリエイトは、自社ビジネスをWeb媒体の管理者に紹介してもらい媒体経由で成約できた件数ごとに紹介料として報酬を支払う仕組みです。
アフィリエイトは、自社で宣伝媒体を用意する必要がありません。媒体所有者の集客力を活用した方法となります。
インフルエンサーマーケティング
インフルエンサーマーケティングとは、SNSを中心とするソーシャルメディアで大きな影響力を持つ「インフルエンサー」に、自社商品やサービスを紹介してもらうことです。自社の認知拡大やブランディングを狙いつつ、顧客獲得や購買に繋げるマーケティング手法になります。
インフルエンサーを起用して情報を発信することで、さまざまなメリットがあります。インフルエンサーにはある程度の固定ファンが存在しているため、「好きなタレントが紹介しているから気になる」「好きなブロガーが使用しているから自分も使ってみたい」などと自然に思わせる効果があるのです。
また、インフルエンサーが実際に商品やサービスを利用して情報発信をするため、広告感がなく、顧客に受け入れてもらいやすいのもメリットの一つです。ユーザー目線で分かりやすくレビューしてもらえるため、説得力があり信頼性が高いと評価されます。
ただし、インフルエンサーのキャスティングは慎重に行うようにしてください。自社商品やサービスとの相性は良いか、ターゲット層とフォロワーはマッチしているか、フォロワー数はどのくらいかによって検討することも必要です。
フォロワー数100万人以上の「トップインフルエンサー」を起用すると、それなりに費用がかかります。フォロワー数1万人以上の「マイクロインフルエンサー」や1万人まで満たない「ナノインフルエンサー」を起用すると、コストの節約ができるでしょう。
Web集客方法6「直接流入」活用
直接流入は、ユーザーのPCに設定されたブックマークやお気に入りなどから直接流入するアクセスを指します。または、誘導先URLを直接ブラウザに入力して訪問する属性のことです。
直接流入は、検索エンジンやSNSなどを利用しないで直接Webサイトに訪問してくるため、名刺やQRコード、チラシなどからの流入も考えられます。
イベント
イベントや展示会を開催するのも一つの方法です。自社のパンフレットやWebサイトへのリンクが掲載されたチラシを配布することで、参加者がイベント終了後にWebサイトを訪問してくれるかもしれません。
また、オンラインイベントやウェビナー(オンラインセミナー)を開催することで、イベント費用をかけずにWeb集客が可能となります。
Web集客方法7「外部メディアからの流入」活用
外部メディアからの流入とは、自社ビジネスを外部メディアで取り上げられリンクを掲載されることにより起きる集客方法です。この形式を活用した仕組みがアフィリエイトになります。
外部メディアからの流入は、アフィリエイトの自然な形式としてメディアの好意や共感により実現する方法です。
純広告
純広告とは、ある特定のメディアが保有する広告枠を買い取り、一定期間広告を配信することです。例えば、Yahoo!のトップページ右側にある枠が純広告の一つとなります。Webサイト上で掲載場所が決まっていることが特徴です。
純広告は、不特定多数のユーザーに自社ブランドやサービスをアプローチできるため、潜在層に向けて認知してもらいやすい点がメリットです。
純広告にはテキスト広告、バナー広告、動画広告などさまざまな種類があります。また、自社の予算に応じて配信頻度や料金形態を設定できるのも特徴です。自社のサービスはどの形式の広告が最適か、どの程度の予算で実施するか事前に社内で検討しましょう。
プレスリリース
プレスリリースとは、報道機関に向けた情報発信をして集客を獲得する手法です。各メディアに最新情報の発表や告知を行うことで、コストをかけずに情報サイトやニュースサイトに掲載してもらえます。有名な媒体に取り上げられれば、より多くのWeb集客が見込めるでしょう。
そのためには、メディアに対して有益な情報を提供する必要があります。メディアに取り上げてもらえるような情報発信の仕方を検討することが重要です。多くのメディアが注目するプレスリリースを配信することが、Web集客成功に繋がるのです。
口コミサイト
口コミサイトを活用してWeb集客を狙うのも一つの方法です。口コミサイトは、広告でもなく業者を挟むことがない「一般消費者からのリアルな意見」が把握できます。ユーザーからの信憑性が高い情報となるため、新規顧客獲得が狙えるのが特徴です。
また、良い口コミが広がればSNSを通じて急速に拡散される可能性があるため、幅広いユーザーに商品をアピールできるでしょう。ただし、悪い口コミも同様に拡散される可能性があるため、リスクを理解した上で利用することが望ましいです。
あわせて読みたい
成功するWeb集客戦略の作り方
成功するWeb集客戦略は、顧客のニーズとビジネス目標を結びつける、包括的で具体的なアプローチを必要とします。まず、ターゲットとする顧客が誰であるかを明確に理解することが必要です。年齢、性別、地域、職業、趣味など、顧客の詳細なプロフィールを描き出すことで、彼らがどのような情報を求め、どのような行動をとるかを予測することができます。
顧客ニーズの調査と競合との差別化
Web集客は、情報管理が大事です。日々変化する情報から自社ビジネスに必要な情報と不要な情報を取捨選択して顧客ニーズの動向を追求します。顧客ニーズは、社会情勢や消費者環境の影響を受けて日々変わるため、調査が欠かせません。
調査により得たデータと、自社の特徴部分を組み合わせて差別化することが大事です。差別化は、競合他社にない独自的な特徴となるため、Web集客の重要な武器となります。
コストや労力を費やすのも一つの手段
Web集客は、労力やコストの掛からない方法に固執しない考え方を持ちましょう。Web集客は、無料で手間の掛からない施策ではありません。すべての施策には、仕組みをつくるための時間や知識習得の段階があります。
Web上には、「無料で稼げる」ことを訴求する情報などもありますが、ビジネスとして成功するには、労力やコストを掛けた土台づくりが大事です。
自社商材と集客チャネルの相性は無視しない
Web集客では、自社商材と集客チャネルの相性を無視しないことが重要なポイントとなります。Instagramが人気だからといって、自社商材との相性を考えずに広告を出稿しても反響を得られないかもしれません。SNSだけではなくWeb集客で活用する媒体には、それぞれ相性のよい属性があるため、チャネルごとに自社ビジネスとの相性を調査する必要があります。
市場調査や顧客調査など分析作業は、経験が必要です。市場分析においては、専門家の見解を参考にすることをおすすめします。
あわせて読みたい
ターゲット顧客の理解
ターゲット顧客の理解は、効果的なWeb集客戦略を構築するための重要なステップです。顧客のニーズや興味、行動パターン、購入の決定要因などを把握することで、最も響くメッセージを伝え、最適なタイミングで届けられます。また、ユーザーペルソナを作成することで、顧客像を具体化し、チーム全体で顧客理解を深めることが可能です。
目標設定とKPIの設定
明確な目標とKPIの設定は、Web集客戦略の進行状況を測定し、成功を評価するために不可欠です。目標は具体的、測定可能、達成可能、関連性のある、時間制限のある(SMART)ものであるべきです。KPIは、その目標達成をどのように測定するかを示します。例えば、ウェブサイトのトラフィック、リードの生成、コンバージョン率などが考えられます。
カスタマージャーニーの作成
カスタマージャーニーを作成することも、Web集客を成功させるためのカギとなります。カスタマージャーニーとは、顧客が商品やサービスを購入するまでのプロセスを可視化したものです。カスタマージャーニーを作成する目的は、顧客が商品を知って検討し、実際に購入に至るまでのタッチポイントを洗い出すことです。顧客の思考や気持ちの変化を把握することができるため、最適なマーケティング戦略が立てられます。
自社のコンテンツを整理
自社のコンテンツを整理しましょう。これまでのコンテンツは、自社の武器となり資産となります。コンテンツが整理されていなければ、いくら有益な情報を発信していたとしても、ユーザーが求めている情報まで辿り着きません。
また、コンテンツは二次利用して活用することがおすすめです。これまでのコンテンツを整理し社内で把握しておきましょう。一度提供したコンテンツを使い回すことで「コンテンツの資産運用」が可能となるのです。
Webサイト運用体制の構築
Web集客を効率的に行うためには、Webサイトの運用体制を構築しておくことが大切です。例えば、Webサイトの運用にはコンテンツ企画や画像の更新、アクセス解析、お問い合わせ対応などさまざまな業務があります。これらのタスクを円滑に行える体制を整えておくことが、Web集客戦略を最大限に発揮させる秘訣となるのです。

めぐみやのWeb集客コンサルティング
Webサイトを活用して売上と利益向上を目指しませんか?
めぐみやが集客からサイト運営まで一貫してサポート致します。
Web集客の効果測定と改善
Web集客の成功を実現するためには、その効果を定期的に測定し、必要に応じて戦略を修正することが重要です。例えば、Web解析ツールの活用、A/Bテストの実施、そして改善を繰り返すというステップが挙げられます。これらのプロセスを通じて、Web集客の効果を最大化し、継続的にビジネス成果を向上させることが可能です。
このプロセスは一定の周期で行われ、その結果をもとに最適なマーケティング戦略を継続的に作り上げていくことが求められます。
Web解析ツールの活用
Web解析ツールは、Webサイトの訪問者の行動を詳細に追跡し分析するための重要なツールです。Google Analyticsなどの解析ツールを活用することで、ユーザーの行動パターン、流入源、最も人気のあるコンテンツなど、Web集客の成果を明確に把握できます。分析した情報を活用することで、より効果的なマーケティング戦略を策定し、改善できるのです。また、これらのツールは定量的なデータだけでなく、質的な情報も提供してくれます。たとえば、訪問者がサイト内でどのような経路を辿っているのか、どのページで離脱しているのかなどの情報も得られます。
A/Bテストの活用
A/Bテストは、2つの異なるバージョンのWebページや広告を一部のユーザーに表示し、どちらがより良いパフォーマンスを発揮するかを比較する手法です。このテストは、具体的なデータに基づいてWebサイトのデザインやコンテンツを改善するための有効な手段となります。また、A/Bテストはユーザー体験の最適化とコンバージョン率の向上に不可欠なツールです。各バージョンのパフォーマンスを比較することで、ユーザーが最も反応するデザインやコンテンツが何であるかを把握し、結果を基に改善を行うことができます。また、A/Bテストを定期的に行うことで、マーケティング戦略を常に最適な状態に保つことが可能になります。
PDCAサイクルの実施
PDCAサイクルとは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)のプロセスを繰り返し、業務効率を高めるための改善方法です。PDCAサイクルを的確に回すことで、目標達成や成果を出すためにやるべきことが見えてきます。まずは明確な目標を立てることが大切です。詳細な目標と期限を決め、定期的に進捗を確認するようにしましょう。
改善の繰り返し
効果的なWeb集客戦略は一度に完成するものではありません。Web解析ツールで得たデータを元に、A/Bテストを通じて何が最も効果的であるかを見つけ出し、その結果をもとにWebサイトや広告キャンペーンを改善する、というプロセスを繰り返すことが重要です。このようにして、継続的な改善を行うことで、最終的にはより多くの顧客を獲得し、ビジネスの成果を向上させることができます。一度設定した戦略を固定するのではなく、常に変化する市場環境や顧客のニーズに応じて戦略を見直し、修正し、最適化することを意味します。このプロセスを通じて、企業はより効果的なWeb集客を実現し、経済的な成功を達成することができます。
あわせて読みたい
Web集客は調査と実益を兼ねた併用が大事
Web集客は、調査と実益を兼ねて、日々の実績を積み重ねていくことが大事です。やみくもにWebサイトを作ったり、広告を掲載したりするのではなく、すべてを実績として活かす考え方で取り組みましょう。
長期目線で企画と運用計画を
Web集客では、軸となるWebサイトの構築が必要です。まずは、長期目線でWebサイトの企画と運用の計画を立てることから始めます。Webサイトの運用は、長期的な取り組みです。
Webサイトを評価する検索エンジンに認められて、検索結果ページに表示されるまで必要なコンテンツを追加したり、調整したりを繰り返して育てる時期が必要となります。
市場調査のためにリスティング広告を出稿
Webサイトのテーマやコンテンツ内容を設定するには、市場調査が必要です。市場調査のツールとしてスポット的にリスティング広告を出稿することは、データの入手方法として効果があります。リスティング広告は、出稿したいキーワードの入札で掲載権利を獲得できれば、すぐに反応を確かめられます。
自社ビジネスが市場において、どの程度価値があるのか?結果次第では、軌道修正も必要になるでしょう。
調査で得た結果をWebサイトに反映
リスティング広告の出稿により得た検索需要の結果は、Webサイトのテーマやコンテンツ設計に反映させます。実際の検索ニーズから得たデータの活用となるため、実現性の高い取り組みとなるでしょう。入手したデータは、Webサイトのコンテンツに活用するうえで、主観的な判断ではなく、あくまでもユーザー目線となる客観的な判断が求められます。
専門知識や経験が不足していたら専門家へ依頼
Webサイトの設計段階では、専門知識や経験が必要です。経験を積み重ねることが目的でない限り、専門知識と経験値を専門家の依頼で解決することが結果的にメリットを持たらすでしょう。
専門家の経験と知識を早く得るメリット
専門家の経験と知識を早く得るメリットは、3つあります。
●結果的に時短となる
Webサイトの企画から制作、運用は一筋縄に進められません。最終目的となるビジネスゴールやビジネスカテゴリ、競合優位性、顧客属性により異なります。Web上にある情報だけを頼りにして運用したとしても、同じ結果を出せる保証がないのが現状です。
そのため、早い段階から専門家に依頼して専門家の知見と実績を活かせれば、結果的に時短となります。
●ムダな労力を減らせる
専門家に依頼することは、無駄な労力の削減になります。Web集客を必要とする人は、何らかのビジネス(商材)を扱う事業者です。そのため、本来ならば事業に専念して集客の負担を減らすことが理想ではないでしょうか。
専門家への依頼は、本業における自社商材の品質向上や顧客管理に注力できる時間の創出が可能です。「餅は餅屋」ということわざのように、不得意分野に掛けるムダな労力を減らす方向で考えることがポイントになります。
●経験が反映されるため成功しやすくなる
専門家への依頼は、専門家が積み重ねてきた経験を自社Web集客への反映となります。プロの経験が反映されるため、未経験者が実行した集客よりも成功しやすくなるのは当然です。
専門家に依頼する際のリスク
専門家への依頼は、メリットばかりではありません。依頼する際のリスクも考えられます。
●費用が掛かる
専門家への依頼は、Web集客の対価として費用が発生します。一概には言えませんが、ビジネス規模や負担する範囲、目標とする見込み売上などで費用が異なります。
そのため、事前に打ち合わせが必要です。専門家により提供できるサービスも特徴があります。まずは、気軽に問い合わせてみることから始めてみましょう。
●ノウハウを残せない
専門家への依頼は、ノウハウの伝授ではありません。あくまでも成果に向けた取り組みです。専門家への依頼は、依頼する顧客に対して成功への近道をたどることになります。そのため、取り組み施策に対して、依頼主の判断待ち状態にしてしまうとなかなか進まない状況を作り出すでしょう。
依頼する場合は、自社にノウハウが残らないことを前提にして、集客を委任する姿勢でのぞむことが必要です。
Web集客を専門家に依頼する最大のメリット
Web集客を専門家に依頼するメリットは、日々変わるWeb事情に対して変化への対応を任せられることです。
●Web環境の変化への対応を任せられる
Web環境の変化は、実社会の変化以上にスピード感があります。1年前まで有効だった仕組みが使えなくなったり、無料で使えていたツールが有料化したりと、変化のスパンが容赦なく訪れるのが特徴です。Web集客の専門家は、Web環境の変化に対して、日々アンテナを張り巡らしている状態となります。
もし、依頼主の企業様がご自身でWeb環境の変化を追求する場合は、本業の片手間でこなすことが難しくなります。Web集客は、いまや集客方法の中心的存在です。そのため、今後も参入する業者が増えることが考えられます。つまり、競合が増えれば、施策の精度も向上させなければ通用しなくなるでしょう。
本業の片手間でできるほど簡単な取り組みではありません。専門家への依頼は、早ければ早いほど、自社ビジネスの特徴をWeb集客向けにカスタマイズできます。それらの対応も含めて任せられる点が最大のメリットではないでしょうか。
●本業に集中できる
さらに、Web集客を専門家に任せることは、依頼主のビジネスに取り組む姿勢を整える役割もあります。先ほども触れましたが、本業を抱えながら片手間でWeb集客を実施しても良い結果は期待できません。たとえ、一時だけ結果を出したとしても長続きできる構想まで考察できないでしょう。
ECサイトの店主は、販売する商品に対して時間を掛けることが必要です。Webサイトのデザインやバナーの大きさに試行錯誤している時間が結果的に無駄な時間となります。本業に集中できることは、商品に磨きをかけることです。ぜひ、切り分けて考えることをおすすめします。
まとめ
本記事では、Web集客について最新の状況からどのように進めていけば良いか?ポイントやWeb集客の種類など紹介してきました。Web集客は、多様化するニーズと同じく、あらゆる媒体を活用できます。この記事で紹介した手法を手当たり次第に活用するのではなく、自社ビジネスと市場の動向、ターゲット属性にあわせて考えることが必要です。
そのためには、専門家の知識と実績が活かされる分野でもあります。ひと昔前のホームページ制作とは格段に違うレベルで競合他社と差別化が必要です。テレワークが常態化している昨今では、これからますますWeb需要が浸透するでしょう。そのため、早くから集客チャネルを確立するための判断が明暗を分けます。とても未経験者では太刀打ちできない状況です。まずは、専門家への気軽な相談から始めてみましょう。
- Web集客はターゲット層に合わせたコンテンツの最適化が重要
- 効果的なWeb集客は多チャンネル戦略とデータ分析が鍵
- 検索エンジンの活用はWeb集客の基本
あわせて読みたい
Web集客の方法に関するよくあるご質問
最後によくあるご質問をいくつかご紹介致します。
みなさまのWeb集客にお役に立てば幸いです。
その他、ご不明な点がございましたら以下のリンクよりお気軽にご相談下さいませ。
無料オンライン相談はこちらからどうぞ。
Q
Web集客とは何ですか?
A
Web集客は、ウェブサイトやSNSなどのインターネットを活用して、新しい顧客を獲得または既存の顧客との関係を深化させる手法のことを指します。
Q
効果的なWeb集客の方法は?
A
効果的なWeb集客には、SEO(検索エンジン最適化)、SEM(検索エンジンマーケティング)、コンテンツマーケティング、SNSマーケティングなどがあります。
Q
SEOとは何ですか?
A
SEOは、検索エンジンの結果ページでのウェブサイトの順位を上げるための最適化手法を指します。主に、キーワードの選定、内部・外部の最適化が行われます。
Q
SNSマーケティングのメリットは?
A
SNSマーケティングのメリットは、ターゲットとなる顧客との直接的なコミュニケーションが可能であり、ブランドの認知度向上や顧客ロイヤリティの向上が期待できることです。
Q
コンテンツマーケティングの重要性は?
A
コンテンツマーケティングは、価値ある情報を提供することで顧客の信頼を獲得し、長期的な関係を築くことができる手法です。質の高いコンテンツを提供することで、ブランドの価値を高めることができます。
Q
ペイドアド(有料広告)の役割は?
A
ペイドアドは、短期間での集客や特定のキャンペーンの支援として有効です。広告をクリックするごとに費用が発生するPPC(ペイ・パー・クリック)や表示回数に応じて費用が発生するCPM(コスト・パー・ミリ)などがあります。
Q
メールマーケティングの活用方法は?
A
メールマーケティングは、ニュースレターやキャンペーン情報を顧客や見込み顧客に直接送信する方法です。セグメント化されたターゲットリストを活用することで、効果的なコミュニケーションが可能です。
Q
Web集客の成功指標は?
A
Web集客の成功指標には、サイトの訪問者数、コンバージョン率、平均セッション時間、直帰率などがあります。
Q
ランディングページの最適化のコツは?
A
ランディングページの最適化のコツは、明確なコール・トゥ・アクション(CTA)、分かりやすいデザイン、信頼性を高める要素の追加、ページの読み込み速度の向上などです。
Q
Web集客のためのリターゲティングとは?
A
リターゲティングは、一度サイトを訪れたがアクションを起こさなかったユーザーに再度広告を表示する手法です。過去の行動に基づいたターゲティングが可能で、高いコンバージョン率を期待できます。
Q
モバイル最適化の重要性は?
A
モバイル最適化は、スマートフォンやタブレットのユーザーが増えている現代において、ユーザーエクスペリエンスを向上させるために不可欠です。モバイルフレンドリーなデザインは、SEOにも寄与します。