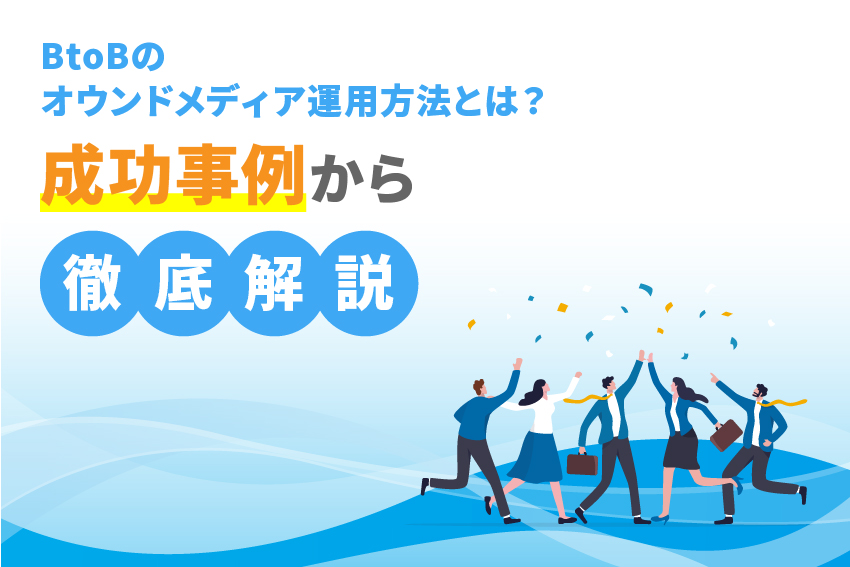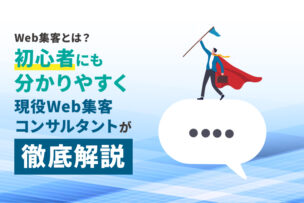記事の監修

Web集客・マーケティングの専門家として、13年間にわたり厳格な基準と緻密な戦略をもって中小企業の成功を導く。
一時的な集客の手法に頼ることなく、中長期的な効果を持続させる本質的なWeb集客の構築に注力。
『恵ある集客を。』をスローガンに掲げてクライアント様のサービスや商品の核心的な魅力を、的確にターゲットに伝えることを重視したWebサイト運用をサポート。
企業が自社発行の広報誌やパンフレットにより、見込み客との信頼関係を構築していく取り組みをWeb上でサイトやブログにより展開していく媒体となるオウンドメディアについて、今回はBtoBを基準に解説していきます。
BtoBにおけるオウンドメディアを立ち上げる時や運用時には、どのような点に注意をしていけばよいのでしょうか?特に、企業が運営するオウンドメディアは、ビジネスにつながらなければ意味がありません。
そのため、オウンドメディアを売上(リード獲得)につなげるためにはどうしたよいのか?BtoBのオウンドメディア活用事例となる厳選5サイトも交えて紹介していきましょう。オウンドメディアの運用を検討している企業のWeb担当者の参考になれば幸いです。
- オウンドメディアのBtoB活用について知りたい方
- 企業におけるオウンドメディアのメリットを知りたい方
- BtoBオウンドメディア成功ポイントを知りたい方
目次
オウンドメディアとは?
オウンドメディアとは、企業や個人が自ら所有・運営するメディアのことです。これにはウェブサイト、ブログ、SNSアカウントなどが含まれ、自由にコンテンツを公開できるプラットフォームとなっています。特にBtoBにおいて、オウンドメディアは非常に有効なマーケティング手段とされています。
一般的な広告やPR活動は、高い費用がかかる上に効果が一時的であることが多いです。しかし、オウンドメディアは比較的低いコストで継続的に情報を発信できます。その結果、長期的に顧客との信頼関係を築くことが可能です。
また、オウンドメディアを通じて専門知識や成功事例を共有することで、ターゲットとなるビジネスパートナーに対して自社の価値を明確にアピールできます。 BtoBビジネスにおいては、一般消費者よりも専門性や信頼性が求められるため、そのような情報提供は非常に効果的です。
さらに、オウンドメディアはSEO(検索エンジン最適化)にも貢献します。質の高いコンテンツを継続的に提供することで、検索エンジンの評価が高まり、自社ウェブサイトへのアクセスが増える可能性が高くなります。これがリード生成につながり、新たなビジネスチャンスを生み出すためには重要です。
オウンドメディアはBtoBビジネスにおいては、コスト効率が良く、長期的な信頼関係の構築、専門性の証明、SEO効果の三つの大きなメリットがあります。そのため、多くの企業がオウンドメディアの導入と運営に力を入れています。
BtoBにおけるオウンドメディア起ち上げの状況
昨今、企業がオウンドメディアを起ち上げることはめずらしくありません。BtoBにおけるオウンドメディアを起ち上げている状況では、次のような目的が考えられます。
オウンドメディアには、顧客獲得だけではなく会社の運営に関わる全般的な部分に影響を与えていく可能性があるのです。しかし、オウンドメディアを起ち上げている企業の多くは、「競合がやっているから」「今、注目されているから」という理由だけで取り組んでいます。
オウンドメディアを起ち上げる状況では、途中で挫折をしないで続けていくための注意点や考え方が必要になるのです。では、順を追って解説していきましょう。
なぜ、オウンドメディアなのか?
はじめに、BtoBがオウンドメディアを起ち上げる理由について取り上げてみました。オウンドメディアは、Web上における自社の長期的な資産となるのです。Web上の資産となるサイトやブログが、ユーザーとのコミュニティを作るコンテンツとなります。
それでは、BtoBにおけるオウンドメディアがどのようなコンテンツとなるのか?紹介しましょう。。
企業が持つユーザーとつながる発信媒体
オウンドメディアは、企業の資産となる発信媒体です。企業情報全般をユーザーの視点から発信していくことが基本スタンスになります。
コンテンツマーケティングの有望施策
さらに、オウンドメディアは、検索エンジンの評価を高める基準となる良質なコンテンツ制作の取り組みです。そのため、コンテンツマーケティングによるWeb集客では、オウンドメディアが有望な施策になるでしょう。
企業におけるオウンドメディアのメリット
次に、BtoBにおけるオウンドメディアの起ち上げについて、メディアを発信する企業にとって、どのようなメリットがあるのでしょうか?オウンドメディアを運営していくことで得られるメリットを紹介します。
ユーザービリティを向上できる
企業が発信するコーポレートサイトは、「会社の名刺やパンフレット」のような内容がほとんどです。そのため、ユーザーにとって「自分ごと」のように受け入れられないことが考えられます。
オウンドメディアは、コーポレートサイトのような企業情報の発信を優先したWebサイトではありません。優先されるのは、ユーザーに役立つことです。結果、ユーザーに役立つ情報を発信することにより、ユーザービリティが向上されます。
あわせて読みたい
競合と差別化できる(ブランディング)
オウンドメディアは、競合との差別化ができます。その理由は、オウンドメディアから発信していくコンテンツが自社の強み部分になるからです。自社の強みにより競合と差別化ができれば、ブランディング効果にもなり、長期的に安定した運用が目指せます。
あわせて読みたい
顧客の信頼と共感を獲得
オウンドメディアは、ユーザー目線による情報発信となるので、見込み客の信頼度を高めることができます。そして、ユーザービリティの高い居心地のよさが顧客に共感を与えていくことになるのです。
あわせて読みたい
オンライン上の営業資料となる
オウンドメディアの基本スタイルは、顧客目線であることと、ユーザーの抱える問題、商品を使った後の未来などの情報が蓄積されていきます。その豊富な情報がオンライン上で活用できる営業資料にもなるのです。
長期的に活用できる施策
競合と差別化されたオウンドメディアは、ブランディング効果も上がってきます。そのため、競合との価格競争や付加サービス戦略の必要がない安定した運営が見込めるのです。安定したオウンドメディアの運営は、長期的に活用することができるでしょう。
あわせて読みたい
企業におけるオウンドメディアのデメリット
オウンドメディアを起ち上げた先に見えてくるブランディング効果によるメリットは、長期的な施策となります。しかし、企業にとって次に紹介する3つのデメリットを乗り越える必要もあるのです。
継続にリソースが必要
オウンドメディアは、常にユーザーが興味を持つコンテンツを作り続けるための体力が必要になります。それは、企画やサイト構成、画像、動画、記事作成に携わる人的リソースのことです。
オウンドメディアに訪問するユーザーを増やすためには、日々のコンテンツ制作や更新、解析による改善などをくり返し続けていく必要があるでしょう。そのための人的リソースを確保することが大前提です。
長期的な施策のため時間がかかる
上記に取り上げたオウンドメディア制作と運用へのリソースを長期的に行うことが自社発信の媒体を資産化させていく活動になります。つまり、オウンドメディアの構築と運用は、時間のかかる長期的目線での施策となるのです。
質の高いコンテンツ制作が必要
また、オウンドメディアはコンテンツを増やすことが重要だからと言って、闇雲に記事を量産追加することではありません。オウンドメディアは、SNSなどで拡散されるような質の高いコンテンツの制作が必要なのです。オウンドメディアのコンテンツは、シンプルでユーザーの興味を引くことが求められます。
あわせて読みたい
BtoBオウンドメディア運営の手順
オウンドメディアは、先述の通り企業が自らのプラットフォームで情報を発信する手段です。BtoB市場においてもその有用性は高く、正確な戦略と運営手順が求められます。以下に、BtoBオウンドメディアを成功させるための基本的な手順を解説します。
目標設定
成功のためには明確な目標設定が不可欠です。このステージで何を達成したいのかを明確にし、それに応じたKPI(Key Performance Indicator)を設定します。たとえば、売上向上を目標とするなら、月々のリード数や成約数をKPIとして設定できます。また、ブランド認知度を高める場合は、ウェブサイトの訪問数やページビュー、ソーシャルメディアでの言及数などが考慮されるでしょう。目標設定が不明確だと、後の運営で方向性を見失うリスクが高まります。しっかりと目標を設定して、その達成に必要な指標を明確にすることが第一歩です。
ターゲット設定
読者層のニーズを正確に把握することがターゲット設定の鍵です。企業が提供する製品やサービスに最も興味を持ち、購入する可能性の高い層を特定します。さらには、この層が抱える疑問や課題に対する解決策を提供できるコンテンツを検討します。購買段階や業種、役職なども考慮に入れ、できるだけ詳細なターゲット・ペルソナを作成すると良いでしょう。
コンテンツプランニング
一度ターゲットと目標が設定されたら、次はどのようなコンテンツを作るかの詳細な計画を立てます。テーマ、キーワード、投稿頻度などを決定する際、SEO(検索エンジン最適化)も考慮することが重要です。例えば、重要なキーワードに対するランキングを向上させることで、目標とする読者層からの訪問数を増やす戦略が考えられます。
コンテンツ作成
コンテンツは読者にとって価値のあるものでなければなりません。記事はもちろん、ビデオやインフォグラフィック、ポッドキャストなど、多様なフォーマットで高品質なコンテンツを提供します。重要なのは、目標とする読者層が求める「価値」をしっかりと提供すること。そのためには事前のリサーチとその結果を反映した質の高いコンテンツ作りが求められます。
プロモーション
コンテンツが完成したら、効果的なプロモーション戦略を考えます。SNS、メールマーケティング、他のメディアとの連携など、多角的なアプローチで目標とする読者層にリーチする方法を検討します。特に、他の業界関連メディアとの連携やゲストポスティングは、新たな読者層を獲得する良い手法とされています。
分析と改善
最後に、データを基にした分析と改善が必要です。Google Analyticsなどのツールを用いて、KPIと実績を定期的にチェックします。必要な改善点を特定したら、それを次のコンテンツ作成やプロモーションに生かし、継続的にオウンドメディアを成長させていきます。
各ステップでの詳細な計画と実行、そしてその結果と改善が、BtoBオウンドメディアの成功へとつながります。
BtoBオウンドメディア成功ポイント

オウンドメディアは、企業が直接所有しコントロールできるメディアですが成功への道は簡単ではありません。特にBtoBの文脈でオウンドメディアを効果的に運用するためには、独自の戦略とテクニックが求められます。以下、その成功ポイントをいくつか解説します。
ターゲットオーディエンスの明確化
先述しましたがBtoBオウンドメディアにおいて最も重要なのは、誰に何を伝えるのかを明確にすることです。これは従来のマーケティングにおいても同じですが、オウンドメディアにおいては尚更のこと。具体的には、企業が目指すターゲット層の課題やニーズを徹底的に研究し、それに対する解決策や価値をコンテンツで提供する必要があります。この工程が曖昧であれば、どれだけ優れたコンテンツを作成しても、それが正確に届く保証はありません。先ずは、ターゲットオーディエンスを特定し、その人々が抱える問題や欲求を明らかにすることから始めましょう。
高品質なコンテンツ作成
BtoBにおけるオウンドメディアでの成功のためには、高品質なコンテンツが必要不可欠ですが、単に量をこなすのではなく、質にこだわるべきです。具体的には、業界のトレンド、新しいテクノロジー、ケーススタディなど、対象オーディエンスが価値を感じる情報を提供することが重要です。また、検索エンジンを通じて新たな読者を獲得するためには、SEO対策がしっかりと施されたコンテンツが不可欠です。
一貫したブランドメッセージ
オウンドメディアは企業のブランド戦略の一部です。そのため、全てのコンテンツでブランドメッセージを一貫させることが必要です。例えば、企業のミッションやビジョンに基づいて、コンテンツが作成されるべきです。読者が様々なコンテンツを通して同じ核となるメッセージや価値観を感じることで、ブランドへの信頼と認知が高まります。
データ分析と改善
こちらも先程説明しましたがコンテンツが公開されたら終わりではありません。アクセス解析ツールを使って効果を測り、改善を繰り返すことが重要です。Google Analyticsなどのツールを用いて、どの記事がよく読まれているのか、どのキーワードで検索されているのかを把握しましょう。そのデータを基に、さらに読者の興味を引くような新しいコンテンツを企画することが成功へと繋がります。
長期的な視点
オウンドメディアは短期的な成果よりも、長期的にビジネスを支える重要なマーケティング資産です。短期的な成果に目を奪われがちですが、一度築き上げたオウンドメディアの価値は長期にわたって収益やブランド価値に寄与するため、短期的な数字に一喜一憂せず、着実な成長を目指しましょう。
このように、BtoBオウンドメディア成功のためには多角的なアプローチと戦略が必要です。それぞれのポイントが連動し合うことで、成功への道が開かれるでしょう。
BtoBのオウンドメディア起ち上げ時の注意点
続いて、BtoBにおけるオウンドメディアの注意点を“起ち上げ時”と“運用時”に分けて解説しましょう。まず、オウンドメディアの起ち上げでの注意点からです。
目的とゴールは設定されているか
オウンドメディアは、長期的な施策となることと、サイトボリューム的にも膨大な量になる可能性があります。そのため、自社の「目指すゴール」をオウンドメディアの目的として設定する必要があるでしょう。もし、ゴールを設定しないで運用開始した場合、途中でオウンドメディアの本来の目的とちがう方向性に進んでしまうことも考えられるからです。
伝えたい相手「ペルソナ」は明確になっているか
自社の目的と同時に設定しておくべき指標として、ターゲット設定があげられます。ターゲット設定は、自社の目的となるゴール実現の対象となるターゲット顧客のことです。具体的なターゲットを設定するには、伝えたい相手となるペルソナ(ターゲットとなる架空の個人)を明確にしましょう。
コンセプトに沿ったコンテンツが必要
さらに、膨大な情報量となるオウンドメディアには、コンセプトが必要になります。最初に設定した“目的”から展開するメディアコンセプトです。コンセプトは、経営理念のようなイメージですが、あくまでも「ユーザー目線」のコンセプトに沿って作成しましょう。
コンセプトに沿ったオウンドメディアは、更新されていくコンテンツにも一貫性が保たれていきます。その積み重ねが、専門性と信頼性を生みだすのです。
運用体制は準備できているか
先ほどのデメリット部分でも取り上げましたが、オウンドメディアは片手間で起ち上げられるほど簡単な取り組みではありません。そのため、社内の人的リソースをオウンドメディアの制作や運用につぎ込む必要があります。
自社が本来行うべき業務に必要なリソースを確保したうえで、事前に運用体制を確認することが大事です。
メディアコンテンツの配信は計画的に
また、オウンドメディアを起ち上げる段階において、コンテンツの配信計画も設定しておく必要があります。オウンドメディアの運用計画にもなる施策スケジュールは、企画段階や構成制作の段階である程度、明確に設計図を作成することが望ましいでしょう。
あわせて読みたい
BtoBのオウンドメディア運用時の注意点
オウンドメディアをWeb上に公開すると、一息つきたくなるかもしれません。しかし、オウンドメディアは、これからが始まりです。運用開始から油断することにより、なかなか成果の出ない媒体となり、途中で運用中止にならないように注意しましょう。
定期的な振り返りが重要
オウンドメディアの運用時の注意点として、最も重要な点が“振り返り”です。さらに定期的で小まめな振り返りが必要になります。
Googleアナリティクスの活用
「運用開始したオウンドメディアにどの程度のアクセスがあるのか?」日々のアクセス解析による分析は重要です。ただし、運用開始したばかりではアクセス数を期待できません。将来的にメディアの成長過程も確認できるGoogleアナリティクスを導入して、日々のアクセス状況を確認できるようにしましょう。
サーチコンソールの活用
また、Googleアナリティクスとサーチコンソールを連携させることにより、メディアのサイト診断状況も確認できます。
修正と改善をくりかえす
定期的な変動がある検索エンジンへの対応のため、サーチコンソールを活用したサイト改善も必要です。このように、オウンドメディアは、解析と診断により修正と改善をくり返していく取り組みが必須になります。
コンテンツ制作が目的にならないようにする
さらに、運用を取り組む中で本来の目的を見失わないようにしましょう。オウンドメディアを起ち上げた目的から外れて、コンテンツ制作が目的になってしまうと自社が目指す目的とずれていくことも考えられるからです。
定期的な更新が必要
オウンドメディアは、ブログのように定期的な記事の更新が必要になります。その理由は、記事の更新が検索エンジンの評価基準の1つになるからです。多くの企業が記事の更新を継続することに負荷を感じる中、いかに「更新を続けていけるか」がポイントとなります。
見込み客とのコミュニケーションを怠らない
運用における最後の注意点として、見込み客とのコミュニケーションをとることも忘れないようにしましょう。少ないアクセスでも自社のメディアに訪問してきたユーザーとのコミュニティとなるように、問い合わせ可能なフォームを用意しておくことも必要です。
あわせて読みたい
オウンドメディアを売上につなげるための考え方
それでは、BtoBにおけるオウンドメディアをリード獲得(売上)につなげるための考え方について案内します。
オウンドメディアで売上を求め過ぎない
オウンドメディアは、直接購買行動を起こしてもらう販売サイトではありません。あくまでもユーザーとつながるコミュニティの場です。そのため、売上を求め過ぎないようにしましょう。
製品のPRや宣伝をし過ぎない
売上を求め過ぎないということは、自社製品のPRや宣伝も極力抑えることが必要です。売り込み臭いメディアになると、企業の販売サイトと同じ扱いになります。
あくまでもユーザー目線による良質な情報発信
あくまでも、ユーザー目線の役立つ情報を配信する姿勢を基準としていくことです。結果的にユーザーの信頼と共感を得られるようになり、製品の購入にもつながります。それまでは、メディアを成長させることに注力するのです。
ユーザーが納得した上でリード獲得へのコンテンツにナビゲート
オウンドメディアにより、ユーザーの信頼と共感が得られるようになれば、製品などの訴求にも納得されるようになります。その時点からようやく、リード獲得へのコンテンツをメディアに導入し、購買につながるナビゲートをしていくのです。
リード獲得後のクロージング
オウンドメディアのコンテンツ経由でリード獲得のナビゲートが施された後は、メディアからランディングページへ誘導してクロージングします。それは、顧客に全面的に納得された状態でのクロージングとなるのです。
あわせて読みたい
BtoBのオウンドメディア活用厳選5事例
最後にBtoBにおけるオウンドメディア活用事例として、5つのメディアを紹介しましょう。
ROHM TechWeb
IoT機器など電子部品メーカーのローム株式会社が運営するオウンドメディアは、エンジニアを対象とした設計技術情報を無料動画セミナーなど交えて配信しています。
参考サイト:ローム株式会社 オウンドメディア
RENESAS ENGINEER SCHOOL
コンテンツ配信の対象者を専門技術者ではなく、初心者向けに基礎から伝える電子回路、マイコンピュータを扱うルネサスエレクトロニクス株式会社です。
参考サイト:ルネサスエレクトロニクス株式会社 オウンドメディア
マーキング学習塾
マーキング学習塾を運営する株式会社キーエンスは、レーザマーカに特化した学習サイトを詳細に情報配信しています。
参考サイト:株式会社キーエンス オウンドメディア
Tech-Compass
電化製品だけではなく、新エネルギーにも開発の余念がない三洋電気株式会社は、自社の技術を惜しみなく公開しているのです。その対象は、テクノロジー開発に関わるユーザーが対象になります。
参考サイト:三洋電気株式会社 オウンドメディア
cadjapan.com
株式会社大塚商会では、オフィスワークのデジタル化に向けてオートデスク商品について、ユーザー目線に立って建設業界や製造業への情報を配信しています。
参考サイト:株式会社大塚商会 オウンドメディア
まとめ
いままでは、BtoCにおけるオウンドメディアが主流でしたが、今後はBtoBにもオウンドメディアの活用が増えてくることが考えられるでしょう。今回、取り上げた注意点と考え方を企業が発信するオウンドメディア制作と運用のヒントとして、途中で挫折しない自社媒体資産の形成に役立ててみてください。
また、オウンドメディア制作と運用は専門性が高いことから、計画段階で専門業者に相談してみることで人的リソースと時間コストの削減につながるでしょう。
- BtoBのオウンドメディアはWeb上で企業が自由にコンテンツを公開できる長期的な資産
- BtoBにおけるオウンドメディアは顧客との長期的な信頼関係を築き専門知識を示すコスト効率の高いマーケティング手段
- オウンドメディアの運用には魅力的なコンテンツの継続的な制作、リソースの割り当て、長期的な取り組みが必要

めぐみやのWeb集客コンサルティング
Webサイトを活用して売上と利益向上を目指しませんか?
めぐみやが集客からサイト運営まで一貫してサポート致します。
BtoBのオウンドメディアに関するよくあるご質問
最後によくあるご質問をいくつかご紹介致します。
みなさまのWeb集客にお役に立てば幸いです。
その他、ご不明な点がございましたら以下のリンクよりお気軽にご相談下さいませ。
無料オンライン相談はこちらからどうぞ。
Q
オウンドメディアとは何ですか?
A
オウンドメディアは、企業や個人が自らのリソースを活用して制作・運営するメディアのことを指します。コンテンツマーケティングの一環として、情報の提供やブランドの価値向上を目指すものです。
Q
BtoBのオウンドメディアの目的は何ですか?
A
BtoBのオウンドメディアの主な目的は、ターゲットとなるビジネスパートナーや企業に対して専門的な情報や価値を提供し、信頼関係の構築やリード獲得を目指すことです。
Q
BtoB向けオウンドメディアのコンテンツの特徴は?
A
BtoB向けのオウンドメディアでは、業界のトレンド、専門的な知識、ケーススタディなど、具体的で深い情報が求められます。一般的な情報よりも、ターゲットとなる企業やビジネスマンに有益な情報を提供することが重要です。
Q
オウンドメディアの運営に必要なリソースは?
A
オウンドメディアの運営には、コンテンツの制作、SEO対策、更新頻度の管理、分析・評価など、多岐にわたるリソースが必要です。特に、質の高いコンテンツを継続的に提供するためには、専門的な知識やスキルが求められます。
Q
BtoBオウンドメディアの効果的な推進方法は?
A
BtoBオウンドメディアを効果的に推進するためには、ターゲットのニーズを正確に把握し、それに応じたコンテンツの提供、SEO対策の強化、ソーシャルメディアなどの外部メディアとの連携が重要です。
Q
オウンドメディアの成功のポイントは?
A
オウンドメディアの成功のポイントは、ターゲットとなる読者のニーズを深く理解し、継続的に価値あるコンテンツを提供すること。また、定期的な分析と改善を繰り返し、読者の反応や変化に柔軟に対応することが求められます。
Q
BtoBのオウンドメディアでのリード獲得の方法は?
A
ホワイトペーパーの提供、ウェビナーの開催、無料トライアルやデモの提供など、価値あるコンテンツやサービスを通じて、訪問者の情報を収集し、リードとして獲得する方法があります。
Q
オウンドメディアのROIを上げる方法は?
A
ROIを上げるためには、効果的なコンテンツマーケティング戦略の策定、ターゲットとなる読者の正確なセグメンテーション、高品質なコンテンツの制作、定期的な分析と最適化が必要です。
Q
BtoBのオウンドメディアのモニタリングツールは?
A
Google Analyticsなど、訪問者の動向やコンバージョンを詳細に分析することができるツールが多くあります。これを利用して、オウンドメディアの効果を定期的に評価・最適化することが推奨されます。
Q
BtoBオウンドメディアの長期的な戦略とは?
A
BtoBオウンドメディアの長期的な戦略は、ブランドの信頼性の構築、専門的な情報の提供を継続することで、リード獲得やカスタマーエンゲージメントを持続的に高めることを目指すものです。