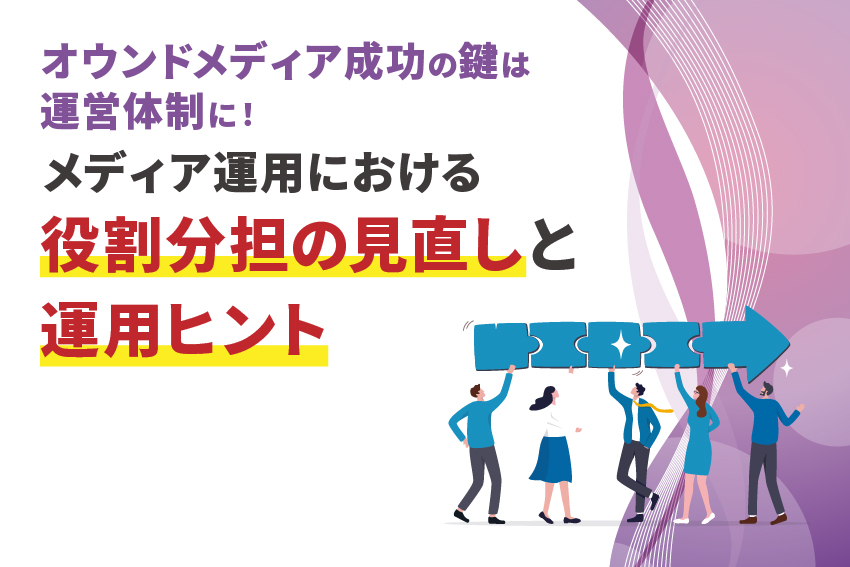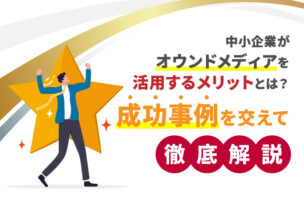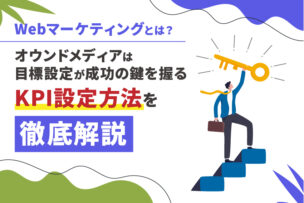記事の監修

Web集客・マーケティングの専門家として、13年間にわたり厳格な基準と緻密な戦略をもって中小企業の成功を導く。
一時的な集客の手法に頼ることなく、中長期的な効果を持続させる本質的なWeb集客の構築に注力。
『恵ある集客を。』をスローガンに掲げてクライアント様のサービスや商品の核心的な魅力を、的確にターゲットに伝えることを重視したWebサイト運用をサポート。
企業が自社のオウンドメディアを運用することが注目されている昨今。オウンドメディア起ち上げに向けて躍起になっているWeb担当者は少なくないでしょう。しかし、オウンドメディアは企業が片手間で運用できるほど簡単ではありません。
その理由は、オウンドメディアの成功は、運用体制に左右されるからです。この記事では、オウンドメディアの運用体制について、具体的な役割と体制の作り方について詳しく解説していきます。企業のオウンドメディア担当者にとって有用な情報になれば幸いです。
- オウンドメディアにおける運用体制について知りたい方
- オウンドメディアの運営体制の種類について知りたい方
- オウンドメディアの運用体制の作り方を知りたい方
目次
なぜ、オウンドメディアは運用体制が大事なのか?
さて、企業が取り組むオウンドメディアは、運用体制を重視しないといけないのは何故でしょうか?その理由は、オウンドメディアの運用に時間と手間がかかるからです。
オウンドメディアの運用は、個人の雑記ブログのような感覚で気ままにできる取り組みではありません。その点を企業の上層部が理解しないで、1人のWeb担当者に任せてしまうことは負担をかけ過ぎることになりかねないのです。
オウンドメディア運用にかかるコスト
オウンドメディアの運用には、時間や手間がかかると説明しました。では具体的なオウンドメディアの運用全般に必要な”やるべき事”を上げてみると次のようになります。
- チーム編成
- 組織内情報開示共有
- メディアの全体構成
- 企画アイデアの抽出
- 取材・データ収集
- 連載に向けた記事の作成
- 外部連携コンテンツ注入
- 全体スケジュール調整
ここまで上げた”やるべき事”を管理しながら進めていくことで、全体の基盤が出来上がることになるのです。さらに、参入するオウンドメディアのテーマによっては、構築段階で取り組む工程が増えることも考えられます。では、このような”やるべき事”をコストに置き換えて見て見ましょう。
人的・時間的コスト
オウンドメディアの運用体制をやるべきことで取り上げてきましたが、コストに置き換えると人的コストと時間的コストに分けて考えることができます。人的コストが、企画担当や制作担当です。また、管理運営担当も必要になります。
時間的コストでは、それら各担当者の作業時間が該当するでしょう。中長期目線で制作から運営していく必要のあるオウンドメディアは、時間的コストで考えると半年から1年単位で見ていかなければなりません。
ここでポイントとなるのが、人的コストを掛けられる人材を社内で抜擢できる状況か?自社の現状を再認識する必要があります。また、時間的コストについても、中長期目線で取り組むオウンドメディアの運営を通常業務の中に組み込むことが可能か?判断することが必要です。
あわせて読みたい
運用体制が整っていれば成功できる理由
オウンドメディアは、人的コストも時間的コストも掛かることを理解した上で運用していきます。オウンドメディアは、中長期目線で取り組む施策だけに運用体制が整っていないことで、途中挫折となる可能性も高くなるのです。
それだけにオウンドメディアの成功のカギは、運用体制にあると言っても過言ではないでしょう。その理由は、自社の人材だけで行う場合、複数の人的リソースを担当させずに1人のWeb担当者に任せてしまうことが考えられるからです。
1人のWeb担当者にオウンドメディアの記事制作やSEO対策など、同時に業務負担させることにより、個人の負担が大きくなり、負荷がかかり過ぎることも懸念されます。この場合、運用前からオウンドメディアに関わる役割を振り分けることで長期的に取り組む施策を安定して実行することができるでしょう。
オウンドメディアの運営体制作りに重要な6つのポイント
オウンドメディアの運営は、企業のブランドや信頼性を高め、持続的な顧客関係を築くための重要な戦略です。しかし、その運営は単なるコンテンツ制作以上の努力を必要とします。オウンドメディアの運営体制を効果的に構築・維持するための6つの重要なポイントについて説明します。これらのポイントは、運営の目的を明確にし、チームの効率と生産性を向上させ、高品質なコンテンツを提供し続けるための基盤を築くものです。それでは、各ポイントについて詳しく見ていきましょう。
目標の策定と共有
オウンドメディア運営において、目標の明確化は必須です。目標を設定することで、運営方針やコンテンツ戦略を明確にし、チーム全体が同じ方向を向いて努力できます。具体的な目標設定のプロセスは、まず市場調査やターゲット分析を実施し、その上で適切な目標を設定することが基本となります。また、目標の共有はコミュニケーションの向上とモチベーションの維持にも貢献します。定期的なミーティングや報告書を用いて、進捗状況や目標達成度を共有することが重要です。
運営業務の洗い出し
オウンドメディア運営には多くのタスクが伴います。タスクの洗い出しを行い、それぞれのタスクに責任者を割り当てることで、効率的な運営体制を築けます。タスクの例としては、コンテンツ制作、SEO対策、分析・評価、運営スケジュールの管理などがあります。タスク洗い出しは運営体制の明確化にも繋がり、無駄な作業を減らし、生産性を向上させる効果が期待できます。
人員と予算の確保
人員と予算はオウンドメディアの質と量を保証する基盤です。人員は十分なスキルと経験を持ち、予算は運営コストや広告コストをカバーできるレベルを確保することが重要です。また、予算は目標達成のために効果的に配分することも求められます。人員と予算の確保は、運営の安定化と持続可能な成長を支える重要な要素となります。
スケジュール管理
スケジュール管理は運営の効率と品質を保つうえで不可欠です。記事の公開スケジュールや広告の配信スケジュールをしっかりと計画し、実行することで、コンテンツのクオリティを保ちながら効率的な運営を実現できます。また、スケジュールの進捗を常にチェックし、必要に応じて調整することで、運営のスムーズな進行を保てます。
外部委託との連携
外部の専門家や制作会社との連携は、高品質なコンテンツの制作や、特定の専門分野での知見を得る手段となります。外部委託は、運営体制の拡充と効率化にも貢献します。適切な外部リソースの選定と連携体制の構築は、オウンドメディア運営の成功に大いに影響します。
継続的な最適化と改善
オウンドメディアは作ったら終わりではなく、常に進化し続けるべきものです。アナリティクスのデータを利用し、コンテンツのパフォーマンスやユーザーの反応を定期的に分析することで、運営の最適化と改善を図ることが可能です。また、ユーザーフィードバックを活用し、コンテンツのクオリティや運営体制の改善に努めることが重要です。
オウンドメディアの運営体制は主に2種類

オウンドメディアの運営においては、主に自社内運営と外部委託の2種類の体制があります。どちらの体制を選択するかは、各企業様の目的、リソース、及び戦略によって大きく左右される重要なポイントとなります。以下にそれぞれの特徴について説明します。
自社内運営
自社内運営は、企業が自身のリソースを用いてオウンドメディアを運営する体制を指します。この体制の最大の利点は、コントロールとアライメントの確保です。企業は自社のビジョンやブランドイメージを直接反映させることができ、日々の運営においてもフィードバックと改善がスムーズに行えます。さらに、自社内での知識蓄積とスキルアップが期待でき、長期的に見て経済的にも効果的であることがあります。しかし、この体制は人材や技術、時間の投資が必要であり、特に人材の確保と育成が重要な課題となります。また、専門知識や技術が不足している場合、効果的な運営が困難になることもあります。このため、自社内運営を選択する際には、十分なリソースと準備が求められます。
外部委託
外部委託は、専門の外部組織にオウンドメディアの運営を委託する体制を指します。この体制の最大の利点は、専門知識と効率性です。外部のプロフェッショナルによる運営は、高いクオリティと効果的なパフォーマンスを期待することができ、また短期間での成果も見込めます。さらに、企業自身が運営に関わる時間とリソースを節約することができ、他の重要な業務に集中することが可能となります。しかし、外部委託にはコストがかかり、また企業のビジョンやブランドイメージの伝達、及びコントロールが困難になることもあります。このため、信頼できるパートナーとの良好な関係が重要となり、また定期的なコミュニケーションと評価が求められます。
オウンドメディア運用の具体的な役割分担
今まで、オウンドメディアを運用するには体制を整えるポイントを解説してきました。それでは、具体的な役割分担について解説します。役割の紹介の前に「なぜ、オウンドメディアの運用は難しいのか?」について知っておく必要があるでしょう。
オウンドメディアの運用は難しい
オウンドメディアは、メディアとして軌道に乗ればアクセスも集まり、高い費用対効果を実感できるようになるので、魅力的な施策と言えます。ただし、あくまでも軌道に乗ることが前提になります。
ここでオウンドメディアの運用を難しく捉えてしまう要因を上げてみましょう。
上に挙げた要因により、オウンドメディアの運用を躊躇してしまう企業が少なくないのです。この点をふまえて、オウンドメディアの運用に必要な役割分担を見ていく必要があります。
オウンドメディアの運用上必要になる役割
それでは、オウンドメディアを運用する上で、どのような役割を振り分けて考えていくべきか?具体的に見ていきましょう。
メディア企画立案
オウンドメディアを構築する段階で、最も重要な設計の部分を決めるメディアの企画立案です。メディアの企画を考える役割は、主に企業のWeb担当者が担うケースが多いでしょう。
ただし、企業のWeb担当者が編集に対して決定権のある責任者の場合は、スピーディーに進む可能性がありますが、決定権のある上司がWebについて知識が乏しい場合、企画立案は難航する可能性があるのです。
その理由は、オウンドメディアについて客観的でないテーマになってしまうこと。自社を優先した都合の良い企画になってしまうため、企業の販売サイトと変わらないユーザーにとっては、物足りないコンテンツになることでしょう。
つまり、オウンドメディアのコンテンツは、アクセスを集めることが目的となるため、ユーザーに役に立つ企画を立てていく必要があるのです。くれぐれも自社の都合に偏った企画にならないように第3者目線の担当者に決定権を持たせることも必要ではないでしょうか。
あわせて読みたい
メディア設計・記事構成
企画段階でオウンドメディアのテーマが確立されてきたら、メディアに訪問してくるユーザーの検索意図を踏まえたアイデア(ブログネタ)の選定に入ります。ここでアイデアの抽出とメディアの設計を同時に行う感覚でオウンドメディアの全体像が見えてくるのです。
メディアの設計では、テーマキーワードの需要価値によって全体の記事構成の規模も変化していきます。例えば、「旅行」のオウンドメディアでは、記事構成も「国内」「海外」「ホテル」「旅館」「食事付」「素泊り」などカテゴリも規模が大きくなるのです。
規模を小さくする場合は、「千葉・房総エリア・海鮮の美味しい食事付旅館」と絞り込むことで、記事構成のカテゴリも具体性とメディアの属性も明確になってきます。このように、企画段階のテーマによって、どの程度の規模のメディアになるのか?を記事構成の制作の前に認識しておく必要があるでしょう。
あわせて読みたい
記事コンテンツ参考データ収集・取材
オウンドメディアの記事構成までを設計できたら、次に記事コンテンツ作成のためのデータ収集や取材が必要になります。この部分で、自社の強みの分野になる情報配信の場合は、データ収集や知識面で大いに差別化が図れることでしょう。
オウンドメディアは、訪問ユーザーの検索意図を意識した検索ユーザーに役に立つ情報を提供していく情報配信になります。そのため、記事コンテンツは信ぴょう性のある事実に基づいた情報であることが必要です。
中長期で安定したアクセスを集めるオウンドメディアに育てていくためには、データ収集と取材に注力することが不可欠になります。その理由は、データ収集と取材を参考にした競合サイトにない記事コンテンツを作成するためです。
記事執筆
記事コンテンツに必要なデータを集めたら、ユーザーに役立つ情報のアイデア部分が用意できたことになります。ようやく、この段階で記事の執筆になるのです。記事の執筆について、社内の人材に任せるか?外注のライターに依頼するか?の選択も必要になってきます。
記事の執筆でのポイントは、オウンドメディアの特徴として長期的な安定した継続投稿が必要とされるため、自社の人的リソースになると通常業務の一環として組み込む必要があるでしょう。つまり、担当者の記事執筆業務に必要な作業時間も考慮してあげないと負担が増えるのです。
あわせて読みたい
記事推敲校正
執筆した記事をそのままWeb上にアップロードする前に、推敲や校正が必要になってきます。オウンドメディアの記事は、ユーザーにとっての読みやすさや文言の打ち間違えなどに注意する必要があるからです。
記事執筆担当者と記事の推敲校正担当者は、できれば違う人が取り掛かることが理想でしょう。ただし人的リソースの関係で推敲校正を担当する人材がいない場合は、記事執筆担当者が記事制作後に再度見直すことにより、誤字脱字などの修正対応になります。
この辺りの作業が業務時間内に組み込めるかが自社でオウンドメディアを運用する場合のポイントとなるでしょう。
メディア効果測定
記事執筆をして、推敲校正で精査した記事コンテンツをWeb上に投稿するまでの流れを説明してきました。この一連の工程を踏まえて長期的なオウンドメディアの運営になっていきます。さらに、オウンドメディアの運営体制ではメディア全体の現状を把握する必要があるでしょう。
それは、オウンドメディアの効果測定のことです。考えられるオウンドメディアの運用で分析していくべき効果測定の指標を上げてみます。
オウンドメディアは、直接購入につながる媒体ではありません。そのため、アクセス解析で確認できるサイト訪問者の数値データを指標とすることになります。また、メディアの最新投稿をSNS上で紹介した際のシェアの数を指標とすることもあるでしょう。
まとめ
いかがでしたか?今回の記事では、オウンドメディアの運用体制について詳しく見てきました。オウンドメディアは、企画段階でも運用段階でも一定の継続期間が必要になります。そのため、時間効率や人的コスト削減を考えたら、専門業者に依頼することも選択肢になるのではないでしょうか。
- オウンドメディアの成功は運用体制に依存し時間と手間がかかるためコンテンツ制作以上の努力が必要
- 目標の明確化タスクの洗い出しと責任者の割り当て人員と予算の確保が重要
- スケジュール管理、外部委託との連携、アナリティクスに基づく運営の最適化と改善が効果的
あわせて読みたい
オウンドメディアの運用体制に関するよくあるご質問
最後によくあるご質問をいくつかご紹介致します。
みなさまのWeb集客にお役に立てば幸いです。
その他、ご不明な点がございましたら以下のリンクよりお気軽にご相談下さいませ。
無料オンライン相談はこちらからどうぞ。
Q
オウンドメディアとは何ですか?
A
オウンドメディアとは、企業や組織が自ら所有・運営するメディアのことを指します。これには、公式ウェブサイトやブログ、SNSアカウントなどが含まれます。
Q
オウンドメディアを運営する際の体制の重要性は?
A
オウンドメディアの成功は適切な体制に大きく依存します。適切なチーム編成や役割分担がなされていないと、効果的なコンテンツの制作や更新が難しくなります。
Q
どのような体制でオウンドメディアを運営すべきですか?
A
オウンドメディアの運営には、コンテンツ制作、デザイン、SEO対策、アクセス分析などの専門家からなるチームが必要です。
Q
小さな企業でもオウンドメディアの体制を整えることは可能ですか?
A
はい、小さな企業でもスタートは小規模からでも、体制を整えて段階的に拡大していくことが推奨されます。
Q
オウンドメディアの運営体制で特に重要視すべきポイントは?
A
定期的なコンテンツ更新、品質の維持、ターゲット層への的確な情報提供、そしてアクセス分析を通じた改善が特に重要です。
Q
オウンドメディアの体制作りの際の最初のステップは?
A
ターゲット層の明確化と、その層に合ったコンテンツテーマや方針の設定が初めのステップとなります。
Q
オウンドメディアの運営体制における外部の専門家の活用は有効ですか?
A
はい、特に専門知識や技術が求められる領域では、外部の専門家との連携が効果的です。
Q
オウンドメディアを成功させるための体制とは、大企業と中小企業で異なりますか?
A
基本的な考え方は同じですが、規模やリソースに応じて柔軟に体制を組むことが必要です。
Q
オウンドメディアの運営に必要な体制を維持するためのコストは高いですか?
A
コストは、運営の規模や目的に応じて変動します。しかし、中長期的な投資としてのリターンを考慮すれば、費用対効果は高いと言えます。
Q
オウンドメディアの体制構築で最も重要なことはなんですか?
A
長期的な運営を見据えた持続可能な体制の構築と、常に変化する市場環境やユーザーのニーズに迅速に対応する柔軟性を持つことが挙げられます。