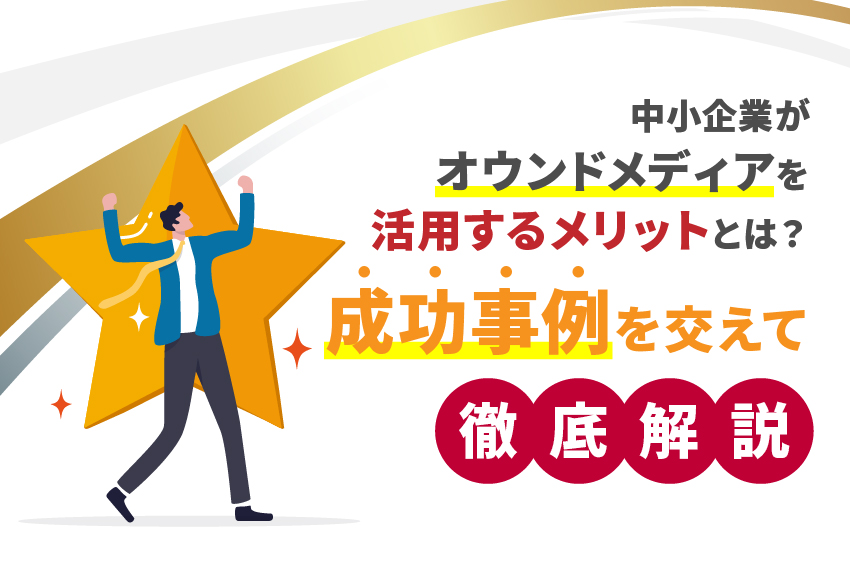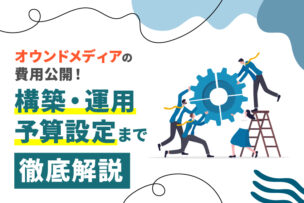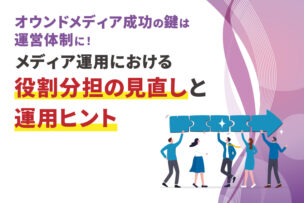記事の監修

Web集客・マーケティングの専門家として、13年間にわたり厳格な基準と緻密な戦略をもって中小企業の成功を導く。
一時的な集客の手法に頼ることなく、中長期的な効果を持続させる本質的なWeb集客の構築に注力。
『恵ある集客を。』をスローガンに掲げてクライアント様のサービスや商品の核心的な魅力を、的確にターゲットに伝えることを重視したWebサイト運用をサポート。
オウンドメディアの運用は、Web上で自社の取り組みをアピールする重要な戦略ではないでしょうか?特にブランディングが確立されていない中小企業にとって、長期目線で認知度を向上できる施策となります。
この記事では、中小企業にとってオウンドメディアを運用することがおすすめな理由と実際に成功しているオウンドメディアの事例を紹介していきます。企業のWeb担当者にとって、オウンドメディアの制作の参考になれば幸いです。
- 中小企業においてオウンドメディアの活用方法を知りたい方
- 中小企業のオウンドメディア戦略を知りたい方
- 中小企業のオウンドメディア成功事例を知りたい方
目次
オウンドメディアが中小企業におすすめな理由
中小企業がオウンドメディアの運用をすることがおすすめの理由を簡単に言うと「今以上にWebサイトの訪問者数を増やすことができる」という点です。つまり、現状のWebサイトの訪問ユーザーよりもアクセスを増やすことが期待できるでしょう。
その辺りを具体的に、オウンドメディアの運用により中小企業が得られるメリットを取り上げてみます。
オウンドメディアのメリット
オウンドメディアを構築して運営していくにあたって、中小企業が得られるメリットを上げると次の通りです。
- 認知拡大
- 企業の信頼性の向上
- 企業の価値向上
オウンドメディアを自社で運用すると以上のようなメリットを得られることになります。それでは、それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。
訪問ユーザーを増やして見込み客を集める
訪問ユーザーを増やして見込み客を集めることは、従来の企業の持つ販売サイトも同じ目的ではなかったでしょうか?しかし、現実的には企業の販売サイトほど訪問ユーザーが集まりにくい媒体と位置付けられるのです。
それは、自社都合の情報を中心とした構成になる企業の販売サイトの性質によります。企業の販売サイトは、訪問ユーザーにとって役に立つ情報の発信ではなく、自社の商品やサービスの案内で構成されているからです。そのため、ビジネス目的の販売色の強い企業の販売サイトは、インターネットユーザーにとって敬遠されがちなWebサイトと位置付けられてしまいます。
そのような状況の中、訪問ユーザーにとって役立つ情報を配信することが目的のオウンドメディアは、認知拡大を期待できるのです。それは、属性の合う訪問ユーザーを集めることを目的としたメディアの構成と情報配信の取り組みによる結果でしょう。
このような流れから、結果的にオウンドメディアに訪れるユーザーが、見込み客へとなり、自然と見込み客を集めるメディアとなっていくのです。
あわせて読みたい
企業の信頼性の向上
さらに、オウンドメディアを構築していくことのメリットは、中小企業の信頼度のアップにもつながります。その理由は、ビジネス色のないユーザーにとって居心地の良い情報配信サイトを提供することで、企業イメージが向上するからです。
初めて会うユーザーに最初から、「この商品すごくいいから買ったほうがいいですよ。」というセールス色を一切、感じさせないユーザー目線のメディアだからこそ訪問者の信頼度を向上させることができるのでしょう。
共感による企業の価値向上
オウンドメディア運用のもう1つのメリットは、ユーザーの信頼を得て共感を持ってもらうことです。この共感という部分は、常にユーザーに役立つ情報を提供して、その都度、配信する情報に納得してもらうことの積み重ねで構築されていきます。
オウンドメディアは、積み重ねによる記事の更新を継続していく必要があるため、記事数が100記事、200記事と増えていくのです。それらコンテンツとなる記事は、ユーザー目線のお役立ち情報で構成されているため、結果的に読者の共感を生むことにつながります。
あわせて読みたい
オウンドメディアはブランディングにつながる
オウンドメディアは、自社の商品やサービスに合った属性のユーザーを集めて、信頼関係を築き、共感をしてもらえる効果が期待できるのです。その流れから、オウンドメディアには、ブランディング効果が期待できるでしょう。
ブランド認知拡大
オウンドメディアの運用により、中小企業が得られるブランディング効果を解説します。それは、ブランドの認知拡大が大きなブランディング効果ではないでしょうか。自社のブランドを認知されることで、競合他社との差別化にもなり、類似商品の価格競争に参加する必要もなくなります。
従来の企業が行うブランド認知拡大は、TVコマーシャルや雑誌広告掲載など不特定多数に露出を続け、莫大な費用をかけて宣伝していくイメージでした。しかし、インターネットが普及した現在では、自社の顧客になる見込み客に向けた訴求ができるオウンドメディアがブランド認知を拡大してくれるのです。
中長期目線のビジョン
ただし、オウンドメディアの構築や運用は簡単に取り組めることではありません。規格の段階から、ユーザー目線を軸にしたアクセスの集まるWebサイトの構成が必要になります。さらに、中長期目線で取り組んでいく必要があることから、自社の運用リソースの確保も重要なビジョンになるでしょう。
つまり、中長期目線で継続することにより、企業のブランディングに効果を出せるわけです。そのため、気軽にオウンドメディアを起ち上げる意識では、ブランディング効果を得る前に挫折してしまうことも考えられます。
オウンドメディア起ち上げにはコンサルが必要
先述したようにオウンドメディアを成功させるためには、中長期目線のビジョンが必要です。ただ、ここで注意しておきたいのは闇雲にオウンドメディアの記事を量産していくだけの長期的な取り組みではありません。
一般的な雑記ブログ感覚で記事を量産しても、メディアの一貫性から外れてしまう可能性があるからです。そのため、オウンドメディアを起ち上げる段階で、メディアを共感してくれる読者の属性をデータに沿ってターゲティングしていくことが必要になります。
このようなオウンドメディアの構築段階で、取り組むべき準備は多々あるのです。中小企業のWeb担当者に全て企画を負担させてしまうことで業務過多になることも考えられるでしょう。その場合は、プロの専門業者にオウンドメディアの構築にまつわるコンサルティングを依頼することで負担を軽減することができます。
あわせて読みたい
中小企業のオウンドメディア戦略
続いて中小企業でも成功できるオウンドメディア戦略について見ていきましょう。
アクセス数より信頼度構築が優先
オウンドメディアを運用していくうえで、効果を期待できるのがメディアへのアクセス数の増加です。そのため、オウンドメディア戦略でもアクセス数の増加ばかりを目指してしまうと、コンテンツの低い情報発信になってしまうことが考えられます。
まずは、オウンドメディアの構築段階で設定した構成案に沿って、訪問してくるユーザーにとって役に立つ情報を調査のうえで丁寧に制作していくことが重要です。コンテンツの信ぴょう性と説得力が伝われば、自然と訪問ユーザーの信頼度は構築されていきます。そのような理由からもコンテンツに注力することを優先としましょう。
あわせて読みたい
顕在ユーザーのニーズに応えるコンテンツ提供
訪問ユーザーの信頼を得ることができれば、そのユーザーはメディアのファンとなってくるでしょう。訪問ユーザーがファン化していくことから、やがて顕在ユーザーとなりオウンドメディアからの新しい情報を待ち望むような状態になります。
顕在ユーザーに向けて、オウンドメディア運営者は常にニーズに応えるコンテンツを提供していくことに注力をしていくのです。この暗黙のルールを守りながら、メディアを運営していくことで結果的にアクセスの集まるオウンドメディアと成長していく流れになります。
中小企業ならではの効果とは?
オウンドメディアを中小企業が運用した場合、企業規模の大きい大手のメディアともWeb上で互角または、それ以上に勝ることが可能になるのです。実際の企業規模が小さくても、Web上では計測することはできません。
それだけに、ユーザーに役立つきちんとした情報の配信を続けていくことで、大手企業のメディア以上の信頼と共感を得ることも不可能ではないのです。この可能性こそが、中小企業ならではのオウンドメディアの効果ではないでしょうか。
中小企業のオウンドメディア運用の進め方
説明した通り、中小企業にとって、デジタル時代に適応するための重要な戦略の一つがオウンドメディアの導入と運用になります。以下では、中小企業が効果的にオウンドメディアを進める方法について詳しく解説します。
オウンドメディアの立ち上げ方
オウンドメディアを立ち上げる際の最初のステップは、使用するプラットフォームの選択です。ブログ、SNS、動画チャンネルなど、多くの選択肢がありますが、ターゲットオーディエンスとの最適なコミュニケーション方法を選択することが鍵です。次に、コンテンツ戦略を策定します。これには、どのような情報を提供するか、どの頻度で更新するかなどの要点が含まれます。
コンテンツ制作のポイント
コンテンツ制作において、ユーザー(見込み客)が求める情報を提供することが最も重要です。また、定期的な更新は、サイトの信頼性とSEOの観点からも必要とされます。コンテンツ作成の際には、キーワードリサーチを行い、ターゲットとなるキーワードを組み込むことで、検索エンジンからのアクセスを増やすことができます。
オウンドメディアの運用と分析
オウンドメディアの運用を効果的に行うためには、アクセス解析ツールの活用が不可欠です。これにより、どのコンテンツがユーザーに受け入れられているのか、どのような改善が必要なのかを把握することができます。KPIの設定とモニタリングを行うことで、継続的にオウンドメディアの品質を向上させることができます。
成功事例から学ぶ
多くの中小企業がオウンドメディアを利用して成功を収めています。本記事でも以下で成功事例を紹介していますので、これらの成功事例を参考にすることで、どのような戦略が効果的であったのか、どのような取り組みが奏功したのかを学ぶことができると思いますので、是非ご覧になって下さい。
ここまで説明した通りオウンドメディアは、中小企業にとっての強力なマーケティングツールとなり得ます。しかし、継続的な運用と最新のトレンドへの対応が求められます。新しい技術やトレンドが登場するたびに、それに適応して進化することで、長期的な成功を収めることができます。
中小企業がオウンドメディアを運用するときの注意点

オウンドメディアは、中小企業が自らのメッセージを伝えるための強力なツールですが、適切な運営を行わなければ、その真価を発揮することは難しいです。以下では、中小企業がオウンドメディアを運用する際の重要な注意点を解説します。
コンテンツの品質
オウンドメディアを運営する上で、一貫した品質の維持は欠かせない要素です。ターゲットオーディエンスに合わせた内容を提供することで、リピート訪問を促し、ブランドへの関心を高めることができます。また、読者のニーズに応える情報を提供することで、信頼性を確立することができます。
更新頻度の維持
定期的なコンテンツの更新は、読者の訪問動機を維持するために不可欠です。コンテンツカレンダーを活用し、計画的な更新を心がけることで、読者に新鮮な情報を提供し続けることができます。
SEOへの取り組みの継続
オウンドメディアの訪問者数を増加させるためには、SEO対策の導入は必須です。適切なキーワード選定と最適化を行い、さらには質の高いバックリンクを獲得することで、検索エンジンでのランキングを向上させることができます。
ユーザーエンゲージメント
コメントやフィードバックは、ユーザーの関与度を示す重要な指標となります。SNSの連携を強化し、アクティブなコミュニケーションを図ることで、オウンドメディアの価値を一層高めることができます。
分析と改善
こちらは先述していますがアクセス解析ツールを活用して、オウンドメディアの効果を定期的にチェックすることは、継続的な成果向上の鍵です。KPIを設定し、その数値をもとにコンテンツやデザインの改善を行うことで、さらなる成果を目指すことができます。
リソースと予算の管理
中小企業は大手企業と比べてリソースや予算が限られています。しかし、効果的なリソースの配分と適切な予算管理を行うことで、持続的なオウンドメディア運営を実現することができます。適切な外部サービスの活用や自社リソースの最適化を図ることで、コストを抑えつつ質の高いコンテンツ提供が可能となります。
中小企業のオウンドメディア成功事例3選
今まで、中小企業にとってのオウンドメディアの運用についてメリットや効果を解説してきました。それでは、実際にオウンドメディアを起ち上げて成功した事例を見ていきましょう。中小企業のオウンドメディアの成功事例を3つ取り上げてみます。
BBQ関連情報のオウンドメディア「BBQ CO!」
最初にBBQ GO!(バーベキュー ゴー!)という国内最大級バーベキュー情報サイトを紹介します。食肉の加工会社ニッポンハムグループが運営するオウンドメディアです。このメディアは、「バーベキュー」をテーマにバーベキューユーザーに役立つ「BBQができる施設のエリア検索・都道府県検索」「BBQ豆知識やレシピなど役立ち情報」などを随時更新しています。
メディアのメインページでは一切、自社の商品やサービスの情報に触れず、バーベキューについての情報配信に注力しているスタイルを貫いているのです。
BBQ CO!
オシャレを学ぶオウンドメディア「オシャレになるための教科書」
次に紹介するオウンドメディアは、株式会社ドラフトが運営するDcollectionになります。メーカーやブランド関係なく、おしゃれに特化したオシャレのための役立ち情報サイトです。
Dcollectionでは、年代別(10代、20代、30代、40代)に季節に合ったコーディネートの提案を具体的に配信しています。例えば、Tシャツやニット、パーカー、パンツなどコーディネートを探して、さらにメールでアドバイスを受けることもできるのです。
アパレルショップの販売サイトではないので、気楽に役立ち情報を確認していくことができる「おしゃれ」をテーマにしたオウンドメディアになります。
オシャレになるための教科書
北欧の暮らしに合う道具についてのオウンドメディア「北欧、暮らしの道具店」
3つ目のオウンドメディアは、「北欧、暮らしの道具店」です。株式会社クラシコムが運営するインテリアや小物、ギフトなどを「北欧」をテーマにして役立ち情報を配信しています。「北欧、暮らしの道具店」の特徴は、独特のデザインのキッチン用品や雑貨などを1品1品、体験レビュー風な記事として「使い道」を丁寧に案内している点です。
お皿1枚にしても色んな食材を乗せてみたり、グラスと組み合わせてみたり、1つのアイテムにつき画像をたくさん使って解説している点が興味を引く点ではないでしょうか。
成功しているオウンドメディアの共通点
上記に紹介したオウンドメディアの成功事例には、共通点があります。
上記にあげた共通点が、紹介したオウンドメディアの成功要素となるのです。それでは、詳しく見ていきましょう。
自社の強みを生かしたテーマで企画・構成
オウンドメディアを制作に入る前の段階から、企画設計をすることです。企画設計では、自社の強みとなる競合他社にない差別化できる部分を明確にして、取り上げていきます。さらに、それら自社の強みと強く関連しているテーマを決定して、オウンドメディアの構成案を作っていくのです。
運営コンセプトに一貫性がある
次に企画設計したオウンドメディアのテーマと構成案が、自社の運営コンセプトと一致しているか?を再確認します。自社の経営理念や顧客へのアプローチなどとメディアのコンセプトに違いが生じていたら、訪問ユーザーへの伝えたいことへの一貫性がなくなってしまうからです。
そのため、オウンドメディアのコンセプトと自社のスタンスは、一致していることが重要です。今回、紹介した成功事例では、一貫してテーマに沿った情報配信を続けています。
運営体制の整備と継続
最後の共通点は、オウンドメディアを構築し、運用していくことに最初から制作費用や運用費用を考慮した運営体制が整っていたことです。人員体制を考えないで、闇雲にオウンドメディアを始めてしまうと、多くの場合途中で挫折してしまう可能性が高くなるでしょう。
あわせて読みたい
まとめ
いかがでしたか?今回は、中小企業がオウンドメディアを運用するべき理由と実際に成功している事例を取り上げてきました。また、中小企業がオウンドメディアを運用することで得られる効果や戦略のポイントについて解説してきました。企業のWeb担当者にとって、実際にどのように進めるべきか?参考になることでしょう。
- 中小企業がオウンドメディアを運用メリットは認知拡大、信頼性向上、企業価値の向上
- オウンドメディアはブランド認知の拡大に貢献し長期的なビジョンのもとで企業のブランディングを支える
- 中小企業でも質の高いコンテンツ提供を通じて大手企業と同等またはそれ以上の信頼と共感を獲得できる可能性がある
あわせて読みたい
中小企業のオウンドメディアに関するよくあるご質問
最後によくあるご質問をいくつかご紹介致します。
みなさまのWeb集客にお役に立てば幸いです。
その他、ご不明な点がございましたら以下のリンクよりお気軽にご相談下さいませ。
無料オンライン相談はこちらからどうぞ。
Q
オウンドメディアとは何ですか?
A
オウンドメディアは企業が独自に所有・運営するコンテンツ配信チャンネルを指し、ブログや公式サイト、SNSアカウントなどが含まれます。
Q
中小企業においてオウンドメディアのメリットは何ですか?
A
中小企業にとってのオウンドメディアのメリットは、広告費用が不要であること、長期的にブランド価値や信頼性を高めることができること、ターゲットとなる顧客層に独自のメッセージを伝えやすいこと、などが挙げられます。
Q
中小企業がオウンドメディアを運営する際の注意点は何ですか?
A
コンテンツの質を保つこと、更新頻度を一定に保つこと、SEO対策を怠らないこと、ターゲット層のニーズを常に把握すること、などが重要です。
Q
オウンドメディアの成功例としてよく挙げられる中小企業はありますか?
A
日本国内においても、多くの中小企業がオウンドメディアでの情報発信に成功しています。具体的な企業名や事例を挙げる場合、実際のリサーチが必要です。
Q
オウンドメディア運営においてコストはかかりますか?
A
初期設定やデザイン、システムの構築には費用がかかることがありますが、運営に関してはコンテンツ制作の人件費や時間が主なコストとなります。
Q
オウンドメディアでの集客を増やす方法はありますか?
A
SEO対策の強化、SNSでの積極的な情報共有、メルマガやニュースレターの活用、質の高いコンテンツ作成、ターゲット層とのコミュニケーション強化などが効果的です。
Q
オウンドメディアでのコンテンツは何を中心に制作すべきですか?
A
ターゲット層の興味・関心や解決すべき課題を中心に、有益な情報や知識、ストーリーを提供する内容が望ましいです。
Q
オウンドメディアと他のメディア(ペイドメディア・アーンドメディア)との違いは?
A
オウンドメディアは企業が自ら運営・所有するメディア。ペイドメディアは広告などでの有料の露出。アーンドメディアは口コミやニュースなど、企業がコントロールできない第三者による露出を指します。
Q
オウンドメディアの運営に外部のエージェンシーを利用する場合のメリットは?
A
プロの知識や経験を活用できること、リソースや時間の節約、専門的なアドバイスを受けられることなどがメリットとして挙げられます。