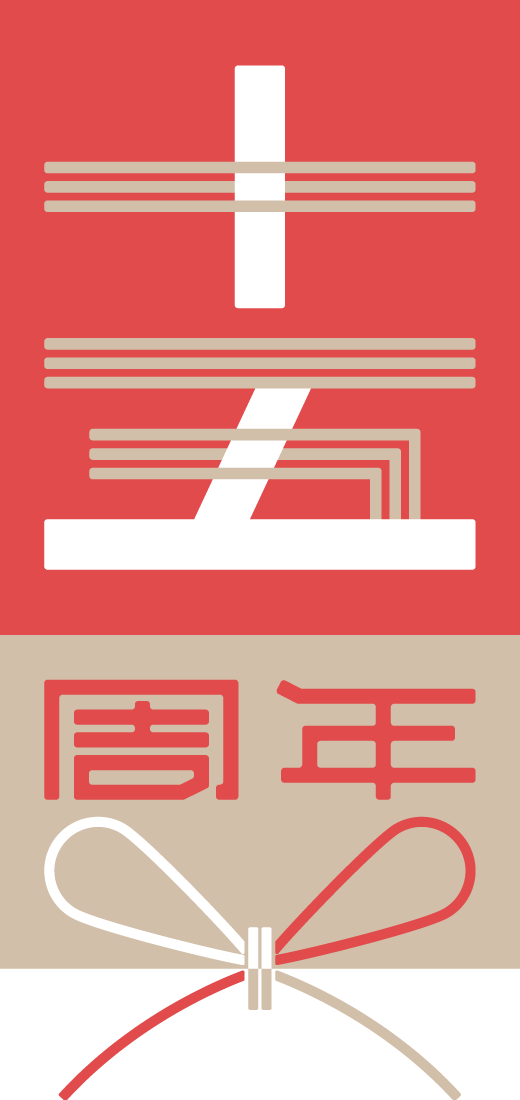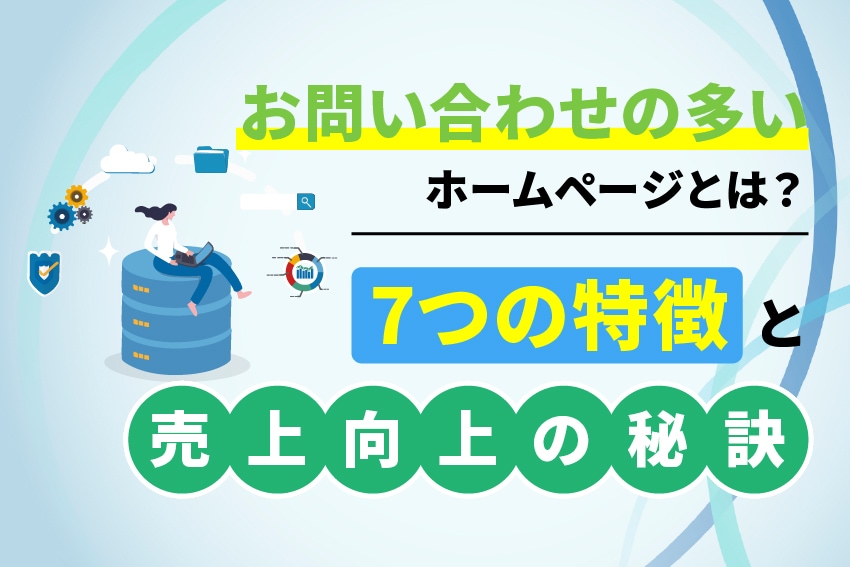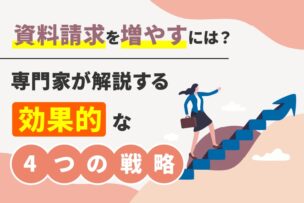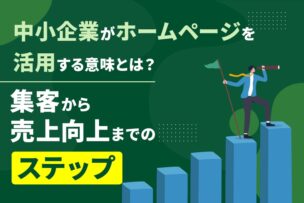記事の監修

Web集客・マーケティングの専門家として、15年間にわたり厳格な基準と緻密な戦略をもって中小企業の成功を導く。
一時的な集客の手法に頼ることなく、中長期的な効果を持続させる本質的なWeb集客の構築に注力。
『恵ある集客を。』をスローガンに掲げてクライアント様のサービスや商品の核心的な魅力を、的確にターゲットに伝えることを重視したWebサイト運用をサポート。
ホームページは単なる会社案内ではなく、顧客獲得のための重要なツールです。しかしながら「せっかくホームページを作ったのに、全然お問い合わせが来ない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
お問い合わせの多いホームページには、いくつか共通点があります。訪問してくれた顧客の心をつかみ、信頼を築き、最終的な行動へとスムーズに導くための仕掛けが入念にされているのです。
ホームページからのお問い合わせを増やして売上を上げたいと感じている方に向けて、ここでは「お問い合わせの多いホームページの7つの特徴」と、「売上向上の秘訣」を分かりやすくご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
- ホームページからの売上を伸ばしたい方
- お問い合わせを増やして売上アップにつなげたい方
- 効率的に見込み客を獲得してビジネスを成長させたい方
目次
お問い合わせの多いホームページは「露出→育成→転換」の3ステップ
STEP
01
STEP
02
お問い合わせの多いホームページは「顧客中心」
まず初めにお伝えしておくべきポイントは、お問い合わせの多いホームページは「顧客中心」で設計されているということです。顧客の気持ちを第一に汲み取ったホームページは、自然とお問い合わせが増えます。
顧客の悩みを解決し、共感を得る
まずは、ホームページ内で顧客の悩みを解決することが大切です。顧客がどんな疑問を抱えているのかを徹底的に分析し、顧客が知りたい情報を分かりやすく掲載します。過不足なく、詳細な情報提供をすることがポイントです。
顧客の不安を解消し、信頼を築く
顧客は、初めて問い合わせをする企業に対して不安を感じるものです。企業の実績、お客様の声、専門性を示すコンテンツを通じて、安心感と信頼感を築き、不安を取り除くことが問い合わせへの大きな後押しになります。
顧客満足度がもたらす効果的な売上向上
お問い合わせの多いホームページは「顧客満足度」が高いと言えます。顧客満足度が高いと、新規顧客の獲得だけでなく、既存顧客からのリピートに繋がり、口コミでの紹介も増えます。顧客満足度を追求することで、長期的かつ安定的な売上向上に直結するのです。
あわせて読みたい
お問い合わせの多いホームページの7つの特徴

ここでは、お問い合わせの多いホームページの7つの特徴をご紹介します。「ホームページのお問い合わせが増えない」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
「企業像と強み」が明確
お問い合わせの多いホームページは、「企業像」と「強み」が明確に伝わります。顧客は、自分が求めているサービスを提供している企業かどうか、短時間で判断したいと考えているものです。「この会社はどんな企業で、何が得意なのか」が一目で分かるように伝えることで、顧客が自分の目的に合致した企業かどうかをすぐに判断できるようになります。
ホームページの第一印象で顧客の心を掴む
ホームページは、訪問して数秒でユーザーの離脱が決まります。そのため、第一印象で「顧客の心を掴む」ことが非常に重要です。洗練されたデザインや分かりやすいサイト構成は、ホームページ全体への信頼感を生み出します。まずは、自社のホームページを客観的に見て、自分がターゲット顧客だとしたら、そのページをさらに詳しく見たくなるかを見直してみましょう。
自社の「強み」を具体的にイメージさせる
Webサイトのトップページには、自社の「強み」を全面に押し出しましょう。競合他社との違いや、顧客に提供できる独自の価値を具体的に掲載することで、「この企業なら自分の課題や悩みが解決できるかもしれない」という期待感を生み出すことができます。自社の強みが明確であれば、顧客はより詳しく情報を調べるためにページを巡回し、お問い合わせへとつながる可能性が高まるのです。
あわせて読みたい
見込み客に対する「集客戦略」が確立
お問い合わせの多いホームページは、見込み客に対する「集客戦略」が確立されています。何の戦略もなしにお問い合わせが増えることはありません。見込み客をページへ呼び込み、さらにサイト内を回遊させる仕組みが入念に考えられ設計されているため、結果としてお問い合わせの増加に繋がるのです。
見込み客へのアプローチがもたらす効果
見込み客は、すでに自社のサービスに興味関心を持っているため、購入やお問い合わせに繋がりやすいです。サービスに興味のない顧客にアプローチするよりも、見込み客に対して集中的な情報提供を行うほうが圧倒的に効率的でしょう。見込み客の「知りたい」を解消し、「あと一歩」の背中を押すような情報提供を行うことで、売上に繋がる可能性を大きく高められます。
見込み客へのSEO対策とAI対策
見込み客が検索しそうなキーワードを予測し、SEO対策を行いましょう。現代では、AIが自動で回答を生成するAIO対策も欠かせません。ユーザーが検索したキーワードに対して、AIの回答として自社サイトの情報が引用されるように最適化することで、検索結果のトップ表示だけでなく、AI経由でも効率的な露出が可能です。また、地域に特化したビジネスの場合は、GEO対策も重要です。GEO対策により、地域にいる見込み客からのお問い合わせ獲得に繋がります。
信頼関係を構築するサイト構成
お問い合わせに繋げるためには、顧客との「信頼関係」です。顧客にとって見づらい、分かりにくいサイトはすぐに離脱されてしまいます。顧客が迷わず、安心してサイト内を回遊できる構成にすることで、企業に対する印象が良くなり、信頼関係の構築に繋がります。「知りたい情報がどこにあるのか分からない」というストレスをなくすことが、お問い合わせへの第一歩となるのです。
あわせて読みたい
競合と差をつける「差別化戦略」が明確
お問い合わせが多いホームページは、競合他社との「差別化戦略」が確立されています。自社の立ち位置を正確に把握し、競合と明確な差をつける施策を実行することが必要不可欠です。この差別化戦略は、単にお問い合わせを増やすだけでなく、企業の成長と売上向上に大きく貢献します。
独自の「価値」を発信
差別化戦略を成功させるためには、独自の「価値」を見つけ出し、発信することがカギとなります。自社にしかない特徴や、他社には真似できない強みを明確にし、それを全面に押し出す戦略を立てましょう。独自の価値をしっかりとアピールすることで、顧客は「この会社にしかできないこと」に魅力を感じ、興味を持つようになります。
顧客の悩みに対する自社ならではの解決策を提示
差別化戦略を考える上では、まず顧客の悩みに着目することが大切です。顧客が抱える課題を深く理解し、「自社だからこそ、この強みを活かしてこのように解決できる」という具体的な解決策を提示しましょう。他社にはない、自社ならではの視点から解決策を示すことで、顧客の関心を引きつけ、お問い合わせへと繋がる可能性が高まります。
あわせて読みたい
顧客が得られる「ベネフィット」が明確
お問い合わせの多いホームページは、顧客が得られる「ベネフィット」が明確に提示されています。単に商品の特徴を提示するだけではなく、「この商品やサービスを使うことで、顧客の悩みがどう解決され、どんな良い結果が手に入るのか」を具体的に示すことが重要です。顧客が実際に受けるメリットを視覚的に伝えることで、購買意欲を高められます。
サービスの詳細ではなく「結果」を語る
自社商品やサービスの特徴を長々と説明するだけでは、なかなかお問い合わせには繋がりません。なぜなら、顧客は「そのサービスを利用して、自分がどう変わるのか」を明確にイメージできないからです。顧客の課題が解消される経過を具体的にイメージさせることで、お問い合わせへと後押しできます。
「事例」や「お客様の声」で信頼を得る
顧客に「結果」を伝える最も効率的な方法の一つが、「事例」や「お客様の声」を掲載することです。実際にサービスを利用した方のリアルな声や成功体験を掲載することで、顧客は安心感と信頼を抱きます。自分と同じような境遇の人が、そのサービスで成功したという事実が、顧客に「自分もこうなるかもしれない」という具体的なイメージを与え、お問い合わせへの確信へと繋がります。
顧客の「知りたい」に応える充実したコンテンツ
お問い合わせの多いホームページは、顧客の「知りたい」に的確に応える、充実したコンテンツを提供しています。コンテンツは、企業独自の専門性や個性を表現するのに最適な方法です。ターゲットとなる顧客が抱える疑問や課題を解決できるような価値のある情報を発信することで、顧客との間に信頼関係が生まれ、最終的にお問い合わせという行動へと繋がります。
ユーザーの検索意図を理解したコンテンツ制作
自社の伝えたい情報だけを羅列したコンテンツでは、ユーザーはすぐに離れてしまいます。重要なのは、「ユーザーが何を知りたいか」を深く理解し、その検索意図に沿ったコンテンツを制作することです。ユーザーの疑問や悩みに的確に応える情報は、信頼性を高めるだけでなく、ユーザーの満足度を向上させ、結果としてお問い合わせに繋がりやすくなります。
あわせて読みたい
専門性と信頼性を示す情報提供(E-E-A-Tの向上)
コンテンツには、専門性と信頼性が必要不可欠です。誰が書いたか不明で根拠もない情報は、ユーザーの心には響きません。説得力のあるコンテンツ制作のためには、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識することが重要です。専門家の監修を入れたり、データに基づいた情報を提供したりすることで、ホームページ全体の信頼性が向上し、安心してお問い合わせをしてもらえるでしょう。
もしもコンテンツ制作にお悩みの方は、めぐみやのコンテンツ制作サービスをご検討ください。それぞれのビジネススタイルに合わせた、的確なコンテンツの企画から制作までをサポートさせていただきます。詳しい内容は、以下のリンクよりご確認ください。
ホームページ内の「回遊率」が高い
お問い合わせの多いホームページは、「回遊率」が高いという特徴があります。これは、ユーザーが企業のサービスに興味を持ち、さらに多くの情報を求めてサイト内を深く探索している状態を意味します。お問い合わせを増やすためには、顧客が「もっと知りたい」と感じるような仕掛けを作り、サイトを楽しく、そしてスムーズに閲覧できる環境を整えることが必要不可欠です。
ユーザーの興味を惹きつける関連コンテンツ
コンテンツ内に関連記事や関連サービスへのリンク(内部リンク)を適切に配置することは、回遊率を高める上で非常に有効です。これにより、ユーザーは自分で情報を探す手間が省け、スムーズに次の情報へと辿り着けます。ユーザーの「もっと知りたい」という好奇心を刺激することで、滞在時間を延ばし、結果としてお問い合わせやコンバージョン率の向上に繋がります。
現在地が分かりやすくストレスのないサイト構造
ユーザーがストレスなくサイトを閲覧できるよう、現在地が明確に分かるサイト構造を目指しましょう。パンくずリストや分かりやすいナビゲーションメニューを設置することで、ユーザーは自分がサイトのどこにいるのかを把握しやすくなります。現在地を見失うと、ユーザーはサイトを閲覧することが億劫になり離脱してしまうため、迷わせない設計が重要です。他のページへ自然に誘導する導線設計を意識しましょう。
顧客が「迷わずお問い合わせできる」構造
お問い合わせの多いホームページは、顧客が迷わずにお問い合わせできる構造が確立されています。見たい情報が見たい場所にあり、お問い合わせへの導線がわかりやすいことは、成果を出すための絶対条件です。顧客が「お問い合わせしたい」と思ったその瞬間の気持ちを逃さないよう、細部まで配慮した設計が求められます。
お問い合わせ方法が分かりやすいか
お問い合わせをしたいという意欲があるにも関わらず、お問い合わせフォームがどこにあるか分からなかったり、方法が複雑で分かりにくかったりすると、顧客はすぐに離脱してしまいます。誰が見てもお問い合わせへの方法が分かりやすく明示されているか、第三者の目で定期的に見直しましょう。フッターやヘッダーなど、常に目に留まる位置に配置することも重要です。
お問い合わせフォームは入力しやすいか
お問い合わせフォームに辿り着いたユーザーを逃さないためには、入力のしやすさがカギとなります。入力項目が多すぎると、ユーザーは面倒に感じて離脱する可能性が高まります。必要最小限の項目に絞り込み、入力中のエラー表示を分かりやすくしたり、プルダウンメニューを活用したりするなど、ユーザーがストレスなく入力できる工夫を凝らしましょう。
お問い合わせフォームまでの自然な導線設計
お問い合わせの多いホームページは、お問い合わせフォームまでの導線設計が非常に上手です。ページを読み進める中で、「もっと詳しく知りたい」「この企業に相談したい」と感じたユーザーを、迷わせることなく自然にお問い合わせへと誘導する仕掛けが大切です。例えば、各コンテンツの終わりに「お問い合わせはこちら」といったボタンを配置するなど、ユーザーの気持ちに寄り添った設計を心がけましょう。
「よくある質問」の設置
「よくある質問」をホームページ内に設置することも、有効な施策です。ユーザーが感じるであろう疑問や不安をできるだけ事前に解消しておくことで、信頼性を高め、お問い合わせへの心理的なハードルを下げられます。些細な疑問が解消されることで、顧客は安心してお問い合わせができるようになるのです。
めぐみやでは、お問い合わせを増やしたいとお悩みを抱えている方に向けて、Web集客コンサルティングサービスやWebサイト制作サービスを提供しております。ホームページに対して抱える課題は、企業それぞれ多種多様です。その悩みに合わせた改善提案から実行までをワンストップで行えるため、費用対効果を高めながら結果を出せます。あなたのホームページのお悩みを、ぜひ一度お聞かせください。

めぐみやのWeb集客コンサルティング
Webサイトを活用して売上と利益向上を目指しませんか?
めぐみやが集客からサイト運営まで一貫してサポート致します。
まとめ
お問い合わせの多いホームページを制作するには、単に情報を掲載するだけでなく、「顧客中心」の視点を持つことが必要不可欠です。まずは露出を高めるためにSEO対策やAI対策を実行し、明確な企業像と「自社の強み」で顧客を惹きつけます。次に、顧客の悩みや不安に寄り添い、具体的なベネフィットや事例で信頼を築くことも大切です。そして、回遊率の高いサイト構造や、入力しやすいフォームなど、ストレスのない「お問い合わせ導線」を設計しましょう。
今回紹介した7つの特徴を取り入れることで、ホームページは単なる情報発信ツールから、売上を向上させる強力なツールへと進化するでしょう。
- 顧客の悩みや不安を解決し、共感を呼ぶ「顧客中心」の視点を持つことが何よりも重要
- 自社の強みや他社との差別化戦略を明確にし、顧客がサービスから得られる「ベネフィット」を具体的にアピールする
- SEO対策やAI対策で集客し、回遊率を高めるコンテンツ制作と、ストレスなく入力できる問い合わせフォームの設計を実行
お問い合わせの多いホームページに関するよくあるご質問
最後によくあるご質問をいくつかご紹介致します。
みなさまのWeb集客にお役に立てば幸いです。
その他、ご不明な点がございましたら以下のリンクよりお気軽にご相談下さいませ。
無料オンライン相談はこちらからどうぞ。
Q
ホームページのお問い合わせが少ないのはなぜですか?
A
お問い合わせが少ない原因として、「問い合わせたくなる導線がない」「ターゲットに刺さる情報が不足している」「スマホ表示が見づらい」「問い合わせフォームが長すぎる」などが挙げられます。アクセス解析で離脱ポイントを確認すると改善のヒントが得られます。
Q
お問い合わせを増やすには、どこを改善すべきですか?
A
主に改善すべきは「導線(CTAボタンの配置や文言)」「信用性(実績・お客様の声・顔出しプロフィール)」「フォームの簡潔さ」「ページスピードやスマホ最適化」などです。特に「誰に・何を伝えるか」を再定義することが重要です。
Q
問い合わせフォームは長いとダメですか?
A
はい、原則としてフォームは短いほうがコンバージョン率が上がります。最低限「名前」「連絡先」「問い合わせ内容」の3点に絞り、詳細情報はやり取りの中で収集するのがベターです。
Q
お問い合わせを増やすためにSNS連携は必要ですか?
A
有効です。SNSで信頼や共感を構築し、興味を持ったユーザーをホームページへ誘導することで、問い合わせにつながりやすくなります。特にBtoBではLinkedInやXの活用がおすすめです。
Q
チャットボットを導入するとお問い合わせは増えますか?
A
増加する可能性は高いです。すぐに質問できる環境が整っていると、ユーザーの不安が解消されやすくなります。ただし、機械的な回答が続くと逆効果になるため、運用設計は慎重に行いましょう。
Q
ホームページからの「問い合わせの質」が悪いです。改善方法は?
A
問い合わせ内容の質が低い場合、ターゲット設定や情報設計がズレている可能性があります。料金・対応範囲・対象顧客などを明確に記載することで、ミスマッチを防げます。
Q
問い合わせ数が急に減った場合、何を確認すべき?
A
サーバーやフォームの不具合、スパム対策の誤作動、SEO順位の急落、SNSや広告停止などが原因になっている可能性があります。まずはGoogle Search ConsoleやGA4で流入状況を確認しましょう。
Q
「お問い合わせはこちら」のリンクが押されていません。改善策は?
A
ボタンの文言、色、配置、周囲の余白、スクロール位置などを改善しましょう。「無料相談する」「今すぐ資料を受け取る」など、行動を促す表現への変更も効果的です。
Q
お問い合わせが来ても商談に進みません。なぜ?
A
問い合わせ直後の対応スピードが遅い、返信がテンプレ的、事前情報が足りないなどが要因です。お問い合わせフォームで「課題・希望・目的」などを聞いておくと、初回対応がスムーズになります。
Q
問い合わせページは独立させるべきですか?
A
はい。独立ページにすることでSEO対策もでき、情報の整理や導線設計も容易になります。あわせて、他のページから常に「1クリックで遷移できる」導線を設けることが重要です。
Q
業種によって問い合わせの増やし方は違いますか?
A
はい、業種ごとにユーザーの検討フローや悩みが異なります。たとえば士業や医療は「信頼性の訴求」、製造業やBtoBサービスでは「実績・導入事例」が問い合わせに直結します。
Q
Google広告やSNS広告はお問い合わせに効果がありますか?
A
正しい設計ができれば効果的です。問い合わせを目的とした広告では「オファー内容」「ランディングページの構成」「計測設定」の3点が成果を左右します。
Q
お問い合わせが来ないホームページはリニューアルすべきですか?
A
必ずしも全面リニューアルは不要です。まずは分析・仮説検証のうえで、CTA改善・フォーム簡略化・コンテンツ追加など、小さな施策から始めるのがリスクも少なくおすすめです。