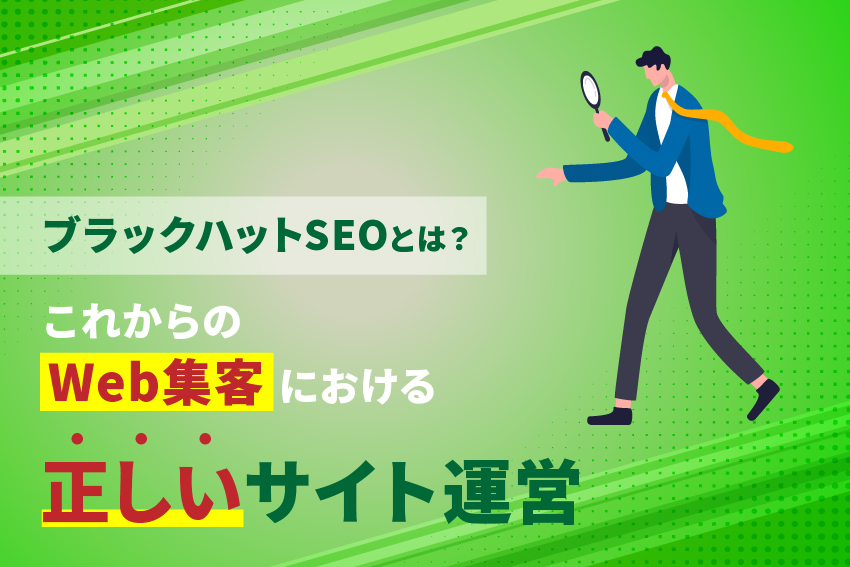記事の監修

Web集客・マーケティングの専門家として、13年間にわたり厳格な基準と緻密な戦略をもって中小企業の成功を導く。
一時的な集客の手法に頼ることなく、中長期的な効果を持続させる本質的なWeb集客の構築に注力。
『恵ある集客を。』をスローガンに掲げてクライアント様のサービスや商品の核心的な魅力を、的確にターゲットに伝えることを重視したWebサイト運用をサポート。
一昔前に流行したSEO対策の一つに「ブラックハットSEO」があります。企業のサイト運用者であれば、耳にしたことがあるのではないでしょうか。
ブラックハットSEOとは、「ブラック」という言葉が付くとおり不正な手段を使って検索順位を上げる手段のことです。広告のコストや時間がかからないことから、一部の間で横行していたSEOの施策です。
そこで、ここではブラックハットSEOの内容やGoogleの対応状況を説明し、正しいサイト運営について解説していきます。企業のサイト運用者は、ぜひ参考にしてください。
- ブラックハットSEOについて知りたい方
- ホワイトハットSEOについて知りたい方
- Googleのガイドラインに沿ったWebサイトの運営方法を知りたい方
目次
ブラックハットSEOとは
ブラックハットSEOとは、検索エンジンの仕組みの裏をかいて不正に検索順位を上げるための施策です。通常、GoogleやYahoo!などの検索エンジンから評価されるためには、良質なコンテンツを充実させて、数多くのユーザーからの指示を得るなどして、時間をかけて良質なサイトを構築していかなければいけません。
しかし、そのようなサイトを構築するためには、膨大な時間と労力が必要となります。そこで、短時間で楽に上位表示されるために、ユーザーの利便性などを一切無視して、検索エンジンに評価されることだけを考えた対策が「ブラックハットSEO」です。
現在ではGoogleがブラックハットSEOに対する対策を行ったため、ペナルティの対象になっており、通用しなくなった手法です。それでは、ブラックハットSEOには、どのような手法が存在したのでしょうか。ここからは、その具体的な内容を紹介していきます。
自作自演リンク
最初に紹介するブラックハットSEOが、「自作自演リンク」です。自作自演リンクとは、自分自身で意図的に被リンクの数を増やしていく手法のことをいいます。
これは、被リンクの数が多いサイトを評価する仕組みを狙った不正な施策です。他のホームページやブログに被リンクがある、つまり紹介されているサイトは良質なコンテンツであると判断するアルゴリズムがGoogleにはあります。このアルゴリズムは現在でも存在し、被リンクは評価されていますが、自作自演リンクが流行したことによって取締が厳しくなっています。
相互リンク
相互リンクとは、他のサイトとお互いに被リンクを貼る手法のことです。例えば、「弊社のサイトに被リンクを貼るので、あなたのサイトにも私の被リンクを貼ってください」というように相互で被リンクを張り合う方法です。
これもリンクの数を増やして評価を上げようとする試みで、過剰な相互リンクは現在ではペナルティの対象になっています。
トラックバック
次に紹介するブラックハットSEOが、「トラックバック」です。トラックバックとは、ブログや掲示場のような、誰もがコメントを投稿できる媒体に自社サイトに誘導するリンクを投稿して、被リンクを増やしていく手法です。
ブログの内容とは全く関係ないコメントを投稿することから「コメントスパム」と呼ばれることもあります。多くのブログサービスのコメント欄に氾濫したことから、ペナルティの対象となり対策が進められました。
キーワードの羅列
次に紹介する「キーワードの羅列」とは、記事中にキーワードを数多く詰め込んで上位に表示させる手法です。
一昔前、検索で使われるキーワードが数多く含まれたページが良質なコンテンツだと判断され、上位に表示されていた時期がありました。この仕組みを利用したのが、このブラックハットSEOの手法です。
現在では、検索アルゴリズムの改善により、不自然なキーワードの羅列は全く効果がなく、むしろマイナス評価の対象となります。
ワードサラダ
「ワードサラダ」とは、特定のキーワードを自動生成により作られた文章、もしくはそのようにして作成されたブログやWEBページのことを指します。検索エンジンの精度が低かった時代に横行したもので、被リンク用のWEBサイトとして使われていました。
ツールによって自動生成された文章は、文法的は正しいものの支離滅裂なものが多く、通常のコンテンツとしては成立しないものでした。現在では、検索エンジンの対策が進み、ペナルティの対象となっております。
クローキング
そして、最後に紹介するブラックハットSEOが、「クローキング」です。クローキングとは、サイトに訪れたユーザーとは別のコンテンツを検索エンジンに読み取らせる行為のことをいいます。
検索エンジンに対しては、SEOを意識したコンテンツを見せることで上位に表示されるようにさせる施策です。これも現在では、検索エンジンの精度が向上し、ペナルティの対象になっています。
ホワイトハットSEOとは
SEOとは、ウェブサイトを検索エンジンに最適化するプロセスを指します。その中で、ホワイトハットSEOは、検索エンジンのガイドラインに従い、誠実な手法を用いるSEOのアプローチを指します。これは長期的な視点でのウェブサイトの評価向上を目指す方法として認識されています。
ホワイトハットSEOの主な方法
SEOの成功の鍵は、正しい戦略と実行です。キーワードリサーチは、適切なキーワードを特定し、コンテンツの方向性を定めるための基盤となります。また、ハイクオリティなコンテンツの提供、サイトのユーザビリティの向上、適切な内部リンクと外部リンクの戦略は、サイトの権威を向上させる要素として不可欠です。
ホワイトハットSEOとブラックハットSEOの違い
ブラックハットSEOは、短期的な成果を求め、検索エンジンのガイドラインを無視または悪用する手法を指します。ホワイトハットとブラックハットの大きな違いは、前者がユーザーと検索エンジンの双方に価値を提供するのに対し、後者は一時的なランキング向上を目的とすることです。
ホワイトハットSEOのメリット
このアプローチを採用すると、持続的なサイトの評価向上が期待できます。さらに、ユーザー体験が最適化されるため、サイトへの訪問者の満足度が向上します。ブラックハットSEOのようなペナルティのリスクも大幅に低減されます。
ホワイトハットSEOの実践方法
続いてホワイトハットSEOの実践方法について解説します。
キーワードリサーチ
キーワードリサーチはSEOの基本中の基本です。ユーザーの検索意図を理解し、適切なキーワードを選定することが成功の鍵です。多くのツールやテクニックが存在し、これを活用して競合分析やトレンドの把握を行うことで、効果的なコンテンツ戦略を立てることができます。
高品質なコンテンツの作成
ユーザーの要求やニーズを満たすコンテンツは、SEOの成功に欠かせません。オリジナルかつ価値ある情報の提供は、サイト訪問者の満足度を高め、リピート訪問を促します。高品質なコンテンツは検索エンジンにも高く評価され、ランキング向上に寄与する要因となります。
オンページSEOの最適化
オンページSEOは、ウェブサイトの各ページが検索エンジンに適切にインデックスされ、ユーザーにとって有益な情報として認識されるための最適化手法です。タイトルタグやメタディスクリプションの適切な設定は、クリックスルーレートを向上させる要因となります。また、画像の最適化やモバイル対応も重要な要素となっています。
サイトの技術的側面の最適化
Webサイトの技術的な面もSEOには欠かせない要素です。特に、高速なページロード時間の確保は、ユーザーエクスペリエンス向上のために不可欠です。さらに、サイトの構造や内部リンク戦略の見直し、レスポンシブデザインの採用などが必要です。
バックリンクの取得
バックリンクは、他のWebサイトからの「推薦」のようなもの。ナチュラルなリンク構築は、サイトの信頼性や権威を高める要因となります。ゲストポスティングや業界団体への参加を通じて、質の高いリンクを獲得する方法があります。
ユーザーエクスペリエンスの向上
ユーザーエクスペリエンスは、Webサイト訪問者がサイトを使いやすく感じるかどうかを示すもの。サイトのユーザビリティ改善は、訪問者の滞在時間を延ばし、コンバージョン率を高める要因となります。
ホワイトハットSEOの長期的な取り組み
SEOは一度やったら終わりではありません。継続的なコンテンツ更新と品質保持が必要です。また、SEOのトレンドやアルゴリズムの変化に柔軟に対応することで、長期的な成功を実現できます。
GoogleによるブラックハットSEO対策

さて、ここまではブラックハットSEOのさまざまな手法について解説してきました。禁止されている施策として、企業のサイト運用者には参考になったのではないでしょうか。
前述したとおり、これらのブラックハットSEOは現在ではGoogle側の対策が進み、現在では禁止行為としてペナルティの対象となっております。そこで、これらのブラックハットSEOに対して、Googleがどのような対策をとっているのかを説明していきます。
ペンギンアップデート
ブラックハットSEOへの対策として最も有名なのが、この「ペンギンアップデート」です。とても有名な言葉ですので、サイト運用者の方であれば何度かは耳にしたことがあるのではないでしょうか。
ペンギンアップデートとは、意図的に被リンクを増やす行為をとったWEBサイトに対してペナルティを与えるものです。先ほど解説した「自作自演リンク」や「相互リンク」などが主に対象になります。
パンダアップデート
ブラックハットSEOへの対策として次に紹介するのが、ペンギンアップデートと並んで登場することが多い「パンダアップデート」です。
パンダアップデートとは、質の低いコンテンツやWEBサイトにペナルティを与えるものです。質の低いコンテンツとは、ユーザーにとって役に立たない情報や他のサイトのコピーコンテンツ、数行しか文章が書かれていないコンテンツが数多くあるサイトです。
先ほどのペンギンアップデートは、サイトの「外部」に設置される被リンクが対象でしたが、このパンダアップデートでは、サイトの「内部」であるコンテンツの中身が対象となりました。
このパンダアップデートにより、SEOの主流は小手先のテクニックから、サイトに訪れるユーザーに目が向けられるようになりました。
あわせて読みたい
Googleのガイドラインに沿った運営
さて、ブラックハットSEOへの対策として、ペンギンアップデートとパンダアップデートについて話をしてきました。これらのアルゴリズムのアップデートにより、ブラックハットSEOは廃れるようになったのです。
そこで、Googleのガイドラインに沿ったサイトの運営が注目されるようになりました。先ほど説明した、いわゆる「ホワイトハットSEO」です。
そこで、ここからはGoogleのガイドラインに沿った正しいサイト運営について解説していきます。
正しいサイト運営とは
Googleのガイドラインを要約すると、「ユーザーにとって有益なコンテンツを評価する」という一言に尽きるでしょう。つまり、サイトに訪れるユーザーを第一に考えてサイトを構築していくことこそが、現代における正しいサイト運営法であり、SEO対策であると言えるのではないでしょうか。
ユーザー目線でコンテンツの質を高める
それでは、サイトに訪れるユーザーにとって有益なコンテンツとは、一体どのようなコンテンツを指すのでしょうか。それは、特定のキーワードで訪問したユーザーに対して、その検索意図に沿った情報が分かりやすく整理されているコンテンツです。
そのためには、企業が発信したい情報を発信するのではなく、ユーザーが求めている情報は何かを考え、満足できるレベルで回答してあげなければいけません。つまり、徹底したユーザー目線でコンテンツの質を高める必要があるのです。
あわせて読みたい
まとめ
さて、ここではブラックハットSEOの数々の手法と、正しいサイト運営の手法について話をしてきました。実際のコンテンツ作成を任されているサイト運営にお役立て出来れば幸いです。
ブラックハットSEOに対するGoogleの対策を理解することで、サイト運営に必要なことが見えてきます。ここで解説した内容を参考にして、ぜひGoogleに評価される正しいサイト運営に取り組んでください。
- ブラックハットSEOとは不正手段を使って検索順位を上げる手法
- ホワイトハットSEOとは長期的なサイトの評価向上を目指しユーザー体験を最適化する誠実なSEO手法
- GoogleはブラックハットSEOに対して厳しい対策を講じている
あわせて読みたい
ブラックハットSEOに関するよくあるご質問
最後によくあるご質問をいくつかご紹介致します。
みなさまのWeb集客にお役に立てば幸いです。
その他、ご不明な点がございましたら以下のリンクよりお気軽にご相談下さいませ。
無料オンライン相談はこちらからどうぞ。
Q
ブラックハットSEOとは何ですか?
A
ブラックハットSEOとは、検索エンジンのランキングを不正に上げるための手法や技術のことを指します。これに対して、正当な方法でサイトのランキングを向上させるホワイトハットSEOというものも存在します。
Q
ブラックハットSEOの具体的な手法は?
A
キーワードスタッフィング、ドアウェイページの作成、不自然なリンクの購入や交換などが主な手法として挙げられます。
Q
なぜブラックハットSEOは推奨されないのですか?
A
ブラックハットSEOの手法は、検索エンジンのガイドラインに違反することが多く、検出されるとペナルティを受けるリスクが高まります。また、ユーザー体験を低下させる可能性があるためです。
Q
ペナルティとは具体的にどのようなものですか?
A
ペナルティは、サイトのランキング低下や、最悪の場合、検索結果からの除外などが考えられます。
Q
ホワイトハットSEOとブラックハットSEOの主な違いは何ですか?
A
ホワイトハットSEOは検索エンジンのガイドラインに従った正当な手法であり、ブラックハットSEOはガイドラインに違反する不正な手法を用いる点が主な違いです。
Q
ブラックハットSEOを利用すると短期間で結果が出るのですか?
A
短期間でのランキング上昇の可能性はあるものの、検出された場合のリスクが非常に高いです。
Q
ブラックハットSEOのリスクを回避する方法は?
A
最も確実な方法は、ブラックハットSEOの手法を使用しないことです。検索エンジンのガイドラインを常に確認し、それに従ったSEO対策を行うことが推奨されます。
Q
どのようにしてブラックハットSEOを検出できますか?
A
検索エンジンのWebマスターツールや、専門のSEOツールを使用してサイトの分析を行うことで、不自然なリンクやコンテンツの変更などを検出することができます。
Q
ブラックハットSEOを使用した結果、ペナルティを受けた場合の対処法は?
A
不正な手法やコンテンツを全て削除・修正した後、検索エンジンへの再評価のリクエストを行うことが一般的です。
Q
ブラックハットSEOとグレーハットSEOの違いは?
A
グレーハットSEOは、ホワイトハットとブラックハットの中間に位置する手法で、ガイドラインの境界線上にあるものを指します。厳密には違反ではないが、検索エンジンからペナルティのリスクがある手法も含まれます。