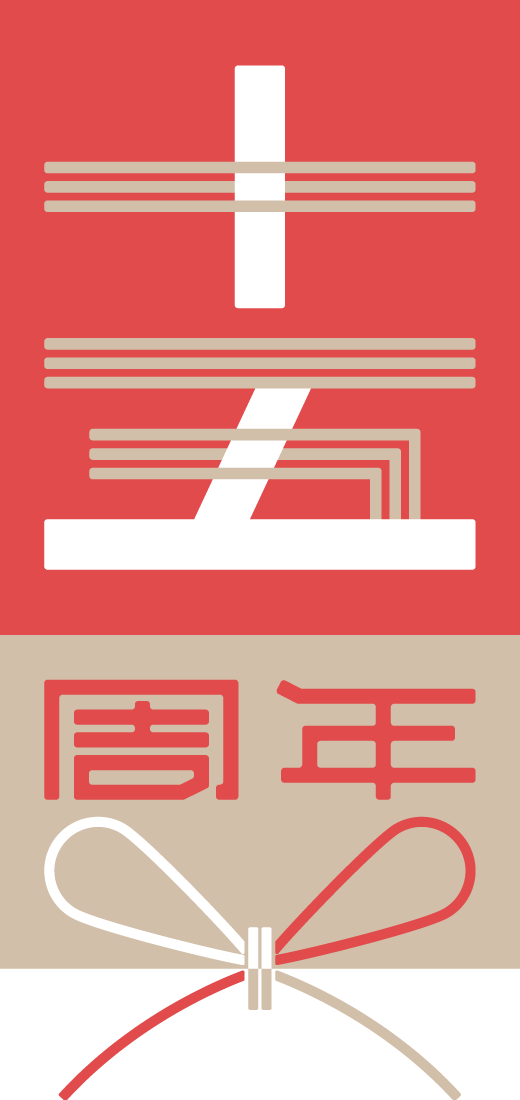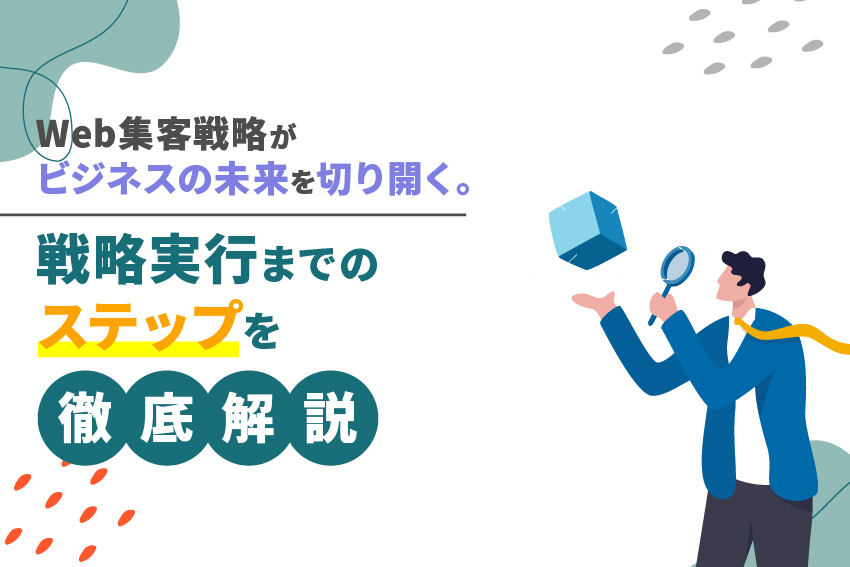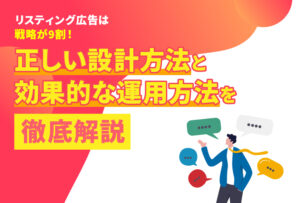記事の監修

Web集客・マーケティングの専門家として、15年間にわたり厳格な基準と緻密な戦略をもって中小企業の成功を導く。
一時的な集客の手法に頼ることなく、中長期的な効果を持続させる本質的なWeb集客の構築に注力。
『恵ある集客を。』をスローガンに掲げてクライアント様のサービスや商品の核心的な魅力を、的確にターゲットに伝えることを重視したWebサイト運用をサポート。
Webで集客をするには、戦略を立てることが不可欠です。Web集客は、時間や手間がかかることが考えられるため、戦略のない施策は無駄な投資となることが考えられます。この記事では、戦略的なWeb集客の説明とその必要性について見ていきます。
さらに、Web集客における戦略立案の実行までのプロセスと心構えも取り上げていきます。自社の集客に悩むWeb担当者の戦略立案のヒントになれば幸いです。
- Web集客戦略について詳しく知りたい方
- Web集客を実施するメリットを知りたい方
- Web集客の実践方法を具体的に知りたい方
目次
Web集客とは
Web集客とは、インターネット上での顧客獲得手法の総称を指す言葉です。時代がデジタル化している現代において、多くの企業や個人がインターネットを活用し、潜在的な顧客を自身のサービスや商品に引きつけるための戦略を立てることが求められています。
Web集客の手法は多岐にわたりますが、その中でも主なものとしてSEO(検索エンジン最適化)、SNSマーケティング、コンテンツマーケティング、オンライン広告(PPC広告など)などが挙げられます。これらの手法は、それぞれの特性や効果を理解し、目的に応じて組み合わせることで、より効果的なWeb集客が可能となります。
例えば、SEOはウェブサイトが検索エンジンの検索結果ページで上位に表示されるように工夫することで、自然な訪問者の流入を増やす手法です。一方、SNSマーケティングは、ソーシャルメディアのプラットフォームを活用してターゲットとなる顧客層にリーチする方法です。
Web集客の魅力は、従来の広告や宣伝とは異なり、リアルタイムでの反応やデータ分析が容易であること、そして効果的なターゲティングにより、高いROI(投資対効果)を期待できることです。これにより、ビジネスオーナーやマーケターは、より効果的な戦略の策定や修正が可能となります。
Web集客に戦略が必要な理由
Web集客は、今日のビジネス環境での成功を左右する重要な要素です。多くの企業や組織がデジタル空間での集客を追求している中、ただ単にオンラインに存在するだけでは、効果的な結果を生み出すことは難しいのが現状です。そこで、目的に合わせた戦略の策定が求められるのです。戦略的なアプローチは、企業の目標を達成し、競合との差別化を図るために不可欠な要素となっています。以下では、Web集客における戦略の重要性について、具体的な理由とともに詳しく解説します。
競合他社との差別化
Web上では無数の競合が存在し、それぞれが顧客の注意を引こうと競っています。戦略的なWeb集客は、この競争の中であなたのビジネスを際立たせるために不可欠です。差別化を図ることで、あなたの提供する価値を顧客に明確に伝え、彼らの心を捉えることが可能になります。独自のブランドストーリー、ターゲット顧客に響くメッセージ、オリジナルコンテンツの提供は、集客効果を高める重要な要素です。
ターゲットオーディエンスの明確化
効果的なWeb集客のためには、明確なターゲットオーディエンスの設定が不可欠です。一般的な集客方法と異なり、Web集客ではデータを活用して正確なターゲットを定め、そのニーズに合わせたコンテンツや広告を展開することができます。このアプローチにより、関心のある顧客群に直接リーチし、より高いコンバージョン率を達成することが可能です。
資源の効果的な活用
Web集客戦略を策定する最大の利点は、限られた資源を効果的に活用できることです。特に中小企業では、予算や人員は限られているため、各リソースを最大限に活用し、投資対効果の高い戦略を実施する必要があります。適切な戦略によってデータ駆動の意思決定を行い、予算を最適な施策に振り分けることができます。
変化する市場環境への対応
デジタルマーケティングは常に変化しており、新しいトレンドに柔軟に対応することが成功の鍵です。技術革新や消費者の行動変化に応じて戦略を進化させることで、企業は競争の一歩先を行くことができます。継続的な市場分析とトレンドの監視により、迅速かつ効果的な戦略修正が可能になります。
持続的な成果を実現
一時的なキャンペーンは短期間での集客には有効かもしれませんが、長期的なビジネス成長には継続的な戦略が必要です。定期的に戦略を見直し、改善を行うことで、ビジネスは持続的な成長を実現することができます。長期にわたる顧客との関係構築とブランド価値の向上を目指す戦略が、企業を成功に導くでしょう。

めぐみやのWeb集客コンサルティング
Webサイトを活用して売上と利益向上を目指しませんか?
めぐみやが集客からサイト運営まで一貫してサポート致します。
Web集客の8つのメリット
Web集客の戦略実行により得られる集客メリットとは、どのようなものでしょうか?根本的な部分として、リアルビジネスによる集客とは違う部分を紹介しましょう。Web集客でのメリットとは、インターネットの仕組みによる恩恵です。特にWeb集客のメリットでは、次の8つが挙げられます。
場所を必要としない
Web集客は、場所を必要としません。実店舗の場合は開業に向けて店舗を用意する必要があります。しかしWeb集客の場合は、インターネット上のコンテンツのため、店舗の場所は不要です。無形のビジネスとなります。
紙媒体における作業が不要
Web集客は、紙媒体での集客が必要ありません。紙媒体のような物理的な集客が不要となるため、印刷や配布などの作業が不要となります。労力と時間コストを省くことが可能です。
24時間365日「いつでも」「どこからでも」認知される
Web集客は、インターネット上に集客コンテンツを公開することにより、24時間365日のフル稼働を現実とします。Web集客は、顧客に対して「いつでも」「どこからでも」訴求することが可能です。
不特定多数へ訴求が可能
Web集客は、不特定多数に向けて制限に関係なく訴求できます。紙媒体の場合は、印刷部数が上限となったり、宣伝活動をする担当者の就業時間にも左右されたりするでしょう。Web集客の場合は、インターネット上で複数人が同時に見られるため、不特定多数への訴求を可能とします。
詳細なターゲット訴求が可能
Web集客は、特定の個人にまで絞りこんだ詳細なターゲット設定が可能です。インターネット利用者の増加と層の広さに伴い、パーソナライズ性の向上によるものとなります。ターゲット訴求では、ペルソナを設定して、価値観をもったユーザーに見つけられる仕組みづくりが可能です。
あわせて読みたい
即時性がある
Web集客は即時性を発揮できます。検索連動型広告を活用することにより、自社ビジネスの市場価値を即時判断することが可能です。広告の運用は、集客コンテンツの調査ツールとしても活用でき、実際の反応を確かめてからの始動にも活用できます。
実店舗集客よりコストを抑えられる
Web集客は、実店舗集客よりコストを抑えることが可能です。たとえば実店舗経営の場合は、集客のためにチラシを配布したり、営業担当の労力が必要だったります。しかしWeb集客は、物理的なチラシや営業活動に必要な人手を必要としません。そのため、実店舗集客より集客コストがかからないのです。
集客ツールが資産となる
Web集客をするために構築した集客ツールは、企業の資産となります。企業の資産となる理由は、集客ツールを長期的な施策にできるからです。自社のWebサイトを集客ツールにできた場合、独自の市場において集客できる資産となるでしょう。
あわせて読みたい
流入ごとのWeb集客戦略
それでは、Web集客の戦略を流入ごとに解説します。流入ごとにどのような集客戦略が最適なのか?5つの経路で解説していきましょう。
SEO流入
SEO流入は、Web集客の中でも潜在ユーザーに向けた自然流入が見込める戦略の1つです。SEOとは、インターネット検索で活用する検索エンジンに評価されて、検索キーワード検索結果上位表示にWebサイトが掲載されるための最適化対策のことをいいます。
SEO流入では、SEO評価により検索結果ページの上位表示から流入となるWeb集客の中でも成果につながりやすい施策です。SEOは、「Search Engine (検索エンジン)Optimization(最適化)」の頭文字の略称となります。検索エンジン大手のGoogleやYahoo!に対して施す評価基準を満たすための対策です。
SEOにより流入するユーザーは、目的意識の高い潜在層となります。たとえば、Webブラウザの検索窓に「新宿 西口 ランチ」と入力するユーザーがいたとしましょう。その検索ユーザーは、「新宿駅西口周辺でランチのお店を探している」という目的を持っていることとなります。
その場合、検索エンジンにおける「新宿 西口 ランチ」の検索結果ページには、「新宿駅西口周辺のオススメランチのお店を紹介」しているコンテンツが検索ユーザーに役立つこととなるでしょう。SEO流入では、ユーザー自身が検索エンジンを活用して目的意識を強く持った状態で流入してきます。
Web集客では、SEO流入の成果につながりやすい点が大事です。また、成果につながりやすいSEO流入は、上位表示に時間と労力がかかる点も特徴となります。SEOは、上位表示された場合の費用対効果も高くなりますが、専門的な知識や経験などが必要となるでしょう。
あわせて読みたい
広告流入
広告流入は、企業がWeb戦略をするのに早い結果を得やすい施策となります。広告流入には、種類があり集客目的によって使い分けることになるでしょう。主なWeb広告の種類は次の通りです。
流入経路としては検索連動型広告の場合、先ほど紹介したSEO流入の要素による検索行動流入となります。検索エンジンの検索結果ページ広告枠に掲載される広告のため、誘導文次第でその先にあるページへ流入することとなるでしょう。
また、ネイティブ広告の場合はページコンテンツの1部と認知されるため、コンテンツ内容に興味関心の高い流入が期待できます。他の広告流入では、従来の純広告のような宣伝要素が高いわけではありませんが、掲載媒体の露出度の恩恵を受けることができるでしょう。
ただし昨今の広告出稿では、広告費の高騰が課題となります。その要因は、インターネットの普及とスマホ需要の拡大、さらにコロナ禍におけるネット通販需要が高まる中、多くの企業が広告出稿に参入してきたためです。そのため、入札単価制の広告出稿費用は資金力で競うこととなり、費用の高騰が避けられなくなりました。
ただし、広告運用は費用さえかければすぐに効果を確認できる点が大きなメリットとなります。自社ビジネスにおける市場価値を判断するために欠かせないWeb戦略となるでしょう。
あわせて読みたい
SNS流入
SNS流入は、検索エンジンによる自然検索流入と異なるプラットフォームでの認知拡大と興味関心の高いユーザー層の流入が期待できます。SNSでは、それぞれのユーザーが自分の地域や属性に関係する他のユーザーとつながり、共感により濃い関係性をつくることが可能です。
SNSは、ビジネス色のない趣味や特技などでつながる個人同士が共感を持って情報を共有しあうコミュニケーションの場となります。そのような濃いつながりの場において、企業アカウントが個人アカウントの共感を得るためには、ビジネス目的をおさえることが必要です。
さらにSNSでの情報発信においては、興味関心の高いユーザーの共感を得るコンテンツが重要となります。国内において利用者数の多いSNSそれぞれにおいて、コンテンツの特徴がちがうことも理解しておきましょう。
- Facebook:実名登録のアカウントが中心となり年齢層が高め
- Twitter:手軽な短文メッセージと匿名性の高さ、若年層を中心とした拡散力あり
- Instagram:画像や動画投稿により視覚的な共感でつながる
SNS流入では、自社ビジネスの訴求部分とSNSの特徴をすり合わせて活用することが大事です。SNS上で、共感と信頼が得られれば自社Webサイトへの誘導が自然と機能してきます。
他サイトより流入
Web戦略による流入経路では、他のWebサイトにて紹介される場合もあります。他のWebサイトとは、自社の取り組みに対して第3者が客観的な視点で紹介する形式です。とくにニュース記事やトレンド記事などで話題になることにより、自社の集客力以上の流入効果を得ることも期待できます。ただし、他サイトからの流入は自社で管理することができないため、想定することができません。
直流入
直流入の場合は、企業のWebサイトURLを直接入力して訪れたユーザーやユーザーが活用するブラウザのブックマークから流入する形式です。直流入の場合は、リピーターや企業Webサイトに対して高い興味関心を持っていることが考えられます。そのため直流入による関係性は、顧客との関係性が良好であることといえるでしょう。
Web集客の戦略を立てる前準備
それでは、Web集客に必要な戦略立案前の準備を詳しく見ていきましょう。戦略を立てる前に知っておきたいデータは次の7つです。
経営目的と目標の明示
会社を経営していれば、経営理念や社長の理念などをスローガンとしていることが多いでしょう。経営目的は、経営理念として企業の目指す方向です。目的を明確にして、企業が目指す目標を明示できるように設定することが重要になります。
経営目的は、そのままWeb集客の大きなテーマとなり、自社の強み部分とともにアピール材料の1つとなるでしょう。
ROASの設定
続いて、Web集客にかかるROASの設定をします。ROAS(Return On Advertising Spend)は、広告を運用するWeb集客において「広告費に対してどれだけの売上が上がったか」を数値化して判断する成果指標です。
つまり、ROASは企業が広告費用に投資した資金の回収率を事前に予測するデータになります。Web集客においては、広告の運用以外でもWebサイト制作や動画配信などWebを活用した施策にかけた費用を基準にした分析もできるでしょう。
CPAの設定
先ほどのROASの設定で明確になるのは、売上とWeb施策全体に対しての費用対効果となります。そのため、1人の顧客が商品やサービスを購入するまでにかかった経費については、ROASで判断はできません。
そこで、Web集客の効果をより具体的に分析するために必要な設定があります。それは、CPAといい、1人の顧客がコンバージョン(成約)までにかかったWeb施策費用を数値化する指標です。売上に対してCPAが低ければ利益は上がり、CPAが高ければ利益が下がる仕組みとなります。
自社の許容CPA
CPAを設定する場合、広告の運用においては自社の許容CPAを設定することが重要です。企業は、利益を出すことを重視するためCPAを低くすることに重きをおきます。結果的に自社の許容CPAを設定することにより、確実な利益は出ることでしょう。
ただし、リスティング広告の運用においては、競合他社との競争のために許容CPAを上げざるをえない状況も出てきます。リスティング広告の出稿が入札システムのため、競合との競争は避けられない場合もあり、許容CPAを高く設定することも考えなければいけません。
実行開始から成果までの時間想定
次にWeb集客に必要な戦略を立てる前の準備として、実行開始から成果が出るまでの時間的スケジュールを想定します。実行から成約までの時間的なスケジュールは、Web集客に必要な社内の人的リソースや環境、外注の有無などさらに細分化されたコストを想定できるのです。
顧客理解
Web集客における目標や予算設定などの準備が整ったら、次に自社の商品やサービスを購入して満足してくれる顧客層を明確にする必要があります。その理由は、「ウチの商品を利用して満足する人はどんな人なのか?」を理解しないまま漠然とビジネスを展開してしまうと、無駄な経費がかさみ、経営を圧迫することも考えられるからです。
ターゲティング
顧客を理解するためには、ターゲットを設定することが必要です。「自社の商品を利用して金額以上に価値を感じてもらえる顧客とは、どのような個人なのか?」を具体的にデータ化していきます。ターゲティングは、「都市部にすむ主婦」というグループに向けた設定ではなく、「年齢・性別・職業・家族構成・学歴・趣味」など特定の個人まで絞り込むことが必要です。
顧客心理
そして、ターゲティングによって想定された架空の個人像の心理を基準としたコンテンツを提供していきます。自社の商品やサービスを利用して満足する顧客の心理を具体的に表現していくのです。
Web集客の場合は、リアル店舗と違ってインターネット上で試験的に掲載することもできます。顧客心理をふまえた文章でアピールする場合でも、「どの文章が一番訪問ユーザーが多いか?」判断することもできるのです。
購買心理をふまえた戦略を施策
これまでの顧客を理解するために分析したターゲット設定を基準としたWeb集客の戦略を展開していきます。あくまでも、戦略の基準となるのは、ターゲティングされた顧客です。
認知を高めようとして、多くの市場に集客の手をのばすことは、結果的に経費の圧迫が考えられます。そのため、自社の状況に合わせた広告運用を取り入れる場合は、専門の業者に相談をしてみてもいいでしょう。
あわせて読みたい
競合分析
Web集客の事前準備として、顧客を理解したうえで競合他社の動向も分析する必要があります。自社の商品やサービスと類似した商品を扱う企業や同じ地域内の企業など、「Web上でどのような立ち位置にいるのか?」を分析するのです。
競合分析は、自社の顧客を理解することにより「顧客のニーズを満たす商品やサービスを扱う競合を上回る魅力を提供する」ための判断材料となります。競合に勝つための魅力は、自社の強みとも一致するのです。
あわせて読みたい
戦略を立てる上で重要な確認事項

ここからは、戦略を立てる上での重要な確認事項についてご紹介します。Web集客戦略を立てていく上では、次の項目を事前に明確にしておくことが大切です。最大限の集客効果を発揮するために役立つポイントとなります。
既存顧客リストの有無
戦略を立てる際に、これから獲得する「新規顧客」だけではなく「既存顧客」のリストも確認しておきましょう。新規顧客に向けた施策を実施した結果、既存顧客が離れてしまうことのないように、事前にリピーターへの影響を推測することが必要です。
例えば、新規顧客へのアプローチばかりに注力し、既存顧客へのリマインドが不足してしまうケースや、新規キャンペーンばかり行うことで、既存顧客への優待が不足してしまうケースもあるでしょう。新規顧客獲得のためのサービス内容の大幅な変更により、既存顧客が戸惑い離れていくこともあるかもしれません。さらに、永遠に改善されないサービスが既存顧客を逃す場合もあります。
つまり、Web集客での新しい戦略を立てる上で「戦略実行が既存顧客にどのような影響を与えるのか」を推測する必要があるのです。そのため、既存顧客のリストは効果検証における大切な判断材料となります。新規顧客を獲得するのと同時に、リピーターへの影響も視野に入れておくことが大切です。
メディアリストと現状把握
戦略を立てる上で「メディアリスト」を作成することが望ましいです。現時点で自社との関わりがある・ないに関わらず、マスメディア、Webメディア、ソーシャルメディア(自社ブログ含む)をそれぞれ書き出しましょう。
書き出したメディアと、現状のステータスをまとめていきます。どのメディアが自社サイトに興味を持ってくれているのか、そしてどのメディアにアピールしていきたいのかを整理していきます。アプローチしたいメディアを明確にすることで、行うべき戦略が見えてくるのです。
また、戦略の実行前と実行後のメディア数の変化も可視化しておくと良いでしょう。
戦略の期間
立てた戦略がどのくらいの期間で結果が出るのかを予測しておくことが必要です。期間を明確にしておくことで、実際に実行した戦略が成功したのかどうか見極める判断材料となります。
短期間で大きな効果が出ているからといって、長く続ければそれだけの効果が見込めるとは限りません。短期間で実施するからこそ最大限の効果が得られることもあります。もちろん、その反対で長期的に続けることが大きな効果に繋がることもあります。戦略と同様、期間を明確にしておくことは大切です。
長期的な戦略の場合は、時間的な想定だけでなく数量的な目安も必要になるでしょう。例えばWebサイトの場合は、コンテンツ記事の更新頻度やページ数などを目安にし、継続していくことが求められます。
注意点として「立てた戦略の期間は、必ずしも正確に遂行しなければならない」わけではありません。あくまで目安としての期間を立てておき、状況に応じて早い段階で切り上げたり、一定期間延長したりなど、臨機応変な対応が必要になります。効果検証をしながら様子を見て実施していきましょう。
あわせて読みたい
戦略に必要なリソース
長期の場合でも短期の場合でも、戦略に必要なリソースを明確にしておきましょう。せっかく立てた戦略でも、リソース不足が原因となり途中で断念してしまうことがあるからです。上記で「結果が求められる期間」を明確にし、同時に「必要なリソース」を割り出して、あらゆる事態にも対応できるように準備しておきましょう。
リソース不足にお悩みの方は、現時点の業務フローを見直し、削減できる方法はないか検討してみてください。社内で補うのが難しい場合は、専門家に外注するのも一つの方法です。施策や戦略の実施方針に見直せる点があれば、より効率的にWeb集客を行える体制を構築できます。ぜひ、戦略を実行する前にリソースを確保しておくことをおすすめします。
外注可能作業を検討
上記でお伝えしたように、自社内製で戦略を実行に移すことが困難な場合、専門業者に依頼することが望ましいです。外注することで結果的にコストの削減につながるケースもあります。内製の場合、戦略を実行する担当者の業務負担が増え、時間的にも人的にも通常業務以外の取り組みが増えてしまうでしょう。
新たな人材確保は、年間で考えると多額の出費となります。知識や技術を教育するためのリソースも新たに必要となるため、むしろ業務量が増えるだけでなく、年間の人件費も必要です。新たな人材確保も悪くはありませんが、すぐに社内の成果には繋がらないため、長い目で見るべき戦略と言えます。
その反面、専門家はすでに専門知識や技術を持ち合わせており、即戦力として稼働してもらえます。専門業者に依頼したほうが、迅速かつ少ないコストで実行できるケースも多いのです。Web集客の戦略が円滑に実行できる手段となるでしょう。

めぐみやのWeb集客コンサルティング
Webサイトを活用して売上と利益向上を目指しませんか?
めぐみやが集客からサイト運営まで一貫してサポート致します。
戦略を実行する上での心構え
Web集客に必要な戦略立案までの準備が整いました。それでは、実際に戦略を実行する上での心構えも見ていきましょう。
業種により戦略は違う
Web集客の戦略に必要な準備が整い、実行するフェーズに至った場合、単純に「では、広告を出稿しよう」と進めることはおすすめできません。その理由は「Web集客は業種によって戦略を変える必要がある」からです。
例えば、健康食品を扱う業者と中古車の買取り業者が同じ戦略を実行した場合、片方は「商品の販売」で片方は「商品にするための仕入れ」という明確な違いがあります。
業種によって、購買(成約)までの目的や経路が異なるため、戦略の実行についても「自社のビジネスに合った訴求」をしていく必要があります。
さまざまな業種によって戦略が異なるのは、このような商品やサービスの特徴があるからです。同じWeb集客のための広告出稿でも、自社ビジネスとマッチした工夫の仕方が求められます。
業種により異なる戦略は、大きく3つに分けられます。一つは、他社よりも低コストでの販売や製造を狙う「コストリーダーシップ戦略」。二つ目は、顧客の「特定のニーズ」を満たすための商品やサービスを提供する「差別化戦略」。三つ目は、狙う市場を限定することで、狭い中での専門的ポジションを確立する「集中戦略」です。
この3つのビジネス戦略が成功につながる大きな方法でしょう。そして、これらの戦略を具体的に行動レベルへ落とし込んでいく際の「広告」や「Webサイト制作」「SNSマーケティング」などが手段となるのです。
つまり、目先の「手段」のみを考えていると、実行フェーズで適切な方法が見極められず苦戦することとなります。自社ビジネスを客観的に見て、広い視野から戦略を捉えていくことで、ベストな実行方法と細かな戦略が見えてくるのです。
顧客の購買行動の把握
ただし、基本的な顧客の行動パターンは共通定義できます。それは「顧客は商品やサービスを認知して、比較検討の結果で購買を決める」という流れです。
顧客はまず、特定の商品やサービスを認知した後、インターネットのWebサイトや口コミで商品に関する情報を検索します。実際に購入した方のレビューや商品の詳細を入念に確認し、本当に購入すべき商品かどうかを見極めるのです。同じ商品やサービスを展開している他社商品も見比べるでしょう。
検討の末「購入したい」と決心すれば、やっと商品を購入します。つまり、商品やサービスを認知してもらうことが目的の戦略であれば、その先の「購入に至るまでの仕組み」までも想定する必要があるのです。この顧客の購買行動を頭に入れて、それぞれの戦略を実行することが大切です。
新商品や新規サービスを発売する際は、特に顧客の心理を追求し準備していく必要があります。他の企業には見られなかった画期的な商品やサービスは、顧客がすぐに飛びつくとは限らないからです。確かに、世の中で話題となっている新商品を「誰も持っていないうちにすぐに購入したい」と感じる方がいます。また「使用する人が増えてきたら購入する」と感じる顧客もいるでしょう。
しかし、ほとんどの顧客は「現在使用しているもので不自由がないから、買わない」「画期的だけどよく分からない商品は買わない」などと懸念を示すパターンが一般的なのです。前述とこれらの顧客との差を「キャズム」と呼びます。このキャズムを超えるような商品やサービスを打ち出すこと、キャズムを感じさせない売り方をすることが、我々に求められる試練となるでしょう。
新商品やサービスを発売する際は特に、これらの顧客心理までをも分析し、対策をしていく必要があります。
競合乱立の市場を避ける
顧客の行動パターンをふまえると、商品やサービスを認知されたあとに競合との比較や検討をすることが想定されます。自社が取り扱う商品が競合の乱立する市場である場合、競合との価格競争になることも考えられるでしょう。
価格競争は、結果的に経営を不安定にする要因となります。そのため、可能な限り競合が乱立する市場を避けることが必要なのです。
Web集客の成功事例を学ぶ
また、Web集客の戦略を実行するうえで、自社の商品やサービスに似た競合他社の戦略による結果を分析することも大いに役に立ちます。競合の成功事例から「なぜ、成果が出たのか?」Web上で展開した取り組みを具体的に学ぶのです。
自社が一からあらゆる手段で戦略を実行しなくても、競合他社がすでに実施している前例を参考にすることで、失敗するリスクを予測することも可能です。しかし「他社が失敗しているからこの方法は成功しない」「他社が成功しているから自社でも同じ方法で成功するだろう」と安易に考えるのは避けましょう。あくまで自社の戦略を成功させるための1つのデータとして取り入れるようにしてください。
自社で不足する部分を補う
成功事例から得たデータから、「ウチにはこの部分が不足している」というポイントを抽出していきます。ただし、同じような戦略を立てることではなく「この部分はウチでしかできないサービス」という自社の強み部分をアピールするのです。結果的に、自社で不足する部分を補うことができるでしょう。
あわせて読みたい
Web集客戦略を実行するプロセス
Web集客の戦略を実行するには、Web上で集客できるまでのユーザー行動を理解することが必要です。ユーザーが「どのような流れにより購買行動を起こすのか?」を具体的にデータ化します。
そして、Web集客の戦略では実行までのプロセスを理解する必要があります。今からお伝えする「Web集客の流れ」を基本として「どのような手順で集客をすればよいのか?」という実行プロセスを明確にしましょう。
Web集客の流れを知る
Web集客の流れを知ることは、Web集客の本質的な部分を知ることにも繋がります。昨今のWeb事情では、SNSをはじめとするアプリやツールが流行し、似たようなサービスが乱立しています。それだけに、流行を追う形となる情報に流されやすくなるのです。
例えば「最近は動画配信からのアクセスが熱い」「ライブ配信アプリから誘導できる」「やっぱりインスタが盛り上がっている」などの主観的な情報に振り回されて右往左往してしまうことです。
Web集客の基本は、アプリやツールに依存することなく「全体像の流れを知る」ことから捉えることが大切です。具体的には、次の流れになります。
- Web上で認知する
- 興味・欲求の高い層を増やす
- 購買行動に出てもらう
Web集客の成功にはさまざまな方法や手段がありますが、あくまでもこの3つの流れを基本として捉えておきましょう。
Web集客の目的と目標を再認識
集客にWebを活用するには、目的を明確にしていく必要があります。「なぜ、Webで集客をするのか?」集客により「どのようなゴールを目指すのか?」を具体的に設定するのです。
目的があいまいな状態なままだと、Web集客により目指すゴールを具体的に深堀することができません。そのため、準備の段階でWeb集客の目的を明確にする必要があります。
顧客の共感を得るポイントを設定
Web集客の実行プロセスとして、顧客の共感を拡大していく設定がポイントとなるでしょう。顧客に共感してもらうためには、居心地の良いWebサイトなど客観的なアピールが必要です。
Web集客を実行に移すには、以上のようなプロセスをふまえて戦略を立てていきます。さらに、Web集客では戦略を立てる前に準備をしておいたほうがいいデータがあるのです。準備に必要なデータを用意することが戦略を実行するときの大きな手助けとなるでしょう。
社内行事を踏まえた計画
ある程度戦略の方向性が定まってきたら、社内行事も踏まえて実行の計画を立てましょう。社会情勢やインターネット業界の背景を合わせて検討するのと同様に、社内行事にも目を向けておくことが大切です。
計画している戦略をむやみやたらとしたいままに実行してしまえば、他部署の集客戦略の妨げになったり、企業全体のプロジェクトに影響を与えてしまうケースもあります。
他部署との連携をしっかりと行い、社内行事を踏まえた集客戦略を行うことが、最大限の効果を発揮できるのです。反対に言えば、社内行事や他部署のプロジェクトと連携したWeb戦略を立てることも、一つの集客方法となります。
定期的な振り返り日時を設定
集客戦略を実施する上で、定期的な振り返りが必要です。毎日経過観察することももちろん大切ですが、定期的な振り返り日時を設定し、社内Mtgを行うこともおすすめです。
決まった日時に効果検証や分析をすることで、実行途中で上手く行かなかったり結果が表れなかったりした時に軌道修正が効くからです。日々、他の業務にも追われている状況だと思いますので、あらかじめ振り返るタイミングを設定しておくことでスケジュール管理もしやすくなるでしょう。
アクシデントへの対策
Web集客のみならず言えることですが、アクシデントへの対策も事前に想定しておくことが必要です。アクシデントとは、集客結果が出ないことではありません。自社サイトにおけるシステムエラーやサーバーダウン、情報漏洩などが挙げられます。
Webサイトが想定外のアクセス数に耐えられずダウンしてしまうことも想定しておきましょう。ハッキングによる情報漏洩が起こった際の対策フローも確認しておき、関係各社に共有しておくことで、アクシデントが起こってしまった時に冷静な対処ができるのです。
自社メディアによる戦略「オウンドメディア」
自社のWebサイトが長期的な資産の集客ツールとなる戦略のことを「オウンドメディア戦略」と言います。オウンドメディア戦略は、自社メディアによる潜在顧客への訴求です。オウンドメディアは、検索エンジンGoogleの評価基準となるコンテンツSEOを駆使した施策となります。
具体的には、オウンドメディア上で自社ビジネスを直接訴求しない形式です。たとえば自社のビジネスが「水道工事・補修サービス」の場合、水周りの修理などを訴求したくなるでしょう。オウンドメディアの運用では、「水周りの修理」についてサービスの紹介はしません。
メディアに訪問するユーザーが「どのようなコンテンツを求めているのか?」に対して、答えとなる情報を用意します。オウンドメディアは、インターネット上で調べものをするユーザーに向けた役立つコンテンツを提供する施策です。
あわせて読みたい
オウンドメディアに必要なSEO戦略
オウンドメディア戦略を実施するには、SEO流入を目的とするSEO戦略が必要となります。コンテンツを評価されて、検索結果ページの上位に表示されることを目的としたSEOには、検索エンジンの評価を受けることが大事です。
ただし検索エンジンの評価は、ユーザーに役立つ情報をコンテンツとすることが評価基準となるため、ユーザー目線でのWebサイト構築を目指すことがSEO戦略につながります。そのため、オウンドメディアによるSEO戦略は時間と労力のかかる長期的な戦略となるでしょう。
オウンドメディアによる効果
オウンドメディアによる効果は、自社のビジネスの潜在価値を求めるユーザーを結び付けることです。自社のビジネスの潜在価値に共感する見込み客がメディアに訪問する仕組みづくりとなります。仕組みができることにより、検索エンジンからの購買意欲の高い潜在層を集客可能です。オウンドメディアは、自然検索からの流入となるため、共感と信頼をもった見込み客の集客が期待できます。
競合とちがう独占市場での集客「差別化」
Web集客にオウンドメディアを活用することにより競合とちがう独占市場で集客できるでしょう。具体的には、参入企業の多い広告運用の場合、集客が見込まれた広告枠に競合が集まります。そのため、競合との資金力競争となり、市場が飽和することも考えられるでしょう。
オウンドメディアによる検索の場は、潜在層への訴求となるため、直接的なキーワードによる集客ではありません。そのため、競合が参入しない独占市場の開拓にもなるのです。結果的に独占市場での集客は、自社ビジネスと競合他社との差別化にもなります。差別化は、自社の強みとなる独占的な特徴を訴求する取り組みとなるでしょう。
強みが自社の売り「ブランディング」
競合との差別化となる自社の強みは、自社の売り部分ともいえます。自社の売り部分となる強みは、自社だけの特徴をあらわしているため、ブランディングの形成となるのです。ブランディングは、自社の特徴を認知させる効果があります。つまり、オウンドメディアの運用は、自然流入による長期的なブランディング戦略なのです。
あわせて読みたい
Web集客マーケティングの戦略立案
めぐみやでは、Web集客コンサルティングサービスを強みとしております。実際に、数々の企業におけるWebサイトの集客数をアップさせた実績のある専門家が、お客様に最適なWeb集客マーケティングをご提案いたします。
戦略の立案だけでなく、計画実行から効果検証、改善提案まで、Webサイトの運用全体をワンストップでサポート可能です。お客様の多彩なビジネスや背景の状況を踏まえ、共に集客し続けるWebサイトを構築しましょう。少しでも興味を持たれた方は、無料相談にぜひお問い合わせください。

めぐみやのWeb集客コンサルティング
Webサイトを活用して売上と利益向上を目指しませんか?
めぐみやが集客からサイト運営まで一貫してサポート致します。
まとめ
今回のWeb集客の戦略について、いかがだったでしょうか。Web集客は、やみくもに実行するのではなく戦略を立ててすることにより、次につながるデータ分析にもなります。コロナウイルスの影響により、ますます加速していくインターネット需要は今後、集客の軸となるでしょう。顧客の情報収集がインターネットを中心とする中で、Web集客における戦略は、今後ますます重要性を増すことでしょう。
インターネット需要を見越した企業がすぐにビジネス戦略の一環として、オウンドメディアの運用を取り入れたとしてもすぐに成果を出すことはできません。オウンドメディアの構築から運用まで、時間と労力がかかります。さらにWeb戦略の専門知識や経験などない場合は、試行錯誤することが考えられるでしょう。
今回の記事を参考にぜひ、専門家への相談を考えてみることが早い解決策ともなります。オウンドメディアは、構築まで時間もかかる戦略のため、早い段階からの取り組みが必要となるためです。参考になれば幸いです。
Web集客の戦略に関するよくあるご質問
最後によくあるご質問をいくつかご紹介致します。
みなさまのWeb集客にお役に立てば幸いです。
その他、ご不明な点がございましたら以下のリンクよりお気軽にご相談下さいませ。
無料オンライン相談はこちらからどうぞ。
Q
Web集客とは何ですか?
A
Web集客とは、インターネットを使用して潜在的な顧客を自社のサイトやサービスに誘導し、リードや売上を増加させるための一連の戦略や手法を指します。
Q
Web集客の基本的な戦略は何ですか?
A
Web集客の基本的な戦略には、SEO(検索エンジン最適化)、SEM(検索エンジンマーケティング)、SNSマーケティング、コンテンツマーケティング、メールマーケティングなどがあります。
Q
SEOとは何ですか?
A
SEOは、検索エンジンの自然な検索結果でのランキングを向上させるための技術や戦略を指します。これにより、サイトへの訪問者数や可視性を増加させることができます。
Q
SNSマーケティングのポイントは何ですか?
A
SNSマーケティングのポイントは、ターゲットとなるユーザー層を正確に把握し、彼らの関心やニーズに合わせたコンテンツを提供することです。また、ユーザーとのコミュニケーションを大切にし、ブランドのファンを増やすことも重要です。
Q
Web集客でのコンテンツマーケティングの重要性は?
A
コンテンツマーケティングは、価値ある情報やコンテンツを提供することで、潜在的な顧客の信頼や関心を引き付け、長期的な関係を築く戦略です。これにより、ブランドの認知度を高めるだけでなく、リードの獲得や顧客のロイヤルティも高めることができます。
Q
Web集客のためのランディングページとは?
A
ランディングページは、Web広告やメールマーケティングなどのリンクから訪問者が初めて訪れるページのことを指し、特定のアクション(購入、問い合わせなど)を取らせることを目的として設計されます。
Q
リターゲティング広告の役割は?
A
リターゲティング広告は、一度サイトを訪れたが何らかのアクションを取らなかったユーザーに再度広告を表示し、サイトへの再訪問やアクションを促す戦略です。
Q
Web集客におけるKPIとは何ですか?
A
KPI(Key Performance Indicator)は、Web集客活動の成果を測定・評価するための指標です。例えば、サイトの訪問者数、コンバージョン率、平均セッション時間などが該当します。
Q
Web集客を成功させるためのポイントは?
A
Web集客を成功させるためのポイントは、ターゲットとなるユーザーを正確に把握し、彼らのニーズや問題点を解決するコンテンツやサービスを提供することです。また、様々なチャネルや手法を組み合わせて、効果的なマーケティングを展開することが重要です。
Q
Web集客戦略を立てる際の最初のステップは?
A
Web集客戦略を立てる際の最初のステップは、ビジネスの目標やターゲットユーザー、競合他社の状況などをしっかりと分析することです。これにより、効果的な戦略や手法を選定するための基盤が築かれます。