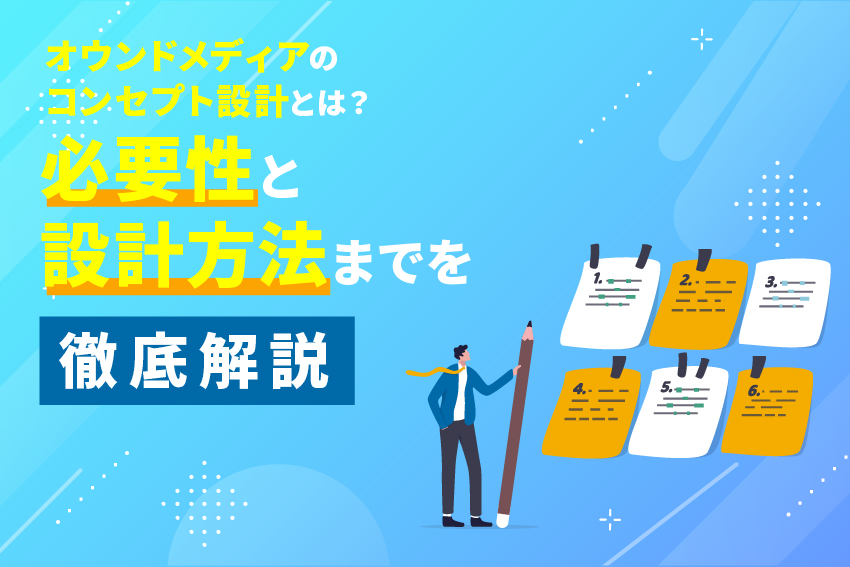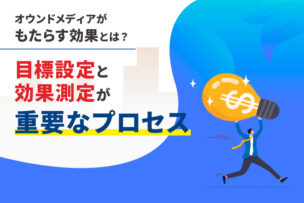記事の監修

Web集客・マーケティングの専門家として、13年間にわたり厳格な基準と緻密な戦略をもって中小企業の成功を導く。
一時的な集客の手法に頼ることなく、中長期的な効果を持続させる本質的なWeb集客の構築に注力。
『恵ある集客を。』をスローガンに掲げてクライアント様のサービスや商品の核心的な魅力を、的確にターゲットに伝えることを重視したWebサイト運用をサポート。
最近のWebマーケティングでは、「コンテンツが大事」「企業はオウンドメディアを持つべき」という風潮が見られます。ですが、単純に「オウンドメディアを運営しよう」としても、コンセプトがなければ、メディア運用も長続きはしないでしょう。
では、オウンドメディアにコンセプトが大事なのはなぜなのか?
この記事では、オウンドメディアのコンセプトについて、提供側の企業の立場から「どのように考えて、設定してビジネスに繋げていけば良いのか?」徹底的に解説してきます。オウンドメディア構築を模索しているWeb担当者様に役立てられるコンセプト作りの参考になれば幸いです。
- オウンドメディアのコンセプトについて知りたい方
- オウンドメディアの具体的なコンセプト設計方法について知りたい方
- オウンドメディアのコンセプト事例について知りたい方
目次
オウンドメディアのコンセプトとは
オウンドメディアのコンセプトとは具体的には何になるでしょうか?
それは、オウンドメディアに訪れるユーザーとオウンドメディアを運営する企業の役割をつなぎ合わせるテーマになるフレーズのことを指します。
違う言い方をすると、企業のコーポレートサイトや販売サイトでは伝えられない商品やサービスを取り巻く課題と、その課題に興味関心のある読者を結びつける役目を果たせるのが、オウンドメディアのコンセプトになります。
例えば、印刷通販のオウンドメディアの場合、印刷の需要や必要性を促進するためのお役立ち情報を提供しています。印刷にまつわる疑問や豆知識を調べてくるユーザー向けに「初心者でもできる印刷基礎」や「印刷で映える!覚えておきたい写真の撮り方」など役立つ記事ばかりで構成されているメディアです。
参考サイト:IRODORIC公式サイト
参考にあげたオウンドメディアのコンセプトは、「印刷を知ろう」ではないでしょうか。「印刷」にもっと関心を持ってもらいたい企業の課題と、自分でもできる「印刷ノウハウ」を知りたいユーザーを見事につなぐコンセプトを提供しているメディアになっていますね。
そもそもコンセプトとは
コンセプトは、あるものに対しての観念や概念のことをあらわします。対象となるものは広範囲にわたります。たとえば、学術的な分野や教育、ビジネス、芸術、科学、技術、社会など、さまざまな分野で使われている状況です。
コンセプトは、一般的には、抽象的なアイデアや概念、または物事の重要な要素や属性をあらわします。特徴としては、特定の主題や問題、または領域に関連するアイデアや概念を指すでしょう。コンセプトの特徴は、それら概念を一貫性のもとで掲げることです。コンセプトを示すことで、対象となるものの軸が明確となるでしょう。
あわせて読みたい
オウンドメディアにコンセプトは必要?
先程取り上げた印刷のオウンドメディアの例からも理解できるように、オウンドメディアには、コンセプトは必要なのです。
その理由は、リアル店舗のような人と人とが直接取引していくビジネスとは違って、Web上のビジネスは一方通行になりがちなため、顧客と企業を結び付ける共通テーマが必要になります。その必要なテーマこそ、オウンドメディアのコンセプトになるのです。
見ず知らずの相手同士がお互いの利益だけを求める状況ではなくて、専門家の企業としてできることとユーザーとして関われることを結び付けていく力をオウンドメディアは持っているでしょう。
必要な理由:Web集客が一方通行になるから
オウンドメディアにコンセプトが必要な理由は、Web集客の一方通行が懸念されるためです。Web集客は、対話型のコミュニケーションではありません。インターネット上で掲載されている情報に対して、必要性のある潜在層が接触します。
接点のあった潜在層は、Webコンテンツに対して反応を求めていません。そのため、一般的には一方通行のコミュニケーションとなるでしょう。それだけに、訪問ユーザーの興味関心を高める情報やレイアウトなどが重要になります。
必要な理由:企業と顧客の接点を明確にするため
オウンドメディアは、企業のビジネスに関連性の高いキーワードなどでビジネスニーズに近い顧客をつなぐ役目を果たします。そのため、企業と顧客の接点となる情報を盛り込むことが大事です。店舗型営業では、その地域に訪れた人を外観から誘導する方法となるでしょう。Web集客の場合は、検索エンジンからの流入やSNS、ポータルサイトなどからの接点が期待できます。
企業の現状と課題を解決できるコンセプトへ
では、オウンドメディアのコンセプトを決める前に、企業の現状と課題を解決する答えをどのように見つけていけばよいのでしょうか?
企業の現状の課題は、外部に解決策を求める前に一度、内部を見直してみることが解決のカギになることでしょう。
何故ならば、ユーザー以上に企業の社内スタッフは、商品やサービスの専門家だからです。専門家として、商品やサービスに対しての経験や知識は豊富なのは当然のこと。ならば、社内スタッフが自社の現状を客観的に明確化していくことから始めましょう。
ここで、オウンドメディアのコンセプトになる企業の課題の掘り出し方のヒントを紹介します。社内会議では、見えてこない企業の持つべきコンセプトを掘り出していくためには、企業の置かれている事実を明確にしていくことが先決です。
ここで注意してほしい点は、企業の課題を先に取り上げないことです。企業の課題が先に出てしまうと解決策を求めて右往左往して、一向にコンセプトが見えてこないままになります。
企業の課題を出す前に、現在の事実を明確にしていくことから始めましょう。順序としては、「事実」を取り上げて、「課題」とすり合わせてみること。その結果、見えてくる「結論」こそが、コンセプトの基になる企業側の課題になります。
例えば、企業の「事実」が、「家族連れのリピータ―ばかりで20代~30代の独身客が来ないピザ屋」という統計データから、「課題」は、「家族連れに喜ばれる点を理解して、家族連れに向けた更なるサービスの向上」という方向性が見えてくるなどです。事実になるデータを無視して「20代~30代の独身客をもっと増やす」と決めてしまうと、自社の商品やサービスの特徴までを無視した「課題」を追うことになります。
この捉え方の違いが、企業とユーザーの間の溝を作る原因になるのです。
コンセプトの考え方
オウンドメディアのコンセプトの考え方は、事実とすり合わせた企業の課題と読者になるユーザーの求める情報を結びつけるテーマを決めがポイントになります。
例えば、「企業の課題」が「家族連れが何度もリピートしたくなるピザ屋」とユーザーの求める情報「小さい子供も安心して食べられて、子連れで満足できる飲食店はあるだろうか?」をつなぎ合わせるテーマが、オウンドメディアのコンセプトになります。
この場合、「各テーブルが仕切られていて、家族連れに嬉しい豊富なキッズメニューと食べ放題のお店の選び方」という情報サイトではいかがでしょうか。家族連れにとって安心して食事を楽しめることを訴求できるテーマが、好感度をアップして情報収集意欲をかき立てることになるでしょう。
このようにコンセプトの考え方は、「企業の課題」と「ユーザーの情報収集行動」をつなぎ合わせる中立的なテーマを選ぶことが理想になります。
企業と顧客をつなぐ中立的な立場で考える
オウンドメディアのコンセプトは、企業と顧客をつなぐ中立的な立場で考えることが大切です。企業が主観的な考え方でコンセプトを決めてしまうと、顧客側からすれば「商品の売り込み」とみなされます。逆に、顧客の課題に焦点を当て顧客目線の情報を取りあつかえば客観的な内容で訴求できます。
このように、オウンドメディアは自社の媒体だとしても客観的な視点で運用することが大事です。それには、あつかう情報に対して中立的であることを念頭におきましょう。
企業の課題とのすり合わせ
オウンドメディアは、顧客の求める課題解決と企業の課題解決とのすり合わせになるでしょう。たとえば、当然のことながら企業の課題は売上拡大です。オウンドメディアの運用も売上を伸ばすための施策になります。前述した顧客目線での客観的な情報を提供できれば、顧客の求める課題解決にも役立ちます。
顧客の情報収集とのすり合わせ
オウンドメディアのコンセプトは、企業と顧客をつなぐ概念です。課題を通じてすり合わせられればコミュニケーションの場としても活用できます。顧客は、メディアに対して好意的な印象を持っているため、自ら情報収集の場として活用します。その情報の中に、中立的な立場で自社ビジネスを訴求することが必要です。
あわせて読みたい
オウンドメディアの具体的なコンセプト設計方法
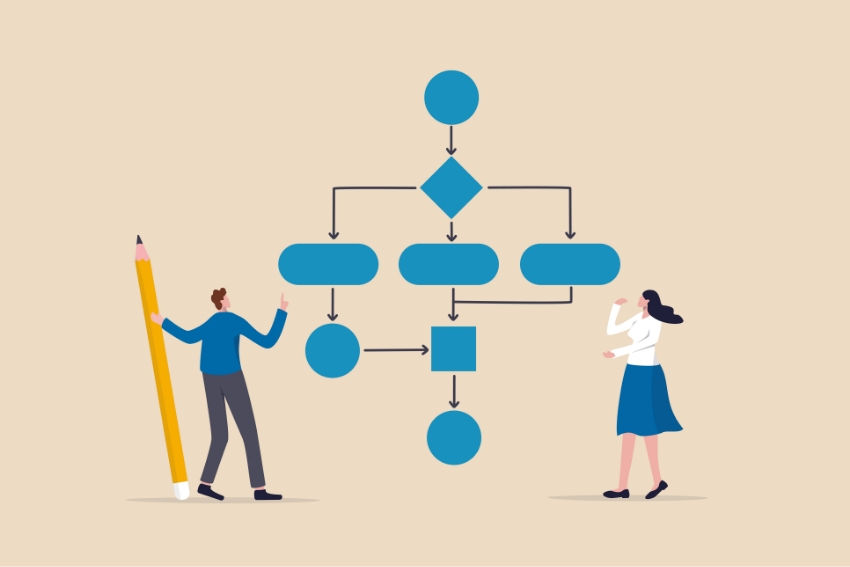
オウンドメディアのコンセプトを具体的に設計するためには、次の手順で進めていきます。
- 自社の強みやウリを再確認
- コンセプトの明確化
- コンセプトに沿ったペルソナの設定
- カスタマージャーニーの設計
- メディアの出口になるマネタイズの設定
では、順を追ってみていきましょう。
自社の強みや売りを再確認
自社の強みや売りを再確認することは、独自性の発見になります。そのためには、自社の商品やサービスと競合他社の類似商品との違いを客観的に比較する必要があるのです。
ここで誤解をしてほしくないのが、自社の商品やサービスを過大評価することではなく、事実を具体的に取り上げていくことです。つまり、自社の商品やサービスの強みが確認できることで、売りの部分が、大きな特徴になりアピールポイントとなります。さらに、独自性のある強みの部分をコンセプトに繋げていくことが重要なのです。
自社商品と他社商品を客観的に比較する
オウンドメディアでは、中立的な立場で事実を掲載しなければなりません。一般的に企業は自社の都合の良い方向へ向かいがちです。オウンドメディアは読者目線の媒体です。読者目線でコンテンツを作らなければ共感を得られません。
たとえば、商品やサービスを紹介する比較検討のコンテンツを作る際は、あえて自社商品と他社商品を客観的に比較する必要があります。オウンドメディアは、中立的な立場で提供するからこそ、共感を得られます。
自社の強みを明確にする
自社商品と他社商品を客観的に比較した際、不利になる部分も明確にすることも大事です。自社の不利になる部分をあえて明確にすることは、読者の信頼を高める要素にもなります。ただしそれには、自社の強みが明確になっていることが先決です。自社の強みが明確になっていれば、他の部分で他社が勝っていても問題ありません。強み部分に適した顧客に訴求しましょう。
自社の売りをブランディング活用する
自社の強みは、自社の売りとなります。自社の売りは、競合他社が真似のできない特徴として差別化できる部分です。差別化は、自社独自のブランドの形成にもなるブランディング効果を期待できます。そのため、ブランディング効果に向けて差別化できる強み部分を確立させましょう。
コンセプトの明確化
事実に沿った企業の課題を明確に設定できていれば、自社の強みとコンセプトを合わせていくことができるでしょう。
コンセプトの明確化では、自社の売りの部分を強調したテーマにしていくことが、オウンドメディアの中で最終的に選ばれる流れを構築できるようになるでしょう。自社の強みが見えてくれば、明確になったコンセプトを軸にしたオウンドメディアの設計に取り掛かります。常に手順を進めていく中で明確にしたコンセプトからブレないようにテーマを掲げておくことが重要です。
自社のテーマを確立
コンセプトを明確にする際は、自社の売りを強調したテーマの確立が必要になります。コンセプトのあるべき姿は、一貫していることです。企業のコンセプトが都度変更しているようだと、顧客への認知が期待できません。そのため、コンセプトは途中で変更する必要のない一貫したテーマであることが大事です。
テーマが決まれば設計に取りかかれる
オウンドメディアは、コンセプトのもとテーマを決める必要があります。その理由は、テーマが決まらなければ、設計にも取り掛かれないからです。会社の経営と同じで、会社設立には企業理念を用意しなければなりません。企業理念のもと同調した人材が集まったり、取引先とやり取りしたりできるでしょう。オウンドメディアの運用においてもコンセプトが先です。そのうえで設計を始められます。
一貫性と継続性を重視して取り組む
コンセプトをもとに、オウンドメディアの設計が始まれば、あとは一貫性と継続性を重視するだけです。立ち上げたばかりは、メディアの方向性に迷いが生じることもあります。成果のない状態であればなおさら方向性に対して不安を感じるかもしれません。それでも一貫性と継続性は重視する必要があります。その理由は、絞り込んだテーマの専門性を引きだすには、一貫した継続が求められるからです。
ペルソナの設定
次にオウンドメディアの読者になってくれるターゲットユーザーを具体的に明確にしていきます。先程から例にあげている「家族連れ」だけではターゲットはぼやけてしまうでしょう。よりコンセプトに当てはまるターゲットユーザーに向けたコンテンツを提供するには、ぺルソナを設定する必要があります。
ペルソナの設定とは、ターゲットユーザーをより具体化した仮想モデルの人の設定のことです。ペルソナの設定により、「コンセプトに強く共感を持ってくれるユーザーがどんな人なのか?」明確に想像することができるようになります。
ただし、オウンドメディアのペルソナの場合は、1つのペルソナに固執しないことも必要です。設定されたペルソナは、具体的すぎて一部の対象ユーザーだけに偏ってしまう恐れがあります。例えば、オウンドメディアで共感してくれるユーザーが「家族連れ」の場合、「3人家族」「5人家族」「3世代家族」なども統計データとしてあれば、全て「事実」になるからです。
事実を無視して、1つのペルソナだけでコンセプトを設定してしまうことも、長期間の運用を目的とするオウンドメディアには向きません。必要なのは、企業の事実とすり合わせた課題から設定されるペルソナを最低パターン用意しておくことです。そして、設定されたペルソナごとにカテゴリ分けやコンテンツを振り分けることでユーザーの見やすさも向上してくるでしょう。
具体的なペルソナ設定手順
ここでは、具体的なペルソナ設定手順を解説します。先ほどの「家族連れが何度もリピートしたくなるピザ屋」の例から家族構成によって変わるペルソナの設定を紹介します。
●3人家族の場合
例にあげたオウンドメディアのテーマが、「各テーブルが仕切られていて、家族連れに嬉しい豊富なキッズメニューと食べ放題のお店の選び方」という客観的な視点です。そのコンテンツのひとつとして3人家族の場合のペルソナは、通常の4人掛けテーブルでも対応できます。もしここで幼児と若い世代の夫婦の3人家族を設定した場合は、父親のイメージや母親のイメージなども具体的であると説得力が増してきます。
- 父親:父親としての自覚に欠けて母親の大変さへの配慮が少ない
- 母親:外食の度に子供の世話と店への気遣いで気が落ち着かない
- 幼児:マイペースで泣き叫んだり動き回ったりして目が離せない
このような3人家族の母親は、夫の協力が足りなくてストレスを抱えるかもしれません。つまり課題は、両親と子供がストレスを感じないで楽しめる外食にあります。
●5人家族の場合
5人家族の場合は、次のようなペルソナが設定できます。
- 父親:妻と交替で子守りをしながら外食を楽しむ
- 母親:夫の協力に期待しつつも不安をかかえながら外食を楽しむ
- 小学生の長男:ピザが好きで妹や弟のことなど上の空
- 5歳の長女:3歳の弟と張り合うことしか考えていない
- 3歳の次男:5歳の姉に負けたくないと考えている
このような5人家族では、6人掛けテーブルで席の位置やピザが提供される順番だけでも兄弟げんかが始まるかもしれません。
●3世代家族の場合
3世代家族の場合は、次のようなペルソナを設定します。
- 祖父:とくにピザが好きなわけでもないが家族で食卓を囲みたい
- 祖母:日頃顔を見せない孫たちとの時間を大切にしたい
- 父親:祖父と祖母に孫を会わせて安心している
- 母親:義父と義母に気を遣っている
- 小学生の長男:ピザが好きで妹や弟のことなど上の空
- 5歳の長女:3歳の弟と張り合うことしか考えていない
- 3歳の次男:5歳の姉に負けたくないと考えている
それぞれに思いは異なりますが、7名の外食をどのように楽しむかが店の手腕ではないでしょうか。
複数のペルソナ設定の共通点を整理
複数のペルソナ設定の共通点は、それぞれの考えていることが異なっているということです。とくに小さな子供のいる家族連れは、外食をするのも至難の業と考えられます。「子どもが店に迷惑をかけないか」や「子どもの面倒で味を楽しめない」などの不安もあることでしょう。
ペルソナ設定から見えてくるポイントは、「家族連れでも親も子供も楽しめる工夫」を盛り込むことです。このように、具体的なペルソナを設定することで、サービス提供側の工夫する部分も明確になってきます。
軸になる訴求ポイントを絞る
ペルソナの例から、軸になる訴求ポイントを絞り込みます。訴求ポイントは、「家族連れ全員が楽しめる工夫」です。たとえば、他の席の客と完全に区切れる仕切りだけではなく、幼児がこぼしたり落としたりしない工夫や充実したキッズメニューなどが考えられます。このような施策は、具体的なペルソナの設定がなければ始まりません。
カスタマージャーニーの設計
続いて、ペルソナで設定した仮想顧客が、「どのように行動していけば自社の商品やサービスを購入してくれるのか?」という行動フローを可視化していきます。この行動フローを設計することが、カスタマージャーニーの設計です。
ここでも設定したコンセプトから外れないことが重要になり、コンセプトに沿ってどのように行動フローを設計していくかがポイントになります。カスタマージャーニーの設計は、4つの時間軸という段階にそれぞれの要素を当てはめていきます。
4つの時間軸
- 認知
- 情報入手
- 比較検討
- 購買行動
時間軸になる4つの段階に当てはめる行動は、次の要素です。
- 設定したペルソナの状況
- 設定したペルソナの心理状態
- 設定したペルソナが必要とする情報
- 設定したペルソナの予測される行動パターン
4つの時間軸と4つの行動要素を明確に設計することで、設定されたペルソナが更に実在する人のようにオウンドメディアの中でシナリオを作り上げていくことになります。
●認知段階のペルソナの行動
認知段階のペルソナは、その商品が自分のニーズに合っているかどうかを確認します。この段階で、ひとつでも興味関心をひくポイントがあると、印象に残ることになります。
●情報入手段階のペルソナの行動
興味関心を持ち始めたことで、ペルソナは情報入手の段階へと変容します。情報入手の段階では、その商品と類似商品はあるか、その商品を利用した人がいるかなどです。情報入手段階のペルソナは、「その商品を利用すべきかどうか」の検討段階にもなっています。
●比較検討段階のペルソナの行動
比較検討段階のペルソナは、商品に対して類似品や競合品などを比較します。比較検討段階のペルソナは、検討対象の中から選ぶ確率が高くなるでしょう。
●購買行動段階のペルソナの行動
比較検討の段階で自分に適していると判断できた場合は、購買行動目前の状態です。ここまでくると、あと一押しで購買成立となります。
メディアの出口になるマネタイズ
カスタマージャーニーの設計により、メディアのシナリオが明確になっていたら、最後の出口となる「マネタイズ」を設定しましょう。マネタイズが設定できていなければ、ボランティア的なWebサイトになります。あくまでも企業の戦略として作成するオウンドメディアも収益化ができなければ、ビジネスとして成り立ちません。
オウンドメディアの収益化として、一般的なマネタイズ施策を上げてみましょう。
オウンドメディアのコンセプトによってもマネタイズ施策は違ってきます。ポイントになるのが、「いかに気持ちよく行動してもらえるか」です。
圧倒的に情報の質や量の乏しいオウンドメディアでは、マネタイズに至るまでユーザーがコンテンツに満足しない可能性もあります。そのため、マネタイズの設定の時点でも「ここで販売へ誘導したらコンセプトから外れないか?」と考えながら、ゴールを決めていくことが重要なのです。
マネタイズ対象で異なる訴求コンテンツ
マネタイズを顧客自ら行動してもらうためには、自然の流れで誘導することが大事です。自然の流れで誘導するには、マネタイズを対象ごとに変更する必要があります。たとえば、次のとおりです。
- 広告:コンテンツのターゲットに適したランディングページへの誘導
- デジタルコンテンツの販売:検討中の見込み客に適した活用方法などの情報
- 有料イベントの紹介:リードナーチャリング目的となる参加者限定のオンライン展示会などの招待
- 商品やサービスの販売:ニーズが合えば販売のオファーを送ることも可能
マネタイズは、対象ごとの顧客心理に合わせた訴求が求められます。
あわせて読みたい
正しいコンセプト設計で効果的な運用を実現
オウンドメディアは企業や個人が直接コントロールできるメディアです。しかし、ただ運用しているだけでは、その有用性は半減してしまう可能性があります。重要なのは先述した通り「正しいコンセプト設計」です。
コンセプトは大綱
オウンドメディアのコンセプトは、一言で言えばその「大綱」です。何を伝えたいのか、どのような価値を提供するのかを明確にしましょう。明確なコンセプトがあることで、内容の一貫性とブランドメッセージが強化されます。
ターゲット層を明確に
効果的な運用を目指すには、ターゲットとする層を明確に設定することが不可欠です。そうすることで、適切な内容やキーワード、スタイルに集中できます。
品質と量、両方を考慮
コンテンツの品質は非常に重要ですが、一定の量も必要です。これはSEO対策やユーザーエンゲージメントにも直結します。しかし、量を追求するあまり品質が低下しては元も子もありません。
継続的な改善と分析
効果的なオウンドメディア運用には、継続的な改善と分析が不可欠です。運用開始後、データを収集して分析することで、何がうまく行っているのか、何が改善されるべきなのかを明らかにできます。
重ねてになりますが、オウンドメディアの効果的な運用は「正しいコンセプト設計」から始まります。これにより、ブランドイメージの向上、高いユーザーエンゲージメント、そして最終的にはビジネス成果につながるでしょう。
オウンドメディアのコンセプト事例
最後にオウンドメディアのコンセプトの事例を見ていきましょう。
コンセプト設計で読者ユーザー層に合った情報で成功した事例
「名刺管理Hacks」をメディア運営しているSansan株式会社では、「AI名刺管理」を掲げて法人向けのクラウド名刺管理サービスを提供しています。
自社Webサイトでは、クラウド名刺管理サービスの販売促進ですが、オウンドメディアの「名刺管理Hacks」では、「名刺」にまつわる情報が豊富に掲載されているのです。
オウンドメディアのコンセプトに当てはめてみると、企業の課題は、「クラウド名刺管理サービスの申し込みユーザーの獲得」になります。対象となる読者ユーザーは、「名刺の管理に興味がある」レベルの管理サービスやソフトについて未知の状態の人が多いのです。
そこで「名刺管理Hacks」で打ち出しているコンセプトは、自社の商品でだけではなく「名刺管理について役立つ情報」になります。コンセプトがユーザーに向いているため、競合他社の「名刺管理ソフト」などサービスも比較したコンテンツも掲載しているのです。まさに自社の都合を度外視した「名刺管理に関連する情報」の中立的なメディアの役割を果たしていることがコンセプトから外れていない点になります。
コンセプト設計でリード獲得した事例
コンセプト設計で見込み客の獲得に成功した事例として株式会社スマートキャンプのボクシルマガジンがあげられます。ボクシルマガジンの成功要因は、戦略を立ててオウンドメディアの設計に着手した点です。それにより、対象読者に沿ったコンテンツの提供を実現しています。
成果は、Webサイトに訪問したユニークユーザーの増加です。ユニークユーザー30万の実績を生み出し、公開中の150記事の中から30記事が検索1位となっています。ボクシルマガジンのコンセプトは、SaaS製品に興味関心を持つ企業のステークホルダーを対象にして、ツール活用の知識や特徴を客観的な視点で配信しているところです。
コンセプト設計でブランディングに成功した事例
コンセプト設計でブランディングに成功した事例では、サイボウズ株式会社のサイボウズ式があげられます。サイボウズ式は、ビジネス関連の情報入手に積極的なビジネスパーソンを対象にしたWebマガジンです。サイボウズ式の強みは、外部の力ではなく自社の企画力やインタビューコンテンツなどを生かしていることではないでしょうか。
とくに会社組織で課題となる働き方やビジネスマンとしての行動に対して、タイムリーなコンテンツを提供しています。その姿勢が読者の共感を得てブランディングの形成へとつながっている状況です。また、中立的な立場を維持している点もコンセプトとして評価を受けている点です。自社製品を優先的に紹介せず、あくまでもユーザー目線に立った情報提供に徹している点が一貫しています。
まとめ
オウンドメディアのコンセプト作りは、自社の経営事情を先に考えるのではなくて、企業の持つ課題とユーザーの求める情報をつなぐ役割があることに気づいてもらえたかと思います。
オウンドメディアは、ペルソナの設定などコンセプトがユーザー視点を重要視しているので、長期的な構築と運営を必要とします。それだけに企業のWeb担当者様にとって、オウンドメディアのコンセプトは長期目線での取り組みと継続が大きなポイントにした視点で考えることが大切です。
- オウンドメディアのコンセプトは企業とユーザーを結びつけるテーマ
- コンセプトは顧客と企業を結び付ける共通テーマが必要
- コンセプト設計には企業の現状と課題の理解が重要
あわせて読みたい
オウンドメディアのコンセプトに関するよくあるご質問
最後によくあるご質問をいくつかご紹介致します。
みなさまのWeb集客にお役に立てば幸いです。
その他、ご不明な点がございましたら以下のリンクよりお気軽にご相談下さいませ。
無料オンライン相談はこちらからどうぞ。
Q
オウンドメディアとは何ですか?
A
オウンドメディアは、企業や組織が自ら所有・運営するメディアを指します。情報の発信源となり、直接顧客や利用者とのコミュニケーションをとる手段として使用されます。
Q
オウンドメディアの目的は何ですか?
A
オウンドメディアの主な目的は、ブランドの認知度向上、信頼の構築、顧客との関係性の深化、そして長期的なビジネスの成長を実現することです。
Q
コンセプトがしっかりしていると、オウンドメディアのどんな利点があるの?
A
コンセプトが明確であると、情報発信の方向性がはっきりし、一貫性が保たれるため、読者や訪問者の信頼を得やすくなります。また、編集方針やコンテンツ作成がスムーズに行える利点もあります。
Q
オウンドメディアのコンセプトとブランディングとの関係は?
A
オウンドメディアのコンセプトはブランディングと密接に関連しています。コンセプトを通じて、ブランドの価値やメッセージを伝えることで、消費者との絆を強化することが可能となります。
Q
オウンドメディアを成功させるためのポイントは?
A
オウンドメディアを成功させるためのポイントは、一貫性のあるコンセプトのもとでの情報発信、ターゲット層のニーズに応えるコンテンツの提供、そして定期的な更新や改善を続けることです。
Q
オウンドメディアのコンセプト設定の失敗例は?
A
コンセプト設定の失敗例としては、ターゲット層のニーズを無視した内容、ブランドの特徴や価値が伝わらない情報、一貫性のない情報発信などが挙げられます。
Q
コンセプトの変更や見直しは必要ですか?
A
はい、市場やターゲット層の変化、ブランドの方向性の変更などに応じて、コンセプトの見直しや変更を行うことは必要です。
Q
オウンドメディアの運営で最も大切なことは何ですか?
A
オウンドメディアの運営で最も大切なことは、コンセプトを元にしたターゲット層のニーズに応える価値あるコンテンツを提供し、継続的に情報発信を行うことです。