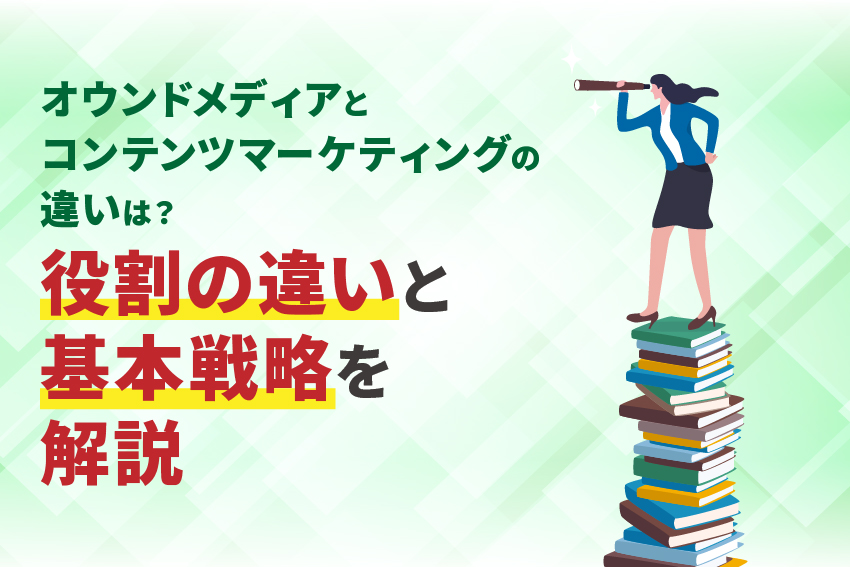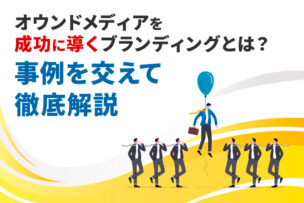記事の監修

Web集客・マーケティングの専門家として、13年間にわたり厳格な基準と緻密な戦略をもって中小企業の成功を導く。
一時的な集客の手法に頼ることなく、中長期的な効果を持続させる本質的なWeb集客の構築に注力。
『恵ある集客を。』をスローガンに掲げてクライアント様のサービスや商品の核心的な魅力を、的確にターゲットに伝えることを重視したWebサイト運用をサポート。
現在、オウンドメディアは企業マーケティングとして有用なマーケティング方法の1つに数えられています。これから立ち上げることを検討している方にコンテンツマーケティングの特徴や基本的な戦略などについて解説します。
※「オウンドメディア」は出版文化社の登録商標です。
- オウンドメディアとコンテンツマーケティングの違いついて知りたい方
- オウンドメディアの役割とメリットについて知りたい方
- オウンドメディア事例を知りたい方
目次
オウンドメディアとコンテンツマーケティングの違い
オウンドメディアを説明するときに、用語としてコンテンツマーケティングが登場することは珍しくありません。オウンドメディアはコンテンツマーケティングと何が違うのかなどを詳しく説明します。
オウンドメディアとは?
オウンドメディア(Owned Media)は、自社の持つメディア、もしくは個人で所有しているメディア(=情報媒体)です。最近のオウンドメディアの役割は、専門性に特化したコンテンツを提供することで、ファンを獲得するためのメディアとして位置づけています。
トリプルメディアに分類される
現在の企業マーケティングにおいて、オウンドメディアは、ペイドメディア(Paid Media)、アーンドメディア(Earned Media)に並んでトリプルメディアの1つとして数えられています。
ペイドメディア
以前は、メディアの宣伝といえば、ペイドメディアが該当していました。新聞やテレビ、雑誌などのマスメディアに広告を掲載。いわゆるスポンサーとして出資します。広告費がかかる点や潜在顧客との意思疎通が出来ないことが難点です。
アーンドメディア
情報発信をSNSなどでする方法です。自社で所持できないメディアであることが多く、意見や批判をコントロールできないことが難点です。
オウンドメディア(今回取り上げているメディア)
自社メディアを使って宣伝や集客、専門性の高い情報を提供しながら見込み客獲得を目指す方法です。費用がかからない分、メディアを育てるための下地や独自性の高いオリジナルコンテンツの提供が必要です。
コンテンツマーケティングとの違い
オウンドメディアは、マーケティングをする意味では、コンテンツマーケティングの種類にカテゴライズされます。
企業マーケティングで使われる一般的なコンテンツマーケティングという言葉は、メディアを限定しないため、自社メディアに限らずさまざまなメディアを通してコンテンツ・情報の提供が行われます。そのため、利用するメディアによっては費用がかさみ、コストパフォーマンスが落ちるケースも散見されます。しかし、オウンドメディアでコンテンツ提供する場合、広告費やプラットフォームの費用をほとんどかけずにコンテンツの提供と集客が出来ます。
また、自社のメディアに限る手法であるため、情報拡散や炎上などの制御が効かないメディアを避けられるというメリットがあります。
オウンドメディアはコンテンツマーケティングの一部であり、戦略としての1選択肢です。アーンドメディアも手法は違いますが、コンテンツマーケティングの1つです。したがって、これからオウンドメディアを立ち上げるのであれば、コンテンツマーケティングを周到しつつもオウンドメディアに必要な要素を理解する必要があるでしょう。
例えば、化粧品や美容グッズ関連の製品であれば、美容コンテンツ。新聞社であれば独自ニュースサイトのコンテンツ。IT事業者であればエンジニアや技術関連についてのコンテンツやソフトウェアの提供。食品であれば健康や食に関するコンテンツといった具合で、それぞれ関連性の強いものを専門化しています。
あわせて読みたい
オウンドメディアの役割
メディアにはメインとなる自社メディアや広告先などさまざまな目的を持つ他社メディアが存在します。中でも、オウンドメディアにしかない目的があります。それは、既存の顧客ではなく、潜在顧客(消費者)に対して積極的にアプローチしていくことです。
しかし、消費者は情報のあふれる現代社会の中で有益な情報かどうかを見極めています。興味を惹かれないような情報、ネットにあふれている程度の浅い情報では、見込み客を引き込むことは出来ません。
現在のオウンドメディアの役割とは?
オウンドメディアに求めるのは、情報や製品に対する専門家としての役割です。企業が販売している自社の製品なら、それは製品を専門に扱っていることになります。特定の情報を専門に取り扱う場合、電子メールを使ったメールマガジンや自社サイトやブログから会員制/非会員制のコンテンツとして提供します。
以上から、オウンドメディアは運営維持に人材や管理者が必要ですが、広告費はかかりません。複数のメディアに広告を出す必要はなく、専門家としての立場とメイン事業の広告としての役割を一挙に兼ねることが出来ます。
中・長期的なビジョンで実践
オウンドメディアは短期的な結果を出すのに不向きなメディスタイルです。必要なのは、中長期的なビジョンを持って、具体的な方策をめぐらせ、直接の利益には関係ないような情報も出していく。そういった、コンテンツを提供していきます。
特にオウンドメディアは自社が展開するメディアとして、効果と費用のバランス(費用対効果)、どれほど貢献したのか(貢献度)、など結果として目に見えにくい部分が多く存在しています。そのため、「継続して運営できなくはないが、効果が出ないから」と経営判断で運営を終了してしまうこともあります。立ち上げる時に短期的には結果が出ないことや効果に時間と具体的な方法が必要であることを事前に理解しておきましょう。
役割として何を構築するのか?
オウンドメディアは、これまでに専門家と広告の役割を両方持つと述べました。メイン事業を中心として、オウンドメディアの目的は企業の顔の一側面として認知してもらう。すなわち、メディアを通して悩みや問題を解消するが、営利性の伴わないメディアとして知ってもらうことです。
あわせて読みたい
オウンドメディアの4つメリット

先述の通りオウンドメディアとは、企業が自ら所有・運営するメディアのことを指します。例えば、企業のウェブサイト、ブログ、またはソーシャルメディアアカウントなどがこれに該当します。このようなオウンドメディアは、現代のビジネス環境で非常に重要な役割を果たしています。そんなオウンドメディアがなぜ今、企業にとって重要なのか?を説明します。
信頼性と権威性の構築
まず最初に、オウンドメディアを運営することで、企業は自らの信頼性と権威性を高めることができます。特に、専門的な知識や情報を共有することで、ターゲットとする顧客層からの信頼を勝ち取ることが可能になります。
コスト効率
次に、オウンドメディアは非常にコスト効率が良い手段であります。一度コンテンツを作成してしまえば、維持費は最小限で済みます。広告費用がかからずに長期的に利益を生む可能性が高いです。
ユーザーとのコミュニケーション
また、オウンドメディアは企業とユーザーとの直接的なコミュニケーションチャネルとなります。これにより、顧客のフィードバックを直接受け取ることができ、商品やサービスの質を高めるための貴重なインサイトを得られます。
SEO対策
最後に、質の高いコンテンツを提供するオウンドメディアは、SEO(検索エンジン最適化)にも貢献します。これは、より多くの人々が自発的に企業のサイトを訪れることを意味し、ビジネスの成長を持続的に支える要素となります。
以上のように、オウンドメディアには多くのメリットがあり、特に中小企業にとっても手軽に始められる効果的なマーケティング手段と言えます。
オウンドメディアの基本戦略
実際に、立ち上げから運営の段階までオウンドメディアを構築していくことで、テーマや取り扱うコンテンツは明確にしなければなりません。そこで、オウンドメディアの基本戦略について説明します。
ペルソナの設定
近頃のメディアやマーケティングの失敗事例に、ペルソナを捉えないものが含まれます。ペルソナとはある側面や情報から人物を想定することです。マーケティングでは、ペルソナを定義するところからコンテンツ提供の出発点と考えられています。
しかし、失敗した事例の中には、ペルソナを正しく設定できていないケースやそもそもペルソナの記述した情報に間違いがある、もしくは属性範囲が適切でないとものがほとんどです。
オウンドメディアのペルソナで必要なのは、購買で解消するような浅い悩みの設定ではなく、一人ひとりの悩みにエピソードと情報を必要とする人の特徴などを捉えた属性設定(年齢、職業、性別・・・etc.)です。
情報に付加価値を与える
オウンドメディアが求めているのは知恵袋やお悩み投稿サイトのような一時的な解決策の提示ではありません。1つの悩みや問題から解決したのを起点として、オウンドメディアのファンになってもらい、最終的には自社製品や情報提供側に興味を持ってもらうことなのです。
だからこそ、提供する情報は、コンテンツとして充実させるだけでなく、それを読んだり見たりすることで、1コンテンツ(1記事)に限らない、メディアにファンを集める仕組みを形成することです。
また、既存情報は捉え方によって別の価値を与えることができます。製品の販売であれば、消費者としての価格や基本情報ではなく、付加価値のある情報です。製品そのものについて知る機会や関連することを提供する情報に付加すれば、他のコンテンツと区別してファンを獲得しやすくなります。
集客にブログシステムを利用する
オウンドメディアは基本、ホームページのサイト形式で運営します。ですが、集客を考えたとき、ブログシステムを利用することは手段として有効です。ブログにはスタッフブログや芸能人の何気ない日記を記したブログが該当します。しかし、オウンドメディアでブログを利用するには、役割の違いを理解しなければなりません。
ブログをオウンドメディアの形式として選ぶには、まだ、実例が少ないためノウハウが少ないのが現状です。そこで、オウンドメディアとブログの両方を運営することで、オウンドメディアでは発信できないコンテンツを提供します。体験レポートや企業の裏側、ちょっとしたコラムや企業情報とは違うニュースなど。定着したファンがより企業を知るための補助的な役割にするのです。
外注と自社製作のどちらが良いか?
オウンドメディアは立ち上げる時点で、外注と自社製作のどちらにするか検討します。自社で製作しつつ、コンテンツを外注するというやり方で継続する企業もあれば、全て自社で行うところもあります。
どちらが良いのかは、ケースバイケースです。ただし、両者で違いが顕著になるのは費用です。圧倒的に自社製作の方が安く済みます。しかし、オウンドメディアはノウハウがなければ高い効果のあるメディアとして成長させることが難しいため、外注で初期の構築をしてもらうケースも少なくありません。
あわせて読みたい
低予算からのスタート
オウンドメディアを外注製作するための予算相場は、どこに依頼するか、ツールは導入するかの項目次第で変化します。特に、企業主体で本格的にオウンドメディアで力を入れて取り組みたいとき、初期費用の相場は100~300万円ほどになります。月々が10万円ほどの運営維持費用がかかることを考慮します。オウンドメディアを始めて立ち上げるなら、150~200万円の予算が標準です。
全てを自社で立ち上げるのであれば、サーバー代や人件費などがあればよいだけなので、実質的な費用は数万円もかかりません。この辺が、オウンドメディアの低予算で実現できる手段として注目されています。
ただし、外注しないで低予算から開始する場合にはかなりの工夫と質の高いコンテンツが必要です。デザインやサイト制作のノウハウが不足していると製作できるものが限られるため、制限の中で確実なコンテンツを提供する必要があります。したがって、オウンドメディアの全てを自社製作だけに限ると、成功させる難易度は少し高くなります。部分的にでも外注に任せて、軌道に乗せるほうが効果的なこともあることを知っておきましょう。
あわせて読みたい
日本のオウンドメディア事例
最後に、日本の企業でオウンドメディアに取り組んでいる事例の中から、分類されるメディアの特徴ごとに分けて、それぞれ紹介します。
役に立つ情報と商品販売の事例
生活、暮らし、美容、健康といったジャンルで商品販売のオウンドメディアは威力を発揮します。例えば、生活では、「キナリノ」や「北欧、暮らしの道具店」、「無印良品」がオウンドメディアを使って集客しています。
例)「無印良品」の場合、「くらしの良品研究所」がオウンドメディアで、ブログとの連携やリクエストなどを集めて、顧客とのコミュニケーションも同時にしています。
知識・学術などの情報を提供する事例
医療、薬学、法律、不動産、行政、大学、ニュースサイトなどの専門情報を提供しているオウンドメディアです。専門的な情報のQ&Aを主体としたサイトが多いでしょう。
例)ファイザー株式会社では、「がんを学ぶ」や「疼痛.jp」など症例ごとに集客するオウンドメディアを複数展開しています。
専門系のオウンドメディアは、薬事法などで表現が正しくされていることが重要です。特にクリニックの医師や薬剤師が運営する場合、専門家の監修や執筆が信頼性を上げる記事に繋がります。
独自製品の販売事例
オリジナルノートや眼鏡、ブランド酒、快眠グッズなど独自性の強いグッズを個性あるものとして販売するためのオウンドメディアです。IT関連のソフトフェア販売もこの事例に含まれます。
例)NOMOOO(ノモー)はお酒が好きな人に焦点を当てて集客しているオウンドメディアです。焼酎や日本酒などお酒だけでなく、おつまみについても情報発信しています。
動画を利用した事例
スポーツ、体操、料理、食品、インテリア、不動産物件など動画を使ったコンテンツを重視しているオウンドメディアがあります。特にスポーツやジムなど動きのあるコンテンツの方が、リアリティがあって分かりやすいため、マーケティングに動画を使っているわけです。
例)コナミメソッドでは、エクササイズや体操の動きなどを動画で紹介しています。姿勢や鉄棒などのやり方を具体的にアドバイスしながら説明している動画を提供することで、役立つコンテンツの立ち位置を獲得しています。
まとめ
今回の記事では、これからオウンドメディアを立ち上げたいと思っている方に向けた基本的な情報や特徴について紹介しました。オウンドメディアとコンテンツマーケティングが戦略的な面でカテゴリーが違う点や事例を元にどのようなコンテンツを製作すればよいのかを紹介しています。
オウンドメディアとコンテンツマーケティングに関するよくあるご質問
最後によくあるご質問をいくつかご紹介致します。
みなさまのWeb集客にお役に立てば幸いです。
その他、ご不明な点がございましたら以下のリンクよりお気軽にご相談下さいませ。
無料オンライン相談はこちらからどうぞ。
Q
オウンドメディアとは何ですか?
A
オウンドメディアは、企業や団体が自ら所有・運営するメディアのことを指します。例えば、公式ウェブサイトや公式ブログ、SNSアカウントなどが含まれます。
Q
コンテンツマーケティングとはどういうものですか?
A
コンテンツマーケティングは、購入者や利用者を対象とした有益なコンテンツを提供し、ブランドの認知度を上げたり、顧客ロイヤルティを高めるマーケティング手法です。
Q
オウンドメディアの主なメリットは?
A
オウンドメディアの主なメリットは、広告費が不要であること、ブランドのメッセージを直接伝えられること、そして長期的な顧客関係の構築が可能であることです。
Q
コンテンツマーケティングで最も重要な要素は何ですか?
A
コンテンツの質とその内容の有益性です。ターゲットとなる読者や視聴者にとって価値のある情報を提供することが重要です。
Q
オウンドメディアを効果的に活用するためのヒントは?
A
定期的に更新を行い、SEO対策を施すこと、さらにターゲット層のニーズに合わせたコンテンツを提供することが重要です。
Q
コンテンツマーケティングの主な目的は何ですか?
A
ブランドの認知度の向上、顧客の信頼の獲得、そして最終的には売上やリードの増加を目指します。
Q
オウンドメディアでのコンテンツマーケティングの成功例はありますか?
A
はい、多くの企業がオウンドメディアでのコンテンツマーケティングを成功させています。例として、Red BullのメディアハウスやCoca-Colaの「Journey」といったメディアが挙げられます。
Q
コンテンツマーケティングでの失敗例や注意点は?
A
ターゲット層のニーズを無視したコンテンツの制作や、コンテンツの質を犠牲にして量を追求することは避けるべきです。また、継続的な更新を怠ることも成功の妨げとなります。
Q
オウンドメディアの運営において必要なスキルや知識は?
A
SEOの知識、コンテンツ制作スキル、ターゲット層の理解、ウェブアナリティクスの活用能力などが必要とされます。
Q
コンテンツマーケティングのトレンドや最新の動向は?
A
ビデオコンテンツの需要が増加しており、またAIや機械学習を活用したパーソナライズされたコンテンツ提供も注目されています。
Q
オウンドメディアとコンテンツマーケティングの組み合わせの効果は?
A
企業のブランドやメッセージを一貫して伝えられることに加え、コンテンツの提供によって顧客との関係を深化させ、長期的なビジネスの成長をサポートする効果が期待できます。