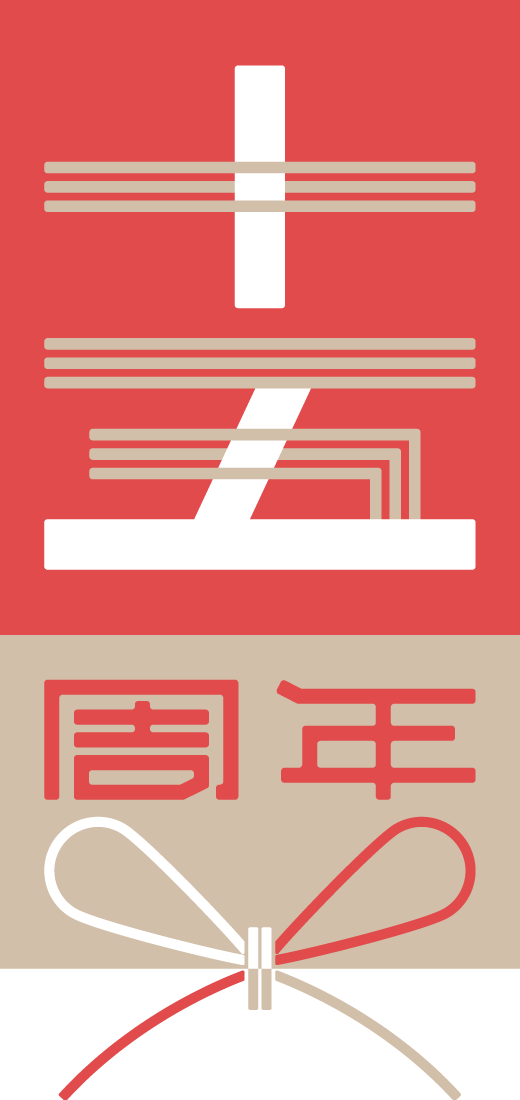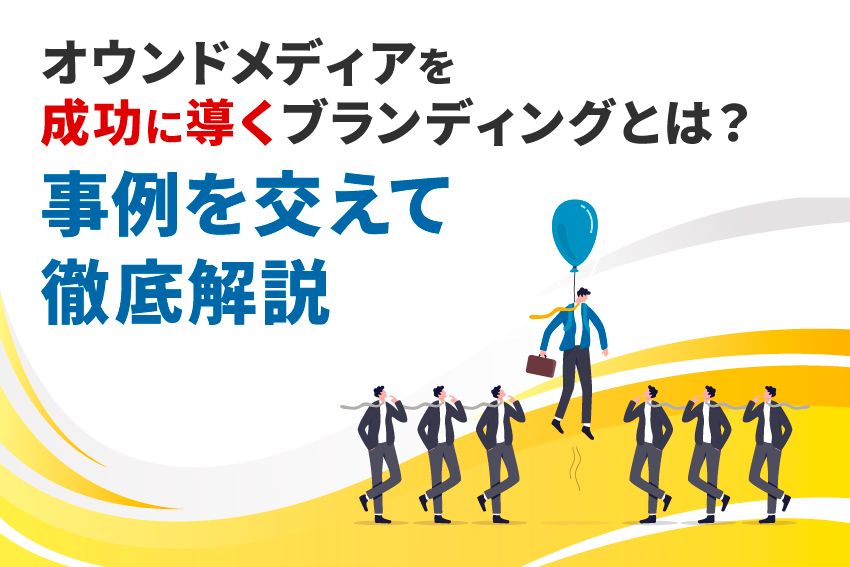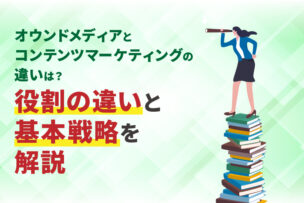記事の監修

Web集客・マーケティングの専門家として、15年間にわたり厳格な基準と緻密な戦略をもって中小企業の成功を導く。
一時的な集客の手法に頼ることなく、中長期的な効果を持続させる本質的なWeb集客の構築に注力。
『恵ある集客を。』をスローガンに掲げてクライアント様のサービスや商品の核心的な魅力を、的確にターゲットに伝えることを重視したWebサイト運用をサポート。
オウンドメディアの成功に欠かせない要素の1つとしてマーケティングの話題に上がるのがブランディングです。
ブランディングとは、企業のブランドを形成するための取り組みを指します。ブランドは、消費者にイメージしてもらうことが大事です。上手にブランディングを活用することで、PRの一環として、オウンドメディアの効果をより高めることができます。
しかし、オウンドメディアの運用は簡単なものではありません。そこで、今回の記事によりノウハウや実績のない企業が「どのようにして、自社ブランドのオウンドメディアをブランディングしてPRすればよいのか」について解説します。オウンドメディアによるメリットの1つ「ブランディングの形成」に価値を見出している企業のWeb担当者は、ブランディングの重要性について認識を深めることができるでしょう。
- オウンドメディアのブランディングの必要性について知りたい方
- オウンドメディアでブランディングするメリットを知りたい方
- オウンドメディアでブランディングに成功事例を知りたい方
目次
オウンドメディアで企業ブランディングはできるのか?
今日のデジタル時代において、企業ブランディングは以前にも増して重要な要素となっています。その中で話題になっているのが、オウンドメディアの活用です。では、オウンドメディアを使って実際に企業ブランディングは可能なのでしょうか?答えは肯定的ですが、成功への道は計画と戦略によって左右されます。
オウンドメディアとは、企業が所有するメディアであり、ウェブサイトやブログ、ソーシャルメディアアカウントなどが該当します。これらのプラットフォームで、企業は自由にコンテンツを公開でき、ターゲットとなる顧客層に直接訴えかけることができます。一方で、管理が自由であるため、失敗する企業も少なくありません。
成功するための鍵は、「質の高いコンテンツ」です。この点が欠けていると、いくら多くの記事や情報を公開しても、読者(=潜在的な顧客)にとっての価値は低くなります。質の高いコンテンツを提供することで、企業は専門性と信頼性を築き上げることができます。
さらに、一貫したメッセージとブランドイメージを維持することも重要です。これによって、顧客は企業に対して強い信頼と愛着を持つようになります。時には、オウンドメディアを用いて直接商品やサービスを販売することもありますが、基本的には長期的な信頼関係の構築が目的です。
オウンドメディアは企業ブランディングに非常に有効な手段ですが、成功へは戦略と計画が必須です。質の高いコンテンツを一貫して提供し、目的に合わせて最適なメディアを選ぶことが、成功への近道と言えるでしょう。
オウンドメディアにおけるブランディングの役割とは?
オウンドメディアを運営する上で重要とされているのがブランディングです。オウンドメディアにとってブランディングをすることにはどのような意味があるのでしょうか?そこで、オウンドメディアがブランディングを通して果たす役割について各々説明します。
他企業と差別化
ブランドは主に、ロゴやデザイン、代表的な製品やサービスから商品や企業の名前が分かるのが特徴です。そして、ブランディングはWebマーケティングに限ったものではありません。
例えば、スポーツ用のシューズでいえば、アディダスやアシックスなどがよく知られています。バッグならルイヴィトンやエルメス、紙おむつならムーニーマンやパンパース、飲料ならアサヒやコカ・コーラ社など。どれも大勢の人々が知る有名ブランドです。すでにテレビ広告や現実の広告媒体で宣伝されているため、高い認知度とブランド化がされています。同業種の競合は多いですが、その会社にしかない魅力にファンが付いています。
Web上のオウンドメディアもブランディングをすることで、商品の特徴やサービス、名前が認知されるようになります。これにより、自社だけの立ち位置を明確化することができます。Web時代に突入した現在、コンテンツマーケティングをWebサイトやブログにまで拡大させていないならば試す価値はあります。
オウンドメディアでブランディングをすることによって、インターネット上にしかいない見込み客の層を引き込める可能性が高まります。実店舗でしか成果を出してこなかった中小企業や零細企業、ニッチの客層しかいない個性が強すぎる業種の企業店舗にとって費用対効果の高い戦略です。
あわせて読みたい
ファンの獲得
ブランドを周知することで得られるメリットは、ファンを獲得できることです。ブランディングとファン獲得は、オウンドメディア運営をする目的でもあります。ファンに自社製品の購入やサービスを受けてもらい、収益を得ることが戦略上のポイントです。
アメリカから始まったコンテンツマーケティングの世界では、ファン(見込み客)の獲得が重要視されていて、そこからいかに利益に繋げられるかを多くの企業が目指しています。オウンドメディアはアメリカではすでに企業の多くに浸透している手法です。
成功例のあるオウンドメディアはブランディングをしなければ、現在の立ち位置が存在していなかったといえるほどです。ブランドとして価値を見出したことが市場で大きな役目を果たしています。
あわせて読みたい
市場の価格競争を避ける
オウンドメディアは、利益を得ることに偏向しないメディアとよくいわれます。集客するのはあくまでも潜在的な見込み客で、何かを買いたいと求める顧客を直接は集客しません。
製品をそのまま売り込むには、品質や価格勝負になりがちです。負ければ需要は落ち込み、価格競争に負けたことになります。競争に負けた企業がどうなるかは、それこそ言うまでもないでしょう。
しかし、オウンドメディアが育てたコンテンツから付いたファンにとって、製品は価格だけでは考えない「ブランド」としての認識が広まっているため、価格競争に巻き込まれることなく、一定の収益を上げ将来の見込み客として定着します。
この段階まで来れば、類似サービスや同業者に対して価格差だけに縛られた運営が必要ありません。そのブランドに対するファンが生まれて気に入ったものを高く評価し、新たなファンを呼び込むというサイクルが出来るため必要なくなるわけです。
あわせて読みたい
セールスプロモーションのコストカット
オウンドメディアは自社所有のメディアとして、見込み客を集めた後も運営していくことが可能です。コンテンツが話題になれば自然に顧客が増える集客の流れが構築できます。また、独自の自社ブランドとして集客できるようになれば、オウンドメディアの運営がセールスプロモーションの役割も果たすようになります。したがって、プロモーションによる販売促進やサービス紹介にかかる広告費のコストカットが可能です。

めぐみやのWeb集客コンサルティング
Webサイトを活用して売上と利益向上を目指しませんか?
めぐみやが集客からサイト運営まで一貫してサポート致します。
オウンドメディアでブランディングするメリット
オウンドメディアでブランディングするメリットについて詳しく解説しましょう。企業がオウンドメディアを運営することにより、5つのメリットを得られます。
資産となる自社メディアを持てる
企業がオウンドメディアでブランディングした場合、ブランディングされたWebサイトは企業の資産となるでしょう。本来ならば、テレビCMや新聞、雑誌などの広告枠を活用したターゲットが絞れていないブランディングでした。しかし、オウンドメディアによるブランディングは、自社の購買層となる見込み客に向けたターゲットが絞れています。そのため、好感を持った認知を向上させることになるでしょう。
自社メディアは、長期的な集客サイトとしてWeb上で独自の市場で集客を続けます。このような集客資産となる自社メディアを持てることが大きなメリットとなるのです。
検索ユーザーに向けた広範囲へのリーチ
オウンドメディアによるブランディングは、広範囲の検索ユーザーに向けたリーチを実現します。検索ユーザーは、ニッチなキーワードであってもインターネット検索するすべてのユーザーを対象に、そのキーワードの検索者に対して訴求が可能です。対象がすべてのユーザーとなるため、広範囲なリーチを可能とできる点がメリットになります。
顧客との関係を保持できるコミュニティの作成
オウンドメディアによりブランディングすると、メディア読者との関係性を濃くすることが可能です。関係性を深める要因は、オウンドメディアで築いてきた「信頼」と「共感」になります。オウンドメディアにより、メディア読者と「信頼」や「共感」をもつ関係性が築ければ、コミュニティとしての役割もはたすでしょう。
顧客との関係を保持できるコミュニティの作成は、既存顧客の掘り起こしや継続したリピーターを増やすことにつながります。オウンドメディアによるブランディングは、顧客との関係性も高めることが期待できるのです。
見込み客の信頼と共感を得る
顧客とのコミュニティの形成には、信頼と共感を得ることが大事な点について、紹介しました。オウンドメディアは、ブランディングにより他社と差別化された独自の市場で見込み客を獲得できます。独自の市場では、自社の強み部分の訴求により、見込み客に信頼と共感を与えることになるでしょう。
たとえば、健康器具でブランドイメージが確立している「タニタ」の場合は、コンセプトが「世界の人々の健康づくりに貢献」です。「タニタ=健康である」というブランディングが確立されているため、タニタ食堂などタニタが手掛ける“食”のサービスに関して、健康的なイメージを訴求できます。「タニタ」の場合は、見込み客にブランディングにより「健康」をイメージさせて、信頼や共感を与えることとなるでしょう。
参考データ:タニタ公式ページ
SNSでの拡散や紹介が期待できる
オウンドメディアによるブランディングでは、SNSでの拡散や紹介が期待できます。ブランディングが構築されることにより、その商品やサービスに需要をもつ属性が集まるSNSなどで情報発信されることが考えられるでしょう。たとえば、芸能人が愛用している化粧品などをSNSで紹介することにより、情報が勝手に拡散する状態と同じです。
SNSで紹介されることは、SNSユーザーがオウンドメディアのコンテンツに信頼と共感を持ったことが要因となります。コンテンツにより、信頼と共感が得られれば、自然とオウンドメディアのコンテンツが紹介され、場合によっては拡散されることが期待できるのです。
また、検索エンジン利用ユーザーとは違う属性となるのがSNSユーザーとなります。SNSユーザーは、自分が共感するSNSのグループに参加して、そのグループ内での情報を共有するでしょう。オウンドメディアでは、コンセプトに共通するSNSグループに紹介されることで濃い関係性をつくることができるのです。

めぐみやのWeb集客コンサルティング
Webサイトを活用して売上と利益向上を目指しませんか?
めぐみやが集客からサイト運営まで一貫してサポート致します。
オウンドメディアにはブランディングが必要か?
オウンドメディアにブランディングが本当に必要なのかと思う方もいるかもしれません。確かに、ブランディングはマーケティングや広告主体の発想で広まった経緯があります。しかし、よく誤解される部分でもあるのですが、ブランディングは「いま」あるブランドの認知をそのままコンテンツマーケティングとして利用するのではありません。
すでに見出されてしまっている既存の価値観の中で戦うことは、資産力を前提とした市場の戦いに巻き込まれることを意味します。価格を一時的に下げたとしても、資産のある別の競合企業が同様に価格勝負を挑めば、時間の経過と伴に不利な状況は変わらず、負けてしまいます。
ブランディングが必ず必要と言っているのではなく、現在のSEOの状況やWebコンテンツの需要からみれば、今後成長しシェアを獲得できる場所や価値創造の余地が多く残されているのがブランディングです。
オウンドメディア成功はブランディングの力が大きい
オウンドメディアは、コーポレートサイト(自社の公式ウェブサイト等)に準じた扱いとして運営します。コーポレートサイトは実際、顧客とのコミュニケーションをはかる場ではありますが、相互に意見を交わして企業の身近な顧客を作るための機能としては十分ではありません。
コーポレートサイトに個性が色濃く出る時代で、企業の中にはホームページとして積極的に活用せずに概要や最低限のサービス情報だけを載せてコンテンツを増やしていく使い方をしない企業も多いでしょう。コミュニケーションをとるにしても細部までは不可能で、最低限の役割は果たしているが、それが見込み客となり自然なコンバージョンに結びつけるには役割が不足します。
オウンドメディアで成功した企業は、ブランディングによるところが大きかったのも事実です。自社製品やサービスから独自の情報(1次情報)として価値を見出して発信していく。それが価値として認められ広がっていけば後は自然と見込み客が集まって結果につながるというわけです。
オウンドメディアのSEO施策にもブランディングが求められる時代に
実は、オウンドメディアのブランディングは、市場の中で自社だけの立ち居地を確保するだけでなく、SEO施策にとっても必要性が高まっています。SEOでは現在、個性があり情報価値の高いコンテンツが検索で上位を取ります。
ブランディングが正しく、自社の個性を見出したものでコンテンツを形成しているのであれば、コンテンツを提供する上で有用なサイトとして検索エンジンに認められます。
ターゲット選びによってはブランディングが損なわれる
顧客に製品やサービスを勧める上で、「こんなペルソナの人にコンテンツを読んで欲しい」という【ターゲット選び】が重要になります。ブランディングにとってニーズの合わない顧客やエンゲージメントにつながらない集客はオウンドメディアの運営そのものを揺るがしかねません。
長期運営にもかかわらず、目的である見込み客からのサービス利用や購入が将来的に発生しない。客層のズレによって、コミュニケーション部分も機能を果たせず、顧客から得られた情報をメディアの運営に反映しても成果につながらないなど十分に考えられます。
あわせて読みたい
ブランディングでの注意点

オウンドメディアによるブランディングには、注意すべき点があります。ここでは、ブランディングについての注意点を4つ、紹介しましょう。
戦略から戦術までが一貫性で成り立っていること
ブランディングでは、戦略から戦術まで一貫性で成り立っていることが大事です。戦略面でいえば、オウンドメディアのコンセプトに沿って、メディアの進む方向性を明確にします。メディア運営中に、方向転換してしまうことは、一貫性のないオウンドメディアとなるでしょう。
オウンドメディアのファンとなった見込み客は、メディアコンセプトに共感しています。そのような濃い関係性のある見込み客に対して、方向性を変えることはブランドイメージからかけ離れることになるでしょう。オウンドメディアは、ブランディングを確立するために戦略から戦術まで一貫性で成り立っていることが大事です。
ユーザーの持つブランドイメージが商材に反映されていること
ブランディングされるオウンドメディアは、ブランドイメージが商材に反映しています。先述した「タニタ」の例からも、ブランドイメージが「健康器具」となるため、商材が健康に配慮されていることが重要となるでしょう。ブランドイメージは、見込み客がブランディングにより植え付けられた認識です。その認識を持ったうえで、企業の商材をチェックするようになります。
ユーザーの持つブランドイメージに沿わない商材を提供した場合、ユーザーはイメージにない商材に対して、違和感をおぼえます。「タニタ」の例でいえば、「健康なイメージ」から外れた商材をあつかえないことです。
商材の見た目ばかり重視しないで機能や使いやすさに配慮すること
オウンドメディア経由で誘導する自社の商材に対して、商材の見た目ばかりを重視して、機能や使いやすさを配慮しなければ見込み客が購買行動を起こさないでしょう。商材は、見た目も大事です。しかし、インターネット上での情報提供では商材に対して詳しい情報を提供することが必要となります。
実店舗販売とちがい、インターネットでは商材を手にとってチェックすることができません。その分、詳しい機能や「どのように使うと便利か?」使いやすさについて紹介することが大事です。使いやすさも商材のブランドイメージとなり、ブランディングにつながるでしょう。
顧客目線のブランドストーリーにより自社が届ける価値の伝達
ブランディングされたオウンドメディアでは、顧客目線のブランドをストーリー化されています。具体的には、顧客の要望や問題に対して取り組んだ点などをストーリー展開で紹介する流れです。ブランドストーリーは、あくまでも顧客目線であることが前提となります。
自社都合のブランドストーリーは、単なる企業の歴史でしかありません。常に顧客目線で「顧客に対して、どのように問題を解決しようと取り組んだのか?」をストーリー展開で紹介する形式です。顧客目線のブランドストーリーは、結果的に自社が届ける価値を顧客に伝えることとなります。ブランディングにより、商材を通した顧客価値を伝達できるのです。
あわせて読みたい
オウンドメディアのブランディング方法
ここからは、オウンドメディア運営でブランディングをする方法について順番に説明します。
オウンドメディアならではの企業PRやブランディングを見出す
オウンドメディアを運営する企業にとって、何が強みで個性はどこにあるのか?ブランドがすでにある企業が立ち上げるなら、概ね自社ブランドについては捉えているでしょう。そこからブランドを価値ある個性にするのであれば、Web顧客の目線からどう映るのかを考えます。つまり、顧客が欲していて、企業側が提供できるニーズを共有するブランディングやPRの部分が重要です。
オウンドメディアは自社の資産を形成する大切なプロジェクトです。長期間の運営になるのですから、ブランディングやPRの詳細を決めるときは目的に合わせて1つずつ内容を決めましょう。誰が担当して、どのくらいの規模のコンテンツをいくつ投下するか?稟議なども使い、社内で話し合って決定を下していくことが最初の過程では大切です。
あわせて読みたい
市場を調査する
ブランディングの具体案やコンテンツの詳細について出揃ったところで、実際に市場調査をします。いわゆるキーワード調査やペルソナを決める調査とはまた別です。市場で実際に運営しようとしているメディアが通用するのかを確認します。
市場調査については、場合により順序が入れ替わることもあります。また、すでに顧客とコミュニケーションが取れるメディアがある場合はそれを活用すれば、この手順を省略して次のステップに進むこともできます。
ですが、基本的にはブランディングを生かす形でオウンドメディアを運営するので、運営戦略や方針などを確認しつつ問題点を探っていく過程であるといえます。企業ブログを利用する方法などさまざまなメディアでの検証が考えられます。自社に合った方法で行います。
顧客からのヒアリング
想定している顧客のイメージからずれていないか、一致しているのであれば、メディアに対しての反応はどのようなものかを把握する過程です。ページビューや滞在時間のようなサイトアクセス情報からも分かることは多いでしょう。加えて、コンテンツに対する顧客の反応を知られる機会です。
万が一、想定していたのと違い顧客の反応が弱いと感じたのであれば、ペルソナや提供するコンテンツ自体に問題がある可能性があります。ヒアリングの内容を吟味して、検証から新たな制作内容に検討を加えましょう。
ブランディングした商品・サービスとして見込み客を集客
オウンドメディアの運営は中盤の過程で述べたような明確な反応や結果が分からないケースもたくさんあります。ほとんど反応が得られない場合もあるため、最初の数ヶ月はコンテンツを公開するだけで、結果が伴わずとも我慢が必要です。
長期的な運用を前提として、見込み客を集客するための仕組み作りこそじっくりと腰を落ち着けて運営するのがベストです。集客の全体量が足りないと感じたら、SEO施策やキーワードの見直しを検討します。
あわせて読みたい
オウンドメディアのブランディングから見えてくるもの
見込み客を得たら、経営用語でいう「エンゲージメント(商品に愛着を持つ状態に)」することが、オウンドメディアの主軸です。オウンドメディアにしか出来なかったこと、ではなく、オウンドメディアだから可能になったこと。それがブランディングによって見えてくるものです。
安易な気持ちでは始めない
オウンドメディアは一度始めたら、最後まで走りきる覚悟を持って続けましょう。中途半端なかたちで終わってしまうことで、せっかく集めた見込み客が離れるだけでなく、ブランドイメージを損なうなどあまり良い印象でないことは確かです。
自社の強みをブランディングするのに最適
オウンドメディアは他メディアよりもブランディングを実施するのに向いています。一般的に、ブランドを認知してサービスを知ってもらえるようにするのは、集客をするだけでは成立しません。
ステークホルダーにブランドとして認められる必要があります。ステークホルダーとは、利害関係者の呼称全般で顧客や取引相手、株式会社なら株主など関係性の強い相手のことです。オウンドメディアは顧客の中にコアなファンを加えたケースです。
自社で主導するブランディングですが、自社だけでは決まらないのがデメリットであると同時にメリットなのです。双方にとっての有益性が認められてこそ優れたメディアとして価値を発揮します。そして、コンテンツは企業の資産の一部になり情報として蓄積されます。
自社コンセプトに磨きがかかり目的が明確になる
企業は、ブランディングされたオウンドメディアを運営することにより、自社のコンセプトに磨きがかかり全社で共通認識となる目的を明確にできます。ブランディングにより、自社のブランドイメージの認知が広がれば、ブランドイメージにそった企業理念にも磨きがかかるでしょう。
コンセプトが明確で強力なものとなれば、企業が目指す目標も明確になります。ブランディングされたオウンドメディアは、企業の経営指標にも大きな影響をあたえるのです。
あわせて読みたい
コンテンツ内製の経験値を蓄えられる
企業のオウンドメディアをブランディングできた場合、その取り組みは経験値となります。自社の強みをコンセプトとしたブランディングは、オウンドメディアの重要なコンテンツです。ブランディングから見えてくるものは、自社の強みを明確にしたコンテンツを自社で作った経験があげられます。コンテンツ内製の経験値は、自社の資産となるでしょう。
あわせて読みたい
オウンドメディアでブランディングに成功した事例3選
オウンドメディアによりブランディングに成功した企業の事例を紹介します。
サイボウズ式
サイボウズ株式会社が運営するオウンドメディア「サイボウズ式」は、ビジネスノウハウだけではなく、これからの「働き方」や新しい生活様式に合った「会社の在り方」、「家庭と仕事の両立」などに注目した読者目線のメディアです。サイボウズ式のコンセプトは、「新しい価値を生み出すチーム」となります。コンセプトに沿って、常に「新しい価値」を追求したコラムやインタビュー記事など配信している姿勢です。
サイボウズ式では、自社で企画をしたコラムやインタビュー記事を読者目線で配信しています。配信内容は、「会社・組織・働き方・生き方」をテーマとして、「いかに新しい価値をビジネスに取り入れるか」ヒントとなるコンテンツばかりです。サイボウズ式は、一貫性をもって2012年より、ユーザー目線で役立つ情報を配信してきました。その取り組みが、ブランドイメージとなり、IT系のビジネスパーソンが組織運営や働き方のヒントとして活用しています。オウンドメディアとしては、直接的に商材の紹介をしない形式です。集客は、読者によるSNSでの拡散となり、結果的にメディアのPVを月間20万ほどに上げています。
参考データ:サイボウズ式
ジモコロ
地域ごとに振り分けた求人情報を配信するエリア型求人サイト「イーアイデム」を運営する株式会社アイデムと株式会社バーグハンバーグバーグが共同で運営するオウンドメディア「ジモコロ」です。ジモコロの特徴は、コンテンツ制作のために地方の魅力を伝える現地取材の上で記事化しています。オリジナリティある面白い記事を強みとして、他社のメディアと差別化しているジモコロです。
ジモコロは、「地元」をイメージして地方の求人につながる地方の楽しみを伝えるメディアとブランディングされています。ジモコロは、2015年より運営され現在月間110万PVの実績のオウンドメディアとなりました。
参考データ:ジモコロ
LIGブログ
サラリーマンの共感を得ることに成功している株式会社LIGが運営する「LIGブログ」です。LIGブログは、IT系企業のサラリーマンに役立つ実践的なノウハウを発信しています。LIGブログは、実践的なWeb技術のノウハウ記事やビジネス関連のコラム記事、企業の紹介などを一貫したコンセプトの下で取り組んでいる姿勢です。
とくにLIGブログの成功要因として、SNSでのフォロワー数があげられます。Facebookでの「いいね」総数が5万9千以上です。オウンドメディアのPV数も月間500万となっています。
参考データ:LIGブログ
まとめ
今回は、オウンドメディアにブランディングの発想を取り入れて運営する方法について紹介しました。PRの場として、ブランディングを生かすためのポイントは、ブランドの認知を広げることです。ブランドの認知向上が実現できれば、ファンを獲得できるサイクルを回すことができます。このような好循環のサイクルを回せるメディアを構築することがオウンドメディアによるブランディングの目的です。
オウンドメディアによるブランディングは、短期的な目線ではうまくいきません。長期で続ける覚悟を持ってメディア運用を開始しましょう。自社内製だけでの限界を感じた場合、専門業者の知識や経験が必要となります。オウンドメディアによるブランディングには、専門業者のもつ蓄積されたWeb集客の知識やオウンドメディアを手がけてきた経験を活かすことが大事です。
ムダに右往左往するよりも、実際の制作から培ってきた経験を活かせる専門業者への依頼をオススメします。結果的に時間リソースや人的リソースの削減にもつながり、コスト面に好影響を与えることが考えられるでしょう。

めぐみやのWeb集客コンサルティング
Webサイトを活用して売上と利益向上を目指しませんか?
めぐみやが集客からサイト運営まで一貫してサポート致します。
- オウンドメディアの成功には専門性と信頼性を築き上げ長期的な信頼関係の構築が必要
- 自社商品やサービスの知名度を上げ自社だけの立ち位置を明確化し競合との差別化ができる
- ブランディングを通じてファンを獲得し収益性を上げることが大きなメリット
オウンドメディアとブランディングに関するよくあるご質問
最後によくあるご質問をいくつかご紹介致します。
みなさまのWeb集客にお役に立てば幸いです。
その他、ご不明な点がございましたら以下のリンクよりお気軽にご相談下さいませ。
無料オンライン相談はこちらからどうぞ。
Q
オウンドメディアとは何ですか?
A
オウンドメディアとは、企業や個人が自ら所有・運営するメディアのことです。ウェブサイト、ブログ、SNSアカウントなどが一般的な例です。このメディアを通じて、自社の製品やサービス、価値観を直接顧客に伝えることができます。
Q
ブランディングとオウンドメディアはどう関連していますか?
A
ブランディングは企業や製品の「ブランドイメージ」を構築する活動であり、オウンドメディアはその一つの手段です。オウンドメディアを活用することで、継続的に価値のあるコンテンツを提供し、ブランドの信頼性や認知度を高めることが可能です。
Q
オウンドメディアでよく使われるコンテンツ形式は何ですか?
A
ブログ記事、動画、インフォグラフィック、ニュースレターなどが一般的です。コンテンツの形式は、ターゲットとする顧客や配信するメッセージによって変わる場合があります。
Q
オウンドメディアの運営にどれくらいの費用がかかりますか?
A
費用は様々ですが、プラットフォームの選択、コンテンツのクオリティ、更新頻度、マーケティング活動などによって変わります。最低限の運営では月数万円から、本格的な運営では数百万円以上かかる場合もあります。
Q
オウンドメディアでのSEO対策は必要ですか?
A
必要です。高品質なコンテンツを提供するだけでなく、SEO対策を施すことで検索エンジンからの自然な流入を得ることができます。
Q
ブランディングを成功させるためには、オウンドメディアで何をすべきですか?
A
一貫したメッセージと高品質なコンテンツを提供することが基本です。また、ターゲットとする顧客に有用な情報を提供し、信頼関係を築くことが重要です。