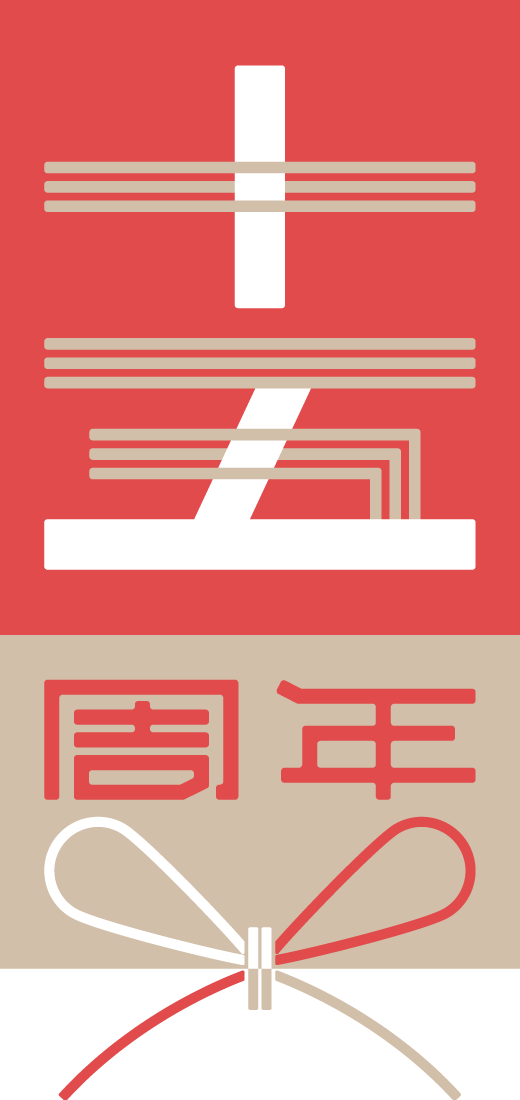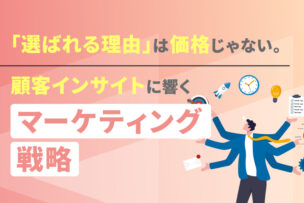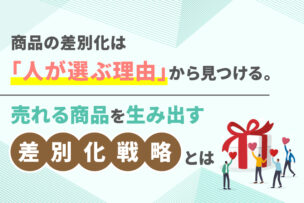記事の監修

Web集客・マーケティングの専門家として、15年間にわたり厳格な基準と緻密な戦略をもって中小企業の成功を導く。
一時的な集客の手法に頼ることなく、中長期的な効果を持続させる本質的なWeb集客の構築に注力。
『恵ある集客を。』をスローガンに掲げてクライアント様のサービスや商品の核心的な魅力を、的確にターゲットに伝えることを重視したWebサイト運用をサポート。
「記事を公開したのに検索順位が上がらない」
「どのように改善すれば良いのか分からない」
などとお悩みの企業担当者は非常に多いものです。
検索順位が上がらない理由は、検索順位を決定づけるGoogle評価基準が原因であったり、コンテンツの質やサイトの技術面に課題があったりなどが考えられます。
本記事では、
- 検索順位が上がらない理由① Googleに正しく評価されていない
- 検索順位が上がらない理由② コンテンツの質が低い
- 検索順位が上がらない理由③ サイトの技術的な問題
の3つの柱で原因と改善策を解説していきます。
自社サイトの検索順位を上げる方法が分からない方は、ぜひ読んでみてください。
目次
検索順位が上がらない理由を3ステップで解説
STEP
01
STEP
02
STEP
03
サイトの「構造」が最適化されていない
ユーザーのストレスをなくしGoogleのスムーズな評価へ繋げる
どんなに良いコンテンツであっても、サイト全体の構造や技術的な設定に問題があると、検索順位は上がりません。ページの表示速度が遅い、スマホで見にくい、サイト内の関連ページへの導線が不適切であることなどが挙げられます。サイト構造は、ユーザーのみならずGoogleにとっても重要な要素です。
検索順位が上がらない理由① Googleに正しく評価されていない
検索順位が上がらない理由の一つは、自社のWebサイトがGoogleに正しく評価されていないことです。検索順位を決定づけるGoogleのシステムに、自社のページが正しく認識されていなかったり、ペナルティを受けていたりなどが主な要因となります。
早速、Googleに正しく評価されるための具体的なチェックポイントを見ていきましょう。
インデックスされていない
そもそもGoogleにインデックスされていなければ、検索順位がつきません。インデックスとは、Googleのロボットである「クローラー」がページを認識し、データベースに情報を登録することです。
自社のページがインデックスされているかどうかは、Google Search Console(グーグルサーチコンソール)で確認できます。確認方法は、Googleサーチコンソールの「URL検査ツール」にページのURLを入力するか、Googleの検索窓に「site:自社ページのURL」と入力して検索することで確認できます。
インデックスされていない場合は、Googleサーチコンソールから登録をリクエストしましょう。
Googleペナルティを受けている
Googleからペナルティを受けていることも、検索順位が上がらない重大な原因の一つです。例えば、低品質なコンテンツがあったり、不自然なリンクがあったり、過剰なキーワードの詰め込みがあったり、他サイトとの重複コンテンツだと認識されていることが原因となります。
Googleのペナルティには、2つのパターンがあります。一つは「手動ペナルティ」と呼び、Googleの担当者がサイトを見て違反と判断し、評価をするケースです。手動ペナルティの場合、Googleサーチコンソールに違反内容の通知が届くため、必ず確認しておきましょう。
二つめは、検索アルゴリズムによる「自動ペナルティ」です。検索アルゴリズムのアップデートによって自動的に低評価を受けるケースです。自動ペナルティは通知が届かない場合があるため、急激なアクセス数や検索順位の低下がみられたら、自動ペナルティを受けている可能性を疑いましょう。
AIに選ばれていない
現在の検索エンジンでは、検索結果にAIによる自動解答が表示されることが増えています。AIによる回答に自社のページが選ばれると、検索結果の一番上に表示されますが、選ばれていなければ、AIからの評価が低いと判断できます。
AIに選ばれやすいコンテンツを作るためには、AIが情報を抽出しやすいような文章へと工夫することが大切です。例えば、次の4点が挙げられます。
- 主語と述語をしっかりと記載し、一文を短くまとめる
- 結論や重要な情報を冒頭に記載し、その後に根拠を述べる
- 1つの段落に1つの内容を意識する
- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を強化し、信頼できる情報源だと示す
カニバリゼーションが起きている
カニバリゼーションが起きていることも原因の一つに挙げられます。カニバリゼーションとは、自社サイト内での複数のページが同じキーワードのため、競合となり、互いの順位を奪い合っている状態を指します。
例えば、「コーヒー おすすめ」というキーワードに対して、自社が2つの記事を公開していると、Googleはどちらのページを上位表示させるべきか判断できず、結果として両方の順位が伸び悩んでしまうのです。
カニバリゼーションが発生している場合は、テーマが重複している内容の記事を統合したり、それぞれの記事で狙うキーワードや検索意図をしっかりと分けることが必要です。一つのキーワードに対して一つのページとなるように整理しましょう。
Googleに正しく評価されるためのチェックポイント
Googleにページを正しく評価してもらうには、SEOの土台をしっかりと固めることが必須です。まずはGoogleサーチコンソールを導入し、インデックスやペナルティの通知など、致命的なエラーがないか定期的に確認しましょう。
次に、情報量が少ない、重複しているといった低品質なコンテンツをチェックし、質を高めたり似ているページを統合したりします。そして最も重要なのは、各ページで狙うキーワードを一つに絞り、コンテンツのテーマと目的を明確化することです。これらの基盤を徹底することで、Googleが自社サイトの価値を正しく認識できるようになります。
技術的な要素や専門知識が必要なため、「自社で改善するのが難しい」「具体的なやり方がわからない」とお悩みの方は、ぜひ御社めぐみやのWeb集客コンサルティングサービスをご検討ください。プロのノウハウに基づいて、上位記事へと成長させるための最適な改善提案を行います。詳しい内容と事例は、以下のリンクをご覧ください。

めぐみやのWeb集客コンサルティング
Webサイトを活用して売上と利益向上を目指しませんか?
めぐみやが集客からサイト運営まで一貫してサポート致します。
あわせて読みたい
検索順位が上がらない理由② コンテンツの質が低い

検索順位が上がらない理由の二つ目は、コンテンツの質が低いとGoogleに判断されていることです。先ほどご説明したとおり、低品質なコンテンツはGoogleペナルティを受ける要因にもなります。
ここでは、コンテンツの質が低いと判断されている具体的な理由と、質を上げるための方法を一緒にご紹介していきます。
ユーザーニーズを満たしていない
読者が本当に知りたい情報をしっかりとコンテンツ内で伝えられていない場合、コンテンツは評価されません。
例えば、自社のビジネス向けクラウドサービスについて説明するコンテンツの場合を考えてみましょう。機能一覧や複雑な技術仕様ばかりを羅列していても、読者である企業担当者は魅力を感じません。
それよりも「このサービスを導入することで残業時間が何時間削減されるのか」「情報漏洩のリスクがどのように解消されるのか」といった、ユーザーにとっての具体的なメリットをしっかりと記載することが必要です。
常に「読者の疑問はすべて解決できたか」という視点でコンテンツを見直しましょう。
キーワードに対する内容のズレ
狙うキーワードに対して、コンテンツ全体の内容がずれていることも、順位が上がらない大きな原因です。設定したキーワードに対して、読者がどのような情報を求めているのかを深く振り返り、その情報に沿った内容となっているか確認しましょう。
例えば、「SEO 対策」というキーワードで検索する読者は、SEOの具体的な手順や最新のノウハウを求めていることがほとんどです。それに対し、記事の内容が「SEOとは何か」という説明ばかりであったら、内容がズレていると判断されます。
E-E-A-Tの不足
質の低いコンテンツと判断されている要因の一つに、E-E-A-Tの不足が挙げられます。E-E-A-Tとは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、 Trustworthiness(信頼性)の頭文字をとったものです。
例えば、旅行の記事を書くケースを考えてみましょう。
- Experience(経験):実際に行った人が書く記事の方が、行っていない人が書いた記事より説得力があります。
- Expertise(専門性):旅行が趣味で全国各地を旅している人が書いた記事の方が、たまにしか行かない人より詳しい情報を持っています。
- Authoritativeness(権威性):有名な旅行会社や専門家が書いた記事の方が、世間一般に認められやすく信頼されます。
- Trustworthiness(信頼性):記事の情報源や運営者情報が明確で、安全性が保障されている必要があります。
このように、信頼できる情報の掲載は、高品質なコンテンツを作成するにあたり必要不可欠な要素です。
独自性・情報量が少ない
コンテンツの独自性が低く、情報量が少ないと検索順位が上がらない要因となります。多くの情報が溢れている中で、自社の記事を読んでもらうためには、自社にしか伝えられない独自性が必要です。ありきたりな内容の記事が多くある中で、オリジナル性がある記事は、唯一無二のコンテンツとなります。
また、情報量が少なすぎると読者が十分に知りたい情報が得られない可能性があります。情報が多すぎるのも良くありませんが、適切な量の情報掲載が大切です。
キーワードの競争率が高い
狙うキーワードの競争率が高いと、検索上位表示はなかなか難しいものです。競争率が高いことは、つまり多くの企業や権威性のあるサイトがそのキーワードで記事を書いているため、上位を狙う難易度が高くなるのです。
特に立ち上げたばかりのサイトやE-E-A-Tが低いサイトは、最初から競争率の高いキーワードを狙うのではなく、競合が少ないニッチなロングテールキーワードから狙う戦略が有効的です。
ユーザーに選ばれる高品質なコンテンツの作り方
ユーザーに選ばれ、検索順位で評価される高品質なコンテンツを作るには、徹底的なユーザーニーズの分析が必要です。ユーザーが「なぜ」「何を」知りたいのか深く掘り下げます。独自に行った調査データや製品の使用経験など、他社には真似できない一次情報と経験を加えてオリジナリティを出すことも大切です。
そして、著者や情報源を明確に記載し、E-E-A-T(信頼性)を証明しましょう。キーワードに対する関連テーマを網羅的にカバーし、その記事だけで読者の検索行動を終わらせるようにすることが重要です。
もしも、高品質なコンテンツを用意する時間やリソースが足りないとお悩みであれば、ぜひ御社めぐみやのWebコンテンツ制作代行サービスをご検討ください。読者の反響を得られる質の高いコンテンツ設計から制作、改善提案まで一連のサポートが可能です。詳しくは、以下のリンクよりご覧ください。

めぐみやのWebコンテンツ制作代行
見込み客に響くWebコンテンツ作りにお悩みではありませんか?
ターゲットを確実に捉えるコンテンツ制作で見込み客の獲得をサポート致します。
あわせて読みたい
検索順位が上がらない理由③ サイトの技術的な問題
検索順位が上がらない理由の三つ目は、サイトの技術的な問題が挙げられます。ユーザーがWebページを見にくいと感じ、Googleから評価されにくいサイト設計では、どんなに良質なコンテンツであっても検索上位にはなりにくいものです。
具体的なサイトの技術的な課題を見ていきましょう。
ページの表示速度が遅い
まずサイトの技術的な問題として、ページの表示速度が遅いことが挙げられます。Googleの調査によると、リンクをタップした際、次のページが表示されるまで3秒かかると、ユーザーの53%が離脱すると言われています。
ページの表示速度が遅いと、ユーザーは待つことなくすぐに離脱してしまい、Googleからの評価を著しく下げる要因となるのです。
表示速度を上げるためには、ページ内の画像サイズを圧縮して最適化したり、ブラウザキャッシュを設定して再訪問時の読み込み速度を向上させたりなどの対策を行いましょう。
モバイルフレンドリーでない
モバイルフレンドリーでないことも、検索順位が上がらない大きな理由の一つです。現代では、PCだけでなく、スマートフォンやタブレットなどの多種多様なデバイスで情報が見られています。Googleも、モバイルでの使いやすさを重視しており、検索順位の決定要因の一つとなっています。
PCに合わせた画面を他の端末でみると、デザインが切れていたり、文字の大きさが適切でなく読みにくかったりなど、ユーザーにとってストレスを感じるページとなってしまいます。現代では、レスポンシブデザインを採用するなど、すべてのデバイスで最適に表示されるモバイルフレンドリーに対応したサイトへの移行が必須です。
内部リンク・被リンクが適切でない
内部リンクや被リンクが適切に配置されているか確認してみましょう。内部リンクや被リンクは、Googleのクローラーがページを巡回し、サイト内の評価を判断するための重要な「道」となります。
内部リンクは、サイト内の関連性の高い記事同士を適切にリンクで繋ぐことです。クローラーが効率的にサイト内を巡回でき、ユーザーにとっても必要な情報に辿り着きやすいメリットがあります。
被リンクは、特に権威性の高い外部サイトからリンクを受けることで、Googleからの信頼性を高め、検索順位の向上につながります。一方、質の低いサイトからの被リンクはマイナス評価となるため、良質な被リンクを取得する施策が必要です。
クローラビリティが低い
クローラビリティが低いと、クローラーがサイトの隅々まで巡回しきれず、結果として公開したページがインデックスされなかったり、正しく評価されなかったりして検索順位が上がりません。
クローラビリティを上げるためには、サイトマップをGoogleサーチコンソールに登録し、クローラーにサイトの構造を伝えること、重要なページの導線を明確にすることが大切です。
タイトル・見出しタグが適切でない
タイトルタグや見出しタグが適切でないことも、検索順位を落とす原因となります。タグは、クローラーに「このページは何について書かれているか」を伝える重要な役割を持っています。
タイトルタグには、ページの内容を正確に表し、最も重要なキーワードを含める必要があります。もちろん、ユーザーが検索結果でクリックしたくなるような魅力的なタイトルにすることも大切です。
見出しタグについては、H1タグはページに一つのみ使用し、H2以降のタグは論理的な階層構造となるように設定します。見出しタグを適切に設定することで、クローラーは内容を理解しやすくなり、ユーザーにとっても読みやすいサイト構成となるのです。
SEOに強いサイト構造へ改善するポイント
SEOに強いサイト構造へ改善するには、「ユーザーの使いやすさ」と「クローラーの巡回しやすさ」を両立させることが重要です。ページの表示速度を改善し、ユーザーの離脱を防ぐことと、すべてのデバイスで快適に閲覧できるようモバイルフレンドリーへの対応を徹底することがポイントとなります。
また、サイト構造をシンプル化し、ユーザーが目的のページまでスムーズに辿り着けるような導線を意識しましょう。正確にページを評価してもらうため、内部リンクを適切に配置することも効果的です。この技術的な基盤を整えることで、Googleはサイトを高く評価しやすくなります。
もし、自社のリソースや専門的な知識が不足している場合は、めぐみやのWebサイト制作サービスをご検討ください。それぞれの企業の強みを活かしたサイト設計やコンテンツに落とし込みます。SEO対策はもちろん、サイト制作後の運営も視野に入れ、検索上位表示を目指せるサポートが可能です。詳しい事例は、以下のリンクよりご覧いただけます。

めぐみやのWebサイト制作
効果的なWebサイトを作りたいけれどどうすれば良いかお悩みではありませんか?
集客と運用の実績を活かし御社ビジネスの成果に直結するWebサイトを構築致します。
あわせて読みたい
まとめ
検索順位が上がらない主な原因は、Googleの評価、コンテンツの質、サイトの技術の3つです。まずは、Googleサーチコンソールでインデックス状態やペナルティを確認し、評価を受け取る土台をしっかりと固めましょう。そして、ユーザーの疑問を完全に解消するため、E-E-A-Tや独自性を満たした高品質なコンテンツを作成し、多くのユーザーに見てもらえる準備を整えることがポイントです。
また、ページの表示速度やモバイルフレンドリー対応、適切な内部リンク設定を行うなど、技術的な改善と対策を行うことで、サイトの価値がGoogleに正しく伝わります。
- AIが情報を抽出しやすいような文章へと工夫し、AIに選ばれやすいコンテンツ制作が大切
- 自社にしか伝えられない独自性を含めたコンテンツ制作がポイント
- 権威性の高い外部サイトからの被リンクが、Googleからの信頼性を高め検索順位の向上につながる
検索順位が上がらないに関するよくあるご質問
最後によくあるご質問をいくつかご紹介致します。
みなさまのWeb集客にお役に立てば幸いです。
その他、ご不明な点がございましたら以下のリンクよりお気軽にご相談下さいませ。
無料オンライン相談はこちらからどうぞ。
Q
なぜ検索順位が上がらないのですか?
A
主な原因は、検索エンジンの評価基準(コンテンツの質・専門性・権威性・ユーザー体験など)を満たしていないことです。単に記事数を増やすだけではなく、「検索意図に合った有益な情報」を提供する必要があります。
Q
毎日更新しているのに順位が上がらないのはなぜ?
A
更新頻度よりも「内容の質」と「ユーザーの満足度」が重視されます。更新が薄い内容やリライトばかりだと、評価は上がりません。改善には「ユーザーの疑問を解消する深いコンテンツ」が不可欠です。
Q
外部リンクを増やしても効果が出ないのは?
A
被リンクの質が低いと評価されないためです。相互リンクや無関係なサイトからのリンクは逆効果になる場合もあります。権威性の高いサイトから自然に獲得できるリンクを目指しましょう。
Q
競合より記事数も多いのに勝てない理由は?
A
記事数よりも「検索意図をどれだけ満たしているか」が重要です。競合がユーザーの課題を深く解決している場合、記事数ではなく「内容の濃さ」で差がつきます。
Q
SEOのテクニカル面を改善したのに順位が動かないのは?
A
技術的SEO(サイト速度、モバイル対応、内部リンク最適化など)は基盤ですが、それだけでは順位は上がりません。評価の大半はコンテンツと被リンクの質に依存しています。
Q
キーワードをたくさん入れているのに効果がないのはなぜ?
A
キーワードを詰め込みすぎると「不自然」と判断され、逆に順位が下がることもあります。自然な文章で検索意図に沿った情報提供をすることが大切です。
Q
検索ボリュームの大きいキーワードで順位が上がらないのは?
A
ビッグワードは競合が強いため、上位表示には相当な資源が必要です。まずは「スモールワード」「ロングテールキーワード」で成果を積み重ねるのがおすすめです。
Q
SNSや広告で流入があるのに検索順位が改善しないのは?
A
SNS流入や広告流入は直接SEOに影響しません。検索順位に影響するのは、検索からのユーザー行動(クリック率・滞在時間・離脱率など)です。
Q
ドメインを新しくしたら順位が下がったのはなぜ?
A
新規ドメインは信頼性が低く、評価が蓄積されていないためです。古いドメインのSEO資産(被リンクやコンテンツ評価)を引き継げていない可能性があります。リダイレクト設定の確認が必要です。
Q
上位記事を模倣しても順位が上がらないのは?
A
「模倣」だけでは差別化ができず、検索エンジンからオリジナリティがないと判断されます。独自の視点や事例、専門家コメントなど「独自性」を加えることが重要です。
Q
長文コンテンツなのに順位が低いのはなぜ?
A
文字数の多さは評価基準ではありません。長文でも冗長でユーザーの疑問に答えていなければ順位は上がりません。重要なのは「情報の網羅性と分かりやすさ」です。
Q
コンテンツをリライトしても成果が出ない理由は?
A
単なるリライトではなく、「検索意図の再定義」「不足情報の追加」「最新情報の反映」が必要です。Googleは「新しさ」ではなく「有益さ」を評価します。
Q
内部リンクを増やしたのに順位が変わらないのは?
A
内部リンクは関連性が高いページ同士を結ぶことで効果を発揮します。単純に数を増やすだけではなく、ユーザーが回遊しやすい導線を意識することが大切です。
Q
検索順位が一時的に上がってもすぐ下がるのはなぜ?
A
アルゴリズムがテスト的に表示順位を変動させる「ダンス現象」の可能性があります。安定して順位を保つには「継続的な改善」と「ユーザー満足度の積み上げ」が欠かせません。