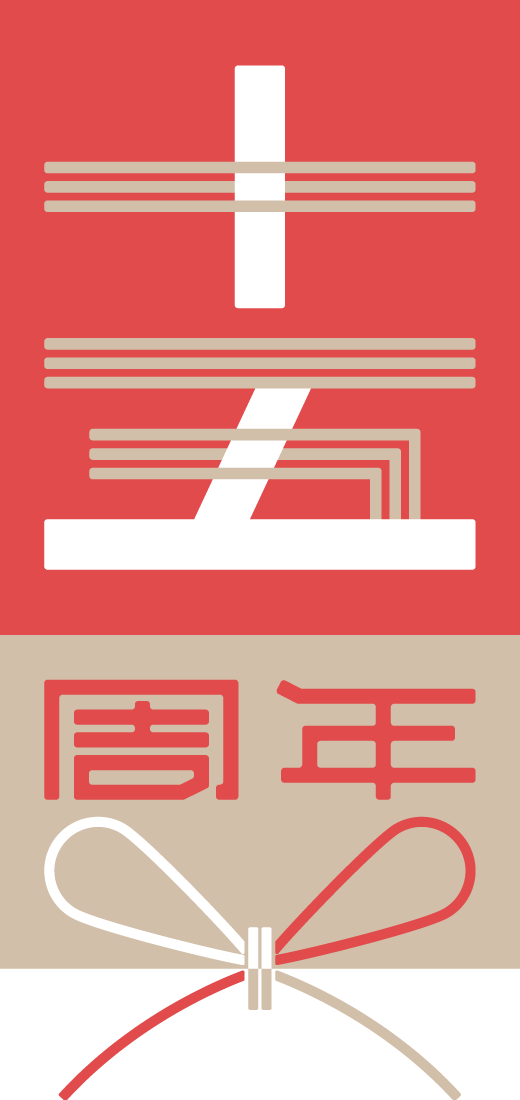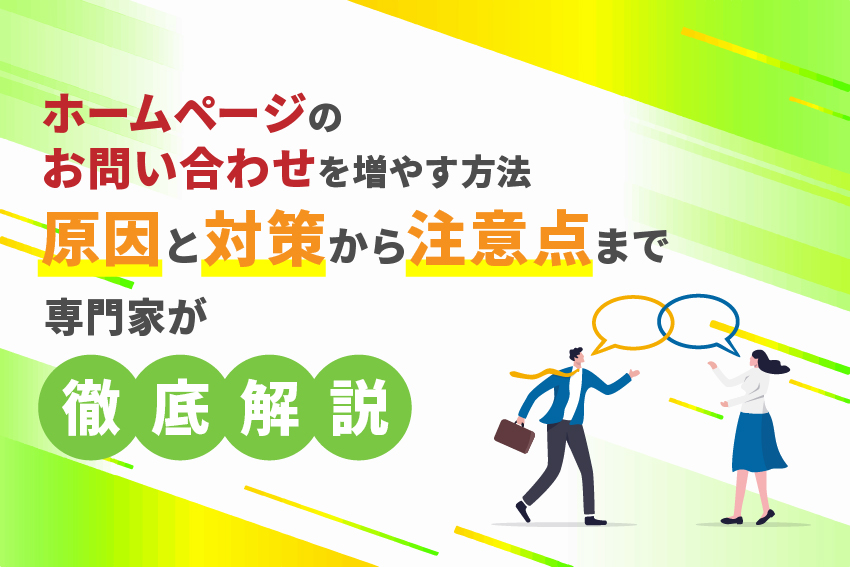記事の監修

Web集客・マーケティングの専門家として、15年間にわたり厳格な基準と緻密な戦略をもって中小企業の成功を導く。
一時的な集客の手法に頼ることなく、中長期的な効果を持続させる本質的なWeb集客の構築に注力。
『恵ある集客を。』をスローガンに掲げてクライアント様のサービスや商品の核心的な魅力を、的確にターゲットに伝えることを重視したWebサイト運用をサポート。
ホームページを作り、いざ公開!!しかし、問い合わせが全く来ない・・。
そんなご経験、みなさまも一度はあると思います(現在、そのような状況かもしれません)。実際のところ、ホームページを作っただけで問い合わせは来ません。
ホームページは、検索エンジンの検索結果1ページ目に表示されないものも含めて、数えきれないほど存在します。誰からも反応されないホームページが、インターネット上には限りなく存在しているのです。問い合わせが来ないホームページは、結果的に「誰も見ていない」と言っても過言ではありません。
では、問い合わせが多いホームページはどのような施策・運営をしているのでしょうか?今回の記事は、ホームページからの問い合わせを増やすために必要なすべてをご紹介致します。企業の集客に携わるWeb担当者必見の内容です。ぜひ、参考にしてみてください。
- ホームページからの問い合わせを増やしたい方
- ホームページからの問い合わせが来ない原因を知りたい方
- ホームページからの問い合わせを増やす方法を知りたい方
目次
ホームページからの問い合わせが来ない原因
ホームページは多くの企業やサービスにとって、顧客との最初の接点の場となります。しかし、適切な設計や戦略を実施しないと、期待する問い合わせや成果が得られません。以下、主な原因とその対策を詳しく解説します。
集客数が少ない
そもそもホームページへの集客数が少ないと、問い合わせは来ません。そしてホームページが見られていなければ、ホームページを作成した意味がないのです。一般的にはアクセス数の約1%が問い合わせに繋がるといわれています。つまり、1件の問い合わせを獲得するには100人の訪問者を獲得しなければなりません。SEO対策や広告を活用し集客を獲得することから始めましょう。
ホームページ自体の見やすさ
ホームページが見にくくはありませんか。ユーザーがホームページに訪れ、第一印象で「見にくい」と感じればすぐに離脱してしまいます。文字が大きすぎる、デザインに一貫性がない、メニュー欄が分かりづらいなど、Webサイトを訪れた瞬間に見にくいと感じる原因があるのかもしれません。ユーザーは、知りたい情報を知るためにホームページを訪れます。難しいことを考えず、まずは第三者の視点に立ってホームページを見直してみましょう。
ホームページのデザインとユーザビリティ
ユーザーは、すばやく情報を取得できるページを求めています。 古いデザインや複雑な構造のホームページは、ユーザーの興味を引くことができません。また、多くの人々がスマートフォンでWebサイトを閲覧するため、モバイル対応していないサイトは大きな機会を失っています。さらに、読み込み速度が遅いサイトは、訪問者がすぐに去ってしまう原因となります。デザインの鮮度とユーザビリティは、訪問者をページに留めるための鍵なのです。
問い合わせフォームの導線と使いやすさ
問い合わせフォームは、顧客と直接コミュニケーションがとれる手段です。その問い合わせフォームが見つからない、またはアクセスしにくい位置にあると、コミュニケーションの機会を逃しているのかもしれません。また、フォームの入力項目が多すぎる、または複雑すぎると、ユーザーは途中で放棄する可能性があります。さらに、確認や完了ページがなければ、送信の成功を確認することができず、ユーザーに不安を感じさせる原因となります。
SEO(検索エンジン最適化)の問題
ホームページが検索エンジンで上位表示されない場合、訪問者の流入が少なくなります。これは、低い検索順位や関連するキーワードの最適化が不足しているためかもしれません。また、不適切なバックリンクやペナルティのリスクも考慮する必要があります。SEOは、オンラインビジネスの成功において欠かせない要素であり、定期的なチェックと更新が必要です。
ホームページの信頼性と認知度
訪問者がホームページを信頼するためには、十分な企業情報やプライバシーポリシーが明示されていることが必要です。また、ユーザーレビューや評価が低い、または存在しないと、新しい訪問者の信頼を得ることが難しくなります。SNSや他のプラットフォームでの活動を通じて、認知度を高めることは非常に効果的です。
ターゲット層とのミスマッチ
ホームページの内容やデザインがターゲットとなる顧客層に合致していなければ、問い合わせの機会が失われる可能性があります。マーケティング戦略の再評価と、ターゲット層の深い理解が求められます。
コンテンツの質と関連性
ホームページのコンテンツは、その企業やサービスの顔とも言えます。目的に合わない、または関連性の低いコンテンツは、訪問者を混乱させ、信頼を損なう可能性があります。また、コンテンツの更新が不足していると、サイトが放置されているとの印象を与えかねません。画像や動画の品質も非常に重要です。魅力的で関連性の高いコンテンツは、ユーザーエンゲージメントを向上させる鍵となります。
商品やサービスの発信方法
ホームページの問い合わせが来ない原因として、商品やサービスの発信方法が的確でない可能性があります。自社商品やサービスの魅力が十分に伝わっておらず、そもそも魅力的だと感じてもらえていないのかもしれません。商品やサービスに興味を持ってもらえなければ、そもそも問い合わせの意欲が生まれないのです。自社商品やサービスの魅力や強みを的確にアピールできているか見直してみましょう。
ベネフィットの不足
ホームページの問い合わせが来ない理由の一つに、ベネフィットの不足が挙げられます。「ユーザーにとって商品やサービスを利用することで得られる利益」が伝わっていなければ、商品やサービスの必要性を感じないため問い合わせまで辿り着きません。自社サービスを利用したその先にあるユーザーの姿をイメージさせるための「必要な情報」が不足している可能性があります。

めぐみやのWeb集客コンサルティング
Webサイトを活用して売上と利益向上を目指しませんか?
めぐみやが集客からサイト運営まで一貫してサポート致します。
問い合わせが多いホームページの3つの特徴
ホームページからの問い合わせを増やしたい!といっても、魔法のように急に増えるものではありません。まずは、問い合わせが多いホームページの特徴を把握して、それを自社のホームページに取り込む事が最も近道になるのです。では、問い合わせが多いホームページはどのような特徴があるのでしょうか。
1.自社サービスの魅力や強みをしっかり訴求している
お客様から問い合わせが多いホームページの特徴は、見込み客が納得するサービスを提供している点です。ホームページ上で、自社サービスの魅力や強みをしっかりと見込み客に対して訴求できています。自社サービスの魅力や強みの訴求は一見、簡単で当たり前のようですが、自社都合の魅力や強みになっているホームページを多く見かけます。
つまり、自社サービスの魅力や強みを客観的に理解していないホームページは意外にも多いのです。自社サービスの魅力や強みを客観的に理解するには、お客様目線で見た自社サービスの価値や強みを再確認することが大事になります。お客様目線とは、自社都合を含まないお客様都合です。できれば専門家などの客観的な視点も取り入れながら、自社のホームページを見直してみましょう。
あわせて読みたい
2.質の高い集客を実現している
どんなに素敵で魅力的なホームページを作っても、集客対策をしないと問い合わせは来ません。ホームページは、インターネット上に掲載したらお客様が自動的に訪問すると思ったら大間違いです。ここで誤解を解くために、ホームページのあるべき姿と集客の関係性を解説します。問い合わせの多いホームページは、質の高い集客を実現していることが特徴です。
問い合わせが多いホームページの2つ目の特徴として、将来見込み客になる可能性のある潜在的なユーザーなどを集客することを目的としています。さらに集客ができているホームページは、質の高い集客コンテンツが豊富にあることが多いです。
ホームページを品質のよいコンテンツにする施策は、一朝一夕で実現できる事ではありません。日々のホームページ運営実績から得られる集客効果から生まれてくる成果になります。つまり、質の高い集客を実現しているホームページを作るには、日々の積み重ねを続けていく必要があるのです。
ホームページ制作や運用の経験が浅い場合は、日々の積み重ねを間違った方向で進めてしまう可能性もあります。間違った方向性で進めてしまうリスクは、失敗による時間的なリスクです。時間的なリスクに対して、早めの成果を求めている場合は専門家への相談は必要不可欠ではないでしょうか?
インターネット環境は、日々変化しています。そのため、専門家に依頼することで時代に合ったホームページ運用が実現することも事実です。ぜひ、検討してみてください。
3.掲載されている情報がいつも最新である
お客様目線で運営されているホームページは、掲載されている情報が最新で更新頻度も高いです。日々ホームページの更新を行なうことで、お客様の安心感にも繋がり、SEO対策の効果にもなります。結果、問い合わせが増える方向にも繋がるのです。
ホームページの更新は、社内で更新のルールやスケジュールなどを定めて運用すれば、比較的簡単に導入が出来るでしょう。
あわせて読みたい
ホームページの問い合わせを増やす施策
それでは、みなさまが一番知りたい部分になる「ホームページの問い合わせ」を増やす施策を解説します。問い合わせを増やすためには、これら5つがポイントです。
自社サービスの強みや訴求相手を絞る「分析法」
まず初めに自社のサービスをもう一度確認してみることから始めましょう。自分では理解しているつもりでも、お客様から見た印象とサービス提供側から見た印象には「ズレ」があります。お客様目線に立って、「ウチのサービスの優れている部分は何だろう?」と厳しい見方をしていく必要があるのです。その際、第3者の意見も大きなヒントになるでしょう。
客観的に見た「自社の強み」を過去に利用されたお客様の声からも判断することは可能です。さらにサービスを届ける相手を絞ることも重要なポイントになります。「誰に提供したら満足するサービスなのか?」を具体的に分析していくのです。決して万人に共通する内容ではなく、サービスを届けて大きな価値を感じられる相手に向けた内容でホームページを構成していきましょう。
ターゲティング
自社の強みや訴求相手を絞る具体的な方法は、ターゲティングによる訴求相手の絞り込みから始めます。ターゲティングとは、その名のとおり、自社ビジネスの対象者を明確にすることです。ターゲティングは、訴求相手を明確にすることにより、訴求内容も具体的になります。
たとえば、自社商品が「ビジネス英会話教材」であれば、ターゲットは英会話を必要とするビジネスマンとなります。英会話の上達を目的にするビジネスマンに向けて、具体的な状況で訴求できます。「教材を使った人がたった半年で海外のクライアント相手に商談できる・・・」など、ターゲットが明確であれば、具体的な訴求ポイントを伝えられるでしょう。
ペルソナ設定
ターゲティングにより訴求相手を絞り込むには、ペルソナ設定が必要です。ペルソナ設定とは、自社の商品やサービスを利用する対象者を架空の個人にまで絞りこむ施策になります。別の言い方をすれば、属性の具体化です。
訴求対象者を具体化することにより、伝える言葉や環境など、最適な状態まで精度をあげられます。ペルソナ設定では、次のような属性を設定します。
- 個人名(架空)
- 年齢
- 性別
- 職業(身分)
- 家族構成
- 居住地
- 趣味
- 日課や利用しているSNSなど
ターゲティングでは、対象相手の属性の幅を持たせて20代~30代女性と設定しますが、ペルソナでは、個人まで絞りこむため26歳と限定する点が特徴です。ペルソナは個人まで絞りこむため、訴求内容も具体的になります。結果的に訴求内容に具体性が出れば、信ぴょう性も高まり問い合わせの障壁も下がるでしょう。
あわせて読みたい
「競合他社にない何を求めているか」を提示
ホームページの問い合わせを増やす方法は、先述したターゲティングやペルソナ設定に引き続き、自社の強みを分析します。自社の強みの分析とは、競合他社のサービスと「何が違うか?」を明確にすることです。
競合他社と同じようなサービスを提供していたら、顧客に料金やホームページの第一印象だけで判断されてしまいます。ホームページをリニューアルするにしても、広告を出すにしても競合他社と比べて自社の優れている点を前面に打ち出した提案が必要になるのです。
自社の優れている点を前面に打ち出すには、潜在的なお客様が「競合他社にない何を求めているか?」を自社のサービスから明確にすることが重要になるでしょう。競合他社にはない自社の優れている点については、過去にサービスを利用したお客様に聞くことでも見つかる可能性はあります。
自社商品を利用したことのある体験者の言葉は、説得力のある訴求に役立つでしょう。常日頃からメールや電話などで、お客様の感想を聞き出せるようなコミュニケーションツールは必要になります。既存顧客との関係性も忘れないようにしましょう。
あわせて読みたい
ホームページの更新頻度を上げる方法
3つ目のポイントになるホームページの更新頻度については、ホームページを広告で運用する方法と検索エンジンに最適な作り方で表示される方法があります。それぞれ解説しましょう。
広告で運用した場合の更新方法
ホームページを広告で運用していく方法はサービス内容にもよりますが、季節感のあるサービスならば一定の期間、同じホームページの内容であっても問題はありません。たとえば、おせち料理を販売する業者ならば、今年つかったホームページ内容を変更しないで翌年使っても値段以外は違和感ないでしょう。おせち料理は、10月~12月にかけて年中行事に便乗して訴求する商材です。
年中行事は、形式が決まっていることが多く、翌年も同じホームページで訴求できる可能性を持っています。ただし、冬をイメージさせるサービスを春や夏に広告でアピールするのは適当ではありません。冬をイメージさせるものでも春や夏に訴求したい場合は、季節ごとにホームページの内容を更新する必要があります。
さらに扱う商品の流動性が高いサービスについては、商品の入れ替えの度にホームページの内容を更新していく必要があるでしょう。ホームページは、くれぐれも広告を見てホームページに訪問されたお客様をがっかりさせない内容で更新していくことがポイントになります。
SEO対策で更新する方法
SEO対策は、検索掲載順位を上げて検索結果上位に表示させるための方法です。SEOによる更新方法は時間と手間がかかり、専門知識も必要になってきます。初心者や経験の浅いWeb担当者には、一朝一夕でできることではありません。SEO対策は検索順位で狙うキーワードを選定したり、キーワードに沿ったページコンテンツを作ったりします。経験がなければ、最初は専門家に任せることで大きな労力を省くことができるでしょう。
SEO対策では、ホームページを更新することを重要視されます。ホームページの更新は、常に分析のもとで判断するため、素人判断で実行しないことがおすすめです。専門家のアドバイスを受けながら、自分でホームページを更新できるようになることが理想になります。
セキュリティ対策
問い合わせフォームのセキュリティ対策を徹底しましょう。問い合わせフォームには個人情報を入力する必要があるため、セキュリティに不安があるとユーザーは問い合わせをやめてしまう可能性があります。第三者による不正アクセスやサイバー攻撃によるデータ改ざん、データの消失などセキュリティリスクがあることを理解することが大切です。
ホームページのセキュリティ対策には、SSL(暗号化)の採用やアクセス制限の導入をしましょう。SSLとは、Webサイト上で送信されるデータを暗号化して、個人情報閲覧を防止する仕組みです。問い合わせフォームのみではなくホームページ全体を保護する「常時SSL化」を採用することで、ユーザーからの信頼度は増加します。また、ホームページ内でIPアドレスの制限をすることで、スパムメールのデータ送信拒否も可能です。
ホームページのセキュリティ対策は、他にもプラグインを導入したりプライバシーマークの取得などさまざまな方法があります。ホームページの問い合わせを増やすには、ユーザーが安心できる問い合わせフォームを構築することが大切です。
CVRの改善
CVR(コンバージョン率)とは、ホームページを訪れたユーザーのうちどれだけの問い合わせや購入がされたかを示す割合です。ホームページへのアクセス数がどんなに多くても、CVRが0であればホームページの意味がありません。ホームページ運用においてCVRを計測し改善することで問い合わせの増加に繋がります。
CVRを算出するうえでコンバージョンの定義を明確にしておきましょう。問い合わせや商品の購入、資料請求や会員登録など企業によって成果(コンバージョン)の設定は異なります。コンバージョンの設定を「資料請求」にするのと「高額商品の購入」にする場合では、コンバージョンへのハードルが異なるのは予測できるでしょう。つまり業界によってCVR数値は大きく異なります。
CVRはGoogleアナリティクス(GA)で確認することが可能です。指定した期間内のデータを抽出できるため、迅速に改善施策を立てられます。

めぐみやのWeb集客コンサルティング
Webサイトを活用して売上と利益向上を目指しませんか?
めぐみやが集客からサイト運営まで一貫してサポート致します。
ホームページの問い合わせを増やす具体的な方法
ここでは、ホームページからの問い合わせを増やす具体的な方法をご紹介します。今すぐにすべて実行できなくても、取り組みやすいものから実施していきましょう。
アクセス数を増やす
ホームページへのアクセス数を増やしましょう。先程もお伝えしたとおり、ホームページのアクセス数が少なければ問い合わせも増えません。ホームページへのアクセスは「検索エンジンからのアクセス」と、SNSや広告など「検索以外からのアクセス」の2つがあります。
検索エンジンからのアクセス数を増やすためには、SEO対策を徹底し、検索結果に表示される順位を上げる必要があります。検索上位表示を目指すために、検索エンジンからの評価が上がるように対策をしましょう。自社のホームページが、ユーザーに対して良質で価値のある情報を提供しているページであると判断してもらうのがポイントです。
検索以外からのアクセスとしては、FacebookやX(旧Twitter)、InstagramなどのSNS投稿があります。また、リスティング広告やディスプレイ広告からのアクセスも同様です。自社のホームページへのアクセスに繋がるよう対策しましょう。しかしSNSはコンテンツの質が低ければユーザーに見てもらえず、広告は有料のため、継続的に費用をかけるのは中小企業にとって現実的ではありません。
また、他サイトに貼られたリンクを経由して自社のホームページへアクセスする経路(リファラル)もありますが、他サイトにリンクを貼ってもらうにはコンテンツの質が高いことが条件です。
まずは自然検索からのアクセス数を増やすことに注力しましょう。
UX・UIを高める
UXとUIを高めることでホームページの問い合わせを増やすことが可能です。UXとは、ユーザーエクスペリエンスの略で、ユーザーがWebサイトを利用した時の体験や経験のことを指します。UXを高めることで、ユーザーがストレスなくWebサイトを利用でき満足度向上に繋がります。
UIとは、ユーザーインターフェースの略で、ユーザーにとっていかにWebサイトが利用しやすいかどうかを示す言葉です。例えば、ホームページのデザインや文字のフォント、ページの表示速度などのすべてがUIに含まれます。UIが優れているほどUXは高まるため、ホームページの問い合わせが増える可能性も高まります。

めぐみやのWebサイト制作
効果的なWebサイトを作りたいけれどどうすれば良いかお悩みではありませんか?
集客と運用の実績を活かし御社ビジネスの成果に直結するWebサイトを構築致します。
スマホ対応にする
ホームページをスマホ対応にしましょう。スマホでホームページが見られるだけではスマホ対応にはならないため注意してください。スマホに合わせてホームページ内の画面幅やボタンサイズを変更するなど、画面を最適化することでユーザーが見やすく操作しやすい状態にすることが「スマホ対応」になります。
Googleが提供する「モバイルフレンドリーテスト」で簡単に確認できるため、自社のホームページがスマホ対応になっているか調査してみましょう。
ホームページのスマホ対応によってユーザーのストレスは減るため、滞在時間が長くなり問い合わせに繋がる可能性が高まります。
魅力的なキャッチコピーの変更
ホームページのキャッチコピーは、ユーザーの第一印象(ファーストインプレッション)を左右する重要な役割があります。ユーザーの心を掴む魅力的なキャッチコピーに変更しましょう。キャッチコピーが魅力的だと「ホームページをもっと覗いてみよう」と興味を持ってもらえます。
キャッチコピーを設定する際は、どんな人にメッセージを届けたいかターゲットを明確にしましょう。「できるだけ多くの人に届くキャッチコピーにしたい」と思うかもしれませんが、ターゲットが広範囲だと誰の心にも響かないキャッチコピーになってしまいます。ターゲットを明確にし、特定の人に向けた強いメッセージにすることがポイントです。
キャンペーンの実施
キャンペーンの実施を検討しましょう。キャンペーンを行うことで、自社の新商品やサービスを認知してもらう効果があります。まずはユーザーの認知を獲得して、自社への関心を持ってもらい購入に繋げましょう。ホームページ上だけでなくキャンペーンサイトを導入することで、アクセス数やクリック数が把握しやすく、SNSを活用したプロモーションもしやすくなります。
ベネフィットの提示
ベネフィットを提示しましょう。まずは、商品やサービスを利用することで得られるメリットを伝え、その上で「ユーザー自身がそのサービスを利用することで得られる利益・体験」を明確にすることが大切です。「その商品を使ったらどう変わるのか」「そのサービスを利用するとどんな良い体験ができるのか」商品やサービスを利用する前と利用した後では、少なからず身に起こる「良い変化」があるはずです。良い変化が起こった後の「未来の姿」をユーザーに具体的にイメージさせることが大切なのです。
離脱率が高いページの修正
Googleアナリティクスなどを活用して離脱率が高いページを調査しましょう。離脱率が高いページが分かれば、そのページを見直し修正することでユーザーの滞在時間が増え、問い合わせにも繋がります。ユーザーの目的を今一度確認し、コンテンツの内容と一致しているか見直してみましょう。
実績・事例コンテンツで訴求
自社のサービスや商品の紹介と合わせて、実績や実例を掲載することで問い合わせが増える可能性があります。実績や実例コンテンツによって、自社サービスに対する信頼感や商品を購入することへの期待感を高めることが可能です。サービスを利用する際のユーザーの疑問や、商品購入時の不安感を払拭する効果も期待できます。
問い合わせに繋がるバナーの設置
ユーザーが簡単に問い合わせフォームへ移動できる導線を設計しましょう。ユーザーがどのページからでも問い合わせができるよう全ページにバナーを設置することも検討してみてください。ただバナーを設置するだけでなく、画像でアピールするのも方法の一つです。「お気軽にお問い合わせください」などの文章を加えて、ユーザーが問い合わせしたくなるように促すことが大切です。
電話問い合わせの実施
問い合わせフォームだけでなく、電話問い合わせの導線も設置しましょう。すぐに問い合わせをしたいユーザーは電話を利用する傾向があります。電話番号を掲載するのも良いですが、クリックしただけで電話がかけられるように設定する機能もおすすめです。ユーザーがスムーズに問い合わせができるような導線設計を心がけましょう。
ツールやシステムの活用
ホームページの問い合わせをより増やす方法として、ツールやシステムの導入が挙げられます。例えば、チャットbotを活用し、よくある問い合わせ内容をあらかじめ表示させておくことで、ユーザーはクリックするだけで簡単に疑問を解決できます。また、チャットbotであれば、24時間365日問い合わせ対応が可能となります。社内のリソースを確保しつつ、顧客満足度の向上に繋がるのです。
さらに、メール共有システムを利用すれば、複数の担当者が同じメールアドレスを使用できるため、情報の共有はもちろん、複数人で顧客に対するメール返信が可能となります。例えば、問い合わせ件数が多く、担当者一人での顧客対応が追いつかなければ、ユーザーは「問い合わせをしたのに対応が遅い」と感じてしまい、企業全体のイメージダウンにもなりかねません。ツールやシステムを活用することで、企業のイメージを向上させ、より多くの問い合わせを獲得することが可能です。
ホームページの定期的な更新
ホームページを定期的に更新することが、問い合わせの獲得に繋がることもあります。ユーザーの立場になって考えてみましょう。コンテンツの最新更新日が古い日付であるWebサイトに、問い合わせをするのは不安ではありませんか。運用されていないホームページは、問い合わせをしても見てもらえないかもしれないと感じたり、そもそも問い合わせをしようと思わないでしょう。ホームページが生きていることをユーザーに伝えるためにも、最新情報への更新を怠らないようにしてください。
あわせて読みたい
「よくある質問」で疑問を解消
ホームページを読み進めていくにつれ、訪問者の疑問や不安を解消できたか?客観的に判断することが大事です。ホームページの構成では、「よくある質問」を設置して疑問の解消に役立ちます。「よくある質問」では、事前に考えられる疑問に対して先回りして解決する回答コンテンツを作ることです。「よくある質問」は、単なる疑問解消コンテンツではなく、自社のカスタマーサポートの負担を軽くできます。
また、「よくある質問」のないホームページの場合は、疑問を抱えたままページ内を回遊している訪問者を放置していれば離脱するリスクが高くなるでしょう。離脱を防ぐには、常に移動できる場所に「よくある質問」ページへのリンクを設置しておくことが大事です。
SNSで宣伝する
FacebookやX(旧Twitter)、Instagramなどで宣伝し、SNSからの流入を増やしましょう。SNSはユーザー同士で共有できる機能があるため、自社サービスや商品の情報を広く拡散できる可能性があります。企業の認知度向上が見込めるため、新規顧客の獲得にも繋がります。またSNSでホームページをリンクし商品紹介することで、ユーザーをホームページに誘導しましょう。SNSを上手く活用できれば、広告費の削減にもなります。

めぐみやのWeb集客コンサルティング
Webサイトを活用して売上と利益向上を目指しませんか?
めぐみやが集客からサイト運営まで一貫してサポート致します。
問い合わせしたくなるホームページの構成
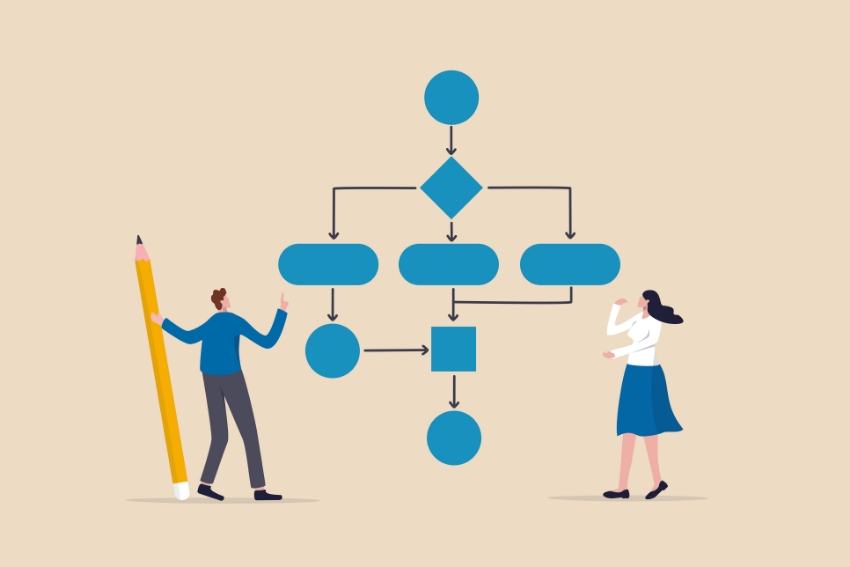
ホームページの問い合わせを増やすためには、ホームページ構成を見直すことも1つの方法です。実際には、ホームページの構成を変更しただけで改善できる場合もあります。
問い合わせフォームの最適化
EFO(Entry Form Optimization)とは入力フォーム最適化の略で、ユーザーが短時間で正確に入力完了できるようにフォームの項目やデザイン、機能を最適化することです。EFOを行うことでホームページの問い合わせやコンバージョン率の向上に繋がります。
Webサービスの会員登録やアンケートの回答をする際に、入力項目が多くて面倒だと感じたことはありませんか。無料体験の商品なのにクレジットカード登録画面があり、手間だと感じて途中離脱するユーザーもいるかもしれません。
ホームページの問い合わせフォームでも同様です。ユーザーに「問い合わせしたい」というモチベーションを維持してもらうために、入力項目を最小限にしましょう。自動入力機能や外部ID連携機能などを取り入れることで、ユーザーの負担を最小限にできます。また、「これなら簡単に入力できそう」と思わせるようなデザインになっているか見直してみてください。ユーザーの手間を減らしストレスのないフォームに改善することで、ホームページの問い合わせを増やすことが可能です。
ホームページの問い合わせに誘導する導線設計
訪問者が先を知りたくなる導線設計とは、ホームページ訪問者の心理状態の変化に沿った導線を作ることを指します。心理状態に沿って導線を設計することは、自社ビジネスに対して興味関心を高めてもらうために必要です。あくまでも1例にすぎませんが具体的には、次のような流れで訪問者の興味関心を高めます。
権威性を訴求
権威性の訴求では、自社商品やサービスに対して、業界の権威ある人や関連性のある専門家の見解などを掲載できれば、訪問者の信ぴょう性と安心感を高めることが可能です。
権威性の訴求では、「この専門家が勧めている内容ならば」と興味関心を持たせる役割になります。たとえば、テレビコマーシャルなどで芸能人が紹介する商品やサービスに好感を持つイメージと同じです。権威性を出すには、芸能人や専門家だけではなく、有名な文献やWebサイトを引用することでも効果があるでしょう。
また、権威性は専門家の見解などではなく、自社の実績も活用できます。権威性のある実績は、次のとおりです。
- 自社商品やサービスの販売数:「累計〇〇万個販売」など
- 有名人の利用:「タレントの○○さんも愛用中」など
- 評価・表彰:「〇〇評価年間ランキング1位獲得」など
共感を得るために課題提示
権威性により訪問者の信頼をつかんだら、共感を得るための課題提示が必要です。自社商品やサービスに価値を持つ訪問者の課題を具体的に掲載します。たとえば、「作業着の泥汚れ、こすっても落ちませんよね」など、訪問者が共感する課題を提示して同じ目線にいることを伝えるイメージです。
ベネフィットの伝達
ベネフィットの伝達では、自社商品やサービスを使った後の恩恵を明確にします。先ほどの作業着の例では、「作業着の汚れがこすらないで落ちるから、誰でもカンタンにきれいに仕上げられます」など、商品購入の先に見える未来を提示することが大事です。
レビューや購入者の感想を掲載
訪問者は、ベネフィットに対して「うまいこと言って、だまされるのではないか?」と、半信半疑な状態です。訪問者の半信半疑な状態をなくすには、レビューや購入者の感想などで、さらに信ぴょう性を高めます。
実際の購入者が使ったうえでの感想の効果は効果的です。使ってみないとわからない部分は多く、先人の意見に動かされるケースも少なくありません。レビューの掲載は、購買意欲を高める後押しになるでしょう。
行動を促す
問い合わせを求めるには、この時点で行動を促すことが必要です。わかりやすい問い合わせフォームを設置したり、電話番号やメール、LINEなどへの誘導を訴求します。
時間的リスクを訴求する
行動を促す際は、時間的なリスクも提示することで緊急性や希少性を持たせることが可能です。「限定〇〇人まで」や「3日間限定のキャンペーン」など、すぐに問い合わせるように訴求することで、問い合わせの後押しになります。
あわせて読みたい
ヘッダー画像の選定
ヘッダー画像の選定は、ホームページの問い合わせを増やすために重要な部分です。ヘッダー画像は、ホームページに訪問したユーザーが最初に見る部分となります。そのため、最初に目に入った画像が魅力的でなかったら、離脱されるリスクも抱えている大事な部分となるでしょう。そのため、ヘッダー画像には訪問者をひきつける文言(テキストの挿入)が必要です。
ヘッダー画像では、先ほどの導線設計で説明した「権威性」の掲載として、権威性のある自社の実績なども効果があります。最初に見る画像で権威性を訴求できれば、「見る価値あり」と判断される可能性が高くなるからです。また、ヘッダー画像には、共感を得るためのキャッチコピーも効果的です。ターゲットとなる訪問者が共感するベネフィットなど掲載できれば、本文を読み進めてもらえる可能性が高くなります。
最適なCTAボタンの設置
問い合わせを増やすためのCTAボタンは、行動を起こさせるための重要な部分です。ターゲット層に適したデザインやテキストによりCTAボタンを設置することが大事です。自社商品やサービスの価値を理解している顕在層に対しては、ホームページの最初の部分で行動を促しても効果があるでしょう。
ターゲティングにより設定されたユーザーが潜在層であれば、ホームページの導線で最も興味関心を高めている部分にCTAボタンを設置することが重要です。その際、CTAボタンがわかりやすいものであることが必要です。逆効果になるのは、CTAボタンの乱用です。CTAボタンを設置し過ぎると誘導されているイメージが強くなり、不審に思われます。CTAボタンは、最適な場所に必要最低限の設置が必要です。
ホームページと問い合わせフォームのデザインを統一
ホームページと問い合わせフォームのデザインを統一しましょう。ホームページ全体と問い合わせフォームのデザインが統一されていないと、ユーザーは違和感を抱いて「個人情報が漏れるのではないか」と不安を感じてしまいます。問い合わせフォームでの離脱率を下げるためにもホームページのデザインに合った問い合わせフォームを設置しましょう。
お客様の声や事例の導入
CTAボタンの近くにお客様の声やサービス利用の事例などを導入すれば、訴求効果を高められます。お客様の声や事例は、導線設計でも紹介した「購入者の感想」の掲載です。
お客様の声は、自社の都合のよい内容に修正しないようにしましょう。自社都合で編集されたメリットばかりのお客様の声は、逆に怪しく思われる可能性があります。お客様の声が自社商品のイメージを悪くする内容であれば、真筆に受け止めて改善すること(または改善したこと)を補足するレビューへの回答も効果的です。メリットとデメリットは、バランスよく掲載することが信ぴょう性を高める役割になります。
チャットボットの活用
チャットボットとは、ユーザーからの質問に自動で答えてくれるプログラムのことです。AI技術の発展はここ近年急激に向上しており、導入を検討する企業も増えてきています。
チャットボットを導入することで、単純な問い合わせに対する返信業務を大幅に軽減できます。また、チャットボットはホームページ内のすべてに表示されるため、ユーザーが不安や疑問を解決したいと思った時に即時対応が可能です。また、ユーザーが求めているコンテンツが掲載されているページをチャットボットに回答させることで、自社のホームページ内での回遊率が向上し、結果的にユーザーの滞在時間が伸びます。
チャットボットを活用することで、ユーザーは短時間で情報収集ができるため、問い合わせのアクションを起こす確率も向上するでしょう。チャットボットの回答で問い合わせフォームへ誘導する設定もできます。
自動返信メールの活用
問い合わせをしたユーザーに対して、円滑な返信を行うには自動返信メールの活用がおすすめです。長時間返信がないとユーザーは不安や不信感を抱き、競合他社へ流入する可能性があります。自動返信メールを活用することで、返信作業に人材が割けなくても即日対応が可能となります。問い合わせをしたユーザーを逃さないために、円滑な返信が行えるような体制を整えておくことが重要です。
あわせて読みたい
ホームページの問い合わせを増やすための注意点
ホームページの問い合わせを増やすために、具体的な方法や構成をご紹介してきました。ここでは、これらの問い合わせを増やす対策を行う前に押さえておきたい注意点をご紹介します。
ユーザー目線に立ち客観的に現状分析
まずはユーザー目線に立って、客観的に自社のホームページを分析しましょう。毎日ホームページを運用している担当者自身では、気が付かないこともあります。他部署の社員に意見や感想をヒアリングしたり、専門家に相談したりなど、顧客目線でホームページを見直してみましょう。
優先順位を決めて一つずつ改善
ホームページの問い合わせを増やす具体的な施策や対策を行う際は、優先順位を決めて一つずつ取り組んでいきましょう。あれもこれもと一気に改善策を講じても、どの対策に効果があったのか分かりづらいため、原因の究明やさらなる対策を練ることが難しくなります。
まず初めに、ホームページの問い合わせを増やす「目的」を明確にしておきましょう。売上の向上なのか、集客のための顧客リストの確保なのか。「ホームページの問い合わせを増やしたい」と感じているのなら、その先に目指す目的を明確にすることで優先順位を定め、着実な成果を出すために一つずつ改善することが大切です。
専門的な目線でホームページ診断
ホームページの問い合わせを増やすために、自社のホームページにおける現状を把握することが必要です。社内にWeb知識や運用スキルがない場合は、専門家に相談することも検討してみてください。多くの企業のホームページを運用してきたプロの目線から、ホームページを診断してもらえます。また、的確な改善策を提案してくれるため、自社の問い合わせを増やすだけでなく、ホームページにおける目標達成や成果獲得が期待できます。
あわせて読みたい
ホームページ運営における2つの勘違い
先述致しましたが、ホームページ公開後の取り組みとしてほとんどの場合「すぐに問い合わせは来ない」のが一般的です。「すぐに問合せが来ない」ことが一般的であるのに、思わず考えてしまう勘違いが2つあります。
心機一転!サイトをリニューアルすれば問合せが増える?
1つ目の勘違いは、心機一転でホームページをリニューアルすれば「問い合わせが増える」と思うことです。
リニューアル前のホームページがよほど使いにくかったら話は別ですが、通常のホームページでしたら、リニューアルしても問い合わせが急増することはありません。まずは、ホームページ上で自社のサービスが適切に訴求出来ているかの確認をしましょう。「ホームページ上で自社のサービスが適切に訴求出来ているか」を確認するためには、アクセス解析を使うことが必要です。アクセス解析とは、自社ホームページに訪れる訪問者の動向を数値分析する解析方法になります。アクセス解析は、無料で利用できますが専門用語の理解が必要です。
アクセス解析により、その日のホームページに訪問した人数やよく読まれているページの表示回数などデータから分析してホームページの状況を確認できます。リニューアルをする前に自社のホームページの状態を確認することが重要になります。
あわせて読みたい
広告費を掛けて集客をすれば問い合わせが増える?
2つ目の勘違いは、広告費を掛けて集客すれば「問い合わせが増える」と思うことです。広告費を掛けて集客しても、先述通り肝心なのはホームページの中身になります。コンテンツが充実していないと直帰率ばかりが高くなり、結果、問い合わせには繋がりません。つまり、順番が間違っているのです。初めにホームページの中身を充実させてから、広告費をかけてホームページの反応を見ていきましょう。
さらにリスティング広告などで宣伝してホームページに誘導できたとしても、コンテンツにガッカリされるようでは、広告費が無駄になってしまいます。多額な広告費を掛ける前に自社集客のノウハウをつけて長期的な戦略で運営を行ないましょう。
あわせて読みたい
問い合わせが増えてきたら注意する3つのポイント
問い合わせが増えてきた場合は、注意しなければならない3つのポイントの理解が必要です。今までの改善方法に取り組んで、ホームページの問い合わせが増えてきた場合、そのままにして置くことはお勧めできません。
問い合わせに対して丁寧に回答を出していくことが必要になるのです。問い合わせがあっても回答しないでいると、せっかくホームページに魅力を感じてくれたお客様に対して、無視していることにもなります。一方通行のホームページでは、その後の関係性構築に発展しないでしょう。そのためここでは、問い合わせに対して注意するべき2つのポイントを説明しましょう。
マメな回答で問い合わせを放置しない
ホームページの問い合わせが増えてくることは、それだけホームページを見ていただいている証拠のような現象になります。せっかくホームページを見てもらっているのに問い合わせに対して、何もしないで放置したままにしておくことは好ましくありません。
お客様は問い合わせをするほど、ホームページの内容に興味を持っている状態です。ここでさらに興味を高められるフォローやマメな回答をすることが必要になります。
マメな回答は、お客様に対する誠実さのアピールにもなるでしょう。インターネットでは、顔やしぐさをチェックできないため、問い合わせに対しての回答から人物像をアピールするしかありません。このアピール部分は、ショートカットできないため、必要事項として取り組む必要があります。
さらに、問い合わせの回答はできるだけ迅速に返すことも評判を上げるポイントになるでしょう。お互いの顔が見えないホームページの場合、お客様の関心にすぐに答えることができれば、自然と信頼にも繋がってくるからです。そのような理由から、問い合わせには的確に回答することが大事なことを覚えておきましょう。
やり取りは大切なコミュニケーションの始まり
お客様とのやり取りは、インターネットを介した大切なコミュニケーションの始まりになります。お客様とのコミュニケーションが生まれたことは、大きな成果の第一歩です。自社のホームページでお客様に興味を持たれたことの証明になります。大切なコミュニケーションの始まりになりますので、問い合わせを窓口にして円滑な質疑応答を繰り返していきましょう。
さらにお客様の具体的な要望や新しいサービスのヒントになる質問もいただけるかもしれません。そのためにも問い合わせの対応は、疎かにしないように心がけましょう。問い合わせの回答などに不安がある場合は、Web施策の専門家の意見も参考にすることをおすすめします。
専門家の目線では、顧客の心理状態をふまえて最適な訴求内容を提案可能です。悩んでいる時間が長ければ、停滞する時間も長くなります。一度、検討してみてはいかがでしょうか。
ビジネスメールのルールに沿って返信
問い合わせの返信は、ビジネスメールのルールを意識してユーザーが内容を理解しやすいような文面で返信しましょう。一般的でない漢字の使用は避けて、堅苦しくならないように心がけてください。また、絵文字は文字化けの可能性があるのに加えてカジュアルすぎるため使用しないようにしましょう。
メールを受け取ったユーザーがすぐに判断できるよう差出名人名は会社名に設定を行ってください。メールの件名は本文の内容を簡潔に記載して、分かりやすい件名に心がけましょう。自動返信メールの場合は、その旨を記載して区別できるようにしてください。問い合わせの返信例文を社内で共有し、テンプレート化しておくことで迅速な対応が可能となります。
問い合わせメールの返信は、ユーザーの信頼を獲得できる手段でもあります。分かりやすく丁寧な返信を心がけることが大切です。
あわせて読みたい
まとめ
ホームページから問い合わせが来ない場合、ページのリニューアルや広告費を掛けて集客することだけが改善策ではありません。まずは、自社サービスの魅力や強みを明確にして「しっかりと訴求出来ているか」を確認しましょう。それによりホームページの内容や運営体制の見直しを行なうのが一番の近道になります。そのためホームページの運用は、専門知識が必要です。専門知識もなく右往左往しながらホームページを改善するには、集中して取り組む時間が必要になるでしょう。
ホームページを改善するのに時間のない人は、ホームページ作成の専門家に頼むことで手間暇がかからなくなるメリットがあります。専門家に内容や運営体制などを判断してもらうことが自社で行うよりも、早い段階からお問い合わせが期待できることでしょう。最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。
- 自社サービスの価値や強みを客観的に理解し見込み客に対して効果的に訴求することが重要
- 優れたコンテンツを用いて潜在的な顧客を対象とした質の高い集客を行い日々の運営実績から集客効果を高めることが大切
- ホームページ上の情報を最新の状態に保ち定期的な更新を行うことで訪問者の信頼を得て問い合わせを増やすことができる
ホームページからのお問い合わせ増やすためのよくあるご質問
最後によくあるご質問をいくつかご紹介致します。
みなさまのWeb集客にお役に立てば幸いです。
その他、ご不明な点がございましたら以下のリンクよりお気軽にご相談下さいませ。
無料オンライン相談はこちらからどうぞ。
Q
ホームページからの問い合わせを増やすための最も効果的な方法は何ですか?
A
ホームページのデザインやコンテンツを最適化し、CTA(コール・トゥ・アクション)を魅力的に設置することが効果的です。
Q
CTAとは何ですか?
A
CTAは「Call To Action」の略で、訪問者に行動を促すボタンやリンクのことを指します。
Q
問い合わせフォームの位置はどこがベストですか?
A
トップページやランディングページの目立つ位置、特にスクロールせずにすぐに見える位置に設置するのが一般的に効果的です。
Q
問い合わせボタンの色やデザインにはどんな影響がありますか?
A
問い合わせボタンの色やデザインは目立たせることで、訪問者の注目を引く効果があります。しかし、サイト全体のデザインとの調和も考慮する必要があります。
Q
問い合わせの増加を助けるテキストはありますか?
A
「無料相談」「質問はこちら」「今すぐお問い合わせ」などのアクションを促す言葉を使用すると効果的です。
Q
問い合わせを増やすためのホームページのコンテンツはどんなものが良いですか?
A
企業の強みや成功事例、クライアントの声など、訪問者の信頼を得られる情報を掲載すると良いです。
Q
問い合わせフォームの項目数はどれくらいが最適ですか?
A
余計な項目を減らし、必要最低限の項目数にすることで、訪問者の手間を減らし問い合わせを増やすことができます。
Q
問い合わせフォームにキャッチコピーは必要ですか?
A
キャッチコピーを追加することで、訪問者の興味を引きやすくなるため、効果的です。
Q
ホームページの問い合わせ以外の方法でのコンタクト方法は?
A
メールアドレスの表示、電話番号の掲載、SNSのリンク等も考慮すると良いです。
Q
問い合わせの増加を計測する方法は?
A
Google Analyticsなどの分析ツールを使用して、問い合わせの数やコンバージョン率を定期的に確認することが大切です。