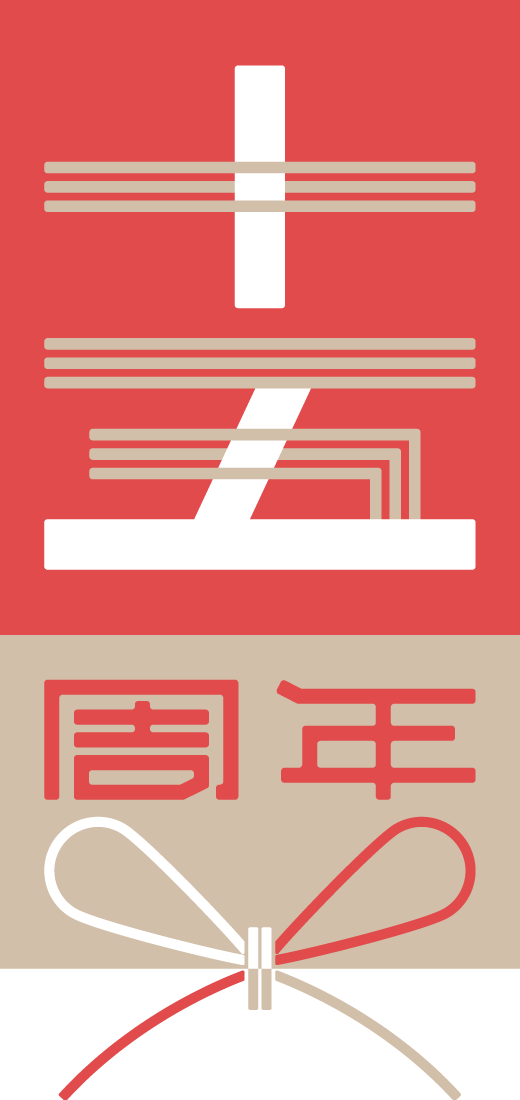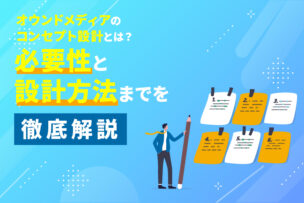記事の監修

Web集客・マーケティングの専門家として、15年間にわたり厳格な基準と緻密な戦略をもって中小企業の成功を導く。
一時的な集客の手法に頼ることなく、中長期的な効果を持続させる本質的なWeb集客の構築に注力。
『恵ある集客を。』をスローガンに掲げてクライアント様のサービスや商品の核心的な魅力を、的確にターゲットに伝えることを重視したWebサイト運用をサポート。
オウンドメディアは、自社が運営するWebメディアのことです。企業がオウンドメディアを作る場合、「何となく始めてみた」では失敗する確率のほうが高くなります。そのため、オウンドメディアを作るには、段階ごとのポイントを知っておく必要があるのです。
この記事では、オウンドメディアの作り方を3つのセクションごとに解説します。
- 企画・戦略
- 構築
- コンテンツ制作
また、既にオウンドメディアの運営で成功している企業の事例も紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。
- オウンドメディアの作り方を知りたい方
- オウンドメディアの企画や構築方法を知りたい方
- オウンドメディアの運用方法を知りたい方
目次
オウンドメディア正しい作り方の手順
オウンドメディアの正しい作り方には、手順があります。もちろん、正しいか正しくないかの判断は最終的に読者の見解になります。ただし、大枠で取り組むべき手順は存在します。
オウンドメディアは、企業が発信する自社メディアです。つまり、ビジネス目的が優先となるため、単にインターネット上に掲載されているWebサイトでは目的を果たしたことになりません。重要なことは、企業がメディアにより発信する目的をテーマにかかげることです。テーマに沿ったうえで、手順どおりに進めていくことが正しい作り方ではないでしょうか?
大枠で取り組むべき手順は、次の通りです。
- 目的と目標の設定
- 企画構成
- 構築
- 運用
この記事ではオウンドメディアの正しい作り方を手順にそって、紹介します。
あわせて読みたい
オウンドメディアを正しい手順で作る理由
オウンドメディアを正しい手順で作る理由は、個人の日記ブログとちがい、メディアから得る成果が明確なことです。メディアを起ち上げる段階で、ビジネス目的を明確に持っているため、開始とともに目的に向かってコンテンツを注入していきます。そのため正しい手順をふまないと目的意識が薄れて、成果を得る前に挫折してしまうでしょう。そのような理由から、オウンドメディアは正しい手順で作る必要があります。
企画・戦略
オウンドメディアを作る前の準備段階にあたる「企画・戦略」について解説します。オウンドメディアを企画して戦略を立てていくには、次に挙げる段階を経て設計していきましょう。
「企画・戦略」を7つの段階に沿って設定していきます。
あわせて読みたい
オウンドメディア戦略立案2つのポイント
オウンドメディア戦略の2つのポイントについて解説しましょう。
戦略はフェーズごとに区分する
オウンドメディアの戦略立案におけるポイントは、戦略をフェーズごとに区分することです。企業がオウンドメディアを運営する際に、ありがちな課題としてメディアを活用する目的が複数になることがあげられます。
販売サイトという位置づけにならないオウンドメディアは、一歩引いた立ち位置からあらゆる可能性をもつでしょう。そのため、戦略も目的ごとにフェーズ分けして考えることが大事です。マネタイズに関しては、オウンドメディアの成長を見きわめて行う必要があります。
選択したリソースを効率的に集中実践
基本的にオウンドメディアは、検索エンジンの上位表示による集客です。ただし、メディアの認知度を高めるためにはSNSの拡散力を活用したり、動画配信で紹介したり流入経路を増やすことも必要になります。
流入経路を増やす際に注意するポイントは、あらゆる媒体に手を出してしまってすべてが中途半端のまま負えないことです。戦略面では、検索エンジンの施策が時間を要します。なかなか成果が出ないからとあらゆる流入方法に手を出してしまうと、リソース不足になるでしょう。
選択した流入方法のリソースを活かすためには、効率的に集中実践する必要があります。つまり、ひとつの施策を成果の出せる状態まで集中することです。中途半端では、投資した人的リソースや時間コストなどが無駄になります。効率的にこなすには、ひとつずつ集中することが大事です。
企画・戦略での注意点
オウンドメディア制作では、企画・戦略段階の注意点を理解しておきましょう。最も注意すべき点は、会社組織でオウンドメディアを運営する場合、認識に差が出ることです。共通認識が求められる企画・戦略段階において、メディア運営の目的やコストなどバラバラで理解しているとまとまりません。
そのため、組織全体でオウンドメディアの特性について共通理解をすることが大事です。オウンドメディアの特性は、企業が発信するWebマガジンのようなイメージになります。構築してから成果が出るまで時間がかかることを共通認識しておく必要があるでしょう。企画制作段階が最もリソースを投入する期間となります。この期間において、「成果の出ないムダな投資」と判断した場合、将来見込める大きな集客成果を損出することが考えられるでしょう。あくまでも、広告運用とは真逆な戦略になることを周知しておくことが大事です。
また、オウンドメディア構築の費用面についても共通理解は必要となります。初期構築段階でかかる費用だけではなく、日々の運用体制も整える必要があるため、運用担当者を抜擢しなければいけません。自社の人的リソースにゆとりがなければ、専門業者に依頼することも検討してみましょう。

めぐみやのWebコンテンツ制作代行
見込み客に響くWebコンテンツ作りにお悩みではありませんか?
ターゲットを確実に捉えるコンテンツ制作で見込み客の獲得をサポート致します。
自社の経営課題と戦略設計をつなぎ合わせる
オウンドメディアの制作は、自社の経営課題と戦略設計をつなぎ合わせることが大事です。オウンドメディアの運営目的は、メディア経由の潜在顧客を獲得することがあげられます。潜在顧客獲得に向けて、品質の高い情報コンテンツを盛り込んでいくイメージです。
提供していく情報コンテンツと経営課題が一致していないと、効果が出る前に断念することも考えられます。時間と手間をかけて戦略設計したうえで構築しても、経営課題と食いちがうようなメディアになれば、断念することにもなるでしょう。断念となれば、初期段階で投入したコストがムダになります。そのため、自社経営課題と戦略設計をつなぎ合わせることが大事なのです。
目的・目標の設定
まず、オウンドメディアの目的から明確にしていきましょう。これから作るオウンドメディアに対して、「どのようなユーザーに、どのようなコンテンツを伝えて、どのような行動を起こしてもらいたいか?」の答えを設定します。
例えば、「若いビジネスパースンに向けて、仕事術のヒントになるコンテンツを伝えて、スキルアップに繋がる転職に成功してもらいたい!」という具体的なメディアの目的です。
「何となく始めたブログ感覚の情報発信」という意識では、オウンドメディアを長続きさせることは難しいでしょう。何といっても、目的を持って目標設定することが大事なのです。自社のマーケティングとして、「企業戦略のどの部分をオウンドメディアが担当するのか?」という点も明確にしておきましょう。企業戦略の明確にするべき部分が、目標設定となるゴールです。
そしてオウンドメディアは、ゴールから設定することが重要です。企業戦略でゴールに設定する項目は次の通りです。
- 商品やサービス、社名の認知拡大
- 購買層獲得
- 見込み客になる潜在層の獲得
企業ブランドの認知拡大は、コミュニケーション要素のゴールになります。また、売上増加はマーケティングゴールになるでしょう。設定するゴールは、企業によって異なります。自社の目的に合わせたゴールでオウンドメディアの企業戦略が決まっていくのです。
あわせて読みたい
KPI・KGIの設定
目的を明確にして目標設定するには、具体的な数値に落としこみます。オウンドメディアの運営により、どのような成果を得たいのか?具体的な数値で表すことが大事です。
数値目標の設定では、KPI・KGIを活用します。KPIとは、施策に対しての業績評価となる指標です。KPIは、施策実行のプロセスごとに設定する指標になります。最終ゴール目標がKGIとなり、KGIを逆算したプロセスごとの指標がKPIです。
メディアコンセプトの設計
目標が決まったら、次にオウンドメディアのコンセプトの設計です。まず、メディアに訪問してもらうターゲットを明確にしましょう。また、企業の目的とコンセプトが一致することも確認しておきます。
ここでの注意点は、コンセプトを度外視したコンテンツの提供を避けることです。そのためにコンセプトは明確にしておく必要があります。構築したメディアでコンセプトから外れた方向性を見せてしまうと、リピーターが増えないだけではなく、PVも上がらないオウンドメディアになってしまうからです。このような理由からも、コンセプトの設定には重要視しておくべきでしょう。
あわせて読みたい
ペルソナの設定
メディアコンセプトの設計出来たら、続いてペルソナを設定しましょう。ペルソナは、具体的な架空の人物を想定して、リアルなメッセージを発信していくための施策です。オウンドメディアのコンテンツの一貫性を保つためには、ペルソナの設定は欠かせません。「誰に届けたいコンテンツなのか?」の対象となる「誰か」を設定します。
では、実際にペルソナの設定項目を取り上げてみましょう。
- 属性情報
- 居住地域または出身地
- 年齢
- 性別
- 最終学歴
上記5項目だけでもターゲットとして人物像をイメージできますが、オウンドメディアのペルソナ設定は、より具体的に絞り込んでリアルな「誰か」まで明確にしていきます。
- 家族構成
- 未婚既婚
- 配偶者有り無し
- 子どもの有無
- 同居家族
- 職業年収
- 趣味
- 休日の行動
- 価値観
- 友人や参加しているグループ
- 普段よく見るメディア
ここまで具体的に架空の1人を設定することで、コンテンツ作成時の迷いがなくなります。それは人間の本質として、大勢の人に向けて話しかけるよりも誰か1人に向けて話しかけるほうが、伝えやすいからです。
また、ペルソナの重要ポイントとして、実際のデータを収集して設定することが挙げられます。ペルソナの設定は、想像だけで作成しないようにしましょう。理由は、想像だけの架空のペルソナにリアル感は伝わらないからです。
では、どのようにしてペルソナの設定に役立つデータを集めれば良いのでしょうか?それは、自社の商品やサービスを利用する顧客にアンケートを取ることや、レビューを提供してもらうこと、さらにインタビューなどもできれば効果的です。特に読者ターゲットのヒントは、顧客と接する頻度の高い営業担当やカスタマー担当が持っていることが考えられます。できるだけ生のデータを集めて精度の高いペルソナを設定していきましょう。
ペルソナ設定の注意点
ペルソナ設定により、メディアコンテンツに興味関心を持つ層を具体的にイメージすることが可能です。しかし、ペルソナの設定は、注意点があります。ペルソナ設定の注意点は次の通りです。
- 主観的な判断で設定しない
- 設定する際は実際にいる1人に絞って設定する
- 状況によりペルソナ対象が複数になることもある
- 状況の変化により定期的に見直す
ペルソナは、「架空の誰か」となるため、空想の中のあり得ない人物を想定してしまうことが考えられます。あり得ない人物では、実在しないため成果が期待できません。そのため、見直しながらターゲット設定の精度を上げていくことが大事です。
あわせて読みたい
メディアコンテンツのジャンルやカテゴリを決める
ペルソナが決まったらメディアコンテンツのジャンルやカテゴリを決めます。ジャンルやカテゴリを決める際は、自社商材のもつメディアコンセプトと特徴から見えてくる自社の強みにつながるようにします。
たとえば、自社商材が「勤怠管理システム」の場合、商材の持つ特徴は次のように考えられるでしょう。
- タイムカードレコーダーが不要
- 月末の集計作業が不要
- 手入力が不要
商材の持つ特徴から、メディアのコンセプトは「勤怠管理の効率化」ではないでしょうか。いままで、月末になるとタイムカードの集計で追われることがなくなる点を情報コンテンツにするイメージです。
メディアコンテンツのジャンル設定では、先述したペルソナ設定を活用してターゲット層を絞りこみます。「勤怠管理システム」の場合は、対象が「勤怠管理業務を効率化したい企業の担当者」です。ペルソナに向けたジャンル設定は、ビジネスノウハウ系または経営のお役立ち情報のような要素となります。
- ビジネス
- 労務管理
- 経営(業務効率化)
オウンドメディアのジャンルが決まれば、ジャンルをテーマにしたカテゴリの設定が必要です。カテゴリは、自社商材に関連するキーワードなどからユーザー層が興味関心を持つテーマを選びます。
- 勤怠管理システム導入事例
- 労務管理システムの種類
- クラウドサービスの特徴
- ペーパーレス化
- 社内の業務効率化できる分野
- 属人的な業務一覧など
目的は、勤怠管理システムの導入契約ですが、BtoB製品は高額の契約となるため、メディア自体の見識深さが重要になります。見識のあるオウンドメディアと評価されるには、勤怠管理システムにまつわる関連した情報コンテンツを盛り込んでいくことが大事です。カテゴリの設定は、そのための布石となります。
戦略に沿った見込み客への提供価値を考える
オウンドメディアの構築は、戦略段階で設定したコンセプトを持って、見込み客に価値を提供していくことが必要です。見込み客への価値では、「どのような情報を伝えていけば見込み客が価値を高めてくれるだろうか?」という考え方を基準にします。
先ほど例にあげた勤怠管理システムの場合は、勤怠管理システムを含めた「労務管理システムの種類」や社内における「業務効率化できる分野の選定」など内容を深く広げられるでしょう。コンテンツの精度が上がれば、それだけ見込み客にとっての価値も上がります。提供価値は、リサーチと分析の上で高めていくことが大事です。
編集体制の検討・整備
オウンドメディアは、長期的なメディア運営になります。そのため、体制作りが大事なのです。編集体制の基本は、セクションの確立になります。次に更新作業を維持できるリソースを確保しましょう。実際にセクションごとに「誰がどの作業をこなしていくのか」を決めなければ始まりません。
さらに、クオリティが維持できるチェック要員もいたほうがコンテンツの質が上がります。また、企業全体でメディア運営の意義を事前に周知していくことも必要です。一度、自社の運営チームで検討をしてみて、オウンドメディアの構築前に整備をしておくことをお勧めします。
あわせて読みたい
スケジューリング
オウンドメディアの方向性が決まったら、次にスケジュール管理をしていきましょう。「1カ月に15記事投稿する」「1週間に3記事投稿する」など明確なゴールを決めて、タスクを遂行していく流れで計画を立てていきます。
オウンドメディアの場合は、PV数を目標にします。Googleアナリティクスを使って、反応のある記事の傾向を記録し、次の施策に繋げていくのです。ここまでが「企画・戦略」の段階になります。

めぐみやのWeb集客コンサルティング
Webサイトを活用して売上と利益向上を目指しませんか?
めぐみやが集客からサイト運営まで一貫してサポート致します。
オウンドメディアの構築

オウンドメディアの準備が整ったら、いよいよ構築段階に突入です。ここでは、構築する際のポイントを見ていきましょう。
市場調査と競合分析
まずはじめに行うのが市場調査と競合分析です。市場調査と競合分析は、競争力のあるオウンドメディアを構築するために不可欠です。市場の最新の動向を理解し、競合他社の強みと弱みを評価することで、自社の位置付けと差別化ポイントを明確にすることができます。さらに、キーワードリサーチを通じて、ターゲットオーディエンスが興味を持っているトピックや問題を理解し、それに基づいてコンテンツ戦略を策定することが重要です。
ドメインとホスティング
オウンドメディアの基盤となるドメインとホスティングの選定は、プロジェクトの成功に重要な役割を果たします。ドメイン名は覚えやすく、ブランドのアイデンティティを反映するものである必要があります。また、信頼性と速度を提供するホスティングサービスを選定することで、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、WEbサイトのパフォーマンスに貢献します。
Webサイトのデザインとブランディング
Webサイトのデザインとブランディングは、訪問者にプロフェッショナルで信頼できる印象を与えるために重要です。ロゴ、カラースキーム、タイポグラフィは、ブランドのアイデンティティを強化し、Webサイトの全体的な雰囲気を作り出します。さらに、直感的なナビゲーションとモバイルフレンドリーなデザインは、訪問者がWebサイトで簡単に情報を見つけ、アクションを実行できるようにします。
あわせて読みたい
Webサイトの開発
Webサイトの開発段階では、WordPressなどのコンテンツ管理システム(CMS)の選定、カスタムデザインの適用、そして必要な機能とプラグインのインストールが含まれます。この段階で重要なのは、Webサイトがユーザーフレンドリーで管理しやすいこと、そして拡張可能であることを確認することです。
テストと最適化
テストと最適化は、ユーザーエクスペリエンスを向上させるために不可欠です。Webサイトの速度テスト、ブラウザの互換性テスト、SEOの最適化、そしてユーザビリティのテストを実施し、必要に応じて修正を行います。これにより、Webサイトは検索エンジンにより良く評価され、訪問者にとっても使いやすくなります。
公開とプロモーション
Webサイトの公開とプロモーションは、オウンドメディアの認知度を高めるために重要です。Webサイトを公開し、ソーシャルメディア、メールマーケティング、そして他のオンラインマーケティング戦略を使用して、ターゲットオーディエンスにWebサイトを広めます。さらに、Google Analyticsなどのツールを使用して、Webサイトのトラフィックとエンゲージメントをモニタリングし、効果的なプロモーション戦略を継続的に調整します。
オウンドメディアの構築費用・相場
続いて構築費用の相場について簡単に触れてみたいと思います。オウンドメディアの構築費用は、プロジェクトの規模や要件、そして選択する開発会社によって大きく異なります。初めに、先述したドメイン名とホスティングサービスの費用が必要です。これらは年間で数千円から数万円が相場となっています。次に、Webサイトのデザインと開発が主な費用要因となります。カスタムデザインを望む場合、デザイン費用は数十万円から数百万円、開発費用は数十万円から数百万円以上かかることもあります。
また、SEO(検索エンジン最適化)やSNSマーケティングの取り組みも重要で、これに関連する費用も考慮する必要があります。そして、Webサイト自体のメンテナンス費用も忘れてはいけません。Webサイトの更新やトラブルシューティングなど、定期的なメンテナンスは不可欠であり、これには月額や年額での費用がかかります。

めぐみやのWeb集客コンサルティング
Webサイトを活用して売上と利益向上を目指しませんか?
めぐみやが集客からサイト運営まで一貫してサポート致します。
コンテンツ制作
さて、いよいよコンテンツの制作です。先程のオウンドメディアの構築のポイントで解説したように、すべては分析により決定することになります。つまり、思いつきではコンテンツを作らないようにするのが賢明です。コンテンツの目的や意味を深堀して、ペルソナで設定したターゲットを基準にして作っていきます。
コンテンツの制作は、次の過程で進めていきましょう。
対策キーワードの選定
対策キーワードの選定は、キーワードの検索数やユーザーの需要を重視します。ここで認識しておきたいことは、「ユーザーのニーズがあるキーワードは、競合が多くなる」という点です。
その点も踏まえて、キーワードの抽出を開始します。この時、自社の持つ顧客データなどを参考にキーワードを抽出してもいいでしょう。また、インターネットで関連ワードを追いかけたり、検索ユーザーの目的から連想したりして抽出していきます。
次に、キーワードの取捨選択となる絞り込みです。ジャンル別で分類して、投稿記事のカテゴリ分けにも活用していきましょう。最後に検索ボリュームチェックを実行して、キーワードの優先順位を決定します。その際にキーワードプランナーを使って検索ボリュームを確認することをおすすめします。
検索ボリュームで選ぶ際は、「1~100、100~1000、1000~10000」と、あいまいな範囲の表示の中から選ぶことを理解しておきましょう。
あわせて読みたい
記事構成の設定
ここで記事を作成する段階になってきます。記事を読んだ人が「どのようになっていくことが望ましいか」という観点から、記事構成を設定していきます。記事の概要を設定して、アウトラインが出来上がることで記事に「見出し」も配置できるようになります。記事全体の骨子として、次のように構成を組み立てましょう。
- ユーザーが求めていること
- その要求に対しての提案
- 実際の解決策
- 結論
記事の構成は、「見出し」を設定することによりほとんど完了します。あとは、構成に沿って記事を執筆していく流れになります。
検索意図を意識して読みやすく制作
最後に、コンテンツ制作の注意事項となる検索意図の把握について見ていきましょう。検索意図を意識した記事は、ユーザーにとって読みやすくなるからです。検索意図となる検索キーワードは、サジェストキーワードを書き出してみることで見えてきます。
ペルソナで設定した具体的なターゲットデータとすり合わせて、違和感のないように修正を加えていきます。検索意図に沿っていれば、コンテンツの整合性も取れて読みやすくなります。コンテンツを読みやすく修正するには、検索意図とつなげていくことが効果的です。
以上が、オウンドメディアの作り方のセクションごとの流れになります。ぜひ参考にしてみてください。
あわせて読みたい
オウンドメディア運用
オウンドメディアの構築を終えて、Web上に公開できれば、構築段階から運用段階へと移行します。オウンドメディアの運用では、おもに現状の分析や反応による改善をくり返していきます。また、改善だけではなく新しい情報コンテンツの追加など更新も必要です。
運用段階になると、先述したメディア運営の目標となるKPIのどの位置にいるか?KGIまでどのくらい数値が足りていないか?などが有効的な指標となります。たとえば、KPIの数値が「メディアのインプレッション数」であれば、現状の数値との差異で判断できるでしょう。このように、数値指標を判断基準にして運用することが重要です。
運用する際のポイント
運用する際のポイントは、次の通りです。
- 定期的に測定して分析
- コンセプトからズレていないか
- 想定外のアクセス流入はないか
オウンドメディアを運用する際のポイントは、作り始めたら定期的にメディアの反応を測定していくことです。さらに測定結果を分析して、「コンセプトからズレている記事や反応がないか」も確認していきましょう。そして、想定外のキーワードからのアクセスがあることも考えられます。
キーワードは、Google提供のサーチコンソールを使って、定期的に流入キーワードを確認できます。
オウンドメディアは、長期的な運営になります。基礎になる骨組みがしっかりしていないと途中で続かなくなることもあるため、慎重に進めましょう。
あわせて読みたい
コンテンツの追加・反応による改善
オウンドメディアの運用では、コンテンツの追加や追加したコンテンツの反応をみて、改善をくり返していくことになります。コンテンツは、やみくもに増やしません。メディアコンセプトに沿ったジャンルやカテゴリの情報品質を高めていくコンテンツ追加は有効です。
そのため、反応の悪い情報に対しては深く追求しないことも方法となります。反応が悪いということは、情報の需要がないと判断できるからです。
ここで誤解されやすい点は、自社の満足感ではなくユーザーの満足感が優先となります。自社メディアであるオウンドメディアに対して、「自分の会社が伝えたいことを言ってはいけないのか?」と思われますが、ユーザーが求めていなければ、それは主観的なコンテンツです。主観的なコンテンツばかりで構成されているWebサイトだと、逆に有用な記事を見つける妨げになります。そのような理由からも、コンテンツの反応を見た上での改善は必須なのです。
あわせて読みたい
解析数値を指標として修正
オウンドメディアは、検索エンジンのアクセス解析などを参考にして解析数値を見て判断する必要があります。解析数値は、メディア運用の指標です。指標を参考に、修正をしていくイメージになります。
解析は経験と知識が必要
オウンドメディアの運用では、アクセス解析やサイト診断ツールなどの活用が必要です。もし、自社で解析をする場合は専門的な知識や経験がないと、進めることができません。専門的な経験や知識とは、Webマーケティングのことです。
Webマーケティングは、より多くの消費者を集客してWebサイト上で行動を起こしてもらうための施策になります。Webマーケティングの専門家は、日々あらゆるビジネスの顧客とサービス提供者の需要と価値について実践しているため、その見解を活用することが必要です。
専門家の見解が重要
オウンドメディアの運用は、専門的なWebマーケティングの知識や経験が必要になります。自社のWeb担当者に経験があったとしても、過去に扱ってきたWebサイト運用の経験数が少なければうまくいく保証はありません。そのため、オウンドメディアの運用には、専門家の見解が重要となります。一度相談してみてはいかがでしょうか。

めぐみやのWeb集客コンサルティング
Webサイトを活用して売上と利益向上を目指しませんか?
めぐみやが集客からサイト運営まで一貫してサポート致します。
オウンドメディアの成功事例
ここまで解説してきたオウンドメディアの作り方のポイントを押さえたメディアを3つほど紹介していきましょう。すべて現在進行形で成功している事例です。それぞれのオウンドメディアのコンセプトも確認できるので、ぜひ参考にしてみてください。
キャリアサプリ
株式会社アデコが運営しているメディアです。コンセプトは、「あしたのシゴトが面白くなるウェブマガジン」となります。中心になるのが、仕事の役に立つコンテンツです。具体的にキャリア・転職情報・仕事術・ベンチャー企業の紹介などを発信しています。実際は、人材派遣会社のオウンドメディアです。
若年層のビジネスパースンをターゲットにして、注目されています。
参考URL: https://careersupli.jp/
サイボウズ式
サイボウズ株式会社が運営している面白さを前面に出したメディアです。コンセプトは、「新しい価値を生み出すチームのメディア」になります。サイボウズ式は、会社・組織・働き方に注力した情報発信と、ライフスタイル関連(生き方 家族と仕事)の情報発信です。本来、ソフトウェア開発・販売企業のオウンドメディアになります。
こちらのサイボウズ式では、インタビュー記事が会話調でスラスラ読みやすいことが特徴です。まさに引き込まれる要素のあるオウンドメディアとなるでしょう。
参考URL: https://cybozushiki.cybozu.co.jp/
アドタイ(AdverTimes)
株式会社宣伝会議のメディアになります。ネット新聞のようなデザインです。配信しているコンテンツは、マーケティングや新しいサービスの情報になります。こちらは広告代理店のオウンドメディアです。コンセプトは、「広告界の情報プラットフォーム」になります。ターゲットとなるユーザーは、広告業界関係者、企業の販促担当、広報担当、企画担当に携わる人です。
メディアの特徴は毎日更新しているニュースマガジン調な点です。
参考URL: https://www.advertimes.com/
まとめ
この記事では、オウンドメディアの正しい作り方について、順序立てて徹底した解説をしてきました。参考になりましたでしょうか。。また、実際に成功しているオウンドメディアの事例の紹介はお役に立てたでしょうか?
オウンドメディアの作成は準備段階から設定まで、「やっておくべき重要なこと」が多い施策になります。言い換えると、この「やっておくべき重要な事」を知らないで運営を続けていると一向に成果を感じられないままです。
そのため、長期目線で継続して取り組む必要があります。長期目線で取り組むには、自己判断をしないことです。自己判断で運用した場合、結果的に大きな修正をすることにもなりかねません。大きな修正を避けるためには、専門家の見解が必要です。
オウンドメディアは、作る段階で妥協をしない取り組みが正しい取り組み方になります。正しい方向性へ進むには、専門家の見解は不可欠になるでしょう。結果的に、将来的な安定した成果を期待できるのではないでしょうか。
- オウンドメディアの成功は「企画・戦略」「構築」「コンテンツ制作」ごとの計画が必要
- オウンドメディアは明確なビジネス目的を定めてその目的に沿った手順で進めることが重要
- ターゲットとなるペルソナを具体的に設定しそのペルソナに合わせたメディアコンセプトの設計が重要
オウンドメディアの作り方に関するよくあるご質問
最後によくあるご質問をいくつかご紹介致します。
みなさまのWeb集客にお役に立てば幸いです。
その他、ご不明な点がございましたら以下のリンクよりお気軽にご相談下さいませ。
無料オンライン相談はこちらからどうぞ。
Q
オウンドメディアとは何ですか?
A
オウンドメディアは、企業や個人が自ら所有・運営するメディアのことを指し、ウェブサイトやブログ、SNSアカウントなどが該当します。これにより、独自のコンテンツを提供して顧客と直接的にコミュニケーションを取ることができます。
Q
オウンドメディアのメリットは?
A
オウンドメディアのメリットは、広告費をかけずに長期的に顧客を獲得できることや、自社のブランドを強化しやすいこと、情報の配信を自在にコントロールできる点です。
Q
どのようにしてオウンドメディアを開始すればいいですか?
A
まずは目的と目標を明確に定め、その後でコンテンツのテーマやターゲット層を絞り込みます。次に、プラットフォームの選定(例:ブログ、ウェブサイト、YouTubeなど)を行い、適切なコンテンツの制作・配信を開始します。
Q
オウンドメディアのコンテンツはどう選ぶべきですか?
A
ターゲットとなる読者や視聴者のニーズや興味に応じて、価値ある情報や知識、エンターテインメントを提供する内容を選びます。また、SEO対策を意識してキーワードを取り入れると良いでしょう。
Q
オウンドメディアの更新頻度はどれくらいが良いですか?
A
更新頻度は目的に応じて変わりますが、一般的には週に1回以上の更新が望ましいとされます。しかし、質を追求することが最も重要であり、頻繁に更新するよりも価値あるコンテンツを提供することを優先すべきです。
Q
SEO対策とは何でしょうか?
A
SEO対策は、検索エンジンの検索結果で上位表示されることを目指す取り組みです。キーワード選定、内部リンクの最適化、コンテンツの質の向上などが含まれます。
Q
オウンドメディアに必要なツールはありますか?
A
はい、CMS(コンテンツ管理システム)やアクセス解析ツール、SEOチェックツール、画像編集ソフトなど、様々なツールがオウンドメディアの運営に役立ちます。
Q
オウンドメディアを運営する上での注意点は?
A
コンテンツの質を維持・向上させること、読者や視聴者のフィードバックを大切にすること、SEO対策を継続的に行うこと、デザインやUIの使いやすさを保つことなどが挙げられます。
Q
オウンドメディアの成功の秘訣は?
A
オウンドメディアの成功の秘訣は、継続的に価値あるコンテンツを提供し、読者や視聴者との信頼関係を築くことです。また、ターゲット層のニーズを正確に捉え、それに応じた内容を提供することが重要です。
Q
オウンドメディアとペイドメディア、アーンドメディアの違いは?
A
オウンドメディアは自社で所有・運営するメディア、ペイドメディアは広告などの有料での露出を得るメディア、アーンドメディアは口コミやSNSのシェアなど、第三者からの露出を得るメディアを指します。