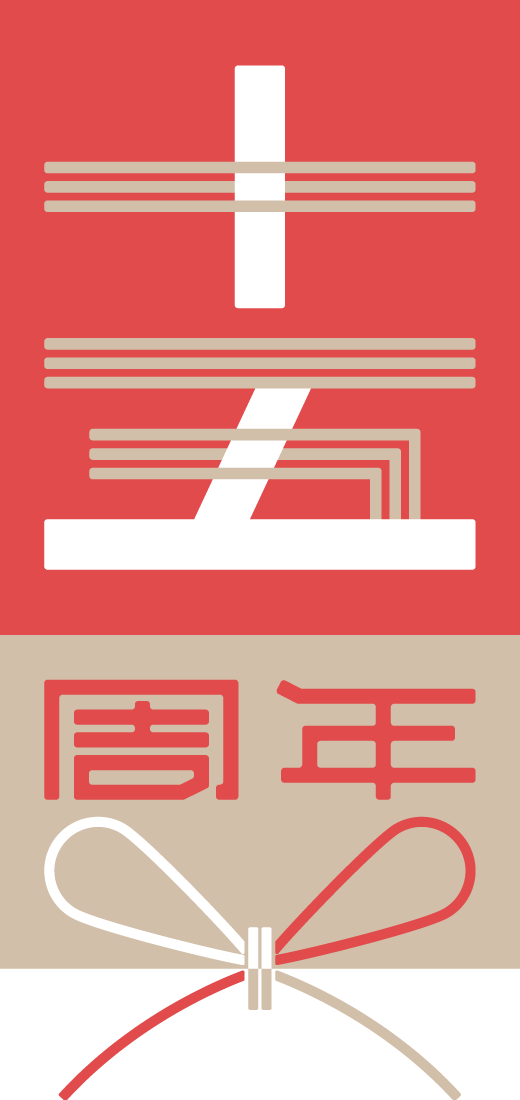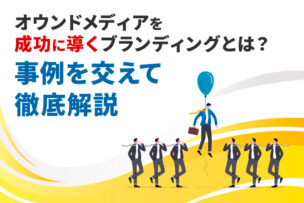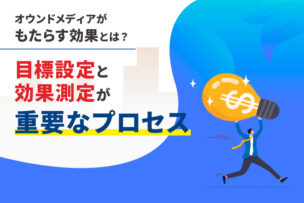記事の監修

Web集客・マーケティングの専門家として、15年間にわたり厳格な基準と緻密な戦略をもって中小企業の成功を導く。
一時的な集客の手法に頼ることなく、中長期的な効果を持続させる本質的なWeb集客の構築に注力。
『恵ある集客を。』をスローガンに掲げてクライアント様のサービスや商品の核心的な魅力を、的確にターゲットに伝えることを重視したWebサイト運用をサポート。
オウンドメディアを運用していくためには、ノウハウと人員・リソースが欠かせない要素です。特にノウハウは、運営を続けていくためには重要です。そこで、オウンドメディアを運用している企業が、ノウハウやリソース不足で成果が得られていないという方に、運用代行の必要があるのかについて解説します。
- オウンドメディアの運用代行について知りたい方
- オウンドメディアを運用代行するメリットについて知りたい方
- オウンドメディア運用代行の費用相場について知りたい方
目次
オウンドメディア運用代行とは?
オウンドメディアという言葉は今やビジネスの世界で頻繁に聞かれるようになりました。この手法は企業が自らのメディアを運営し、商品やサービスの情報を消費者に直接提供するものです。しかしこのオウンドメディア運営には専門的な知識と手間が必要です。ここで登場するのがオウンドメディア運用代行です。
オウンドメディア運用代行とは、企業が自社で持つメディア(例えば、ブログやウェブサイト、SNSなど)の運営を専門の第三者に任せるサービスです。このサービスは、コンテンツの企画から制作、公開、分析まで一連の作業を代行します。
なぜこれが必要なのかと言えば、オウンドメディア運営は専門的なスキルが要求される作業であり、多くの中小企業にとっては負担が大きいからです。SEO対策、コンテンツマーケティング、データ分析など、これら全てに精通している必要があります。
また、定期的に質の高いコンテンツを提供し続けることで、顧客とのエンゲージメントを高め、ブランドの認知度を向上させることができます。このようにオウンドメディア運営は、単なる情報発信以上の価値を持っています。
しかし、これだけの作業を社内で行うには人手とコストがかかります。そこで、コストパフォーマンスと専門性を兼ね備えたオウンドメディア運用代行が選ばれるケースが増えています。
オウンドメディア運用代行会社の選び方
続いてオウンドメディア運用代行会社の選び方についていくつか解説します。
信頼性と実績
選ぶべき最初の基準は信頼性と実績です。口コミや評判をチェックすることはもちろん、過去にどのようなプロジェクトを成功させたか、そのケーススタディをしっかりと確認するべきです。さらに、資格や認定も重要な指標となります。
サービス内容
次に考慮すべきはサービス内容です。コンテンツ作成、SEO対策、SNSマネジメント等、どのようなサービスが提供されているかを詳しく確認し、自社のニーズに合っているかを検討する必要があります。
価格とコストパフォーマンス
選ぶべき三つ目の基準は価格とコストパフォーマンスです。料金体系は明確かつ公平である必要があります。また、予算に応じてサービス内容をカスタマイズできるかも重要なポイントです。
比較と選定
複数の運用代行会社から見積もりを取り、それぞれのサービスと価格を比較しましょう。この段階でチェックリストを作成すると、選定がスムーズに進みます。実際に面談や相談をすることで、より具体的なニーズに応えてくれる企業を見つけられると思います。
契約前の注意点
契約する前には、内容をしっかりと確認する必要があります。途中解約の条件や、サポート体制も確認ポイントです。意図しないトラブルを避けるために、この部分には特に注意を払いましょう。
期的なパートナーシップを築くために
成功するためには、長期的なパートナーシップが重要です。定期的なレビューとフィードバックは、運用の品質を保つために不可欠です。また、KPIを設定し、その達成状況をモニタリングすることも大切です。

めぐみやのWeb集客コンサルティング
オウンドメディアを運用代行するメリット
先述の通りオウンドメディアの運用は、今や企業にとって欠かせないマーケティング戦略の一つです。しかし、コンテンツ作成から運用、分析まで、多くの工程と専門知識が必要です。そこで役立つのが運用代行サービスです。以下、そのメリットを詳しく解説します。
専門性の高いコンテンツ作成
運用代行サービスでは、専門家がコンテンツの作成を担当します。これによって、企業は質の高い記事や動画を提供することが可能です。SEO対策にも繋がりますので、検索エンジンでの順位のランキングアップが期待できます。また、専門家が手がけるコンテンツは、顧客からの信頼も高まるでしょう。ブランドイメージの向上は、長期的なビジネス展開にも寄与します。
時間の効率化
運用代行を利用することで、オウンドメディアの運用にかかる時間を大幅に削減できます。これにより、企業は本業に集中し、全体の生産性が高まる可能性があります。コンテンツの企画から制作、公開、運用、分析まで一手に担う運用代行サービスは、多くの企業が抱える時間的制約を解消します。
定量的な分析と改善
運用代行サービスには、専門のアナリストも含まれることもあります。これによって、パフォーマンスの定量的な分析と、それに基づく改善提案が得られます。 これは、企業が自ら行う場合には困難な場合も多く、ROI(投資対効果)を高める大きな要素となります。
フレキシビリティの向上
運用代行サービスは、市場の変動や企業のビジネス戦略に応じて柔軟に対応できます。この柔軟性により、急な市場の変化や新しいビジネスチャンスにすばやく適応することが可能です。ビジネス環境は常に変わるもの。そのため、柔軟に対応できる運用代行サービスは非常に価値があります。
コスト削減
オウンドメディアの運用を内部で行う場合、人員の確保とその教育、ツールの導入など多くのコストがかかります。しかし、運用代行サービスを用いることで、これらの初期投資や運用コストを大幅に削減することが可能です。
これらのメリットを総合すると、運用代行サービスはオウンドメディア戦略を格段に効果的かつ効率的に進める強力なオプションと言えるでしょう。
あわせて読みたい
オウンドメディア運用代行の費用相場
オウンドメディア運用は、費用がどれくらいかかるのかという疑問は多くの企業オーナーや担当者が持つ課題です。
費用の設定方法は大きく分けて二つです。一つ目は、月額固定費。これは、運用の規模や要望に応じて数十万円から数百万円までの幅があります。二つ目は成果報酬型で、特定のKPI(例:PV数、CVRなど)に応じて報酬が決まります。
オプションサービスも考慮に入れる必要があります。SEO対策やSNS連携、記事の更新頻度などによって、費用は追加されるケースが多いです。また、初期費用としてデザインや設定、コンテンツ作成にかかる費用もプラスされる場合があります。
さらに、選ぶ代行業者によって価格帯は大きく異なる可能性があります。例えば、大手の代行業者はブランド力がある分、費用が高めに設定されることが多いです。一方で、中小規模の業者やフリーランスなどは、低価格での提供が可能な場合があります。
オウンドメディアの運用で見落としがちなこと

運用時に見落とされやすい5つのポイントを紹介します。
リサーチ不足
オウンドメディアで運用が上手くいかない時のポイントとして、1つ目が「リサーチ不足」の可能性です。オウンドメディアのサイトを構築する最初の段階で、想定する顧客やその反応の見込み判断が甘くなり、リサーチ不足の結果として運用は上手くいきません。
本来、ノウハウがあればリサーチ不足を解消するための再リサーチとメディアの修正が出来ます。ですが、そのノウハウがないので難しい、もしくはリソースが追いつかず手が回らないことも少なくありません。
顧客とのコミュニケーション不足
企業にとって顧客はサービスを提供される側としてや製品を購入してもらう相手であると同時にペルソナやカスタマージャーニーマップ(ペルソナの時間毎のアクション)を作成するサンプルでもあります。これにより、全ての人を把握しなくても考えていることや求めていることを知る情報源になります。
しかし、コミュニケーションが不足していると、あらぬ方向に運用の舵を切ってしまうことがあります。よくあるケースなのですが、運用が上手くいかないとき、見た目(配置)やサイトデザインの変更、コンテンツ内容の変更でカバーしようと(依頼)します。これでは、顧客の心理や需要にアプローチすることはできません。
運用していくだけのノウハウ不足
オウンドメディアは、他のメディア(広告やWebコンテンツ)とは違い、明確な手段や手順・方法がありません。これまで取り上げられているどの方法も事例であり、1つの方法を示したものでしかないのです。オウンドメディアを運営する企業の捉え方には実にさまざまです。現在のコンテンツマーケティング業界では、何かの真似をしたり方法だけをなぞるやり方では通用しない厳しい状況です。
その点、オウンドメディアは1つのやり方にとらわれず、ブランディングや個性を発揮して他にないやり方で独自コンテンツを運営していくことが可能でしょう。ところが、新たなコンテンツマーケティングを取り入れて、成功例に続きたい企業が手を出して失敗してしまうケースが後を絶ちません。
多くの企業はノウハウ不足で運用を途中で放棄してしまいます。結果、挫折しやすいメディアとしての印象が強まっています。オウンドメディアは一度成功すれば良いですが、失敗すれば立て直しに時間がかかるからです。
人材・リソース不足
オウンドメディアを運営する際に、リソースの不足を想定できない企業もまた多いのが事実です。コンテンツを作って公開していくだけしか想定せず、企画や取材、維持・運営にかかる人手を全く予想していないことです。
また、ノウハウもあり、継続的な運用が効果をもたらすと確信していても、リソースが足りないせいで運用が困難になってしまうケースがあります。
運用することが目的になってしまう(本末転倒する)
間違った運用方法として、オウンドメディアを運用するのが目的化してしまうことです。企業は立ち上げの際に結果や目的を決めて運用を開始しますが、具体的な結果につながる手段を上手くメディアに生かすことが出来ないため、運用する目的だけでコンテンツを作り続けます。結局のところ、運用を継続すれば状況を打破できるからではなく、続けることで何とかできないかを探る、現状をキープ(実際はダウン)しているに過ぎません。
運用の目的化を脱するためには、何が必要でしょうか?まずはマーケティングでよく使われる「ファネル」を確認して、現在地を確かめる作業をしましょう。ファネルとは、運営のフェーズが今どこにあるのかを知るための指標です。最近ではオウンドメディアを運営する際の企画やメディアの軌道修正のために用いられます。
いま顧客がどの段階にあるのか、客観的に見定めます。認知する段階か、それとも比較検討か、あるいは購入からの継続か。今すべきことを明瞭にして、運用改善からの目的への到達まで何をするのか具体性を高めていくのです。
あわせて読みたい
集客を成果につなげられない原因と運用代行による解決
成果につながらないオウンドメディアを改善する方法として、運用代行がよく利用されます。実際の企業の状態や運用方針などを加味して、問題点や運用代行の優れた点や必要性について確認し、検討しましょう。
真っ白なコンテンツ制作に目的と顧客からのフィードバックを取り入れる
真っ白なコンテンツとは、PR・購買・サービス利用につながる部分が弱いコンテンツのことです。趣味で作られるサイトや個人ブログにいのが特徴です。
オウンドメディアで真っ白なコンテンツばかりを提供していれば集客も得られるかもしれません。しかし、戦略上の問題から、真っ白なコンテンツに集まってきた顧客が、どれだけ自社製品やサービスに興味を示して、アクションを起こすのかを考えると、まず効果を期待できないでしょう。
戦略的にコンテンツを作り、どういう心理的変化やニーズを作り出すかの視点が欠けることで起こりえる問題です。オウンドメディアは直接購入を促すメディアではないため、こうしたコンテンツが生まれやすいです。しかし、潜在顧客を育てるメディアとはいえ、目標を考慮に入れて真っ白なコンテンツを作るのと何も考えずに作るのでは意味が違います。そこで必要なのが、顧客の意見のフィードバックです。
オウンドメディアの場合、真っ白なコンテンツで集まる客層と、自社が想定する購買までいたる客に乖離がある場合は、コンテンツや運営方針について見直すことで問題を解消します。このように、真っ白なコンテンツに対策を加えるためのフィードバックを取り入れることで、現在の状況を正確に把握します。
ノウハウが足りないなら?運用力を補う
オウンドメディア運用が目指すのは、誰が何についてコンテンツを書き、それが利益を生み出す流れを作ることです。運営目標・目的と言い換えても良いでしょう。オウンドメディアの運用上、ブランディングもとても大切ですが、それにばかり気をとられて、何のために認知させようとしているのかわからなくなります。それを防ぐために、最終目標を明確にします。
また、自社のサイトから新規でドメインを取得する場合、最低でも半年~は検索サイトに効果が出る時間がかかるのを覚悟する必要があります。結果が出るのは、そこからさらに見込み客を獲得してファンを増やし、製品購入や消費に繋げて始めてそれが結果に繋がります。
運用代行で補えるのは、ノウハウ、運用計画の策定・実行、計画の結果と分析からの検証、長期運用にかかる負担軽減などです。運営未経験でノウハウある人材がほとんどいないのであれば、代行運用は有用でしょう。
現場のリソース不足なら?リソースを代行で補う
一度始めると、コンテンツの更新にサイト運営、セキュリティ更新、Pdcaサイクルによる改善など多くの業務が発生します。インハウス(自社運用)で全てを補うことは難しいでしょう。特に、社内の体制が整わない、外部に任せるか結論が出ていないときに運用するのは、あまりおすすめできません。
その反面、外部に一部を運用代行を依頼することで効率的な運用を実現します。担当者が少なくても運用が可能になる数少ない方法です。したがって、他の業務を兼任している担当者の多い企業であったとしても運営を続けることが出来ます。

めぐみやのWeb集客コンサルティング
Webサイトを活用して売上と利益向上を目指しませんか?
めぐみやが集客からサイト運営まで一貫してサポート致します。
分析・評価と計画を正しく運用する
ユーザー(見込み客・ファン)を理解し、反応を見てコンテンツに変化をつけるのが分析結果からの仮説と検証です。仮説を立てるためには、分析の指標が必要です。すでに挙げたPdcaサイクル(計画~改善、実行までまとめて運用する方法)もその1つです。
加えて、オウンドメディアの運用で知っておきたい指標は、
の2つです。
どちらも目標を達成するための企業業績を確認する指標です。Kpiは中間目標です。この中間目標に対して、KgiのgはGoal、つまり最終目標と考えましょう。どちらも必要ですが、運用について問題を解消したり今後の方向性を判断するならば、まずはKpiの分析です。Kpiを検討する場合、図によるツリーやフロー形式にして、細かい部分を書き出していきます。
オウンドメディアのKpi指標の見方
●成果が得られない原因を見る指標
●具体的な数値による指標
- お問い合わせの数
- サービスや資料のダウンロード数
- メールマガジンや会員登録数
- 全体の見込み客・ファンの想定数
Google提供のアナリティクスは、導入したならアクセスやサイト移動、購入にいたるコンバージョンまでの過程をたどる数値として活用します。上手く活用すればどのくらいの集客が出来ていて、見込み客が何人いるのか想定数を算出できます。Kpiの指標と合わせて確認しましょう。
オウンドメディアに必要な分析とは?
オウンドメディアを構築している企業には大きく分けて二つあります。BtoB(Business to business)とBtoC(Business to Consumer)です。BtoBは企業に向けて、BtoCは主に顧客(消費者=Consumer)に向けて、サービスや製品の提供をしています。BtoBは企業間取引とも呼称されます。
企業において取引形態ごとの購入・サービス利用に影響する数値
●BtoB
- お問い合わせの数
- サービスや資料のダウンロード数
●BtoC
自社がどの取引を中心とした企業であるのかを知り、オウンドメディア運営にとって効果的な分析の指標項目を探しましょう。
結果の分析から計画を方向修正する
例えば、オウンドメディアのコンテンツにアクセスした顧客がお問い合わせをすれば、お問い合わせ数を誘導したのがどのコンテンツか分かります。ページビュー(PV)数が思ったように増えないのは、キーワードのボリュームが原因なのか、それともSeoが不十分なのか、分析により把握できます。
Googleではキーワードプランナーなどボリュームを把握するツールには事欠きません。検索順位やクリックの数、滞在時間などを総合的に判断して、コンテンツを充実させるべきか、Seoに力を入れるべきかを適宜判断します。
必要なときに必要なものを提供するのがコンテンツマーケティングでは基本です。それも、オウンドメディアによる役立つ情報でファンを得られるように実践し続ける必要があります。以上に挙げた項目の分析結果から得られた情報は、計画を修正・再考するのに活用しましょう。
まとめ
オウンドメディアを運用代行するポイントについて紹介しました。リソースやノウハウの不足が見られるようであれば、運用代行を検討することも業務の効率化には必要なこです。効果の高い方法で、運用を続けるためのヒントを指標や分析によって得られるようにしましょう。

めぐみやのWeb集客コンサルティング
Webサイトを活用して売上と利益向上を目指しませんか?
めぐみやが集客からサイト運営まで一貫してサポート致します。
- オウンドメディア運用代行とはコンテンツ作成から分析までを専門家が行うサービス
- 運用代行利用により時間の効率化とコスト削減が可能
- 専門性の高いコンテンツによりSEO対策効果とブランドイメージ向上が期待できる
オウンドメディアの運用代行に関するよくあるご質問
最後によくあるご質問をいくつかご紹介致します。
みなさまのWeb集客にお役に立てば幸いです。
その他、ご不明な点がございましたら以下のリンクよりお気軽にご相談下さいませ。
無料オンライン相談はこちらからどうぞ。
Q
オウンドメディアとは何ですか?
A
オウンドメディアとは、企業や団体が自ら所有・運用するメディアのことを指します。主に、企業の公式ウェブサイトやブログ、SNSアカウントなどが該当します。
Q
オウンドメディアの運用代行とは?
A
オウンドメディアの運用代行とは、企業の代わりにオウンドメディアのコンテンツ制作や更新、運営全般を行ってくれるサービスを指します。
Q
運用代行を利用するメリットは?
A
運用代行を利用するメリットは、専門的な知識が必要なコンテンツ制作やSEO対策を専門家に任せられること、定期的な更新が保証されること、社内リソースを他の業務に集中できることなどがあります。
Q
運用代行の料金はどれくらい?
A
運用代行の料金は、サービス内容や提供会社によって異なりますが、月額数万円から数十万円の範囲が一般的です。
Q
どのような業者を選べば良いの?
A
信頼性の高い実績がある業者や、自社のニーズに合ったサービス内容を提供している業者を選ぶことが大切です。
Q
オウンドメディア運用代行の契約期間は?
A
業者によって異なりますが、月額での契約や一定期間の契約など、様々な契約形態があります。
Q
オウンドメディアとペイドメディアの違いは?
A
オウンドメディアは自社が所有するメディアであり、ペイドメディアは広告などの有料メディアを指します。オウンドメディアは長期的なブランド構築に有効であり、ペイドメディアは短期的な効果が期待できます。
Q
オウンドメディアの主な目的は何ですか?
A
オウンドメディアの主な目的は、ブランドの認知度向上、顧客との関係構築、信頼性の確立、SEO効果の向上などがあります。
Q
運用代行を始める際の注意点は?
A
運用代行を始める際の注意点は、明確な目的を設定すること、業者とのコミュニケーションを密にすること、契約内容をしっかりと確認することなどがあります。