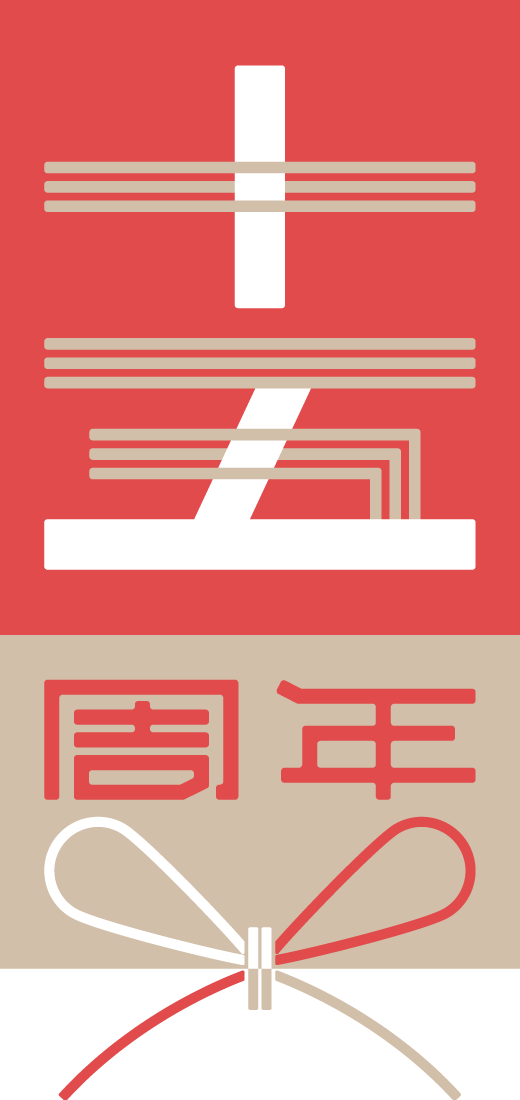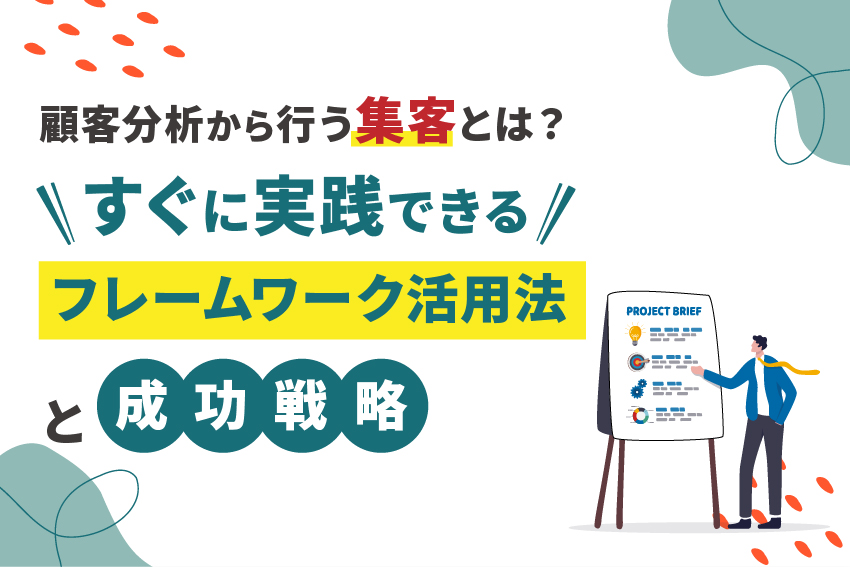記事の監修

Web集客・マーケティングの専門家として、15年間にわたり厳格な基準と緻密な戦略をもって中小企業の成功を導く。
一時的な集客の手法に頼ることなく、中長期的な効果を持続させる本質的なWeb集客の構築に注力。
『恵ある集客を。』をスローガンに掲げてクライアント様のサービスや商品の核心的な魅力を、的確にターゲットに伝えることを重視したWebサイト運用をサポート。
ビジネスにおいて「顧客とは?」と言われ、単なるお客様としか答えられない場合は、今以上にビジネスを拡大していくことが難しくなるでしょう。その理由は「現代の顧客は、自分の意思で商品やサービスを選んで購入できる時代」だからです。インターネットが普及していなかった頃ならば、顧客心理を理解していなくても、商品やサービスが大量に売れたことでしょう。
しかし、インターネットが普及している現代では、個人がスマートフォンなどのモバイル端末によって情報の入手が可能です。そのため、現代では顧客を理解しなければビジネスが成り立ちません。古き良き時代のモノを作れば飛ぶように売れる状況は終わったのです。時代の変化に合わせるためには、顧客分析が必要になります。
この記事では、顧客分析に必要な4つの理解と、顧客分析によって、目的を実現するフレームワークの活用法をご紹介します。自社の顧客分析に取り組もうとしているビジネスオーナーにとって、ヒントとなることでしょう。
- 顧客分析について知りたい方
- 顧客分析の実施方法を知りたい方
- 顧客分析をWeb集客に活用したい方
目次
顧客分析とは?
まずはじめに顧客分析の概要について簡単に説明致します。
顧客分析とは、企業が提供する製品やサービスに対する顧客のニーズ、行動、特性を理解するためのプロセスです。この分析は、マーケティング戦略の策定や製品開発、サービス改善に不可欠な要素とされています。
顧客分析は、企業と顧客との関係を深め、最終的には収益向上に寄与するものです。具体的には、顧客の年齢、性別、地域、購入履歴、興味・趣味など多岐にわたるデータを集め、それを解析します。この解析結果をもとに、より効果的なマーケティング活動や、顧客満足度の向上が図られます。
顧客分析の主な手法
顧客分析を行う際にはいくつかの主要な手法があります。第一にデータ収集です。 アンケート、インタビュー、オンライン行動追跡など、さまざまな方法で顧客情報を収集します。
次にセグメンテーションがあります。これは、収集したデータを特定の基準、例えば年齢や地域、興味などで分類する作業です。セグメンテーションによって、マーケティングメッセージや製品開発が高度にパーソナライズされます。
最後にデータ解析があります。ここでは統計的手法やAI・機械学習を用いて顧客の行動やニーズを解明します。
顧客分析の活用事例
顧客分析は多くの企業で活用されていますが、その具体的な事例にはどのようなものがあるでしょうか。一つはマーケティング戦略への適用です。 顧客分析によって明らかになった顧客の特性やニーズに合わせて、ターゲティングされた広告やプロモーションが可能となります。
また、製品開発やサービス改善にもこの分析は非常に有用です。例えば、特定の顧客層が求めている機能やサービスを提供することで、顧客満足度が向上しリテンション(継続利用率)も高まる可能性があります。
では、なぜ顧客分析が広く活用されているのでしょうか。
なぜ今、顧客分析が必要なのか?
「集客成功や商品購入に繋げるためには顧客分析が重要である」と言われ、実際に多くの企業が顧客分析を活用したマーケティング戦略を立て、あらゆる施策の必要要素としています。
では、なぜこれほどまでに顧客分析が大切なのでしょうか?大きな要因としては「顧客ニーズの変化とデジタル化が進んだ現代の情勢」が挙げられます。
顧客ニーズの多様化と市場の変化
インターネットが普及し、情報社会となった現代において、顧客のニーズがより細分化し、複雑化していることが顧客分析が必要な大きな要因の一つです。従来は、マス広告や画一的なプロモーションが主流でした。しかし、これまでのマーケティング戦略やプロモーションだけでは、顧客に響かなくなっているのです。
また、多くの競合他社が出現していることで、より効率的なプロモーションを行うには「顧客に対する深い理解」が必要不可欠となっています。顧客一人ひとりの洗剤的なニーズや購買行動の背景をしっかりと把握することで、的確かつ効率的なアプローチが可能となるのです。
データに基づいた意思決定の必要性
さらに現代では、Webを活用してさまざまなデータが簡単に収集できるようになりました。これまでのような勘や経験に頼るだけでなく、客観的なデータに基づいた戦略を立てることが重要視されているのです。
データを活用したマーケティング戦略や改善施策は、より精度が高く、業務効率化に繋がります。限られた資源を最大限に活用し、成果を出しやすい環境を構築できるのです。
あわせて読みたい
顧客分析には目的がある
ビジネスにおいて顧客分析は、明確な目的がなければ効率的に進められません。例えば「自社の目標はどのくらいの売上を目指しているのか」「どのような成長を描いているのか」といった、具体的なゴールを設定することが重要です。
顧客分析は、これらの目的を達成するために実行します。顧客分析で明確にしておくべき目的とは、次の3つです。
- 現状を把握して課題を見つけるため
- 施策を決めるため
- 売上と顧客満足度を向上させるため
言い換えると、顧客を深く理解していなければ「売上を増やすことができない」と言っても過言ではありません。それほど、顧客分析はビジネスにおいて重要な指標となるのです。
それでは、次の項から、顧客分析の3つの目的を解説します。
現状を正確に把握して課題を見つける
ビジネスの現状は、自社の現状を市場目線や顧客目線、内情から判断します。顧客分析を行う目的の1つとして、現状を把握することがもっとも重要な準備となるでしょう。現状を知るには、扱う商品やサービスが「なぜ売れたのか?」「なぜ売れないのか?」について分析追求していく必要があります。
顧客分析ができない企業の場合、売れた理由や売れない理由まで深く追求していないことが考えられるでしょう。現状を知るためには「何となく」ではなく、明確な数値による分析が必要です。特に仕入れを必要とするビジネスの場合は、数値判断によりコスト管理の指標となるでしょう。
自社ビジネスの全体像を知るため
現状を知る理由は、自社ビジネスの全体像を理解するひとつの指標だからです。自社のビジネスを取りまく内的要因から外的要因まですべてを把握しておく必要があります。ポイントは、自社ビジネスに客観的な問いかけをしてみることです。主語を商品やサービスに置いて次のように問いかけてみます。
- 自社商品はいつの時期に売れるか?
- 自社商品はどこだったら売れるか?
- 自社商品は誰だったら買ってくれるか?
- 自社商品は何の目的で購入されるのか?
- 自社商品はどのような方法で購入されるのか?
このように、自社商品やサービスを主語にして問いかけ、自社ビジネスの全体像を追求します。例えば、防犯ブザーを製造する企業であれば次のように追求することもできるでしょう。
- ウチで開発した防犯ブザーは3月~4月にかけて売れる→引っ越しなど新生活が要因
- ウチで開発した防犯ブザーは詳細に説明してくれる専門店
- ウチで開発した防犯ブザーは新生活を始める大学に入学する人や新卒者など
- ウチで開発した防犯ブザーは近所付き合いのない都会の防犯対策を目的に購入される
- ウチで開発した防犯ブザーはネットショップ経由で売れる
問いかけに対して、具体的な商品名やサービス名を当てはめるだけで、自社ビジネスの顧客像が見えてきます。この分析は、基本的な手法で単なる「いつ、どこで、誰が、何の目的で、どのような方法で」にあてはめただけの取り組みです。このように顧客分析は、問いかけと答えを明確にして、自社ビジネスの顧客をあらゆる角度から具体化します。
自社ビジネスの課題を見つけるため
自社ビジネスの全体像を知った後は、課題となっている要素を正確に把握することが求められます。自社ビジネスの課題を見つけるための具体的な方法は、自社と顧客との接点(顧客体験の各段階)に着目することがポイントです。
自社が把握している強み・弱みと、実際の顧客体験とのギャップがないかを測定・分析します。例えば、「購入後のサポート体制が不十分」「Webサイトの使い勝手が悪い」といった課題は、顧客分析で明らかになる課題の一例です。
顧客の行動やアンケート結果、口コミやレビューといったデータを詳細に分析することで、自社が抱えている具体的な課題が発見できます。これは、効果的な改善策を検討し、実行するためには欠かせないフェーズです。
施策を決める
顧客分析の目的は、現状から施策を決める判断材料になります。現状を把握できていても、現状を踏まえた集客が展開されていなければ、顧客は獲得できません。顧客が求めるニーズを理解して、そのニーズを基準に施策を決めます。
また、決めた施策は実行しなければ、効果を判断することは不可能です。施策の実行結果は、そのまま継続したり、改善したりを繰り返すことで、方向性が合っているか判断できるようになります。つまり、施策はPDCAを回すことで磨かれていくわけです。
効率的なマーケティング施策を立案するため
マーケティング施策を効率よく進めるには、PDCAサイクルを回して精度を高めていくことが大事です。ただし、PDCAサイクルを回す前提で、ビジネスの課題を明確にしておかなければ的外れな施策になります。
また、進めている施策について「なぜこの方法をとるのか」の理解がなければレスポンスは悪くなります。マーケティング施策立案を効率よく進めるには、解決する課題(現状)を明確にしましょう。
売上と顧客満足度を向上させる
ここまで紹介してきた「現状を理解し、課題を見つけ、施策を立てる」という段取りを繰り返し実行していくと、次第に施策による効果測定と評価が可能となります。「この施策は効果がなかった」「この施策は効果が出ている」などと、具体的なデータに基づいて判断できるようになるはずです。これらの評価によって、効果のある施策だけを絞って実施することができるようになります。
ここで重要なのは「効果のない施策を実行した失敗経験があるからこそ、効果のある施策が生きてくる」という点です。つまり、顧客分析の最終的な目的は「いかに効率的で効果的な施策を生み出せるか」になります。失敗したからこそ、次に活かすというプロセスを繰り返し行うことで、無駄のない集客活動と高い成果を実現できるのです。
そして、高い集客効果が得られた結果、売上や顧客満足度が向上し、ビジネスが右肩上がりに成長していくでしょう。顧客分析は、単なるデータ収集ではなく、事業成長へ向かう道しるべとなるのです。
あわせて読みたい
顧客の購買行動と満足度を高めるためのポイント
ムダのない集客で実現できる成果とは、顧客の購買行動と満足度を高められることです。では、売上が必然的に増える顧客の購買行動と満足度を高める具体的なポイントとは何でしょうか。
顧客の特徴やニーズの理解
顧客の購買行動と満足度を高める具体的なポイントは、顧客がどのような人物なのかを知るための特徴を理解することが考えられます。また、その顧客のニーズも理解しなければ満足度を高められないでしょう。顧客像を具体化するには、ターゲット設定で活用する「ペルソナ設定」が有効です。ペルソナ設定によって、「ある顧客」から「特定の誰か」まで絞り込んだ具体的な訴求ができます。さらに、設定したペルソナが求めているニーズも明確になるでしょう。
顧客の行動を明確に把握
顧客の購買行動と満足度を高める具体的なポイントは、顧客の行動を明確に把握することです。顧客は、どうして自社商品を購入するのか?を一連の行動プロセスで把握します。マーケティングの観点では、カスタマージャーニー(顧客体験)をマップ化したものが使われます。カスタマージャーニーマップは、顧客心理の変容ポイントごとの行動の変化を可視化できるフレームワークです。
顧客心理を理解
顧客の特徴やニーズ、行動を具体化できれば、それらを整理することで顧客心理を理解できます。顧客心理を理解できれば、何を提供すれば響くかを推測できるため、効率の良い集客を実現できるでしょう。その理由は、後述する長期的な運営を可能にしたコンテンツマーケティングへとつながります。
あわせて読みたい
顧客分析で理解すべき4つのこと

顧客分析の目的について、3つに分けて説明してきました。それでは、顧客分析で理解すべき重要なポイントについて、4つに分けて解説しましょう。解説の具体例として、「農薬を散布できるドローン」を商品として取り扱う企業を想定してみます。
①顧客は誰か?
顧客分析を理解するには、「自社の顧客は誰か?」を知る必要があります。どのような顧客層であれば「自社の商品やサービスに満足してくれるのか?」を理解して、施策に反映させることが必要です。顧客を定義するためには、ターゲティングを施して、自社の顧客層を可視化します。
ターゲティング
ターゲティングとは、セグメンテーション(属性)分析をして自社の市場を細分化する分析です。細分化された市場から、ターゲットを絞り込んでいく顧客層の具体化です。
●セグメンテーション分析
顧客層を具体化していくためには、セグメンテーション分析が欠かせません。顧客ニーズの多様化がすすむ現代において、セグメンテーション分析は必要不可欠なマーケティング手法となります。セグメンテーション分析は、セグメンテーション変数にそって属性を絞りこんでいくのです。具体的な変数について解説しましょう。
セグメンテーション変数の中でも、主に次のようなセグメンテーションを軸にして、ターゲットを絞り込んでいきます。
- 地域・気候・人口などを絞りこむ地理的変数
- 年齢・性別・身分などを絞りこむ人口動態変数
- 性格・価値観・生活様式などを絞りこむ心理的変数
- 活動内容などを絞りこむ行動変数
セグメンテーション分析は、変数ごとに属性を細分化することです。属性を細分化して、ターゲットとなる「誰か」を明確にします。
「農薬を散布できるドローン」を取り扱うビジネスの例から、次のような顧客層を想定してみましょう。
- 地理的変数→新潟県山間部の雪の多い地域に住む少子高齢化のすすむ過疎地区
- 人口動態変数→農業を営む50代男性
- 心理的変数→地元愛が強く農業の発展に熱心なバイタリティ溢れる人
- 行動変数→最近やっとスマートフォンで情報収集できるようになった
変数から、ある程度のドローンビジネスの顧客層が想像できるようになりました。
●ペルソナ設定
先ほど、顧客の購買行動と満足度を高める方法として、ペルソナ設定が有効だとお伝えしました。ここでは、ペルソナの具体的な設定方法のコツを解説します。
ペルソナを設定する際は、自社商品を利用する「顧客の心理」を正しく理解し把握することが重要です。そのためには「実際にいそうな顧客」をいかに具体化できるかがカギとなります。単に年齢や性別といった基本的な情報だけでなく、普段どのような生活をしているのか、どのような情報に触れているのか、何を感じ、何を考えているのかといった、顧客の心理を深い部分まで追求する必要があります。
まずは、ペルソナに当てはまる人物を一人抽出しましょう。特定の一人の顧客を思い浮かべて、一旦ペルソナ像に設定したら、続いては周辺人物へのインタビューやアンケート、観察といった多角的な方法で、徹底した情報収集を行います。休日の過ごし方、好きな本やメディア、最近チャレンジしていること、日々の生活で抱えている悩み、そして検索するキーワードまで、ありとあらゆる情報を収集します。
情報が収集できたら、これらのデータを踏まえた詳細なペルソナ像を設定します。顧客の情報収集をしていく中で、仮説と検証を繰り返しながら修正を加えていき、最終的に自社にとって最適なペルソナを築き上げていきましょう。
ペルソナがどのような成功体験を望み、どのようなコンプレックスを抱えているのか。どんな人生を送りたいと考えているのか。ペルソナの特徴を3つ程度にまとめて書き出せるようにしておくと、社内で共有しやすくなります。
②顧客は何を求めている?
次にターゲットを絞って設定した顧客が「何を求めているのか?」について、理解することが必要です。「顧客が何を求めているのか?」理解するためには、顧客ニーズを深堀りしていきます。ここから、顧客の理解を深めるための分析手法をあらゆる角度で活用していきます。
顧客ニーズを知る
顧客のニーズを知ることにより、「どのような状態に高い価値を感じるのか」を基準とした施策が立てられるのです。顧客ニーズの深掘りには、フレームワークを使った3C分析を活用します。
●フレームワークの3C分析
3C分析は、自社商品やサービスの市場規模や顧客を示すCustomerの「C」と自社の競合となるConpetitorの「C」、自社の現状を示すCompanyの「C」、それぞれの頭文字「C」をとって3C分析と呼ばれる環境分析手法です。
先ほどのドローンビジネスの例を3C分析に落としこんでみましょう。
- 顧客→少子高齢化が進む地方で農業を営む50代男性
- 競合→農薬散布ドローンを販売する企業
- 現状→農薬散布テストを5年間で3,000回行った実績がある
具体例から、顧客の50代男性とドローンビジネスにおける自社の現状が近い状態にあることが見えてきます。
顧客の市場規模を知る
3C分析では、顧客層を理解することはできますが、商品の市場規模については、より深く分析する必要があるでしょう。市場規模の分析は、市場の成長性を客観的に判断していくのです。市場規模を調べるためには、国税調査によりデータ化された各省庁や業界団体などにより発表されています。
ターゲティングと環境分析により、明確になった顧客に対して、市場規模を理解して自分のビジネスの立ち位置を理解しましょう。
●フレームワークの4P分析
市場規模を理解したうえで、マーケティングミックスにより実行戦略を設定します。4P分析は、実行プロセスを決めるための分析です。4P分析は、「Product(製品)」、「Price(価格)」、「Place(流通)」、「Promotion(販売促進)」の頭文字をとって4P分析といいます。
- 製品→ターゲットに向けて自社の強みを生かしてどのように売るのか
- 価格→ターゲットはいくらで購入してくれるのか?価格設定
- 販売促進→ターゲットにどのような提案をしていくか(広告・Webサイト・SNS)
- 流通→ターゲットに届けるための経路や手段
4P分析に「農薬散布ドローン」の例をあてはめてみましょう。
- 製品→実行テストに合格した機能性に優れた農薬散布ドローン
- 価格→農薬散布にかかる委託費用の半分以下(例:300万→150万円以下)
- 販売促進→スマートフォン検索で確認できる広告
- 流通→広告からWebサイトで情報提供して共感をもってもらう
4P 分析により、ターゲットとなる新潟県在住の50代男性に向けて、広告を出稿し、Webサイトに誘導することを設定しました。これにより、Webサイトがターゲット層の共感を高めるコンテンツで構成されていることが必要となります。
顧客の購買プロセスを知る
Webサイトのコンテンツ構成の前に、顧客の購買意思がどのように決定されていくか?購買プロセスを理解することが大切です。購買プロセスを理解するためには、AIDASの法則を活用します。
●カスタマージャーニーマップ
顧客の購買プロセスを知るためには、カスタマージャーニーマップが有効です。カスタマージャーニーマップとは、ペルソナが自社の商品やサービスを認識し、最終的に購入に至るまでの「体験プロセス」を、時系列のストーリーで図示したものです。これによって、企業は顧客目線で購買までの体験を具体的に把握できるようになります。
カスタマージャーニーマップの作成で特に大切なのは、各段階における顧客の心理状況に着目すること、そしてネガティブな要素をしっかりと可視化することです。顧客が抱えている悩みや課題について、どのような心理状態で、どのような方法で解決しようとするのかを深く探ります。顧客が実際に経験する具体的な行動と感情を設計し、それぞれのプロセスをスムーズに進めてもらうことが、最終的なコンバージョン率の向上に繋がるのです。
具体的な作成方法として、まずはペルソナの体験プロセスをいくつかの段階に分けて描き出します。各段階での詳細な行動と、顧客が接触する「タッチポイント」に着目してみてください。タッチポイントとは、例えばWebサイトやブログ記事、アプリ、予約システム、実店舗、チラシ、クーポン、SNSなどが挙げられます。
そして各段階で顧客がどのようなことを感じているのか、ポジティブな心理とネガティブな心理をそれぞれ書き出し、分析します。ここで浮上してくるネガティブな要素こそが、顧客が抱えている真の課題となるのです。分析後は、これらのニーズを満たし、課題を解決するための具体的な方法を検討する作業に移ります。顧客が一連のプロセスの中で判断をするタイミング、その判断のポイントを可視化することが、カスタマージャーニーマップの主な目的です。
●AIDASの法則
マーケティング施策のひとつAIDASの法則は、次の5つの項目にそったプロセスの理解です。
- Attention(注意)
- Interest(興味)
- Desire(欲求)
- Action(行動)
- Satisfaction(満足)
5つの項目の頭文字をとってAIDASの法則と呼ばれ、商品やサービスが購入されるまでのプロセスを項目を参考にして、設定していきます。広告から誘導した先のランディングページなどで、消費者の購買プロセスにそって活用される場合が多いでしょう。
③新規顧客の分析
いままでの分析手法の解説から、自社商品やサービスにあった顧客の分析において、顧客像と市場、購買プロセスまでの説明をしてきました。では顧客を「新規顧客」と「既存顧客」に分けて分析する場合は、どのようにすればよいのでしょうか?
Webサイトへの流入経路を知る
新規顧客を理解するためには、Webサイトの流入経路を知ることが必要です。Webサイトの流入経路を知るためには、Webサイトの診断指標となるアクセス解析を活用します。
●アクセス解析
アクセス解析とは、Webサイトに訪問したユーザーのインターネット上における流入経路を知る数値指標の分析です。アクセス解析を活用することにより、Webサイトを訪問する新規顧客の数と動向を理解できるでしょう。
具体的には、Webサイトに訪れた新規訪問者の数値指標のことをユニークユーザー(UU)と言います。ユニークユーザーの動向を分析できれば、新規顧客に向けた施策を立てる参考となるのです。アクセス解析を実行する場合は、Webサイトなどに解析タグを設置する解析ツールを活用します。
●コンテンツ分析・改善
新規顧客に向けた施策として、見込み客が求めるコンテンツを提供する必要があります。新規顧客の行動から、コンテンツの品質を分析して、Webサイトの改善に取り組んでいくことが重要です。
④既存顧客の分析
4つ目の顧客理解のポイントは、既存顧客の分析になります。既存顧客の場合は、リピーター分析となり、すでに実行されている顧客行動の実績から購買行動を分析して、顧客にランク付けをしていくことが可能です。
購買行動の分析
購買行動の分析には、既存顧客の購買実績を評価するRFM分析と、顧客が「どんな商品やサービスを購入したか」判断指標となるCTB分析の2つがあります。
●RFM分析
RFM分析は、次の3つを評価指標とする購買実績を分析する方法です。
- Recency(最後に購入した日)
- Frequency(訪問回数)
- Monetary(購入金額)
上記3項目の頭文字をとってRFM分析と呼ばれています。RFM分析では、3つの視点により顧客を分類して、グループ化した結果から既存顧客に向けた施策を立てていくのです。RFM分析の特徴は、最後に購入した直近の購買行動が判断できるため、今後を見すえた施策の参考になります。
●CTB分析
CTB分析は、次の3項目を購買予測に活用したデータ分析です。
- Category(商品やサービスのジャンル)
- Taste(商品やサービスの形態)
- Brand(商品やサービスのブランド)
3項目の頭文字をとって、CTB分析といいます。CTB分析では、3つの既存顧客の購買実績から、もっとも需要の高い商品やサービスを選定することができるでしょう。
顧客にランクをつける
既存顧客の購買実績を分析することにより、既存顧客にランクをつけて振り分けることもできます。先ほど紹介したRFM分析により、顧客ランクをつけることも可能です。さらに購買金額から判断するデシル分析があります。
●デシル分析
デシル分析は、すべての既存顧客を10分割して、分割したデータを評価内容にそって並べかえて判断する分析手法です。たとえば、500人の既存顧客がいれば、500人を10分割します。1つの分割されたグループを1デシルという単位でグループ化して、10のグループの状態を評価するのです。
評価内容は、「購入金額の多い順」で10分割したり、「購入金額の低い順」で10分割したり、様々な要素から分析できます。
●行動トレンド分析
もし、自社が既存顧客を複数抱えている事業を継続しているのであれば、その既存顧客の中の上顧客を選定できるはずです。上顧客は、既存顧客の中でも自社ビジネスに大きく貢献してくれる優良顧客のことを指します。行動トレンド分析は、そのような優良顧客を対象にして成功パターンから最も効果的なトレンド(勝ちパターン)を分析する手法です。
行動トレンド分析では、自社の既存顧客の中から優良顧客だけを絞り込みます。その絞り込んだ顧客だけのグループを対象にしたニーズを明確化して商品やサービスに再現します。この行動トレンド分析を用いることで、自社ビジネスの最も大きな強み部分を引きだせます。その強み部分は、自社のブランド化にも役立つ重要なテーマにもなるでしょう。
●コホート分析
行動トレンド分析では、優良顧客をグループ化して自社のニーズを引きだす分析方法でした。同じような分析方法で、グループを作成して実行する方法にコホート分析があります。コホート分析とは、顧客や見込み客などを一定の条件でグループ化します。コホート分析の場合は、ひとつのグループだけではなく複数のグループを比較する分析方法です。
それぞれのグループは、条件をもとに分類します。たとえば、Webサイト訪問者を3つの条件でグループ分けしたとしましょう。
訪問者をこのような3つのグループに分類して、次の変化を分析します。
- いつまで滞在していたか
- 滞在中に何か行動を起こしたか
- 滞在中に行動を起こさないで離脱したか
コホート分析により、顧客行動を時間軸や行動軸において、それぞれのグループ属性と照らし合わせた分析ができます。これは、あくまでも一例ですが次のような結果も得られるかもしれません。
- 自然検索から流入した訪問者→5分以上滞在していたが何も起こさないで離脱してしまった
- 直接流入(URLを入力)した訪問者→5分以上滞在して、そのうちの3分の1のユーザーが資料請求をした
- SNS経由で流入した訪問者→流入後まもなく離脱してしまった
あくまでも一例になりますが、このような顧客行動データを分析できれば、どの属性のユーザーを対策すべきかの判断に役立ちます。
●特定顧客の抽出
より顧客を特定する施策としては、特定顧客の抽出が有効です。特定顧客の抽出は、顧客情報を入手してその情報に沿った戦略を立てる手法となります。たとえば、有料級のツールを無料提供する際にメールアドレスだけではなく、電話番号や住所、職業などの情報提供を求める仕組みです。
よくあるのは、業務効率化に役立つツールを期間限定で無料で使えるなど。有料級のツールを無料で試せることから個人情報を提供するユーザーは少なくないでしょう。入手した情報をもとによりその属性に適した製品やサービスの紹介へとアップセルやクロスセルの手法へとつなげられます。
あわせて読みたい
顧客分析を成功させるためのカギ
顧客を理解するには、ここまでご紹介してきた分析方法を活用することで、効率的よく施策を施すことができるでしょう。ただし、分析作業は本業の片手間として取り組めるほど楽ではありません。顧客分析は、知識と経験が必要だからです。
データだけでは判断できない「顧客の本音」
顧客分析を行っていく上で忘れてはならないことは「定量的なデータだけでは判断できない」という点です。前述したように、現代ではWebを活用したさまざまなデータが簡単に収集できます。しかし、データ分析が目的ではありません。数字の背景にある「顧客の本音」に、いかに気付けるのかも大切なポイントなのです。
定性調査
インタビューやアンケートなどの定性調査もぜひ実施してみてください。数値データだけでは分からない顧客の感情、動機、背景を深く理解するための効率的な方法になります。1対1のインタビューや、グループ形式のインタビュー、自由記述式のアンケートなどを活用し、顧客の心理を探りましょう。
顧客との対話
実際に現場に足を運び、顧客の様子を観察したり、話を聞いたりする機会を設けましょう。また、担当者が実際に顧客の立場になって、自社サービスを利用してみることも大切です。実際に体験することで、新たな発見や課題点が見つかることもあります。
顧客の生の情報を取りこぼさないように意識することが、顧客分析を行う上で抑えておきたいポイントです。想像だけにとどまらず、リアルな顧客を観察したり、実際にインタビューしたりなどの事実データがあることが望ましいのです。
顧客分析を継続させるための注意点
これらの顧客分析は、一度実施したら終了ではありません。継続的な顧客分析こそが、時間をかけて確実な成果に繋がります。ここでは、顧客分析を継続させるための注意点を解説します。
PDCAサイクル
継続した成果を生み出すためには、PDCAサイクルを徹底して回すことが重要です。常に分析結果を確認し、その知見を実際のマーケティング施策に落とし込むことで、継続的な改善効果が得られます。顧客データは常に変化するため、定期的な見直しと改善を繰り返すことで、施策や戦略の精度を段階的に高められます。顧客のニーズや市場のトレンドを常に監視し、柔軟に戦略を調節していく姿勢が求められます。
データの活用と分析スキル
顧客分析を継続させるためには、収集した分析データを有効的に活用するスキルが求められます。これには、専門的な分析手法やツールを扱うスキルが必要不可欠です。特に自社で顧客分析を進める場合は、分析スキルの習得と人材育成にも力を入れるべきでしょう。
顧客分析には、散在するさまざまなデータを統合し、適切な分析ツールを選定・導入する作業が必要です。さらに、マーケティング全体の知識を持っているとなお良いです。社内でのスキルアップ研修を企画したり、外部の専門家による研修を検討することも効果的です。その場合は、専門家や外部のコンサルタントの力を借りることも、効率的かつ有効な手段となります。
専門業者へ依頼
顧客分析をはじめ、Web集客へ取り組む際には、経験豊富な専門業者の力を借りることも有効な選択となります。顧客分析やWeb集客に関するノウハウや経験は、なかなか簡単に手に入るものではありません。自社で時間を掛けて試行錯誤するよりも、専門家へ依頼するほうが結果的に時間とコストの節約となるでしょう。
専門家への依頼は、経験と知識を兼ね備えているからこそ、時間と手間をかけない自社の顧客分析が可能となります。
データ分析における専門知識と経験
専門業者は、顧客分析に必要なデータ収集、分析ツール選定、複雑なデータの解釈における深い専門知識と豊富な経験を兼ね備えています。顧客の行動パターンや潜在ニーズを正確に判断する能力は、自社だけでは叶わないケースもあるでしょう。
専門家は、どんなデータが重要なのか、どのような指標に着目すべきかを知っています。自社では気づきにくい課題や機会を発見するチャンスにもなるのです。専門家に依頼することで、データに基づいたより精度の高い施策立案が可能となります。
客観的な視点と効率的な施策実行
専門家に依頼することで、自社では得にくい客観的な視点からの分析が期待できます。社内の人間では見落としがちな盲点や、自社の成功体験にとらわれない新しい視点を提供してくれるでしょう。
専門家は、最新のマーケティング市場やトレンド、成功事例を熟知しています。よって、最適な戦略を迅速に提案し、実行に移すことが可能です。専門家に依頼することで、自社のリソースを別のコア業務に集中させ、専門性が高い領域での成果を獲得できるメリットがあります。

めぐみやのWeb集客コンサルティング
Webサイトを活用して売上と利益向上を目指しませんか?
めぐみやが集客からサイト運営まで一貫してサポート致します。
顧客分析の先にあるコンテンツマーケティング
顧客分析を進めるにあたって、じわじわと顧客の考えていることや行動パターンを読めるようになります。顧客行動を可視化できているのであれば、コンテンツマーケティングへの活用は容易です。コンテンツマーケティングとは、顧客分析のもと対象となるターゲットを明確にして、そのターゲットが満足して行動を起こすようなコンテンツを提供するマーケティング手法。
現在、検索エンジン大手のGoogleではコンテンツの品質を第一に評価する方向性が見られます。そのため、コンテンツマーケティングのことをコンテンツSEOと題してサイト運営者に良質なコンテンツ提供を促しています。顧客分析の先には、コンテンツマーケティングの構築が見えてくるでしょう。
顧客を理解していることでコンテンツを効率的・効果的に企画できる
コンテンツマーケティングは、顧客を理解していることから始まっています。そのため、コンテンツを効率的かつ効果的に企画することが可能です。コンテンツを企画する際は、自社ビジネスが顧客に提供する価値や自社にしかできない強みを理解したうえで顧客の理解も進めます。その顧客分析にあたる部分が、今回紹介したマーケティング手法によって明確化されています。
そのため、コンテンツマーケティングを実施するのであれば、必要となる材料がすでに揃っている状態とも考えられるでしょう。いうなれば、すでに近道を通っていることと同じです。
顧客の求める情報のみを扱うためムダがない
コンテンツマーケティングを始める場合は、コンテンツに関して顧客の求める情報のみを扱うためムダがありません。顧客分析で整理した情報は、そのままコンテンツマーケティングのターゲットとして設定できます。さらにそのターゲットが求める価値を自社サービスと近づけるための情報として提供し続けるだけです。事前に調査が完了している施策ほど効率よくムダなく進められます。
顧客が顧客を生み出す拡散効果も期待できる
また、コンテンツマーケティングを実践した場合は、広告運用と異なり自社の行動以外でも顧客が増える可能性を期待できます。それは、顧客が顧客を生み出す拡散効果です。具体的には、良質なコンテンツの存在から、顧客がクチコミなどで勝手に拡散してくれる状態を形成できます。
拡散を期待できる裏側には、良質なコンテンツに対しての信ぴょう性や安心感、共感などが担保されています。その結果、共感を持ったユーザーが勝手にコンテンツを拡散していくわけです。
コンテンツマーケティングの王道「オウンドメディア」
コンテンツマーケティングの王道となるメディアには、オウンドメディアがあります。オウンドメディアは、企業自らが運営する情報配信サイトのことです。一般的な会社ブログと異なる点は、自社都合のコンテンツを配信するのではなく、あくまでもユーザー目線であること。この点を重視して実践していくことがオウンドメディアのコアな部分です。
オウンドメディアは、ユーザーに役立つ情報コンテンツを発信するメディアとして中長期的な視点で運営します。特徴としては、すぐに効果を期待できる施策ではない点を理解しましょう。ただし、運用から安定したアクセスを獲得できれば、長期的な集客を可能とする戦略とも考えられます。
オウンドメディアは長期的なマーケティング施策の代表
オウンドメディアは長期的なマーケティング施策の代表です。広告運用やメルマガなどもありますが長期目線で捉えるとオウンドメディアの運用が長続きします。その理由は、初期費用さえある程度投入しますが、運用を続けるごとに手間や時間を掛けなくても集客を安定させられる費用対効果の高い施策といえるでしょう。
将来の独占市場でビジネスを展開する差別化を目指す
オウンドメディアの運営は、将来の独占市場でビジネスを展開する差別化を目指します。コンテンツマーケティングの軸となる顧客分析ができあがっていれば、その分析データを生かして自社の強みを確立できます。確立された自社の強みは、競合他社との差別化をはかれる要素です。差別化できる部分を打ち出していくことで、ブランディングの形成となり、やがては独占市場での集客を実現することも夢ではないでしょう。
これらの成果を着実に引き出す場合は、専門家の見解が必要です。まずは、相談ベースから始めてみてはいかがでしょうか。
あわせて読みたい
まとめ
今回は、顧客分析について、理解すべき4つのポイントを解説してきました。顧客分析は、Webマーケティングの重要な要素となります。そのため一朝一夕では、取り組めないことが課題です。顧客を理解することは、今後の売上を左右する重要な取り組みとなることから、専門業者に相談してみることが必要となるでしょう。
- 顧客分析は企業が提供する製品やサービスに対する顧客のニーズ、行動、特性を理解するプロセス
- 主要な手法にはデータ収集・セグメンテーション・データ解析がある
- 顧客分析の目的は主にビジネスの現状を知る、施策を決める、売上を増やすために行われる
あわせて読みたい
顧客分析に関するよくあるご質問
最後によくあるご質問をいくつかご紹介致します。
みなさまのWeb集客にお役に立てば幸いです。
その他、ご不明な点がございましたら以下のリンクよりお気軽にご相談下さいませ。
無料オンライン相談はこちらからどうぞ。
Q
顧客分析とは何ですか?
A
顧客分析とは、企業のマーケティングや営業戦略の策定に役立てるために、顧客の属性、購入傾向、ニーズなどの情報を収集・分析するプロセスのことを指します。
Q
顧客分析の目的は何ですか?
A
顧客分析の主な目的は、顧客の理解を深め、より効果的なマーケティングや商品開発、サービス提供を行うための戦略を策定することです。
Q
顧客分析を行う際の一般的な手法は?
A
顧客分析を行う手法には、アンケート調査、購入データの分析、RFM分析(最近の購入日、購入頻度、購入金額)、セグメンテーションなどがあります。
Q
どのようなデータを使用して顧客分析を行いますか?
A
顧客の基本情報、購入履歴、Webサイトの訪問履歴、SNSの活動履歴、カスタマーサポートや問い合わせの記録など、多岐にわたるデータを使用して分析を行います。
Q
顧客セグメンテーションとは何ですか?
A
顧客セグメンテーションは、顧客群を似た特徴や行動を持つグループに分けることを指します。これにより、ターゲットを絞ったマーケティングやサービスを提供することができます。
Q
顧客分析の結果をどのように活用することができますか?
A
顧客分析の結果をもとに、新商品の開発、マーケティング戦略の最適化、ターゲット市場の拡大、顧客満足度の向上などの施策を計画・実施することができます。
Q
顧客分析において最も重要な要素は何ですか?
A
顧客のニーズと期待を正確に理解することが最も重要です。これにより、顧客に適したサービスや商品を提供することができるようになります。
Q
顧客分析を行う際の注意点は?
A
データの品質と整合性を保つこと、プライバシーの確保、分析結果の適切な解釈と活用、定期的な更新と検証などが重要な注意点として挙げられます。
Q
顧客分析ツールの例を教えてください。
A
Google Analytics、Adobe Analytics、Tableau、Power BIなどが顧客分析に使用される代表的なツールとして知られています。
Q
顧客分析とCRM(Customer Relationship Management)はどのような関係がありますか?
A
CRMは顧客との関係を深化・最適化するためのツールや戦略を指し、顧客分析はその一環として行われるものです。顧客データを効果的に活用して関係を強化するために、顧客分析の結果がCRMに取り込まれます。