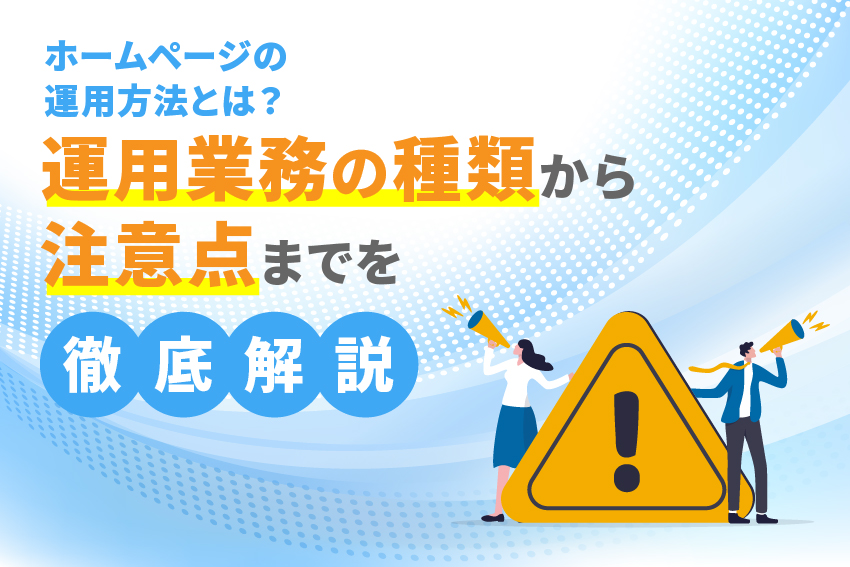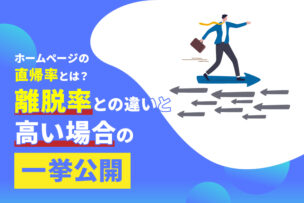記事の監修

Web集客・マーケティングの専門家として、13年間にわたり厳格な基準と緻密な戦略をもって中小企業の成功を導く。
一時的な集客の手法に頼ることなく、中長期的な効果を持続させる本質的なWeb集客の構築に注力。
『恵ある集客を。』をスローガンに掲げてクライアント様のサービスや商品の核心的な魅力を、的確にターゲットに伝えることを重視したWebサイト運用をサポート。
インターネットの台頭とスマートフォンの普及により、企業にとってホームページを運用することが当然の風潮にもなってきています。そのような中、「ホームページってどのように運用していけばいいのか?」はじめようにもどこから始めていいのか迷っている企業の担当者も少なくないでしょう。
ホームページを運用するには、3つのポイントを知っておく必要があります。
- ホームページの運用費用
- ホームページに必要な業務の種類
- ホームページを運用する際の注意点
上記にあげた3つのポイントをはじめに知っておくことで企業に必要な人的コストや時間的コストも見えてくることでしょう。この記事では、ホームページの運用を考えている企業のWeb担当者に向けて、運用のヒントにつながる3つのポイントについて紹介していきます。
- ホームページの運用について知りたい方
- ホームページを運用するメリットを知りたい方
- ホームページの運用するポイントを知りたい方
目次
ホームページを運用すること
はじめに、ホームページの運用するにあたって、知っておくべき3つのポイントのポイントを説明の前に「ホームページを運用する」ことについて、どのような役割と効果を期待できるのか見ていきましょう。
フロントエンドとバックエンドの運用業務がある
ホームページの運用業務は、主に「フロントエンド」と「バックエンド」の2つに分けることができます。
フロントエンドの運用業務では、集客施策をメインで行い、常に最新の情報を更新し続けることで、ホームページを利用するユーザーの獲得を目指しています。一方バックエンドの運用業務では、サーバー周りのインフラ整備を行います。ユーザービリティの維持・向上を目指し、利用しやすいホームページ環境を作り上げることが目的です。
では、それぞれの詳しい業務内容について見ていきましょう。
ホームページ運用におけるフロントエンド業務
フロントエンドの業務内容におけるキーワードが「SEO」です。フロントエンドの運用業務は、主にこのSEOの対策を行っていくことが重要となります。
SEOとは、日本語で「検索エンジンの最適化」といいます。SEO対策に取り組むことで、検索エンジンでの表示順位を上位にすることができます。上位表示されれば、新規ユーザーの獲得や大きなアクセス数が期待することができるのです。
具体的なSEO対策の方法としては、こまめなコンテンツの更新や追加、ターゲットユーザーの検索キーワードに合ったコンテンツの更新などがあります。どれも長期にわたって取り組む必要がある運用方法となっているため、成果を実感するまでには時間を有する場合も考えられます。
作成したコンテンツを多くのユーザーの目に触れさせるためには、集客業務に取り組んでいくことも大切です。フロントエンドの運用業務の一環である集客業務は、現在様々な方法で取り組まれています。
最も一般的な集客方法であると言われているのが「広告運用」です。リスティング広告やディスプレイ広告など、インターネットを利用する人に対し、文字や画像で宣伝することができる方法は、自社ホームページに多くの人を誘導するには非常に有効です。
ほかにも、地域で検索流入を狙う「MEO対策」や「SNS運用」などの集客方法があります。
このように、フロントエンドの運用業務は、ホームページのユーザーを増やすことを目的としています。ユーザーの目に触れる部分を改善・構築していき、ホームページのクオリティを高めていくことが仕事です。
ホームページ運用におけるバックエンド業務
バックエンドの運用業務は、フロントエンドの運用業務と違い、ユーザーからは見えない部分であるインフラ整備やトラブル対応などを担います。
例えば、ホームページを運用するために必要不可欠であるドメイン・サーバーは定期的に契約更新や、SSLサーバー証明書の更新などの業務を行っています。ユーザーからの信頼を高めるためには、これらの業務をきちんと取り組まなければなりません。特に、SSL化についてはSEO評価にも関わるため、忘れずに着手する必要があります。
ほかにも、ホームページの更新やコンテンツの追加を行うためのシステム「CMS」のアップデートやトラブル対応、データのバックアップなど、ユーザーが快適にホームページを利用するために必要な業務を担うこととなります。
快適なホームページ環境を維持するためにも、このようなバックエンド運用業務は欠かせないのです。
あわせて読みたい
自社独自で情報発信する
ホームページを運用することとは、自社の紹介も含めて独自の情報発信を行うことです。独自の情報発信だけに、ホームページの内容を客観的にインターネット上で評価されることになります。
つまり、社内では評判がよくても実際の検索ユーザーから見た自社の取り組みに対しての未知の部分も見えてくる可能性があるのです。ホームページを運用することとは、自社都合よりもインターネットユーザーの立場になったユーザー目線での評価が基準となります。
自社の販売チャネルの確立
ホームページの運用は、自社の発信する販売チャネルの1つとなるでしょう。実店舗の販売チャネルとなると物理的な負担に左右され、コスト面に影響されやすくなります。
その点、ホームページの場合はインターネット上で無数の可能性を持って拡大していくことも考えられるでしょう。その理由は、自社の商品やサービスなどを必要とするニーズの高いユーザーとの接点が持てれば販売チャネルの大きな成長もきたいできるからです。
自社サービスの認知拡大
ホームページの運用は、将来的にも大きな販売チャネルとなる可能性を秘めているだけに、自社の認知拡大となる原石になります。ホームページを通して、企業が想定していなかった属性のユーザーの発見や新しい活用事例までWeb上で展開する検索ユーザーの行動体験から新しい価値の発掘も可能なのです。
以上のように、自社サービスの向上につながる認知拡大が期待できる販売チャネルとなるのがホームページの存在になります。
費用対効果の高いブランディングを実現
自社サービスの認知拡大を実現となるホームページは、同時に費用対効果の高いブランディングも形成できます。通常、ブランディングを強化する場合は広告費を掛けてテレビコマーシャルや新聞雑誌などで自社ビジネスを宣伝する方法が考えられるでしょう。ホームページを運用した場合は、将来的に認知拡大されると同時に「〇〇といえば企業名」と定着されるブランディングを実現できます。このブランディング自体を広告費を掛けずに実現できる点が費用対効果の高い施策といえるでしょう。
あわせて読みたい
ホームページに運用が必要な理由
ホームページは、企業や個人が自分自身を世界に紹介するデジタルな名刺とも言えます。しかし、多くの方がが誤解しているのは、ホームページを一度作成したらそれで完了、という考え方です。実際には、ホームページは「作成」と「運用」の両方が非常に重要です。
常に変わるトレンド
まず一つ目の理由は、インターネットのトレンドや技術が日々進化しているからです。昨日まで効果的だったデザインやコンテンツが、明日には古くなる可能性が高いのです。進化するトレンドに合わせてホームページもアップデートする必要があります。
SEO対策
次に、先述しましたSEO(検索エンジン最適化)も運用が必要な大きな理由です。Googleなどの検索エンジンは定期的にアルゴリズムを更新しています。そのため、運用を怠ると検索順位が下がり、結果的に集客に大きな影響を与える可能性があります。SEO対策は継続的な対策が必要です。
ユーザー体験
最後に、ユーザー体験(UX)の向上も運用を通じて実現します。例えば、使い勝手が悪いと訪問者はすぐに離脱してしまうでしょう。そのため、ユーザーの行動データを元に継続的に改善を行うことが重要です。良いユーザー体験は良いビジネスを生むことに繋がります。
ホームページを運用するメリットとは
ホームページを運用すると、企業はどのようなメリットを得ることができるのでしょうか。ここでは、ホームページを運用することで得られるメリットについてご紹介いたします。
自社製品の販売促進
SEO対策や集客など、戦略的で有効なホームページ運用は、自社製品の販売促進につながります。自社のホームページに多くの人が訪れれば、その分製品やサービスについて、多くの人に知ってもらうことができます。すると、集客力や販売力の強化につながるのです。
ホームページに製品やサービスに関するコンテンツを掲載すれば、24時間いつでも宣伝できる広告として活用することができます。コンテンツを通じて製品やサービスに興味を持ってもらえれば、顧客獲得やさらなる宣伝のチャンスにつながる場合もあるでしょう。
現代は、チラシなどの紙媒体を利用したオフラインの宣伝よりも、ホームページを活用したオンラインの宣伝が有効であり、大きな成果を得やすいのです。
あわせて読みたい
顧客満足度の向上
自社製品やサービスを利用する顧客の満足度を高めるためにも、ホームページを活用することができます。
近年はホームページに問い合わせ用のメールアドレスやメッセージボックスを設置している企業も多いです。これらのアドレスなどは、顧客が製品に関する疑問や不満を直接企業に相談することに活用されています。
例えばアパレル事業の場合、通販を利用して服を購入した際、注文した製品と色やサイズが違うなどの事情があれば、ホームページから手軽に返品・交換対応を行うことができます。迅速な対応は企業の信頼を高めるでしょう。
また、新商品についての情報を知りたいときは、その製品を販売している会社の公式ホームページを確認するかと思います。定期的なコンテンツ更新を行っている企業であれば、顧客もそのホームページの情報を信頼しやすくなります。
製品やサービスの使い方や有責な情報について発信するのも有効です。ユーザーが知りたい情報を掲載することは、顧客満足度を高めます。
ホームページを正しく運用することができれば、顧客の満足度や製品・サービスへの信頼を高めることもできるのです。自社の製品やサービスの価値を高めたいとお考えの場合は、ぜひホームページ運用に取り組んでみてはいかがでしょうか。
企業の信頼度向上
コンテンツを定期的に更新することで、企業としての信頼を高めることもできます。
製品やサービスの正しい情報を公式ホームページで確認しようと考えた時、最終更新日が何年も前だったら、その企業に対するイメージはあまり良くないものとなってしまうでしょう。
逆に、製品・サービスに関する説明や新商品の紹介、事業内容など、事細かに分かりやすく紹介されていたら、企業への信頼度や安心感は高まるのではないでしょうか。
ホームページの運用は、企業の信頼度を向上させるためにも大切なことなのです。
ホームページの運用する際の3つのポイント

さて、将来的に大きな認知拡大に期待がかかるホームページの運用をする際に知っておくべき3つのポイントについて解説していきましょう。ホームページを運用するにあたって、最初に理解しておけば、「ウチの会社の場合は、このくらいの規模のホームページで運用することが望ましい」という指標になることでしょう。
ホームページ運用に必要な業務種類
続きまして、ホームページを運用するために必要な業務の種類を取り上げてみましょう。
- コンテンツとなる情報収集など管理業務
- ページ更新業務
- 顧客からの問い合わせ対応業務
- 社内要望の管理業務
- SNS連携業務
- 保守管理業務
- ホームページ解析・分析・修正・施策提案業務
- 広告との連携運用業務
- 検索エンジンアルゴリズム更新への対応業務
コンテンツとなる情報収集など管理業務
ホームページの運用では、コンテンツとなる情報を収集したり、収集した情報を精査したりする管理業務が必要です。情報の管理業務では、情報一つひとつのソース元や情報の専門性や正確性などが求められます。収集した情報の中には、関連性の低い情報や将来的に必要となる情報などもあるでしょう。
そのため、情報を目的ごとに振り分けたり、不要な情報を排除したりします。この段階の業務は、ホームページを運営する企業のビジネス見識が重要となるため、自社リソースで取り組むことが理想です。ただし、検索エンジンに向けた判断では、客観的な見解が重要となるため、専門家の意見も生きてくるでしょう。
ページ更新業務
ホームページは、アップロードしたら完了ではありません。検索エンジンに評価してもらうためには、ホームページを常に最新の状態に更新する業務があります。記事の更新や最新情報の発信、環境の変化に合わせたアップデートなどが必要です。
顧客からの問い合わせ対応業務
自社ホームページに「資料請求」や「問い合わせフォーム」などを設置している場合は、顧客からの問い合わせ対応業務が必要となるでしょう。問い合わせ対応業務のワークフローができていれば問題ありませんが、行き当たりばったりになってしまうと、1件の問い合わせで余計な業務負担が掛かるため注意が必要です。問い合わせ対応業務をフロー化する場合は、大きなテーマから振り分けて担当を明確にしておきましょう。
- Web担当者の範囲で解決できるレベルの問い合わせ
- 社内他部署もしくは社外などの確認が必要な問い合わせ
なるべくならば、Web担当者の範囲で問い合わせ対応を完了できることが理想ですが、内容によっては他部署の判断待ちとなるイレギュラーな問い合わせも存在するでしょう。
社内要望の管理業務
自社ホームページの運営を担当するWeb担当者は、社内で上がってきた要望などをまとめて管理する業務も携わります。Web担当者ひとりでまかなっている場合は、社内各部署から上がってきたホームページへの要望に優先順位を付けて対応しなければなりません。内容によっては、専門知識や経験が不足していて、外部の専門業者への依頼が必要な場合もあるでしょう。
SNS連携業務
ホームページの運営では、SNSと連携する業務も必要です。企業アカウントを取得して企業活動の取り組みを発信したり、必要に応じてSNS広告を出稿したりします。SNSを選定する際は、自社のビジネスに合った媒体を選ぶことが大事です。
保守管理業務
また、ホームページを運用するには保守管理業務もあります。サーバー環境やページの品質チェック、顧客との接点となるユーザーフォームなど個人情報の安全面などの理解も求められるでしょう。とくに、最近ではクラウド環境を使ったオンラインサービスを介して電子契約が主体となっています。また、本人確認などもスマホと連動した2段階チェックが主流となっているため、自社で用意するオンラインサービスや入力フォームなどは個人情報の安全面の観点からも細心の注意が必要です。
ホームページ解析・分析・修正・施策提案業務
さらに、ホームページの運用にはアクセス解析、データ分析、ページ修正、新規施策立案などホームページ全般の状況理解と分析結果による戦略的判断業務が必要になります。
●施策を新しいコンテンツとして追加・更新する
ホームページの運営は、掲載している情報をそのままの状態にしておくのではなく、施策を立ててコンテンツ化する必要があります。施策をコンテンツ化したら、ホームページに追加・更新して反応を確かめるイメージで進めていきます。Web担当者は、制作後もホームページの定期的なコンテンツ追加・更新に関わることが大切です。
●トラブルなど発生したときの対応
Web担当者は、ホームページの運営において何かトラブルが発生したときの対応も求められます。ついやってしまいがちなトラブルとして、ホームページを設置しているサーバーの契約更新を忘れてしまうことがあげられます。ホームページを長期で運営していく場合は、部署の移動などで担当者が替わったときも考慮して、トラブル発生時の対応マニュアルの作成がおすすめです。
広告との連携運用業務
ホームページを運用開始したままでは、多くのユーザーに訪問してもらうことができません。そのため、初期段階ではリスティング広告など公告を活用して多くのアクセスを集める必要があります。
インターネット上で多くのアクセスを集めるには、ホームページの運用と広告の運用を連携して管理していく業務が必要になるでしょう。
検索エンジンアルゴリズム更新への対応業務
また、ホームページを運用していく中で、検索エンジンに対してホームページを最適化していく業務は必須事項となります。インターネット上でホームページを露出していくためには、検索エンジンのアルゴリズム更新に常に最適となる状態に対応していくことが求められるのです。
●Seo的指標のチェック
検索エンジンのアルゴリズム更新は、頻繁に実行されています。頻繁に更新されている状況で指標がなければ、ホームページを最適な状態にしておけません。ホームページの運営には、Seo的な指標チェックが必要です。Seo的な指標チェックを日々欠かさずに実行することで、検索エンジンのアルゴリズムの進化に適したホームページへと修正ができます。
●Googleアナリティクスの活用
ホームページの運営において、日々の反応を確認できるツールがあります。検索エンジンのGoogleより提供されているGoogleアナリティクスを活用することでホームページにアクセスしてくるユーザーの動向をチェックできるでしょう。Googleアナリティクスは、基本的な機能をほぼ無料で利用できます。ただし、専門用語やツールの使い方などは、ある程度使い慣れていなければ理解できない対応で困る可能性もあります。
●サーチコンソールの活用
Seo的な指標は、Googleアナリティクスによる日々のチェックからアクセス数の変化などが確認できれば、その要因となるホームページの問題などを通知してくれるツールもあります。検索エンジンのGoogleが提供するサーチコンソールでは、以下の機能でホームページの健全性を指摘してくれるでしょう
- インデックスの状態:検索エンジンへの登録
- 検索クエリ:ユーザーが実際に検索で使用した語句の組み合わせ
- クロールエラー:定期的に巡回しているGoogleのロボットが発見する巡回によるエラーのこと
- モバイル表示エラー:スマホ画面で表示した際の可視性や操作性の不具合を指摘
サーチコンソールで指摘されたエラーは、そのまま放置しておくとホームページの評価を落とします。そのため、運営担当者は適切な改善を施せることが求められるでしょう。
あわせて読みたい
運用に必要な費用
まずは、ホームページの運用にかかる費用について見ていきます。ホームページを運用するにあたって、この費用の部分が企業にとって重要な判断材料になるでしょう。ホームページを制作して運用までかかる費用を知ることで、自社で制作するか、専門業者に依頼するか、コスト面から判断することができるのです。
自社で制作した場合の費用
自社でホームページを制作する場合、最低限必要になる費用がサーバー代とドメイン代です。ドメイン代は、種類にもよりますが1つのドメインで年間1,000円~5,000円ほどで登録ができます。また、Webサイトをインターネット上にアップロードさせるためのサーバー(一般的にはレンタルサーバー)利用料金が年間5,000円~100,000円ほどになるでしょう。サーバー代の料金に幅があるのは、保守管理やサポート内容によって違いがあるからです。上記に紹介した料金以外では、ホームページ制作に携わる担当者のスキルに左右されます。
制作担当者がサーバー環境やHTMLコーディング、CSSコーディングに情通していれば、制作ツールを購入する必要がありません。ただし、自社のWeb担当者が専任で取り掛かる必要性があるほど、ホームページの制作や運用にかかる作業時間の確保が必要になるでしょう。
ホームページは、自分でも製作することができます。実際、自社で制作して運用している企業もあるのです。業者に依頼した場合に比べて、自社でホームページを制作および運用した場合は、一定の知識と分析力、作業時間などが必要になってきます。
●自社制作によるメリット
ホームページを自社で制作した場合のメリットについて、見ていきましょう。自社でホームページを作り、運用をしていくことにより、低コストで実施できる点がメリットとなります。
●自社制作によるデメリット
費用を抑えられるホームページページの自社制作と運用によるデメリットは、費用がかからない分、内製でホームページ制作と運用にかかる作業をすべて実行しなければならないことです。
ホームページの制作だけではなくて、運用には「解析・分析・施策・更新・修正」など常にやらなければならないことがあります。自社の人的リソースが十分でない場合は、ホームページの運用途中で挫折してしまう可能性もあるのです。
ホームページ制作業者に依頼した場合の費用
では、ホームページ制作や運用を専門業者に依頼した場合の費用はどれくらいかかるのでしょうか?専門業者に依頼した場合の費用は、依頼内容にも左右されます。参考までにおおよその料金幅の相場を取り上げてみましょう。
●ホームページ制作にかかる費用相場
たとえば、専門業者がテンプレートを活用して、その中でのバリエーションでホームページ制作を依頼した場合は、30,000円~50,000円ほどの相場になります。あくまでテンプレートを活用した必要最低限の情報が記載された初期状態です。
ただし、依頼主によってはデザインやページコンテンツの量に独自性を求めてくる場合もあり、申し込みボタンやユーザーフォームなど機能面も充実させていくことでオーダーメイド制作になることも考えられます。このような依頼の場合は200,000円以上、ホームページの規模によっては1,000,000円以上かかることもあるのです。
また、制作以降のホームページ運用を業者に依頼する場合の費用相場は、月額5,000円~30,000円ほどになります。ホームページの更新や検索結果へのSEO対策に向けた解析など、依頼する内容によって料金が変わるでしょう。
●業者依頼によるメリット
次にホームページの運用などを業者に依頼する場合のメリットを取り上げてみましょう。ホームページの運用を業者に依頼するメリットは、知識と経験と作業時間などをゆだねられる点です。
インターネット事情は、リアル社会以上に環境変化が激しく、ホームページ運用担当者にとって、必要とされる分析や対応が多くなります。日頃からWebに情通していることが求められるので、ホームページの運用業務にかかる作業時間の確保が必要になるでしょう。
そのため、ホームページの運用を業者に任せることで、運用業務にかかる作業時間が不要になることがメリットとなるのです。
●業者依頼によるデメリット
次に業者に依頼した際のデメリットについて見ていきましょう。業者依頼でホームページを制作、運用してもらった場合のデメリットは、依頼内容に沿って費用がかかる点です。
特に、既に業者が用意しているテンプレートを活用したホームページであれば費用を抑えることができますが、依頼主がオリジナル性を求めることによって、追加費用が必要になるでしょう。ただし、専門業者に依頼することで、本格的なホームページを運営することができるのです。自社内製で試行錯誤することもなく、効率のいいホームページの運用となります。
ホームページ運用を外注する際の注意点
ホームページ運用を外注する際は、2つの注意点に気を付けなければなりません。それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。
●運用内容と費用について確認する
ホームページ運用を外注する際は、依頼する内容とそれに伴い発生する費用について詳しく確認しましょう。業務開始前に詳細まできちんと確認しておくことで、スムーズに業務に移ることができます。理想通りのホームページ運用を実現するためにも、イメージのすり合わせは重要です。
外注に必要な費用について、大まかな相場感について紹介します。簡単なコンテンツ修正や月に数回の更新など、負担の軽い業務であれば、2万円程度で依頼することができるでしょう。
コンテンツの更新回数が増えたり、アクセスなどの月次レポートや集客アドバイスなど、担当する業務が増えれば、その分価格も高くなり、~5万円程度の費用負担となることが多いようです。
さらに、本格的な集客支援や施策の実施など、ホームページ運用を丸ごと外注するのであれば、さらに費用は高くなります。
ホームページの運用は、こだわろうと思えば際限なくこだわることが可能です。自社の製品やサービスを宣伝するには、どのような方法が最適なのかを把握して、必要以上にコストをかけず、なおかつ効率よく運用していくことが大切です。
●契約書を用意する
ホームページ運用を外注する場合は、契約書を作成することをおすすめします。業務開始前に契約書を作成しておくことで、業務内容や費用に関する齟齬が生じ継ことを防ぐことができます。外注業者とのトラブルを未然に防ぐためにも、契約書を作成しておくことは大切です。
契約書には、「業務内容」「対応頻度」「費用」などの内容を明記すると良いでしょう。これらを明確にすることで、プラン提案や業務の遂行をスムーズに行うことができるようになります。
トラブルを未然に防ぐためにも、契約書の作成は忘れずに行いましょう。
あわせて読みたい
ホームページ運用によるコストパフォーマンスについて
ホームページの運用を開始して、軌道に乗った場合のコストパフォーマンスについて、解説しましょう。ホームページの制作費は別として、運用費だけで見れば、年間50,000円~300,000円ほどです。
ただし、ホームページの運用は社員を1人雇う必要がありません。インターネット上にアップしたときから自動的に24時間365日、自動的に営業活動をしていくからです。結果的にホームページを運用することで、営業にかかる人的コストを削減につながります。
ホームページ運用における注意点
では、ホームページを運用するにあたって、注意しておくべきことを取り上げておきます。
更新を怠らない
ホームページの運用に必要な業務でも取り上げたホームページの更新は、運用における重要事項です。更新されていないホームページに対して、状況によって検索エンジンが評価を下げることもあります。そのため、ホームページの更新を怠らないことがおすすめです。
●更新していないホームページとは
ホームページを更新しないまま放置しておくと、情報も古くなり古くなった情報に対して需要が減り訪問者が少なくなります。掲載している情報が古いだけではなく、変更や刷新により有効ではなくなった場合は、検索エンジンで表示されることが問題となる可能性もあるでしょう。公的な場となるインターネット上には、あらゆる情報があふれていますが、検索エンジンは情報の正確性や信ぴょう性を重視していることから、間違った情報は淘汰される可能性が高いです。ホームページの更新は重要視しておきましょう。
●評価を下げられると見つけてもらえなくなる
更新しないまま放置しておいたホームページは、検索エンジンから評価を下げられます。その結果、検索結果に表示されない検索圏外のホームページとなるでしょう。検索圏外のホームページは、URLを知る人だけが訪問できる状態です。わざわざURLを打ち込んでホームページを表示する人は、関係者か過去に利用していたユーザーくらいではないでしょうか。基本的に評価を下げられたホームページは、新規顧客へのアプローチのできない存在になります。
●ホームページの更新する部分とは
ホームページの評価を下げられないようにする場合は、更新が必要です。ホームページの更新する部分とは、主に新着情報の掲載(最新記事の投入)が考えられます。記事の投入以外には、既存記事(ページ)のコンテンツを深掘りした追記や修正なども有効です。また、ホームページ自体のデザインやレイアウト、配置されている部分コンテンツなども使いやすく改善することも評価を高める要因となるでしょう。
ロングテールSeoを意識する
ホームページは専門性や独自性のあるコンテンツを検索エンジンから評価されます。そのため、ホームページのテーマキーワードを軸にして、関連キーワードからロングテールSeoを意識してホームページを育てていくことが理想的です。
ロングテールSeoは、Web集客に有効的な手法になります。専門業者のコンサルに相談してみることがおすすめです。
●ロングテールSeoのメリット
ロングテールSeoを採用した場合のメリットは、Web集客する検索市場において競合が少ないことがあげられます。競合の多い検索キーワードであれば、検索エンジンの評価を受けて上位表示するために求められるハードルが高くなるでしょう。ロングテールキーワードであれば、競合が少ない点から上位表示へのハードルも低くなります。だからといって、コンテンツの質を落としてしまうと長期的に安定した集客は見込めないので注意しましょう。
●ロングテールSeoのデメリット
ロングテールSeoは、競合の少ない市場で集客のできる施策ですが、競合の少ない分、検索ボリュームも少なくなるでしょう。そのため、検索ボリュームの少ないキーワードの上位表示を複数実現させて、その上にあるビッグキーワードに匹敵するくらいの少ない流入を積み重ねていくイメージが必要です。ロングテールSeoは、長期目線で継続することで実現する施策と考えられます。
集客が大事なこと
現在のホームページは、過去にあったホームページのように「会社の紹介」だけでは集客につながりません。企業のホームページの目的は、集客です。インターネット上の検索ユーザーのアクセスを集めることが売上につながっていきます。
Web集客は専門的な知識や経験、対応が必要になるので、専門業者にコンサル依頼をすることも選択肢になるでしょう。
●Web集客に必要な専門知識とは
Web集客には、専門知識が必要です。専門的な知識とは、検索エンジンから評価を受けるためのテクニック的なSeoや品質を向上させるコンテンツを作るノウハウなどがあげられます。他にも、企業のビジネスに適したホームページのデザインやホームページの訪問者目線で配置する訴求ポイントなども考えられるでしょう。専門知識は、短期的に詰め込めるわけではありません。一般的なマーケティング視点をWeb集客に置き換えて、仮説と検証をくり返しながら分析のうえで出た有効な施策を実行します。
●Web集客に必要な経験とは
Web集客に必要な経験は、仮説と検証で打ち出した施策を実行して成功または失敗している経験です。ホームページ制作を本業にしている専門家の場合は、失敗例を糧に成功を目指して改善をくり返します。ホームページは、運営元のビジネスモデルや目的の違いにより同じ施策で成功するとは限られていません。そのため、ホームページ制作から運営までの経験値が高い専門家ほど、過去の取り組みを参考に適切な判断をします。
●専門業者に依頼することで時短を可能にする
Web集客は、専門家に依頼することで、依頼者の手間や時間などの負担を削減できます。もし、自分で成功するか失敗するかわからない施策を何度も修正しながら取り組んだ場合、相応の時間と労力を必要とするでしょう。専門家への依頼は、それら負担をすべて任せられるため時短でWeb集客を目指せます。
集客増やすための手段の検討を必ず行う
ホームページへの集客を効率的に行うためには、取り組む手段について知識を身につけ、自社に合った方法を検討する必要があります。ターゲット層や自社製品・サービスの特徴から、どのような集客方法があっているのか慎重に選んでいきましょう。
●SEO対策
本記事内でも繰り返しお伝えしている通り、ホームページの集客にはSEO対策に取り組むことが非常に有効です。特に、検索エンジンにおける上位表示を目指すSEO対策の場合は、幅広い層の人を対象に集客を行うことが可能となります。
取り扱う製品やサービスが、性別や年齢を問わずに使用されるものであれば、SEO対策による宣伝は十分に集客効果を発揮することができるでしょう。
コンテンツの最適化やキーワードの選定、定期的なコンテンツの更新など、ご自身で取り組める施策も多いため、開業から間もない時期や資金を節約したい場合などにもおすすめです。
●リスティング広告
リスティング広告とは、ユーザーが検索したキーワードに応じて表示される広告のことです。こちらのSEO対策と同様に検索エンジンで上位表示されるタイプの広告なので、幅広い人を対象とした宣伝がしたい場合は非常に効果的です。
ただし、リスティング広告の場合は宣伝を行うための費用が必要となります。費用相場はひと月20~30万円と言われており、決して安い額ではありません。宣伝効果を実感することは可能ですが、費用負担が大きくなってしまいます。
宣伝費用を節約したい、無理なく宣伝を継続したいとお考えの方には、あまりおすすめできない方法であるかもしれません。
あわせて読みたい
●コンテンツマーケティング
コンテンツマーケティングとは、ユーザーにとって有益性が高いコンテンツをホームページ上で提供する集客方法です。
コンテンツマーケティングによる集客は、製品やサービスのターゲット層が明確な場合におすすめです。関心度の高い人に向けて集中的に宣伝することが可能となります。
さらに、コンテンツマーケティングを目的に執筆した記事の数々は、その後自社にとっての資産にもなります。価値が高い情報を届けることで、見込み顧客のファン化を目指すことができるでしょう。
費用負担は少ないですが、ターゲットにとって有益なコンテンツにまで育てるには、長い準備期間が必要となるかもしれません。また、ターゲットの関心を探るための調査も必要です。
こつこつと継続的な業務が必要となりますが、効果を発揮することができれば集客をのぞむことができるでしょう。
あわせて読みたい
スマホ対応されているか
最後に、現在のホームページにアクセスしてくるユーザーのほとんどがスマホ経由のモバイルユーザーです。そのため、ホームページもモバイルフレンドリー(スマートフォン表示に対応している)になっていることが求められます。モバイルフレンドリーに対応させることについてもホームページ運用において、重要な注意点になるでしょう。
●モバイルフレンドリーが重要視される理由
ホームページをモバイルフレンドリーに対応させる理由は何でしょうか?モバイルフレンドリーが重要視される理由は、インターネットの利用者の8割以上がスマホ(iPhone含む)経由だからです。検索ユーザーをはじめとして、SNSの利用や動画の視聴なども含めてほとんどのインターネットユーザーがスマホから情報尾をチェックします。そのため、ホームページもスマホで表示されることを前提にスマホ画面での見え方や操作性などを重視しなければなりません。モバイルフレンドリー対応の設定は、PCで表示されている状態とスマホから表示される状態をどちらも最適化して表示します。現代のホームページは、ほぼモバイルフレンドリーに対応させておくことで間違いないです。
●モバイルフレンドリーであるホームページのメリット
モバイルフレンドリーであるホームページには、インターネットユーザーの8割を占めるスマホユーザーのアクセスを期待できるメリットがあります。コロナ禍を経験した現代では、スマホ決済や予約、注文などが主流です。スマホ画面で使いにくいホームページは、数秒で離脱される対象となります。そのため、モバイルフレンドリーであることが大きなメリットとなります。
●モバイルフレンドリーであるホームページのデメリット
モバイルフレンドリーであるホームページには、デメリットなる部分もあります。ホームページ運営担当者がPC画面を中心に更新や改善作業をしている場合、PC画面だけで判断してしまうとスマホ画面での表示エラーなどに気づけない点です。
たとえば、企業の新商品開発とともにホームページのデザインを一新した場合、制作時から関わっている担当者がいれば問題ありませんが、担当者が替わっていればスマホ表示の確認を見落とすかもしれません。
モバイルフレンドリー対応は、PC画面用の表示の仕組みとスマホ画面用の表示の仕組みをコーディングによって切り替えています。制作時はトラブルがなかったことでも、更新を積み重ねたりホームページの微調整をくり返したりすれば、どこか設定で不具合が出てくる可能性もあります。そのため、モバイルフレンドリー対応のホームページは、常にPC表示とスマホ表示のどちらも確認することが必要です。
あわせて読みたい
まとめ
この記事ではホームページの運用について、運用における、費用・業務種類・注意点の説明を紹介してきました。ホームページを運用するにあたって集客をしていくことが理解できたことでしょう。集客のできるホームページを運用するためには、業者に依頼をするコストが掛かります。
ホームページの運用にかかる費用などコンサルに依頼して相談も可能です。専門業者に依頼することで時間効率よくホームページを運用することができるでしょう。依頼するコストと自社リソースを使って内製するコストを算出してみて、最適な判断を見つけてみましょう。
- ホームページはフロントエンドとバックエンドの運用業務が重要
- ホームページを通じて自社の情報を発信し販売チャネルとしての機能を強化することが大切
- ホームページを利用すれば顧客の満足度を高め自社サービスの認知度を広げることが出来る
あわせて読みたい
ホームページの運用に関するよくあるご質問
最後によくあるご質問をいくつかご紹介致します。
みなさまのWeb集客にお役に立てば幸いです。
その他、ご不明な点がございましたら以下のリンクよりお気軽にご相談下さいませ。
無料オンライン相談はこちらからどうぞ。
Q
ホームページの運用に何が必要ですか?
A
ホームページの運用には、定期的なコンテンツ更新、セキュリティ対策、バックアップ、アクセス解析のチェックなどが必要です。
Q
ホームページの更新頻度はどれくらいが良いですか?
A
更新頻度は業種や目的によって異なりますが、少なくとも月1回は更新することが推奨されます。
Q
運用中のホームページでのトラブルを防ぐための方法は?
A
定期的なバックアップ、セキュリティアップデートの適用、SSL証明書の取得などがトラブルを防ぐための基本的な方法です。
Q
アクセス解析を取り入れるメリットは何ですか?
A
アクセス解析を利用することで、訪問者の動向や効果的なコンテンツ、改善点などを把握することができます。
Q
ホームページの運用におけるSEO対策の重要性は?
A
SEO対策を行うことで、検索エンジンからの自然な訪問者を増やすことができ、ビジネスチャンスを拡大することが可能です。
Q
モバイル対応のホームページ運用のポイントは?
A
レスポンシブデザインの採用や、モバイルユーザー向けのUI/UXの最適化が重要です。
Q
ホームページのバックアップはどれくらいの頻度で行うべきですか?
A
サイトの更新頻度や内容にもよりますが、最低でも月1回はバックアップを取ることが推奨されます。
Q
SNSとホームページ運用の連携のメリットは?
A
SNSの投稿をホームページに組み込むことで、訪問者とのエンゲージメントを高めたり、新しい情報を迅速に伝えることができます。
Q
ホームページ運用での画像の扱いに注意すべき点は?
A
画像のファイルサイズやフォーマットを適切に選ぶことで、ページの読み込み速度を早めることができます。
Q
ホームページ運用時のユーザーフィードバックの取り入れ方は?
A
フィードバックフォームの設置や、SNSでの意見収集などを通じて、ユーザーの声を直接取り入れることが有効です。
Q
ホームページ運用の外部委託のメリットとデメリットは?
A
メリットとしては専門知識が必要なタスクを委託できる点。デメリットとしてはコストやコミュニケーションの課題が挙げられます。